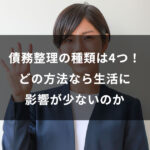この記事は約 18 分で読めます。
- 自由財産とはどういうものか
- 自由財産に該当するもの
- 自由財産の拡張とはどういうものか
- 自由財産の拡張が認められる財産の例
- 財産を隠すと自己破産が認められないおそれがある
- 債務整理時に手元に財産をできるだけ残す方法
自己破産を検討する際、多くの方が「すべての財産を失ってしまうのではないか」と不安に感じることでしょう。しかし、「自由財産」として一定の財産を手元に残せることが、法律で認められています。
今回の記事では、自己破産後も保持できる財産の種類やその仕組みについて詳しく解説します。具体的な対処方法や注意点についても見ていきましょう。
目次 ▼
1章 自由財産とは|自己破産しても残せる財産の仕組み
自己破産を検討する際、すべての財産を失ってしまうのではないかと多くの方が心配されますが、そんなことはありません。「自由財産」として、一定の財産を手元に残すことが法律で認められています。
この章では、自己破産後も保持できる「自由財産」の定義や、その仕組みについて詳しく解説します。これにより、自己破産手続における財産の取り扱いを正しく理解し、安心して手続を進めることができるでしょう。
1-1 自由財産とは
自由財産とは、自己破産手続において差押えの対象とならず、破産者が手元に残せる財産を指します。具体的には、99万円以下の現金や生活必需品、差押禁止財産などです。
自己破産手続では、原則として破産者の財産は債権者への配当に充てられます。しかし、最低限必要な財産は、生活の再建を図るために自由財産として保護されます。また、破産手続開始後に取得した財産(新得財産)も自由財産として、手元に残せます。
なお、差押えを解除する手続とはどういうものか、その方法や期限について、以下の記事で詳しく解説しています。そちらもぜひ、参考にご覧ください。
1-2 自由財産が認められる理由
自由財産が認められる背景には、破産法の目的があります。破産法第1条では、破産者の経済生活の再生の機会を確保することが明記されており、全ての財産を失わせることなく、最低限の生活を維持できるよう配慮されています。
さらに、裁判所の判断により、自由財産の範囲を拡張する「自由財産の拡張」が認められる場合も珍しくありません。これにより、特定の条件下でより多くの財産を保持できるようになります。
なお、自己破産にかかる費用については、自己破産の種類別や内訳、払えない場合の対処方法を含めて、以下の記事で解説しています。そちらもぜひ、参考にご覧ください。
2章 自由財産に該当するもの
自己破産手続においても、破産者が手元に残せる「自由財産」が法律で認められています。これにより、破産後の生活再建に必要な最低限の財産を保持できます。
この章では、次に挙げる「自由財産に該当するもの」について、詳しく見ていきましょう。
- 破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
- 99万円以下の現金
- 差押禁止財産
- 破産管財人が放棄した財産
- 自由財産の拡張が認められた財産
2-1 破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
新得財産とは、破産手続開始決定後に破産者が新たに取得した財産を指します。具体的には、手続開始後に得た給与や賞与、贈与された金品などです。これらの財産は、破産手続開始時点で破産者が所有していた財産とは区別され、自由財産として扱われます。
破産手続では、開始決定時点での財産が「破産財団」として債権者への配当に充てられますが、新得財産はこの破産財団に含まれません。これは、破産者の生活再建を支援するための制度的配慮です。
たとえば、破産手続開始後に得た給与や賞与は新得財産となり、差押えの対象外となります。ただし、手続開始前に受け取ることが確定していた売掛金は、破産財団に含まれる可能性があるため、注意が必要です。
新得財産の概念を正しく理解し、手続開始後の収入や取得物の管理を適切に行うことが、破産後の生活再建において重要となります。とはいえ、一般人にその判断は難しいので、債務整理に長けた司法書士などの助言が必要です。
なお、自己破産において最も重要な「免責許可決定通知書」とはどういうものかや、届くタイミングとその後の流れについては、以下の記事で解説しています。そちらもぜひ、参考にご覧ください。
2-2 99万円以下の現金
自己破産手続において、前述のとおり99万円以下の現金は「自由財産」として手元に残せます。これは生活再建のために必要な最低限の資金を確保するための制度で、破産法第34条第3項第1号および民事執行法第131条第3号に基づくものです。
現金とは、紙幣や硬貨といった手元にある物理的な通貨を指します。一部の裁判所では、普通預金も現金に準じて取り扱う場合もありますが、法律上は現金と預貯金は別個のものとして扱われるのが一般的です。
たとえば、東京地方裁判所では、預貯金については20万円以下であれば自由財産として認める運用がされています。
したがって、銀行口座に預けている預貯金は、たとえその金額が少額であっても、現金とは区別され、自由財産として認められるかどうかは裁判所の判断によります。
99万円を超える預貯金を自由財産として手元に残すためには、「自由財産の拡張」の申立てが必要です。この手続により、裁判所が破産者の生活状況や財産状況を考慮して、自由財産の範囲を広げる可能性があります。
なお、自己破産直前に財産を現金や普通預金に換金した場合、その行為が不適切と判断される可能性があります。特に、債権者を害する目的での財産移動と判断されると、免責不許可事由となるリスクもあるため、注意が必要です。
自己破産の免責不許可事由に該当する要件の詳細と対処法については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
2-3 差押禁止財産
差押禁止財産とは法律上、債務者の生活や生業の維持に必要不可欠と認められ、差押えが禁止されている財産のことです。自己破産手続においても、これらの財産は「自由財産」として保護され、破産者が手元に残せます。
具体的には、国税徴収法第75条に基づき、以下のような財産が差押禁止財産として定められています。
- 滞納者およびその生計を一にする親族の生活に欠かせない衣服、寝具、家具、台所用具
- 滞納者およびその生計を一にする親族の生活に必要な3か月間の食料および燃料
- 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠かせない器具、肥料、労役用家畜およびその飼料、次の収穫まで農業を続行するために必要な種子その他これに類する農産物
- 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕または養殖に欠かせない漁網そのほかの漁具、餌および稚魚その他これに類する水産物
- 技術者、職人、労務者そのほかの主として自己の知的または肉体的な労働により職業または営業に従事する者の業務に欠かせない器具そのほかの物(商品を除く)
- 実印、位牌、勲章、礼拝に供する物、系譜、記録、日記、書簡、所持許可証その他これらに類する物
- 滞納者またはその生計を一にする親族の学習に必要な書籍そのほかの器具
- 滞納者またはその生計を一にする親族の身体に欠かせない義手、義足、義眼、義歯その他これらに類する物
これらの差押禁止財産は、破産手続においても保護され、破産者の生活基盤を維持するために重要な役割を果たします。ただし、具体的な状況によっては判断が異なる場合もあるので、注意が必要です。
なお、差押えの対象外となる財産の種類や、差押えが禁じられている財産について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
2-4 破産管財人が放棄した財産
破産手続において、破産者の財産は原則として「破産財団」として管理・処分され、債権者への配当に充てられますが、破産管財人が換価は困難である、または処分に費用がかかりすぎると判断した財産は、裁判所の許可を得て「破産財団からの放棄」を行います。
破産財団から放棄された財産は、破産者の手元に戻り「自由財産」として扱われます。たとえば、地方にある売却が難しい不動産や、抵当権が設定されており売却しても債権者への配当が見込めない物件などです。
放棄の手続は、破産管財人が裁判所に申請し、許可を得ることで正式に行われます。放棄された財産は、破産者が引き続き所有し、自由に処分できます。
ただし、破産者がこれらの放棄された財産を活用する際には、税金や維持費などの負担が伴う場合も少なくありません。特に不動産の場合、固定資産税や管理費が発生するため、放棄された財産を保持するかどうかは慎重に判断する必要があります。
なお、破産管財人とはどういうものかや、選任されるケースとその理由についについては、以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
2-5 自由財産の拡張が認められた財産
自己破産手続において、法律で定められた自由財産以外にも、裁判所の判断により「自由財産の拡張」が認められる場合があります。
これは、破産者の生活状況や財産の種類・金額などを考慮し、特定の財産を手元に残すことを許可する制度です。具体的な基準や手続については、次章で詳しく解説します。
借金問題から自己破産を検討されている方は、ぜひグリーン司法書士法人にご相談(初回無料・オンラインも可)ください。借金問題のプロである当法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
3章 自由財産の拡張とは
自由財産の拡張とは、自己破産手続において、法律で定められた自由財産の範囲を超えて、破産者の生活再建に必要と認められる財産を手元に残すことを裁判所が許可する制度です。
この制度は、破産法第34条第4項に基づき、破産者の個別事情を考慮して適用されます。具体的には、破産者の生活状況、ほかの自由財産の種類や金額、収入の見込みなどを総合的に判断し、裁判所が自由財産の拡張を認めるかどうかを決定します。
たとえば、病気療養中で高額な医療費が必要な場合や、職業上特定の道具や車両が不可欠な場合などです。
自由財産の拡張を申請するには、破産手続開始決定の確定日から1か月以内に、裁判所に対して申立てを行う必要があります。申立ての際には、拡張を求める財産の詳細や、その必要性を具体的に説明する資料の提出が必要です。
裁判所は、破産管財人の意見を聴取した上で、拡張の可否を判断します。その結果は、各裁判所の運用や破産者の状況に依存します。そのため、申立てを検討する際には、債務整理を専門とする司法書士などに相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
なお、自由財産の拡張とはどういうものかや、認められる範囲や例・申立手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。そちらもぜひ、参考にご覧ください。
4章 自由財産の拡張が認められる財産の例
「自由財産の拡張」が認められる財産の例を挙げておきましょう。
預貯金
給与や年金などが振り込まれた後の普通預金は、生活維持に必要と判断され、自由財産の拡張が認められることがあります。
生命保険の解約返戻金
生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合でも、破産者の健康状態や年齢によっては、保険継続の必要性が認められ、自由財産として扱われることがあります。
自動車
職業上必要不可欠な場合や、公共交通機関が乏しい地域に居住している場合、一定の評価額以下の自動車は自由財産として認められることがあります。
売掛金や報酬金
自営業者の場合、破産手続開始時に発生している売掛金や報酬金が、生活の唯一の収入源であると認められた場合、自由財産の拡張が認められることがあります。
退職金の一部
退職金の支給見込額の8分の1に相当する額が20万円を超える場合でも、破産者の生活状況に応じて、自由財産として認められることがあります。
なお、これらの財産が自由財産として認められるかどうかは、あくまでも各裁判所の運用や破産者の個別事情によって異なります。申立てを検討する際には、債務整理を得意とする司法書士などに相談し、適切なアドバイスを受けましょう。
参考までに、退職金の差押えとはどういうものかや、借金返済や離婚裁判などとの関係性については、以下の記事で詳しく取り上げています。そちらもぜひ、参考にご覧ください。
5章 【注意】財産を隠すと自己破産が認められないおそれがある
自己破産手続において、財産を隠す行為は重大な問題です。破産法第252条第1項第1号では、債権者を害する目的で財産を隠匿する行為が免責不許可事由として明記されています。
具体的には、現金や預貯金、不動産、車両などの資産を申告せず、裁判所や破産管財人から隠す行為などです。また、財産を他人名義に変更するなどの操作も同様に問題視されます。
これらの行為が発覚した場合、裁判所は免責を許可しない可能性が高まり、結果として借金が免除されません。さらに、悪質な場合は詐欺破産罪として刑事罰の対象となり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されるおそれもあります。
自己破産を検討する際は、全ての財産を正直に申告し、手続に誠実に協力することが重要です。財産隠しは重大なリスクを伴うため、絶対に避けるべき行為です。
なお、自己破産する際の財産隠しの危険性や、どこまで調べられるかに関して、以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
6章 債務整理時に手元に財産をできるだけ残す方法
債務整理を検討する際、手元にどれだけ多くの財産を残せるかは重要な課題です。適切な手続を選択することで、財産を守りつつ債務整理を行えます。
この章では、債務整理時に手元に財産をできるだけ残す方法として、次に挙げる2項目にフォーカスして見ていきましょう。
- 自由財産の拡張を申し立てる
- 自己破産以外の債務整理を選択する
6-1 自由財産の拡張を申し立てる
自由財産の拡張を裁判所に申し立てる手続により、通常の自由財産の範囲を超えて、特定の財産を保持することが認められる場合があります。
前述のとおりこの申立ては、破産手続開始決定の確定日から1か月以内に行う必要があります。具体的な手続や必要書類については、債務整理の専門家に相談するのが賢明です。
6-2 自己破産以外の債務整理を選択する
自己破産以外の債務整理方法として、任意整理や個人再生があります。これらの手続では、特定の財産を手元に残しながら債務の整理が可能です。特に、自宅や車などの資産を維持したい場合に有効な選択肢となります。
6-2-1 個人再生
個人再生は、借金の返済が困難な個人が、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りを原則3年間(最長5年間)で分割返済する法的手続です。再生計画に基づく返済を継続する必要があるため、継続的な収入が見込める場合に利用できます。
個人再生の大きなメリットは、住宅ローン特則を利用することで、住宅を手放さずに借金の整理が可能な点です。また、自己破産とは異なり、浪費やギャンブルによる借金も整理の対象です。
ただし、信用情報機関に事故情報が登録されるため、返済期間を含めて8〜10年間は新たな借入やクレジットカードの利用が制限されます。自己破産と同様に官報に掲載されるので、プライバシー上のリスクも否めません。
一般的な手続の流れとしては、まず司法書士などに相談し、申立ての準備を行います。その後、裁判所に申立てを行い、再生計画案を提出し、認可を受けることで手続が完了します。手続には時間と費用がかかるため、専門家への相談が不可欠です。
6-2-2 任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を目指す法的手続です。
任意整理の大きなメリットは、裁判所を通さないため手続が比較的簡便であり、費用や時間の負担が少ない点です。また、整理する借金を任意で選べるので、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いているローンなどを除外できます。
ただし、任意整理はあくまで債権者との合意が前提です。代理人を立てずに自分で行おうとすると、交渉に応じてもらえなかったり、応じてもらえても難航する可能性が高まります。
また、信用情報機関に事故情報が登録されるため、返済期間を含めて8〜10年間は新たな借入やクレジットカードの利用が制限されます。
一般的な手続の流れとしては、専門家に依頼して取引履歴の開示請求を行ってもらい、債務額を確定します。その後、専門家が和解案を作成し、債権者と交渉を行います。合意に至れば、和解契約を締結したうえでの返済計画の始まりです。
なお、債務整理の主な種類ごとの特徴やメリット、デメリットについては、以下の一覧表を参考にしてください。
| 債務整理の種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
| 特徴 | 裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法 | 裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法 | 裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法 |
| メリット | ・手続が比較的簡単で費用が安い ・家族や勤務先に知られない ・厳しい取り立てを止められる ・新たな借入が制限される | ・借金を大幅に減額できる ・住宅や車などの財産を守れる ・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い ・厳しい取り立てを止められる ・新たな借入が制限される | ・借金が全て免除される ・新しい生活をスタートできる ・厳しい取り立てを止められる ・新たな借入が制限される |
| デメリット | ・減額できる金額は債権者との交渉次第 ・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない | ・複雑な裁判所申立てが必要 | ・複雑な裁判所申立てが必要 ・官報に掲載される ・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない ・一定期間、職種制限を受ける |
| 適したケース | ・債務額が大きくなく、将来的に返済できる見込みがある場合 ・任意整理の詳細・解決事例はコチラ ↓ 借金をなくせる任意整理とは?メリット・デメリットや向いている人 任意整理の経験談・解決事例 | ・一定収入はあるが債務額が大きく、任意整理では難しい場合 ・個人再生の詳細・解決事例はコチラ ↓ 小規模個人再生とは|給与所得者再生との違いやメリット・デメリット 個人再生の経験談・解決事例 | ・債務額が非常に大きく、他の方法では返済が難しい場合 ・自己破産の詳細・解決事例はコチラ ↓ 自己破産とは?メリット・デメリットや手続の流れを徹底解説 自己破産の経験談・解決事例 |
債務整理の種類と生活への影響に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
以下の返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理】を使えば、借金問題の解決のために債務整理を行った場合に、借金がどれくらい減るのかの目安がわかります。
返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理】|大阪債務整理・自己破産相談センター
多重債務の返済が難しくなり、お困りの方は、ぜひグリーン司法書士法人の初回無料の相談(オンラインも可)をお気軽にご利用ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
まとめ
自由財産とは、自己破産手続において差押えの対象とならない財産です。手元に財産をできるだけ残す方法としては、自由財産の範囲を広げる「自由財産の拡張」の申立てのほかに、個人再生や任意整理といった債務整理方法があります。
個人再生や任意整理は特定の条件下で財産を保持しつつ、債務の減額や返済条件の見直しを可能とします。とはいえ、各手続にはメリットとデメリットが存在するので、自身の状況に応じて最適な方法を選択するためには、専門家への依頼が不可欠です。
借金問題に直面した際には、早期に債務問題を専門とする司法書士などに相談しましょう。早ければ早いほど解決策の選択肢は多く、スムーズに生活再建に踏み出せます。
なお、自己破産を含む債務整理のいずれの方法でも、代理人として司法書士などの専門家に依頼した後に、債権者に受任通知が送られて、取立てや請求がストップします。その件については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にご覧ください。
自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:自己破産 条件
自己破産の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!