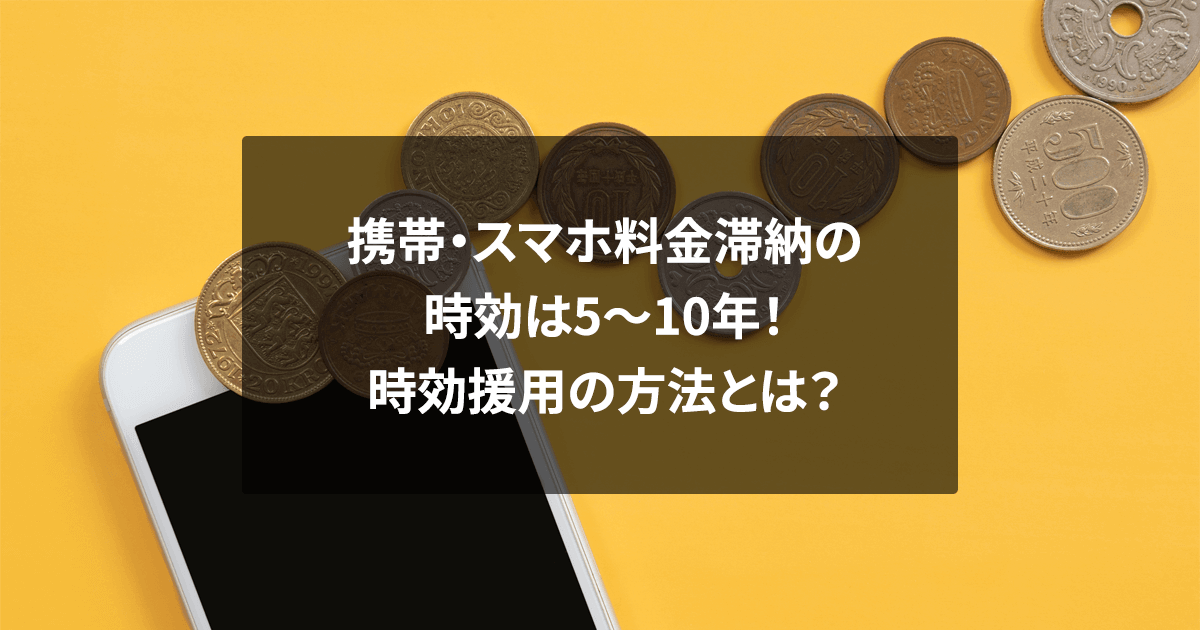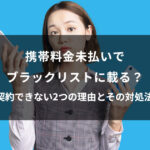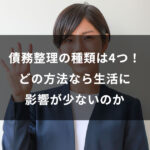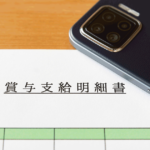この記事は約 16 分で読めます。
- 携帯・スマホの料金の時効が成立する時期
- 携帯・スマホの滞納料金の時効が成立しないケース
- 時効成立のためにその時期を迎えた際にすべきこと
- 携帯・スマホの滞納料金の時効についての注意点
携帯・スマホの利用料金を滞納してしまった場合、その支払い義務はいつまで続くのでしょうか?実は、携帯・スマホ料金滞納の時効は5年から10年とされています。
時効を迎えることで支払い義務が消滅する可能性がありますが、そのためには一定の手続が必要です。今回の記事では、携帯・スマホ料金の時効の詳細や、時効援用の方法について解説します。
長い間滞納している携帯・スマホ料金をどうすればよいか悩んでいるみなさんにとっては、現状での適切な行動の基準となるので、ぜひとも参考にしてください。
目次 ▼
1章 携帯・スマホの料金の時効は5~10年
携帯・スマホの料金の支払いは、日常生活において重要な要素です。しかし、何らかの理由で料金を滞納してしまうこともあります。
料金の滞納が続くと、その債務が時効にかかることがあります。時効が成立すれば、法的に支払う義務がなくなるため、時効の期間や条件を理解しておくことは重要です。
一般的に、携帯・スマホの料金の滞納については、5年または10年の時効が適用されます。しかし、この期間には例外も存在します。次に、具体的な時効の期間とその条件について説明します。
1-1 原則として滞納から5年で時効を迎える
2020年4月1日施行の民法改正により、金融取引以外の商取引による債権も含めて、あらゆる債権の消滅時効の完成する時期は、次のようになっています。
- 主観的起算点:権利を行使できることを知った時から5年
- 客観的起算点:権利を行使できる時から10年
携帯・スマホの料金の滞納についても、原則として滞納開始から5年で時効を迎えます。たとえば、料金の支払いが2019年1月に滞納となった場合、2024年1月が時効が成立する可能性のある時期です。
この5年間に、債権者が債務者に対して裁判を起こすか、裁判所を通した支払督促を行わないかぎり、法的に支払う義務がなくなります。
ただし、時効が成立するためには債務者が、後に述べるような時効援用の手続を行う必要があります。さらに、時効の進行が中断されることもあるため、注意が必要です。
たとえば、滞納期間中に一部でも料金を支払ったり、支払う意思を示したりした場合、時効の期間が「更新」されます。これは、時効がリセットされ、振り出しに戻るということです。
なお、現民法での消滅時効の詳細や、請求を免れるために必要な年数ついて、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
1-2 滞納について裁判が起こされた場合は裁判確定日から10年で時効を迎える
携帯・スマホの料金の滞納に関して、債権者が裁判を起こした場合、時効の期間は裁判確定日から10年です。
裁判が起こされると、滞納料金の支払い義務は裁判の判決により確定します。この判決が確定した日を起算点として、新たに10年の時効期間が開始されるわけです。
たとえば、2020年に裁判が起こされ、2021年1月に判決が確定した場合、2031年1月に時効が成立することになります。この間に、債権者が再度裁判を起こさないかぎり、10年後には法的に支払う義務がなくなります。
裁判による時効の期間は、通常の5年よりも長いため、注意が必要です。裁判が確定した場合でも、時効援用の手続を行うことが必要です。
また、判決が確定すると、債権者が強制執行を行うことができるため、対応には慎重さが求められます。
なお、携帯電話代金の滞納を時効の援用で解決した事例について、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
2章 携帯・スマホの滞納料金が時効を迎えていないケース
1章で述べたように、基本的には滞納から5年または裁判確定日から10年で時効を迎えますが、すべてのケースで時効が成立するわけではありません。携帯・スマホの滞納料金に関して、時効が成立するには一定の条件が必要です。
特定の状況下では、時効の進行が更新されることがあります。たとえば、一部でも料金を支払った場合や、支払いを認める発言や書類にサインした場合、さらに裁判が再度起こされた場合などです。
そのため、時効を援用する場合には、時効が成立しない可能性がある要素を理解しておくことが重要です。この章では、時効が成立しないケースについて詳しく見ていきましょう。
2-1 滞納から5年以内に一部でも料金を支払っているケース
携帯・スマホの滞納料金において、滞納から5年以内に一部でも料金を支払った場合、時効は更新されます。この行為は、債務を認めたことと見なされ、時効の進行が更新されます。
たとえば、5年の時効期間中に一度でも支払いを行うと、その時点から再び5年の時効期間が開始されます。そのため、少額であっても定期的に支払いを続けているかぎり、時効は成立しません。
債権者はこの点を理解して、債務者にわずかでも支払いを促すことが多いです。滞納料金の時効援用のためには、一部支払いが時効更新の原因になることを理解しておく必要があります。
なお、携帯を止められたらどうなるかや、携帯料金が払えなくなった場合の対処法について、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
2-2 滞納から5年以内に支払いを認める発言・書類にサインをしているケース
携帯・スマホの滞納料金に関して、滞納から5年以内に支払いを認める発言をした場合や書類にサインをした場合も、債務を承認したことになり、その時点で時効は更新されます。
たとえば、電話やメールで「支払います」と約束した場合、それは債務を認めたこととなり、時効は更新されます。
さらに、債務承認書や支払い計画書などにサインした場合も同様に時効が更新されます。このような支払いを承諾する行為により、5年の時効期間が再び最初からカウントされるわけです。
債権者は、このような確認を通じて時効を回避しようとすることが多いため、時効を援用する場合は注意が必要です。債務者の側としては、これらの行為が時効のリセットにつながることを認識し、慎重に対応する必要があります。
なお、債務を認めてしまう法的な「債務の承認」にあたる行為と時効成立への影響ついて、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
2-3 滞納から10年以内に再度裁判が起こされたケース
携帯・スマホの滞納料金に関して、滞納から10年以内に再度裁判が起こされたり、裁判所を通した支払督促などが行われた場合は、時効の更新事由に該当し、時効は更新されます。
滞納から10年以内に再度裁判が起こされた場合は、判決が確定した時点から新たに10年の時効期間が始まります。そのまま裁判が終わると、確定した判決にもとづいて強制執行が行われる可能性もあります。
また、裁判所からの通知を無視すると、裁判が欠席判決となり、債務が確定してしまうことがあるため、必ず対応が必要です。
支払督促などが行われた場合は、それが完了した時点から新たに10年の時効期間が始まります。
このような法的処置が行われた場合、法律の専門家に助言を求めることが重要です。
そのため、債務者は裁判所からの連絡に迅速に対応し、必要な対策を講じることが求められます。時効を迎えるまでの間、再度裁判が起こされないようにするためには、司法書士などの専門家のアドバイスを受けることが有効です。
携帯・スマホの料金滞納が長引き、ほかにも借金を抱えて返せなくなりお困りのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
3章 【注意】時効を迎えただけでは携帯・スマホの滞納料金の返済義務はなくならない
携帯・スマホの滞納料金が時効を迎えた場合でも、それだけで返済義務が自動的に消滅するわけではありません。時効の成立を正式に主張する「時効援用」という手続きが必要です。
この手続きを行わないかぎり、債権者からの請求を免れることはできません。時効援用には、一定の手続きと費用が伴うため、注意が必要です。
ここでは、時効援用の具体的な方法と費用について詳しく説明します。正しい知識を持ち、適切に対処することが重要です。
3-1 携帯・スマホの滞納料金を時効援用する方法
時効援用とは、時効が成立していることを債権者に正式に通知し、返済義務を免除してもらう手続きです。まず、時効が成立しているかを確認します。通常、携帯料金の消滅時効は5年ですが、裁判が起こされた場合は10年となります。
次に、時効援用の意思を示す内容証明郵便を債権者に送ります。この文書には、時効が成立していることを明記し、返済を拒否する旨を伝える必要があります。
内容証明郵便を送ることで、時効援用の意思を正式に伝えた証拠として残ります。送付後、債権者からの返答を待ちますが、返答がなくても返済義務は消滅します。
手続きを自分で行うことも可能ですが、司法書士などの専門家に相談して、確実に行うのが賢明です。
なお、携帯電話通信費の時効援用の事例について、以下の記事でご紹介しています。
ぜひ、参考にご覧ください。
3-2 携帯・スマホの滞納料金の時効援用にかかる費用
携帯・スマホの滞納料金に対する時効援用を行う場合、多少の費用がかかります。まず、内容証明郵便を送る際の費用が必要です。内容証明郵便には、およそ1,500円程度数の費用がかかります。
次に、専門家に依頼する場合の報酬は、専門家の種類や地域によって異なります。目安としては、行政書士の場合は1〜2万円程度、司法書士の場合は3〜4万円程度、弁護士の場合は5〜8万円程度が相場です。
行政書士は依頼費用が少なくてすみますが、対応内容は時効援用通知書の作成、送付のみです。消滅時効を迎えている借金の調査および債権者との交渉は依頼できず、対応できる範囲が限られています。
弁護士は最も費用が高く、そのうえ相談料も1時間で5,000円から1万円が別途必要です。司法書士も相談料がかかる場合はありますが、依頼すれば報酬に含めてもらえることが多いです。
また、司法書士は債務が1件あたり140万円を超える場合には代行できませんが、あくまで利息や遅延損害金は別とした「元金」が基準です。携帯・スマホの滞納料金であれば、元金で140万円を超えることは少ないでしょう。
総合的には、通常の携帯電話の時効援用であれば、司法書士に依頼するのがおすすめです。
携帯・スマホの滞納料金が時効の時期を迎えていて、時効援用を検討しているみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
4章 携帯・スマホの滞納料金の時効についての注意点
携帯・スマホの滞納料金の時効について注意すべき点が、主に次の4つあります。
- 債権回収会社に債権譲渡されても時効の起算点は変わらない
- 裁判所から連絡が来たときには無視しない
- 携帯・スマホの再契約をするのが難しくなる
- 時効成立まで滞納することが難しければ債務整理ついて司法書士・弁護士に相談する
個別に、詳しく見ていきましょう。
4-1 債権回収会社に債権譲渡されても時効の起算点は変わらない
携帯料金の滞納について、債権が債権回収会社に譲渡されても、時効の起算点は変わりません。つまり、最後の支払いから5年が経過していれば、債権回収会社に対しても消滅時効を援用できます。
債権譲渡があった場合、消滅時効の援用通知は債権回収会社に送付する必要があります。重要なのは、債権譲渡自体が時効の更新事由にはならないという点です。
ただし、債権回収会社は債務者に対して、法的手続を行う可能性が高いため、債務者側は注意が必要となります。
なお、債権回収会社とはどういうものか、債権回収会社から連絡が来た際にまずすべき最善の対応法ついて、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
4-2 裁判所から連絡が来たときには無視しない
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、絶対にそれを無視してはいけません。無視すると、債権者の言い分どおりの判決が出され、差押えのリスクが高まります。
さらに、判決が確定すると、その時点から新たな10年の時効期間が開始されます。裁判所を通して訴状や支払督促が来た場合には、速やかに答弁書や異議申立書を提出するなどのアクションを起こし、主張を伝えることが重要です。
なお、裁判所からの郵便物が届いた場合の注意点や対処法について、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
4-3 携帯・スマホの再契約をするのが難しくなる
携帯料金の滞納が続くと、同一キャリアでの再契約は困難になります。加えて、大手キャリア間でそのユーザーの滞納情報が共有されるため、ほかのキャリアでも契約が難しくなるでしょう。
また、滞納料金に端末代代金の割賦販売金が含まれている場合は、信用情報機関に事故情報が登録されるため、ローンやクレジットカードの新規契約が困難になり、現在のカードが利用停止になる可能性もあります。
なお、携帯料金の滞納がクレジットカードの審査に及ぼす影響について、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
また、携帯電話の料金滞納でブラックリストに載ってしまう場合の、信用情報の種類や登録期間について、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
4-4 時効成立まで滞納することが難しければ債務整理ついて司法書士・弁護士に相談する
時効成立まで滞納し続けることが難しいケース、たとえば時効までに差押えされそうな動きがある場合や、過去の自分の不用意な行動で時効が更新されていたなどのケースでは、時効援用は現実的な手段ではありません。
そういった、時効成立まで滞納することが難しいケースでは、司法書士などの専門家の助けを借りて債務整理を検討することが賢明です。
債務整理に詳しい専門家は、時効の成立状況の確認から債務整理、時効援用まで一括で対応してくれるため、スムーズに手続を進めることができます。
債務整理の主な種類ごとの特徴やメリット、デメリットについては、以下の表にわかりやすくまとめてあります。
横スクロールできます
| 債務整理の種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法 | 裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法 | 裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法 |
| メリット | ・手続が比較的簡単で費用が安い ・裁判所への申立て記録が残らない ・家族や勤務先に知られない | ・借金を大幅に減額できる ・住宅ローンや車ローンなどの財産を守れる ・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い | ・借金が全て免除される ・新しい生活をスタートできる |
| デメリット | ・減額できる金額は債権者との交渉次第 ・将来、再び借金問題に陥る可能性がある | ・裁判所への申立て記録が残る | ・裁判所への申立て記録が残る ・官報に永久に掲載される ・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない ・一定期間、就業制限を受ける |
| 適したケース | ・債務額が大きくなく、将来的に返済できる見込みがある場合 ・任意整理の詳細・解決事例はコチラ ↓ 借金をなくせる任意整理とは?メリット・デメリットや向いている人 任意整理の経験談・解決事例 | ・一定収入はあるが債務額が大きく、任意整理では難しい場合 ・個人再生の詳細・解決事例はコチラ ↓ 小規模個人再生とは|給与所得者再生との違いやメリット・デメリット 個人再生の経験談・解決事例 | ・債務額が非常に大きく、他の方法では返済が難しい場合 ・自己破産の詳細・解決事例はコチラ ↓ 自己破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れを徹底解説 自己破産の経験談・解決事例 |
債務整理の種類と生活への影響に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
以下の返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理】を使えば、借金問題の解決のために債務整理を行った場合に、借金がどれくらい減るのかの目安がわかります。
さまざまな借金問題を抱えて自力返済が難しくなり、お困りのみなさんは、新たに借入をせずに解決する方法を検討しましょう。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
まとめ
携帯・スマホ料金の滞納には消滅時効が存在し、正しく手続を踏めば支払い義務を回避できる可能性があります。しかし、時効援用の手続は専門知識が必要であり、適切に進めないと時効が成立しないこともあるでしょう。
債権回収会社や裁判所からの通知を無視せず、早めに対策を講じることが重要です。場合によっては司法書士や弁護士に相談することも検討しましょう。
適切なアドバイスを受けることで、最適な解決策が見つかるでしょう。本稿の情報を参考に、滞納による問題に適切に対処してください。
スマホ・携帯料金の滞納などから、借金問題を抱えて自力返済が難しくなり、お困りのみなさんは、新たに借入をしないで解決する方法を検討しましょう。グリーン司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!