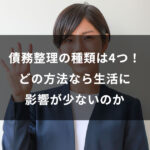この記事は約 16 分で読めます。
- 賃貸契約の連帯保証人に起きやすい7つのトラブルとは
- 賃貸契約の連帯保証人を断りたいときの方法
- 滞納家賃や損害賠償費用を連帯保証人として請求された際の対処法
賃貸契約における連帯保証人制度は、借主が家賃を滞納したり、物件に損害を与えたりした場合に備えて設けられたものです。しかし、この制度は連帯保証人にとって多くのリスクを伴い、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
今回の記事では、賃貸契約の連帯保証人に起きやすいトラブル例を7つご紹介し、それぞれの対処法や、賃貸契約の連帯保証人を断りたいときの対処法、連帯保証人になり滞納家賃や損害賠償費用を請求されたときの対処法を詳しく解説します。
目次 ▼
1章 賃貸の連帯保証人に起きやすいトラブル例7つ
賃貸の連帯保証人に起きやすい主なトラブル例として、次の7つが挙げられます。
- 主が家賃を滞納し連帯保証人に請求されてしまう
- 借主が支払わない原状回復費用や損害賠償費用を請求されてしまう
- 連帯保証人の希望で賃貸借契約を解除できない
- 連帯保証人の地位が相続されてしまう
- 連帯保証人を途中でやめられない
- そもそも勝手に連帯保証人にされてしまっている
- 連帯保証人になってほしいと頼まれて困ってしまう
それぞれのトラブルの内容と対処方法について、詳しく見ていきましょう。
なお、連帯保証人になることのリスクや、回避する方法などについては、以下の記事で詳しく取り上げています。そちらも、併せて参考にお読みください。
1-1 借主が家賃を滞納し連帯保証人に請求されてしまう
賃貸契約において、連帯保証人がもっとも頻繁に直面するトラブルのひとつが、借主が家賃を滞納し、連帯保証人に家賃の支払い請求が来る事態です。連帯保証人は、借主が家賃を滞納した場合、法的にその支払い義務を負います。
それにより、連帯保証人自身が家賃を立て替えなければならない状況に追い込まれるケースは少なくありません。特に、長期間の滞納が続くと、連帯保証人に対する経済的負担が大きくなり、自己破産に至るケースもあります。
このようなトラブルを防ぐためには、連帯保証人になる前に、借主の収入や信用状況の十分な確認が欠かせません。支払い能力に不安を感じるのであれば、連帯保証人を引き受けるべきではありません。
また、信頼して引き受けてしまったけれど、滞納が実際に発生した場合は、早期に対策を講じなければなりません。借主に直ちに連絡を取り、支払いの意志の確認を取りましょう。
なお、家賃を滞納した場合に早急に相談すべき先と、その後の流れについては、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
なお、家賃滞納から強制退去になる場合の詳細や、強制退去になったらその後はどうなるかについて、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
1-2 借主が支払わない原状回復費用や損害賠償費用を請求されてしまう
借主が退去する際に発生する原状回復費用や損害賠償費用も、連帯保証人に請求されるケースがあります。原状回復費用とは、借主が物件を退去する際に、経年劣化以外の損傷や汚れを修復するための費用です。
借主がこれらの費用を支払わない場合、連帯保証人がその負担を肩代わりする必要があります。このような状況は、特に高額な修繕費用が発生する場合に、連帯保証人にとって大きな経済的負担となりかねません。
このトラブルを回避するためには、連帯保証人になる前に、物件の状態を確認し、借主と物件の使用についての取り決めを明確にしておくのが賢明です。
また、連帯保証人としてのリスクを軽減するためには、借主に物件の使用に関する指導を行い、余計な修繕費用が発生しないような適切な管理を促しましょう。
1-3 連帯保証人の希望で賃貸借契約を解除できない
連帯保証人が直面する一般的なトラブルのひとつは、借主との関係が悪化した場合や、連帯保証人としての責務を果たすのが難しくなった場合でも、自分の希望で賃貸借契約を解除できない件です。
賃貸借契約は貸主と借主の間で取り交わされるため、連帯保証人の意思で契約を終了させるのは不可能です。もし、滞納が発生しているにもかかわらず、貸主も借主も賃貸借契約を解除しない場合には、連帯保証人が延々支払続ける必要があります。
賃貸借契約が解除できないので、貸主の同意がなければ連帯保証人の地位が解消されませんが、貸主に損になるので、そのような同意は期待できないでしょう。
また、可能であれば、借主から賃貸借契約の解除と明渡しに関する権限につき委任を受けておくといいでしょう。
1-4 連帯保証人の地位が相続されてしまう
連帯保証人が死亡した場合、その責任は相続人に引き継がれる場合があります。これは、連帯保証人の責務が遺産と同様に相続されるためです。
相続人が連帯保証人の地位を引き継げば、借主が家賃を滞納していた場合や物件の原状回復費用を支払っていないような場合に、相続人がその負担を肩代わりするリスクが生じます。相続人にとって、予期せぬ経済的負担が発生しかねません。
このようなトラブルを回避するためには、連帯保証人が死亡した場合の対策をあらかじめ考えておくのが重要です。相続人は、連帯保証人の地位を引き継ぐのを避けるために、相続放棄を検討できます。
ただし、相続放棄を行うと、連帯保証人の責務だけでなく、ほかの遺産もすべて放棄する必要があります。
また、専門家に相談し、限定承認などの適切な法的手続を踏めば、トラブルを最小限に抑えられます。限定承認とは、相続によって得たプラスの遺産を限度として、マイナスの遺産も引き継ぐ方式です。
なお、令和2年4月1日以降の保証契約においては、相続人の責任は、連帯保証人死亡時の滞納額等に限定されるため、将来的な責任を負うことはありません。相続時に滞納がなければ、何も責任を負わずにすみます。
1-5 連帯保証人を途中でやめられない
連帯保証人の大きなトラブルとして、途中でその地位を辞められない件があります。連帯保証人は契約期間中、借主が義務を履行しない場合に備えて、常に責任を負っています。
そのため、連帯保証人としての責務が思いのほか大きくなった場合でも、自分の意思だけではその地位を辞められません。このような状況では、精神的および経済的な負担が増大し、連帯保証人の生活に大きな影響を与えるでしょう。
したがって、連帯保証人になる前に契約内容を十分に理解し、慎重な検討が欠かせません。なお、連帯保証人の地位が解消されるのは次のパターンしかありません。
・賃貸借契約が解除される
それまでの滞納や明渡しまでの損害賠償などの責任は継続します。
・賃貸人の同意
大家さんに同意をもらえば連帯保証人を辞めることができます。
連帯保証人が簡単に辞められない件や、やめられるケース、請求されたときの対処法などについては、以下の記事で詳しく取り上げています。そちらも、ぜひ参考にご覧ください。
1-6 そもそも勝手に連帯保証人にされてしまっている
賃貸契約において、勝手に連帯保証人にされてしまうケースは珍しくありません。たとえば、親や友人が本人の同意なく連帯保証人として名前を書いてしまった場合、突然請求書が届く場合があります。
このような場合、本人の知らないところで連帯保証人としての責務を負わされるため、大きなトラブルとなりえます。ただし法的には、本人の同意なしに結ばれた連帯保証契約は無効です。
それでも貸主には無効だと分からないので、実際には支払いを求められるケースもあり、迅速な対応が求められます。
このようなトラブルに対処するためには、まず法的に連帯保証契約が無効であるのを主張しましょう。連帯保証契約が本人の同意なしに結ばれた場合、すぐに専門家に相談し、法的な対策を講じる必要があります。
連帯保証契約が無効であるのを証明するために、署名や契約書の確認、証拠の収集が必要です。証拠を集めたうえで、専門家を通じて契約の無効を主張し、債権者に対して責務がないのを証明する手続を行いましょう。
1-7 連帯保証人になってほしいと頼まれて困ってしまう
親しい友人や家族から、連帯保証人になってほしいと頼まれるのは、非常に辛い状況です。連帯保証人になるのは重大な責任を伴い、借主が家賃を滞納した場合や損害賠償が発生した場合に、連帯保証人がその負担を肩代わりしなければならないリスクがあります。
そのため、関係が悪化するリスクを承知のうえで、毅然と断るのが賢明です。無理に引き受け、自分自身が経済的に困窮するリスクが高まるのは避けましょう。
連帯保証人になるのを断るためには、まずリスクを十分に理解し、それを相手に説明するのが大切です。具体的な責任やリスクを伝え、冷静に話し合えば、相手も理解してくれる可能性が高まります。
また、代替案として、家賃保証会社の利用を提案するのもひとつの方法です。家賃保証会社は、連帯保証人の代わりに保証を提供するサービスであり、これを利用すれば、関係を悪化させずに断れます。
なお、賃貸借契約における保証に関して、連帯保証人と保証会社のどちらを選ぶべきか、またどういうケースでは両方必要なのかについては、以下の記事で詳しく取り上げています。そちらも、ぜひ参考にご覧ください。
2章 賃貸契約の連帯保証人を断りたいときの対処法
賃貸契約の連帯保証人を頼まれるのは非常にプレッシャーがかかるものです。連帯保証人になるのは、借主が家賃を滞納した場合にその全額を肩代わりするリスクを伴います。
そのため、まずはリスクがあるから保証人になりたくない旨を正直に伝えるのが大切です。「連帯保証人になると、私自身の生活に大きな負担がかかる可能性があり、そのようなリスクは負えません」と説明しましょう。
また、一度連帯保証人になると、その地位の解除は非常に困難である件も伝える必要があります。契約が成立した後に連帯保証人を辞退するには、債権者(貸主)と借主の同意が必要であり、現実的には難しいです。
このような連帯保証人としてのリスクを十分に理解してもらえば、誤解を避けられます。そのうえで、ただ断るだけではなく、代替案を提示しましょう。
具体的には、前述の家賃保証会社の利用を勧めるのです。家賃保証会社は、借主が家賃を滞納した際に代わりに支払いを行う仕組みを提供しており、これにより連帯保証人のリスクを回避できます。
「家賃保証会社を利用すれば、連帯保証人を立てる必要がなくなります。具体的には、保証会社が家賃を保証するため、万が一滞納する状況があっても、私たちの関係を円満に保てますよ。」と提案するとよいでしょう。
なお、賃貸借契約における連帯保証人の解除方法や、特例および更新拒否については、以下の記事で詳しく取り上げています。そちらも、ぜひ参考にお読みください。
3章 連帯保証人になり滞納家賃や損害賠償費用を請求されたときの対処法
賃貸契約において、連帯保証人がもっともおそれる状況のひとつは、借主が家賃を滞納したり、物件に損害を与えた場合に、その費用を請求される事態です。連帯保証人としての責務は非常に重く、請求額が高額になるケースも少なくありません。
このような状況に直面した場合、適切な対処法を知っておくのが重要です。具体的な対処法としては、次の3つが挙げられます。
- 「賃貸借契約の解約に関する一切の権限と建物明け渡しに関する一切の権限」の委任を受けておく
- 債務整理する
- 求償権を行使して主債務者に請求する
これらの方法を理解したうえで実行すれば、連帯保証人としてのリスクを最小限に抑えられます。それぞれの方法を、詳しく見ていきましょう。
3-1 「賃貸借契約の解約に関する一切の権限と建物明け渡しに関する一切の権限」の委任を受けておく
賃貸借契約において、連帯保証人が借主の滞納家賃や損害賠償費用を請求された場合に有効な対策のひとつが、借主から「賃貸借契約の解約に関する一切の権限と建物明け渡しに関する一切の権限」の委任を受けておく方法です。
それにより、連帯保証人は借主が家賃を滞納した場合に迅速に契約を解約し、物件の明け渡しを求めることができます。さらに、この権限を確実に行使するためには、借主に委任の解除権を放棄させる条項と、委任事務の妨害を排除する条項を契約に含めましょう。
この対策により、連帯保証人は借主が家賃を滞納した場合でも、迅速に対処し損失を最小限に抑えられます。また、契約書に明確な条項を設ければ、法的に強固な立場を確保できます。
この方法は、借主と貸主との間のトラブルを未然に防ぐためにも有効です。専門家に相談し、適切な契約内容を策定しましょう。
3-2 債務整理する
債務整理は、連帯保証人が滞納家賃や損害賠償費用の請求を受けた場合の有効な対処法のひとつです。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産といった方法があります。
任意整理は、専門家である司法書士や弁護士を通じて債権者と交渉し、返済計画の見直しを行う方法です。この方法では、利息の減額や返済期間の延長が可能となり、負担を軽減できます。
個人再生は、裁判所を通じて債務を大幅に減額し、残りの債務を数年にわたって分割払いする計画を立てる方法です。個人再生は、一定の収入がある場合に適しており、住居を失わずに債務を整理できる利点があります。
自己破産は、すべての債務を免除してもらう代わりに、財産を清算する必要がある最終手段です。自己破産を選択すると、信用情報に破産記録が残り、将来的なクレジットやローンの利用が制限されるデメリットがあります。
債務整理のプロセスは、専門家のサポートを受けるのが賢明です。弁護士や司法書士は、適切なアドバイスを提供し、債務者の状況にもっとも適した解決策を見つける手助けをしてくれます。
連帯保証人としての責任を果たしつつ、自身の経済的な再建を図るためには、早期の相談と適切な手続が欠かせません。債務整理を通じて連帯保証人としての負担を軽減し、経済的な安定を取り戻せます。
債務整理の主な種類ごとの特徴やメリット、デメリットについては、以下の表にわかりやすくまとめてあります。
| 債務整理の種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
| 特徴 | 裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法 | 裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法 | 裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法 |
| メリット | ・手続が比較的簡単で費用が安い ・裁判所への申立て記録が残らない ・家族や勤務先に知られない | ・借金を大幅に減額できる ・住宅ローンや車ローンなどの財産を守れる ・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い | ・借金が全て免除される ・新しい生活をスタートできる |
| デメリット | ・減額できる金額は債権者との交渉次第 ・将来、再び借金問題に陥る可能性がある | ・裁判所への申立て記録が残る | ・裁判所への申立て記録が残る ・官報に永久に掲載される ・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない ・一定期間、就業制限を受ける |
| 適したケース | ・債務額が大きくなく、将来的に返済できる見込みがある場合 ・任意整理の詳細・解決事例はコチラ ↓ 借金をなくせる任意整理とは?メリット・デメリットや向いている人 任意整理の経験談・解決事例 | ・一定収入はあるが債務額が大きく、任意整理では難しい場合 ・個人再生の詳細・解決事例はコチラ ↓ 小規模個人再生とは|給与所得者再生との違いやメリット・デメリット 個人再生の経験談・解決事例 | ・債務額が非常に大きく、他の方法では返済が難しい場合 ・自己破産の詳細・解決事例はコチラ ↓ 自己破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れを徹底解説 自己破産の経験談・解決事例 |
債務整理の種類と生活への影響に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
以下の返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理】を使えば、借金問題の解決のために債務整理を行った場合に、借金がどれくらい減るのかの目安がわかります。
返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理 】|大阪債務整理・自己破産相談センター
連帯保証人になったために借金問題を抱えてしまい、自力返済が難しくなってお困りのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
3-3 求償権を行使して主債務者に請求する
求償権の行使は、連帯保証人が主債務者に代わって滞納家賃や損害賠償費用を支払った後に、その支払額を主債務者に請求する権利です。連帯保証人は、この求償権を行使すれば、自身が支払った費用を回収できます。
求償権を行使するには、法的手続を通じて主債務者に対して請求を行う必要があります。これには、弁護士を通じて裁判所に訴訟を起こすことが一般的ですが、費用や時間がかかるうえに、主債務者の資産状況によっては回収が困難です。
また、主債務者との関係性が悪化するリスクも考慮しなければなりません。加えて、実際には主債務者に返済能力がないから連帯保証人に請求が来ているのであって、この方法が効果を持つのは、現実的にはまれです。
なお参考として、賃貸契約の連帯保証人が生活保護になった場合、どうすべきかについては以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
連帯保証人としての責務は非常に重く、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。借主が家賃を滞納した場合や、物件に損害を与えた場合に連帯保証人が請求されるのは、一般的なトラブルのひとつです。
また、連帯保証人が契約解除を希望しても、簡単にその地位の放棄はできません。さらに、連帯保証人の地位が相続されると、相続人にとって予期せぬ負担が生じる場合もあります。
これらのトラブルに対処するためには、事前に契約内容を十分に確認し、必要な準備を行うのが重要です。たとえば、家賃保証会社の利用や、契約書に明確な条項を設けておけば、リスクを軽減できます。
また、トラブルが発生した場合には、専門家のアドバイスを受けながらの迅速な対応が求められます。ここでご紹介した情報を参考に、連帯保証人としてのリスクを理解し、適切な対処法を知っておきましょう。
連帯保証人になってしまい、延滞の請求が来てお困りのみなさんは、ほかにも借金があって自力返済が難しいなら、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!