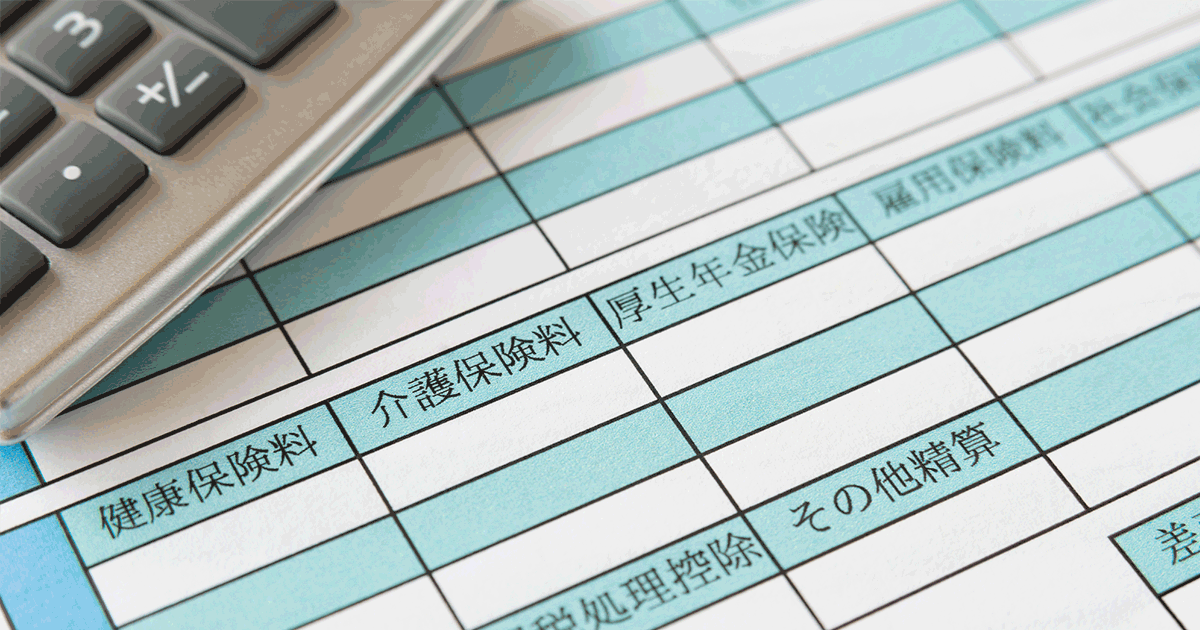この記事は約 11 分で読めます。
- 介護保険料を滞納すると最終的に差押えになる
- 介護保険料が1年間未納だと介護サービスの費用を10割払う必要がある
- 払えない場合は早めにお住まいの市区町村に相談をするのがおすすめ
- 介護保険料を滞納したまま死亡すると相続人が支払う必要がある
介護保険料とは、介護サービスを利用するためにかかる費用を国民で負担する制度です。介護保険料は、満40歳に達したときに徴収が開始され、介護保険料の支払いが義務となります。
そのため、介護保険料の滞納が続くと差押えになるので注意が必要です。
この記事では、介護保険料の滞納から差押えになるまでの流れと介護保険料が払えない場合の対処法を解説します。介護保険料の支払いが苦しい方は、参考にしてください。
目次 ▼
1章 介護保険料を滞納すると差押えになる!
介護保険料は、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)および65歳以上の方(第1号被保険者)が負担する必要があります。地域によっても異なりますが、毎月約6,000円の支払いが目安です。
介護保険料は、国民全体が安心して介護サービスを利用するためにも支払い義務があります。そのため、滞納すると最終的には財産が差押えになるので注意しましょう。差押えになると生活に大きな影響を与えるため、放置しないことが大切です。
では、介護保険料の滞納から差押えになるまでの流れを解説します。
STEP1 督促手数料と延滞金が発生する
納期限を過ぎても支払いができない場合は、督促状や催告書が届きます。督促状は納付期限を過ぎてから20日以内に送付されるため、督促状に記載されている納期限内に支払わなければいけません。
同時に、督促手数料と延滞金が発生するため、滞納している介護保険料に追加で督促手数料と延滞金を支払う必要があります。
督促手数料とは、督促状にかかるお金のことで一通につき70~100円がかかるので注意しましょう。延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて算出され、翌日~1ヶ月未満の場合は年4.3%~14.6%増加、1ヶ月以上の場合は年14.6%増加になります。
STEP2 支払い方法が変わる
介護保険料が1年間未納の場合は、介護保険料の支払い方法が変更になります。
通常であれば、介護サービスの利用は1割から3割負担が一般的ですが、全額(10割)支払わなくてはいけません。申請することで、負担した費用の9割〜7割が払い戻しされます。
例えば、介護サービスの費用が10万円だった場合は、一時的とはいえ10万円全額負担になるので注意しましょう。そのため、未納になっている介護保険料を払い切るほうが安く済む可能性もあります。
STEP3 介護保険給付が一時的に差止めになる
介護保険料が1年6か月間未納の場合は、介護保険給付が一時的に差止めになります。
また、介護サービスを利用する場合は全額支払う必要があるだけではなく、滞納している介護保険料が納付されるまで払い戻しされないので注意しましょう。
滞納を続けている場合は、全額支払った分から滞納している介護保険料に充てられるケースもあります。
STEP4 自己負担が3割に引き上げられる
介護保険料が2年以上未納の場合は、介護保険料の未納期間に応じて自己負担が3割〜4割に引き上げられます。また、高額介護サービスを利用する場合の支給が受けられなくなるので注意しましょう。
例えば、介護保険料を利用して毎月の施設費が20万の老人ホームへ入所していた場合、1割負担であれば2万円の自己負担で済みますが、3割になると6万円の自己負担になるため一気に高額になります。
STEP5 財産が差押えになる
督促状の納期限を無視し続け、介護保険料の未納が続くと財産が差押えになります。介護保険料は通常の借金と異なり、裁判所を通さなくても差押えの手続きができるため、予告なしで差押えに発展するケースも少なくありません。
差押えになると、財産や預金口座のお金を強制的に回収して滞納保険料を徴収します。生活費が差押えになり生活ができなくなる可能性もあるため、払えない場合は役所に早めに相談しましょう。
2章 介護保険料を滞納する原因は?
介護保険料を滞納してしまう原因は、経済的な事情が関係していることがほとんどです。特に、生活費や医療費などの支出が重なると、どうしても介護保険料の支払いが後回しになりがちな方も少なくありません。
ここからは、介護保険料を滞納する原因と滞納を防ぐためのポイントを紹介します。
2-1 介護保険料の値上げで支払いが厳しくなった
高齢化により、介護サービスを必要とする人が増加しているため、介護保険制度を支える保険料も年々引き上げられています。年金生活者や収入が少ない世帯にとっては、支出が増加することで家計の負担が重くなり、介護保険料の支払いが厳しくなるケースが多いです。
介護保険料の負担が増えると、介護保険料の滞納の原因につながるため、支払いが厳しい場合は役所に相談して減額や分割納付などの相談をしましょう。
2-2 支払いできるお金がないから
生活費や医療費などが高額になり、支払いできるお金がないケースも多いです。特に、病気で入院を繰り返していたり年金収入のみで生活していたりと、経済的に厳しい状況の場合は支払う意思があっても、現実的に不可能な場合があります。
経済的な理由による滞納は深刻化しやすいため、役所の相談窓口を利用して適切な支援策がないか相談しましょう。
2-3 未納に気付いていないから
振替や自動引き落としの手続きをしていない場合、支払い忘れで未納状態になっているケースが考えられます。特に、高齢者のなかには、請求書や納付書の管理が難しく、支払い状況を把握できていない方も少なくありません。
わざとではないにせよ、未納になってしまうと延滞金が発生するため、特別徴収の手続きをするか必要に応じて家族や専門家にサポートを依頼するようにしましょう。
3章 介護保険料が払えない場合の対処法
介護保険料が払えないからと滞納し続けると、延滞金の発生や財産の差押えといった厳しい措置が取られる可能性があります。
もし介護保険料が払えない場合は、お住まいの市区町村へ相談して支払い負担を軽減してもらえないか相談しましょう。市区町村によっても異なりますが、介護保険課や納税課、保健福祉センターなどが担当しているケースが多いです。
では、介護保険料が払えないときに取るべき対処法を見ていきましょう。
3-1 分割納付の相談をする
滞納していた介護保険料の一括納付が難しい場合は、分割納付の相談をしましょう。事情によっては保険料の分割納付や減免などが認められるケースがあります。
相談するときは、なぜ支払いが難しいのかを具体的に説明して、確実に支払う意思を見せるようにしましょう。また、いくらなら支払えるのか具体的に提示することで、柔軟に対応してくれる可能性もあります。
3-2 減額・免除の手続きをする
災害により損害を受けた場合や長期間の入院で働けなくなった場合など、支払いが難しい事情がある場合は減額・免除の手続きを受けられる可能性があります。
ただし、減額や免除の基準は市区町村によって異なるため、自分のケースが当てはまるかどうかはお住まいの相談窓口に確認してみましょう。
3-3 個別減額制度を利用する
介護保険料の負担額は収入によって決まるので、世帯収入が少ない場合は介護保険料を減額できる可能性があります。ただし、減額をするには条件を満たしていなければいけません。
預貯金や前年の収入、財産の有無などが条件になっているケースが多く、地区町村によっても基準が異なるため、まずは相談してみるのをおすすめします。
3-4 各市区町村の介護保険窓口に相談する
既に介護保険料を滞納している場合は、できるだけ早く市区町村の介護保険窓口に相談しましょう。市区町村によっては、分割納付や個別減額制度のほかにも独自の救済制度を設けているケースもあります。
払えないからと滞納を続けていると、督促手数料と延滞金によってさらに総支払額が増えてしまいます。時間が経つほど支払いできなくなるため、督促状が届いた時点で相談するのがよいでしょう。
3-5 生活保護の申請をする
今後の収入の見込みがない場合は生活保護を検討するのも一つの方法です。生活保護受給者になると、介護保険料や介護サービス料は介護扶助費として支給されるので支払い負担がなくなります。
生活保護の受給に抵抗を感じている高齢者も多いですが、滞納を続けると介護保険サービスが全額負担になったり差押えになったりとリスクが大きいため、生活保護も選択肢として考えておきましょう。
4章 介護保険料を滞納したまま死亡するとどうなる?
介護保険料を滞納したまま死亡すると、相続によって介護保険料の債務も引き継がれます。そのため、介護保険料を滞納した分は相続人が支払わなければいけません。
死亡により介護保険料額が変更された場合は、死亡日の翌日の前月までを月割りで算定します。 もし、介護保険料を納めすぎていた場合は相続人に還付されますが、不足していた場合は相続人が不足分を納付しなくてはいけません。
介護保険料を滞納したまま死亡すると、相続人に影響が及ぶので注意しましょう。
4-1 相続放棄をすると支払いが不要になる
介護保険料の滞納分は相続されますが、相続人が相続放棄をすると介護保険料の支払い義務は免除されます。相続放棄をすると、故人の財産や負債を一切引き継げませんが、介護保険料の未納分も支払う必要がなくなります。
ただし、介護保険料が非常に高額になっているケースは少なく、ほかの財産で返済できる可能性もあるでしょう。相続放棄をしたほうがよいかは、専門家に相談して一緒に進めるのがおすすめです。
また、相続放棄をする場合でも、家庭裁判所での手続きが必要なため専門家に依頼するようにしましょう。
5章 借金がある場合は借金問題を優先的に解決しよう
借金の返済が原因で、介護保険料の支払いができない場合は借金問題を優先的に解決しましょう。借金は利息によって負担が増え続けるため、放置すると生活に大きな影響を及ぼします。
借金問題が解決すると精神的な負担が軽減されるので、税金や保険料などの必要な支払いに集中できるでしょう。
債務整理は、大きく分けて3種類の方法があります。それぞれ特徴が異なるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら自分に合った方法を確認しましょう。
| 債務整理の種類 | 手続きの方法 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 任意整理 | 利息や手数料など元金以外の支払いをカットする手続き | 借金の返済が長期化して利息が膨らんでしまった人 債務整理したくない借金がある人 |
| 個人再生 | 借金そのものを大幅にカットして完済を目指す手続き | 借金の総額が大きい人 家や車など失いたくない財産がある人 |
| 自己破産 | 借金自体を免除して支払い義務をなくす手続き | 完済の目処が立たず返済不能に陥った人 経済的な事情で返済ができない人 |
5-1 介護保険料は債務整理では解決しない
介護保険料の滞納分は、債務整理で減額や免除にならないので注意が必要です。介護保険料は税金と同様に公的な支払いのため、債務整理の対象にはならず支払い義務が残ります。
そのため、介護保険料の滞納分は債務整理とは別に対応しなければいけません。そのまま放置してしまうと差押えになる可能性もあるため、介護保険料の支払いを解決したい場合は各市区町村に相談しましょう。
6章 介護保険料を滞納するのは危険!早めに窓口に相談しよう
介護保険料の滞納を続けると、督促手数料と延滞金が増えるだけでなく、財産の差押えなどの厳しい措置が取られる可能性があります。介護保険料の支払いが難しいと感じたら、一人で抱え込まずに市区町村の窓口に分納や減額などの相談をしましょう。
いざというときに介護サービスを利用しやすくするためにも、介護保険料を滞納しないことが大切です。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ