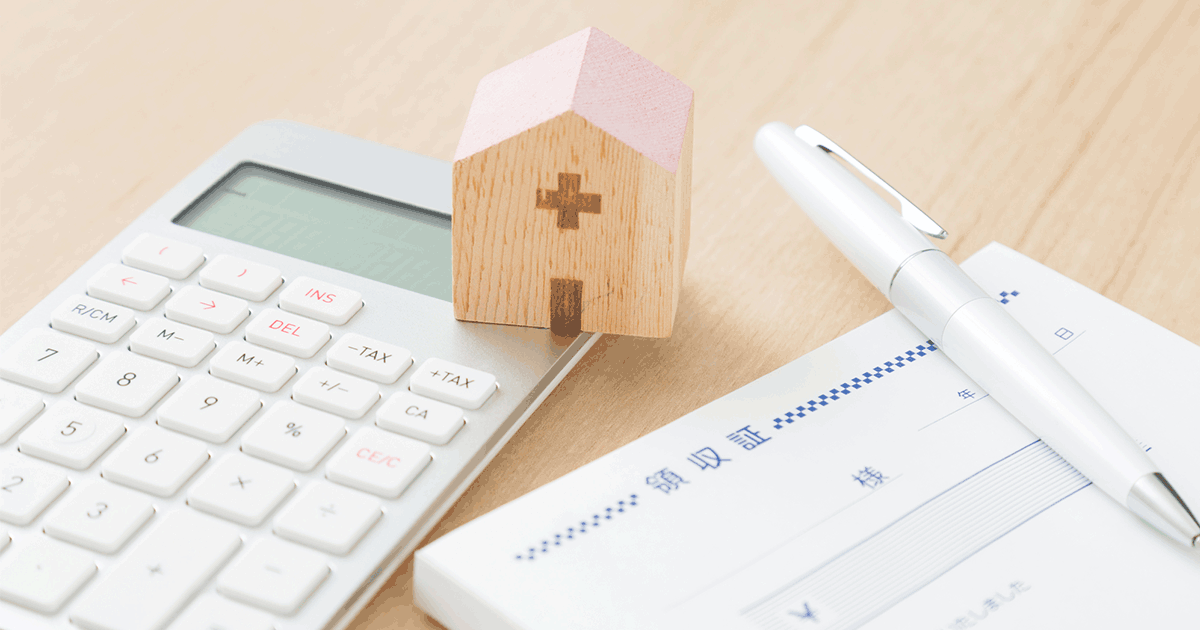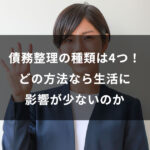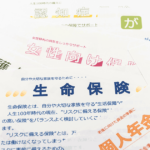この記事は約 16 分で読めます。
- 病院代を払えないときの対処法
- 病院代を払えないときに受けられる支援
- 滞納している病院代も債務整理できること
医療費が高額で払えない状況に陥ったとき、多くの人は途方に暮れるかもしれません。しかし、適切な対処法を知っていれば、その困難を乗り越える手助けとなります。
今回の記事では、病院代を支払うための具体的な方法や、支払いが難しい場合に利用できる公的支援制度について詳しく解説します。また、滞納している病院代も債務整理の対象となる件も見ていきましょう。
ここでご紹介する、自身や家族の健康を守るための医療費の支払いに関する有益な情報を参考に、困ったときに頼れる手段を知り、安心して治療を受けるための準備を整えましょう。
目次 ▼
1章 病院代を払えないときの対処法
治療を受けたものの、お金が足らなくて病院代を払えないときの主な対処法を挙げると、次の6項目が挙げられます。
- クレジットカードで払う
- 医療ローンを利用して支払う
- 家族や知人に相談する
- 病院に後払い・分割払いの相談をする
- クレジットカードローン=キャッシングを利用して現金を用意する
- 医療保険の給付金・保険金を申請する
それぞれの対処法の内容を詳しく見ていきましょう。
1-1 クレジットカードで払う
病院代をクレジットカードで支払うのは、急な出費にも対応できる便利な方法です。特に高額な医療費が発生した場合、分割払いやリボ払いの利用で、月々の支払い負担を軽減できます。
多くの病院では主要なクレジットカードが利用可能であり、受付や公式サイトで対応ブランドを確認できます。クレジットカードの利用で、手持ちの現金が不足していても安心して医療サービスを受けられます。また、ポイントが貯まるのもメリットのひとつです。
なお、クレジットカードで病院代を支払ったものの、請求月にその請求額が支払えなくなった場合や、支払いが遅れる場合の対処法については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、参考にご覧ください。
1-2 医療ローンを利用して支払う
医療ローンの利用で、医療費の支払いを長期にわたる分割払いが可能です。医療ローンは、医療費の支払いに特化したローンです。病院やクリニックの治療費、入院費、検査費用、出産費用、歯列矯正費用など、幅広い医療費に利用できます。
医療ローンの特徴
- 目的別ローン: 医療費以外の用途には利用できない
- 審査: 審査あり。一般的に銀行系の医療ローンの方が審査基準が厳しい
- 金利: 銀行系と信販会社系で異なる。銀行系の方が金利が低いことが多い
- 担保・保証人: 不要なものが多い
医療ローンのメリット
- 高額な医療費を分割払いできる:一括で支払うのが難しい高額な医療費でも、分割払いにすることで家計への負担を軽減できる:金利が比較的低い: 他のローンと比較して金利が低いことが多い
- 手続きが比較的簡単::病院によっては、その場で申し込みできる場合もある
医療ローンのデメリット
- 利息が発生する:借入期間が長くなればなるほど、支払う利息も増える
- 返済義務がある:借りたお金は必ず返済する必要がある
- 審査に通らない場合がある:収入や信用状況によっては、審査に通らない場合がある
医療ローンの利用方法
医療ローンを利用するには、まず金融機関の窓口やホームページで申し込みます。申し込みに必要な書類は、金融機関によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
- 本人確認書類: 免許証、保険証など
- 収入証明書類: 給与明細書、源泉徴収票など
- 口座情報: 銀行口座の通帳やキャッシュカード
1-3 家族や知人に相談する
家族や知人に相談し、一時的に資金を借りるのもひとつの方法です。信頼できる人からの借入れは、金利や返済条件が柔軟であるため、金融機関からの借入れに比べて負担が少ない場合があります。
事前に返済計画を立て、誠実に対応し、信頼関係を保ちましょう。この方法は、ほかの方法が難しい場合に検討するとよいでしょう。なお、親しい間柄であっても、万が一のトラブルを避けるために借用書を作っておきましょう。
なお、身内での貸し借りが贈与税の対象とならないようにするための、借用書の書き方や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
1-4 病院に後払い・分割払いの相談をする
多くの場合、病院の窓口にて後払いまたは分割払いの相談を受けてくれるでしょう。一部の病院では、経済的な理由で支払いが困難な患者に対して、柔軟な支払いプランを提供しています。
事前に病院の会計窓口に相談し、具体的な支払い計画を立てれば、安心して医療サービスを受けられます。こうした支払いプランは、患者の負担軽減を目的としているため、積極的に活用するのが推奨されます。
1-5 クレジットカードローン=キャッシングを利用して現金を用意する
クレジットカードローンとは、クレジットカードに付帯されたキャッシング機能のことを指します。ATMやインターネットバンキングで、カードの利用枠内でお金を借りることが可能です。
なお、キャッシングの金利は比較的高くなります。クレジットカード会社や利用者属性によって異なりますが、一般的には年率15.0%~18.0%程度です。
キャッシングを利用して現金を用意するのもひとつの手段です。クレジットカードのキャッシング機能を使えば、ATMで簡単に現金を引き出せます。
ただし、キャッシングは金利が高いため、あくまでも緊急時の一時的な対応策として利用するのが望ましいです。計画的に返済するためにも、事前に利用限度額や金利条件を確認し、必要最低限の額を引き出すように心がけましょう。
なお、キャッシングの限度額の確認方法や増額・減額の方法については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、参考にご覧ください。
1-6 医療保険の給付金・保険金を申請する
民間の医療保険に加入している場合、給付金や保険金を申請すれば、医療費の負担を軽減できます。保険契約内容を確認し、該当する給付金や保険金がないかチェックしましょう。
申請には診断書や領収書などの書類が必要になるため、必要な書類を揃えて早めに手続を行いましょう。保険会社の窓口や公式サイトで詳細な手続方法を確認し、スムーズに申請を進めるようにしましょう。
なお、医療費が原因で自己破産はできるのかどうかや、支払いが難しいときの対処法ついては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
2章 病院代を払えないときに受けられる支援
経済状況が悪くて、病院代を払えない際に受けられる主な支援としては、次の9項目が挙げられます。
- 高額療養費制度
- 高額療養費貸付制度
- 健康保険限度額適用認定証
- 医療費控除
- 一部負担金減免制度
- 傷病手当金
- 無料低額診療事業
- 付加給付制度
- 生活保護
それぞれの支援の内容を、詳しく見ていきましょう。
2-1 高額療養費制度
高額療養費制度は、医療費が家計に重くのしかからないよう、1か月間の医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を支給する制度です。この制度の上限額は、年齢や所得に応じて異なります。
たとえば70歳未満で年収370万円〜770万円の場合、1か月の自己負担限度額は以下のとおりです。
1か月の自己負担限度額 = 80,100円 +(医療費-267,000円)× 1%
また、70歳以上の人や低所得者には特別な限度額が設定されており、外来のみの費用でも適用される場合があります。
この制度を利用するためには、医療機関や薬局で支払う際に「限度額適用認定証」を提示する必要があります。加えて、過去1年間に3回以上高額療養費制度を利用した場合、4回目以降は自己負担額がさらに引き下げられる「多数回該当」という仕組みもあります。
申請手続は、加入している公的医療保険に対して行い、診療を受けた翌月から2年間はさかのぼって申請が可能です。
2-2 高額療養費貸付制度
高額療養費貸付制度は、急な高額医療費の支払いが必要になった際に、一時的にその費用を貸し付ける制度です。これは、高額療養費制度の申請が承認され、還付されるまでの間に、医療機関への支払いが困難な場合に利用されます。
この貸付制度の利用で、経済的な負担を軽減し、安心して医療を受けられます。利用するためには、加入している医療保険の窓口に申請し、必要な書類を提出します。
高額療養費貸付制度の貸付は無利息であり、返済期限も高額療養費の還付を受けた時点で返済する仕組みとなっています。
つまり、貸付制度とはいえ事実上は、還付の時点まで立替えてもらえるので、この制度を活用すれば、医療費の支払いに困ることなく治療に専念できます。
2-3 健康保険限度額適用認定証
健康保険限度額適用認定証は、高額療養費制度を利用する際に、医療費の自己負担限度額をあらかじめ設定するための証明書です。これを提示すれば、医療機関や薬局での支払いを上限額までに抑えられ、負担を軽減できます。
たとえば、70歳未満の一般所得者の場合、自己負担限度額は以下のようになります。
自己負担限度額 = 80,100円 +(医療費 – 267,000円)× 1%
申請方法は、加入している健康保険組合や市町村の国民健康保険課に必要書類を提出します。限度額適用認定証の取得で、医療機関での支払いがスムーズに進み、医療費の負担を減らせます。
2-4 医療費控除
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得から控除できる制度です。この控除の利用で、所得税の負担を軽減し、経済的な負担を和らげられます。
控除対象となる医療費は、自分自身や家族の治療費、薬代、通院費などが挙げられます。医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。申告の際には、医療費の領収書を保管し、申告書への添付が求められます。
また、控除額は「総所得金額の5%」または「10万円」のいずれか低い金額を超えた部分が対象となります。医療費控除は手間がかかりますが、高額な医療費を支払った場合に、税負担を軽減できます。
2-5 一部負担金減免制度
一部負担金減免制度は、経済的に困窮している世帯を対象に、医療費の自己負担額を減免する制度です。住民税非課税世帯や災害に遭った場合などに適用され、医療費の負担を軽減します。
この制度の利用で、必要な医療を受ける際の経済的負担を軽減できます。申請方法は、市町村の福祉事務所や医療保険組合に対して行います。
申請には、世帯の収入状況や経済的困窮の状況を証明する書類が必要です。この制度により、医療を受けるためのハードルを下げ、安心して治療を続けられます。
2-6 傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがで働けなくなった場合に、所得を補償するための制度です。健康保険に加入している被保険者が対象で、支給額は標準報酬日額の2/3が支給されます。この手当金により、治療中の収入減少を補えます。
申請方法は、加入している健康保険組合に必要書類を提出します。申請には、医師の診断書や事業主の証明が必要です。傷病手当金は最長で1年6か月支給され、経済的な安心感を持ちながら治療に専念できます。
なお、対象となる病気や怪我が業務上で起こった者である場合は、労災保険の休業補償給付が受けられます。
支給額には以下のとおり差があります。
- 傷病手当金:標準報酬日額の約60%
- 労災保険の休業補償給付:標準報酬日額の約80%
両方を同じ案件で受けるのはできませんので、状況に応じて適切な申請をしましょう。
2-7 無料低額診療事業
無料低額診療事業は、経済的に困窮している方を対象に、無料または低額で医療サービスを提供する制度です。全国の社会福祉法人や医療機関で実施されています。
無料低額診療事業の対象者
- 住民税非課税世帯の方などで医療費の支払いにお困りの方
- 生活保護受給中の方、またはこれに準ずる生計困難世帯の方
- その他、長期にわたる病気やけが、失業などで医療費の支払いが難しい方
無料低額診療事業の内容
医療機関が、診察費や検査費、薬剤費などを無料または低額で提供します。具体的な料金は、医療機関や患者さんの状況によって異なるものです。すべての医療機関が実施しているわけではありませんので、事前に実施医療機関を確認する必要があります。
無料低額診療事業の利用方法
実施医療機関に直接申し込みます。必要な書類は、医療機関によって異なりますが、一般的には本人確認書類や所得証明書などが必要です。
利用するためには、対象となる医療機関に直接相談し、必要な手続を行いましょう。この制度を活用すれば、経済的な理由で医療を受けられない状況を改善できます。
2-8 付加給付制度
付加給付制度は、健康保険組合などが独自に設定している給付制度で、高額療養費制度ではカバーしきれない医療費の一部を補助するものです。加入している保険組合によって内容は異なりますが、自己負担額の軽減や追加の給付金が支給される場合があります。
利用するためには、加入している健康保険組合に申請し、必要な書類を提出します。この制度を活用すれば、医療費の負担をさらに軽減し、安心して治療を受けられます。付加給付制度の詳細は、加入している保険組合の案内を確認しましょう。
2-9 生活保護
生活保護は、生活に困窮し、ほかの手段では最低限の生活を維持できない場合に利用できる公的支援制度です。日本国憲法第25条にもとづき、すべての国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を目的としています。
生活保護の適用を受けるためには、資産や収入などを申告し、必要な保護を受ける権利があるのを証明する必要があります。生活保護の申請は、居住地の福祉事務所で行い、申請者の経済状況や生活環境にもとづいて判断されます。
保護の内容には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助などが含まれており、特に医療扶助は医療費の全額が支給されるため、医療費の負担を大幅に軽減できます。この制度の利用で、生活困窮者も安心して必要な医療を受けられるのが特徴です。
なお、生活保護を受けていても自己破産できるのかどうかや、生活保護への影響ついては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください
3章 滞納している病院代も債務整理できる
債務整理は、積み重なって支払いが困難になった債務に対して、法的に整理する手続です。債務整理を行えば、債務の一部または全部を免除してもらえる可能性があります。
この債務整理の対象に、滞納している医療費・病院代も債務として含められます。債務整理には任意整理や個人再生、自己破産などの手続があり、比較的少額の債務であれば任意整理が向いています
任意整理では、依頼した専門家による病院との直接交渉を通じて、分割払いや減額の交渉を行えます。この方法により、滞納金の一部を減らし、無理のない返済計画が立てられるでしょう。
ほかにも借金があって債務総額が大きく、かといって自宅や車などの資産を失いたくない場合は、裁判所を介して行う個人再生があります。借金の大幅な減額が期待できます。
同様に負債総額が大きく、資産を処分して債務を全額免除してもらう自己破産も、選択肢のひとつですが、自己破産にはいくつかの制限(免責不許可事由)があります。
たとえば、病院代が故意に支払われなかった場合や、高額な治療費が過度な美容整形によるものであれば、浪費と判断されて免責が認められない可能性があります。
また、資産隠しや一部の債権者への優先的な返済などがあると問題視されるでしょう。債務整理を検討する際には、専門家のアドバイスを受け、適切な手続を選択するのが賢明です。
債務整理の主な種類ごとの特徴やメリット、デメリットについては、以下の表にわかりやすくまとめてあります。
| 債務整理の種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
| 特徴 | 裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法 | 裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法 | 裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法 |
| メリット | ・手続が比較的簡単で費用が安い ・裁判所への申立て記録が残らない ・家族や勤務先に知られない | ・借金を大幅に減額できる ・住宅ローンや車ローンなどの財産を守れる ・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い | ・借金が全て免除される ・新しい生活をスタートできる |
| デメリット | ・減額できる金額は債権者との交渉次第 ・将来、再び借金問題に陥る可能性がある | ・裁判所への申立て記録が残る | ・裁判所への申立て記録が残る ・官報に永久に掲載される ・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない ・一定期間、就業制限を受ける |
| 適したケース | ・債務額が大きくなく、将来的に返済できる見込みがある場合 ・任意整理の詳細・解決事例はコチラ ↓ 借金をなくせる任意整理とは?メリット・デメリットや向いている人 任意整理の経験談・解決事例 | ・一定収入はあるが債務額が大きく、任意整理では難しい場合 ・個人再生の詳細・解決事例はコチラ ↓ 小規模個人再生とは|給与所得者再生との違いやメリット・デメリット 個人再生の経験談・解決事例 | ・債務額が非常に大きく、他の方法では返済が難しい場合 ・自己破産の詳細・解決事例はコチラ ↓ 自己破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れを徹底解説 自己破産の経験談・解決事例 |
債務整理の種類と生活への影響に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
以下の返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理】を使えば、借金問題の解決のために債務整理を行った場合に、借金がどれくらい減るのかの目安がわかります。
返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理 】|大阪債務整理・自己破産相談センター
病院代やほかの借金がかさんで、自力返済が難しくなりお困りのみなさんは、新たに借入をせずに解決する方法を検討しましょう。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
まとめ
病院代を支払えない場合には、さまざまな対処法があります。クレジットカードや医療ローンの利用や、家族や知人への相談、病院への後払い・分割払いの相談などが考えられます。
また、キャッシングを利用して現金を用意したり、医療保険の給付金・保険金を申請したりするのも有効な手段です。これらの方法を駆使すれば、急な医療費の負担を軽減し、適切な治療を受けるためのサポートを得られます。
なお、病院代が高額で支払いが難しい場合には、公的支援制度の活用も検討しましょう。
高額療養費制度や高額療養費貸付制度、健康保険限度額適用認定証、医療費控除、一部負担金減免制度、傷病手当金、無料低額診療事業、付加給付制度、生活保護など、多岐にわたる支援が提供されています。
また、滞納している病院代も債務整理の対象に含めて、負担を軽減し、再建の道を開けます。適切な支援を受け、経済的な不安を解消し、健康を守るための具体的な手立てを講じることが大切です。
医療費・病院代などを含む借金問題で困っている方は、早めにこれらの手段を検討し、適切なアクションを起こす姿勢が望まれます。
ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ