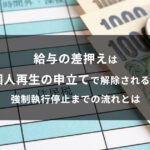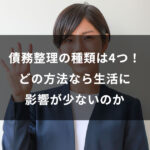この記事は約 14 分で読めます。
- 差押えの対象となる財産
- 差押えされる財産がない場合の扱い
- 差押え回避のためにすべきこと
差押えとは、借金や税金などの支払いを滞納している人に対して、 財産を勝手に処分できないようにする法的な手続です。 滞納した債務を回収するための手段のひとつであり、 裁判所の命令にもとづいて行われます。
差押えが行われるのは、以下のような場合です。
- 消費者金融や住宅ローンなどの融資の返済を滞納している場合
- クレジットカードの支払いを滞納している場合
- 税金を滞納している場合
- 国民健康保険料を滞納している場合
- 慰謝料などの支払いを滞納している場合
借金の返済が滞った場合、債権者は債務者の財産を差押えできますが、すべての財産が対象になるわけではありません。差押えできない財産、いわゆる差押禁止財産は、法律で保護されており、生活に必要な最低限の財産が含まれます。
また、財産がない場合、強制執行は行われませんが、それは一時的なものです。債権者が再度財産を探し出して、差押えを試みることもあります。
今回の記事では、差押えできない財産の具体例とその背景、差押えされる財産などついて見ていきましょう。加えて、差押えを回避するための具体的な方法として、債務整理などについても解説します。
目次 ▼
1章 差押えできないもの(差押禁止財産)
差押えをできない対象は、差押禁止財産と呼ばれます。主なものを挙げると、以下のとおりです。
- 生活に不可欠な動産
- 手取り給与の一部
- 現金の一部
- 年金受給権
- 生活保護給付金
- 児童手当
- 業務に必要な道具
- 宗教的な物品
- 身体の補助器具
- 生活に必要な書類や印鑑
それぞれを補足しておきましょう。
1-1 生活に不可欠な動産
差押禁止動産には、日常生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用品、畳および建具が含まれます。また、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、テレビなどの家電も対象です。
これらは、債務者の生活を維持するために必要不可欠とされているため、差押えから保護されています。
1-2 手取り給与の一部
給料の差押えには制限があり、手取り給与の4分の3は差押えが禁止されています。ただし、手取り給与が44万円を超える場合は、33万円を超える部分のすべてが差押えの対象です。
特定の債権(養育費など)の場合は、差押禁止割合が2分の1に引き下げられることもあります。
1-3 現金の一部
債務者が所持する現金についても差押禁止規定があります。具体的には、66万円以下の現金は差押えから保護されます。これは、債務者の生活費として必要な額を確保するための措置です。
1-4 年金受給権
国民年金、厚生年金などの年金受給権も差押禁止財産に含まれます。年金は、債務者の生活保障のために支給されるものであり、差押えは認められていません。
1-5 生活保護給付金
生活保護法にもとづく給付金も、差押えの対象外です。生活保護は、最低限の生活を保障するための支援であり、差押えはできません。
1-6 児童手当
児童手当も差押禁止財産です。児童手当は子供の養育費として支給されるものであり、差押えによって家庭の生活に悪影響を及ぼすのを防ぐための措置です。
1-7 業務に必要な道具
債務者が仕事や学業で使用するために必要な道具や器具も差押えできません。たとえば、農業従事者の農具や漁業従事者の漁具、学業用の書籍や器具などがこれに該当します。
1-8 宗教的な物品
仏像や位牌、礼拝や祭祀に必要な物品も差押禁止財産に含まれます。これらは宗教的な信仰に関わる重要な物品であり、差押えから保護されるべきとされています。
1-9 身体の補助器具
義手や義足、車いす、補聴器などの身体の補助器具も差押禁止財産です。これらは、債務者が日常生活を送るために必要不可欠なものです。
1-10 生活に必要な書類や印鑑
実印や職業に必要な印鑑、債務者の生活に必要な系譜、日記、商業帳簿なども差押えから保護されます。
上記の差押禁止財産は、債務者の最低限の生活を守るために設けられたものであり、差押えによって生活が立ち行かなくなるのを防ぐための重要な制度です。差押えのリスクがある場合は、事前にこれらの情報を把握し、適切な対策を講じましょう。
なお、差押えを解除するための手続とはどういうものか、その方法や期限について、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
2章 差押えされる財産
差押えされる主な財産を挙げると、以下のとおりです。
- 給料
- 預貯金
- 換金できる財産
- 不動産
それぞれを確認しましょう。
2-1 給料
給料の差押えは、手取り額の4分の1までが差押えの対象です。ただし、手取り額が44万円を超える場合には、33万円を超える部分が差押えの対象になります。特定の債権(例:養育費)については、手取り額の2分の1まで差押え可能です。
なお、給与の差押えが原因で会社をクビになるのは違法であることや、不当解雇時の対処法について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
また、給与の差押えは個人再生の申立てで解除されるかどうかや、強制執行停止までの流れについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
2-2 預貯金
金融機関の口座にある預貯金は、差押命令が裁判所から銀行に通知されることで差押えされます。この手続により、預金口座が凍結され、債務者は預金を引き出せなくなります。
2-3 換金できる財産
換金できる財産とは、宝石、貴金属、車両などです。これらの財産は、市場価値があり、容易に売却して現金化できるため、差押えの対象となります。競売などで売却され、売却代金が債権者に分配されます。
なお、差押えから競売までの流れや、競売にかけられないための対策について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
2-4 不動産
不動産の差押えは、土地や建物などの高価な財産が対象です。差押えられた不動産は競売にかけられ、売却代金が差押債権者に分配されます。
ただし、差押えを申し立てた債権者よりも優先する住宅ローンの抵当権などが付いており、当該債権者への配当が望めない場合は「無剰余取消し」として手続が中止されるケースもあります。
3章 差押えされる財産がないとどうなる?
借金を返済できない場合、債務者は債権者に財産を差し押さえられます。しかし、差し押さえるべき財産がない場合はどうなるのでしょうか。
この状況は、債務者だけでなく、連帯保証人にも影響を及ぼす可能性があります。差押えされる財産がない場合、一時的に強制執行は行われませんが、これは永続的な解決策ではありません。
債権者は債務者の財産状況を再調査し、後日再び強制執行を行えます。さらに、連帯保証人がいる場合、債務者の代わりに保証人の財産が差し押さえられることもあります。
この章では、差し押さえられる財産がない場合の具体的なシナリオと、それに伴うリスクについて詳しく説明します。
3-1 強制執行は行われない
差押え可能な財産がない場合、強制執行はひとまず行われません。これは、債権者が裁判所に対し、債務者の財産を差し押さえるための手続を進めても、対象となる財産そのものが存在しないからです。
この状況では、債務者は一時的に財産を守れますが、これは根本的な解決策ではありません。強制執行が一度行われなくても、債権者は財産の再調査を行い、将来的に債務者が財産を取得した場合に再度差押えを行えます。
一時的に強制執行が行われない状態を「空振り」と呼びますが、これは債務の消滅を意味するものではありません。債権者は債務名義を持ち続け、適切な財産を発見次第、再度差押えを実行できます。
債務者が再就職して収入を得たり、新たに財産を取得したりした場合、再び差押えのリスクが生じます。そのため、差し押さえられる財産がないからといって安心せず、早期に債務整理や専門家への相談を行い、持続可能な解決策を検討しましょう。
3-2 何度も強制執行が行われるおそれがある
差押え可能な財産がない場合でも、強制執行が繰り返し行われるおそれがあります。債務者が一時的に無職で財産がない場合、再就職して収入を得たり、新たに財産を取得したりした時点で、再び差押えが行われる可能性があるでしょう。
債権者は債務名義を持ち続けているため、債務者の状況が変わるたびに再調査を試み、適切なタイミングで強制執行の申立を行います。そのため、借金の放置は問題を長引かせるだけであり、根本的な解決にはつながりません。
また、差押えが行われるたびに手続費用が発生し、債務額がさらに増加するリスクもあります。債務者が将来的に財産を取得する可能性がある場合、債権者は執拗に強制執行を繰り返すかもしれません。
これを防ぐためには、早期に債務整理や専門家への相談を行い、持続可能な返済計画を立てるのが重要です。専門家の助けを借れば、債務の減額や返済条件の緩和を実現し、強制執行のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
なお、強制執行や差押えの対象外となるものは何かについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
3-3 連帯保証人に請求がいくおそれがある
債務者自身に差押え可能な財産がない場合、債権者は連帯保証人に対して支払いを請求できます。連帯保証人は債務者と同等の立場で、債務を全額返済する義務を負っています。
そのため、債務者が財産を持っていない場合、債権者は連帯保証人の財産を差押えできます。連帯保証人が返済不能に陥った場合、その財産も差押えの対象となり、債務者の借金問題が連帯保証人に影響を及ぼす事態になるでしょう。
債務者が連帯保証人を巻き込まずに問題を解決するためには、早期に債務整理を行い、返済計画の見直が重要です。専門家のサポートを受ければ、連帯保証人への負担を軽減し、適切な対策を講じられます。
4章 差押え回避のためにすべきこと
差押えを回避するためには、早めに適切な対策を講じる必要があります。そのためには、専門家のアドバイスを受けるのが不可欠です。
債務者は自分の財産状況を把握し、専門家のサポートのもと、適切な手続を進めるのが賢明です。特に、債務整理や債権者との相談は効果的な方法といえるでしょう。この章では、債務整理と債権者に相談する方法について詳しく説明します。
4-1 債務整理
債務整理は、借金の返済負担を軽減するための法的手続です。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、それぞれの方法には異なるメリットとデメリットがあります。
任意整理は、債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続で、比較的短期間で解決できるのが特徴です。個人再生は、裁判所を通じて借金の一部を免除し、残りを計画的に返済する手続です。
自己破産は、すべての借金を免除してもらう手続ですが、財産の大部分を失い、信用情報に大きな影響を与えます。
債務整理を行う際には、裁判所からの通知が来た後では対処が難しくなるため、早めの対応が重要です。通知が来る前に、専門家に相談し、適切な手続を進めましょう。
債務整理を依頼すると、専門家が代理人となり、債権者からの督促を止められます。債務整理の主な種類ごとの特徴やメリット、デメリットについては、以下の表にわかりやすくまとめてあります。
| 債務整理の種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
| 特徴 | 裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法 | 裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法 | 裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法 |
| メリット | ・手続が比較的簡単で費用が安い ・裁判所への申立て記録が残らない ・家族や勤務先に知られない | ・借金を大幅に減額できる ・住宅ローンや車ローンなどの財産を守れる ・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い | ・借金が全て免除される ・新しい生活をスタートできる |
| デメリット | ・減額できる金額は債権者との交渉次第 ・将来、再び借金問題に陥る可能性がある | ・裁判所への申立て記録が残る | ・裁判所への申立て記録が残る ・官報に永久に掲載される ・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない ・一定期間、就業制限を受ける |
| 適したケース | ・債務額が大きくなく、将来的に返済できる見込みがある場合 ・任意整理の詳細・解決事例はコチラ ↓ 借金をなくせる任意整理とは?メリット・デメリットや向いている人 任意整理の経験談・解決事例 | ・一定収入はあるが債務額が大きく、任意整理では難しい場合 ・個人再生の詳細・解決事例はコチラ ↓ 小規模個人再生とは|給与所得者再生との違いやメリット・デメリット 個人再生の経験談・解決事例 | ・債務額が非常に大きく、他の方法では返済が難しい場合 ・自己破産の詳細・解決事例はコチラ ↓ 自己破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れを徹底解説 自己破産の経験談・解決事例 |
債務整理の種類と生活への影響に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
以下の返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理】を使えば、借金問題の解決のために債務整理を行った場合に、借金がどれくらい減るのかの目安がわかります。
返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理 】|大阪債務整理・自己破産相談センター
借金問題で不動産や給料を差押えされるかもしれない状態にあり、お悩みのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
4-2 債権者に相談する
債権者に相談するのは、差押えを回避するための有効な手段のひとつです。債務者が返済に困っている状況を正直に伝え、柔軟な返済計画を提案すれば、債権者も協力的になる場合があります。
債権者は返済の見込みが立つので、強制執行を避け、円満に問題を解決したいと考えるためです。具体的には、返済期間の延長や月々の返済額の減額、利息の減免などの交渉が考えられます。
債権者との交渉は、自分一人で行うのも可能ですが、専門家の助けを借りればより効果的に進められるでしょう。弁護士や司法書士などの専門家は、法的な知識と交渉力を持っており、債権者との間で有利な条件を引き出せます。
また、専門家のアドバイスを受ければ、無理のない返済計画を立てられます。早めに債権者に相談し、具体的な返済計画の協議により、差押えのリスクを最小限に抑えましょう。
まとめ
差押えの対象となるのは、債務者の給料、預貯金、換金可能な財産、不動産などです。これらは、債権者が法的手続により回収が許される財産であり、債務不履行が続くと差押えが執行されます。
とはいえ、66万円以下の現金や生活に必要不可欠な家財道具、3ヶ月分の食料・燃料、配偶者の結婚前の財産、仕事に必要な道具、信仰に関する物品などは、法律で保護されているため、差押えの対象外です。
差押えを回避するためには、債務整理や債権者との相談による返済計画の見直しが有効です。専門家に声をかけて早期に行動を起こし、差押えを回避して経済的な再建を図りましょう。
借金問題で不動産や給料を差押えされるかもしれない状態にあり、お悩みのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
差押えが想定されるほどの借金問題を抱えてお困りのみなさんは、新たに借入をせずに解決する方法を検討しましょう。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!