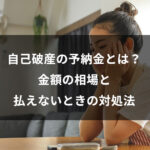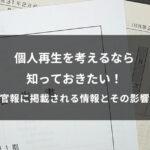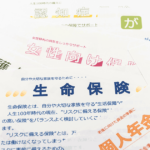この記事は約 14 分で読めます。
- 会社破産にかかる費用の内訳や相場
- 会社破産をする費用がない場合の対処法
- 会社破産は法テラスを利用できないこと
- 会社破産にかかる専門家への費用を抑える方法
会社破産を検討する際、そのためのお金がない場合も少なくありません。会社破産の手続にかかる費用は大きな負担となる場合があります。
特に、中小企業や個人事業主の場合、その費用をどのようにして捻出するかが大きな課題です。今回の記事では、会社破産に必要な費用の内訳と相場について詳しく解説し、費用を捻出するための具体的な対処法を紹介します。
さらに、法人破産にかかる専門家への費用を抑える方法についても触れ、破産手続をスムーズに進めるためのアドバイスを提供します。会社の経営が厳しくなり、会社破産を検討する際の参考にしてください。
目次 ▼
1章 会社破産にかかる費用の内訳・相場
会社破産を行う際には、多くの費用がかかります。破産手続において必要な費用の、内訳の理解が重要です。会社破産にかかる主な費用については、次の5項目が挙げられます。
- 予納金
- 申立手数料
- 郵便切手代
- 官報の掲載費用
- 専門家に支払う報酬
それぞれの内容と、相場を見ていきましょう。
なお、会社の再建ができない場合に選ぶ、会社破産(法人破産)とはどういうものか、廃業との違いなどを以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
1-1 予納金
予納金は、破産手続における主要な費用のひとつであり、破産管財人の報酬や手続に必要な諸費用を賄うために裁判所に納付する金額です。予納金は、破産手続を進めるための初期費用として欠かせません。
予納金の金額は、会社の規模や負債総額に応じて異なるものです。一般的には数十万円から数百万円に及ぶ場合があります。
予納金が不足している場合、破産手続が滞る可能性があります。そのため、予納金の準備は破産手続の初期段階で非常に重要です。
なお、自己破産を行う場合の予納金の相場と、払えないときの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
1-2 申立手数料
申立手数料は、破産手続を裁判所に申請する際に必要な費用です。これを支払うことで破産申立てが受理され、裁判所は破産手続を開始し、破産管財人を選任します。
申立手数料は、一般的には負債総額や会社の規模にかかわらず、数万円程度です。裁判所に提出する申立書とともに支払います。
1-3 郵便切手代
郵便は、破産手続における重要な伝達・連絡手段として使用される手段です。破産管財人や裁判所からの通知、債権者への連絡など、さまざまな場面で郵便が活用されます。
会社破産の手続における郵便切手代は、破産手続において関係者に通知を送るために必要な費用です。破産手続では、多くの関係者に対して通知を行う必要があり、そのための郵便費用が発生します。
この費用は通常、数千円から数万円程度であり、裁判所が指定する金額を支払います。
1-4 官報の掲載費用
官報の掲載費用は、破産手続を公示するために必要な費用です。官報掲載によって、すべての関係者に対する手続の透明性と公正性が保たれます。
この掲載費用は、数万円から数十万円程度であり、手続の初期段階に必要です。官報への掲載は、法的手続の一環として必須です。
破産手続が開始されると、その事実を広く知らせ、特にすべての債権者に対して破産手続の開始を知らせるために行われます。
なお、官報に掲載される情報とその影響については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。
1-5 専門家に支払う報酬
専門家に支払う報酬は、弁護士などの専門家に対して支払う費用です。破産手続は複雑であり、専門的な知識が必要となるため、専門家の支援を受けるのが一般的です。
専門家に支払う報酬は、手続の進行度合いや会社の規模によって異なりますが、数十万円から数百万円に及ぶ場合があります。
なお、会社の破産に要する費用や、充てる資金がない場合の対応策については、以下の記事でも詳しく取り上げています。そちらも併せて、参考にしてください。
2章 会社破産をするお金がない場合の6つの対処法
会社破産を検討する際に、最も頭を悩ませるのはその費用です。破産手続には多額の費用がかかり、その準備ができない場合、手続自体が進まない場合もあります。
しかし費用の準備が難しい場合でも、次に挙げる6つの対処法が存在します。
- 破産のタイミングを先延ばしにしない
- 法人代表者の個人資産を活用する
- 債権を回収する
- 法人財産を適正価格で処分する
- 専門家への依頼後に破産費用を積み立てる
- 予納金の分割払いを交渉する
個別に内容を見ていきましょう。
2-1 破産のタイミングを先延ばしにしない
破産手続のタイミングを先延ばしにすると、費用の問題を悪化させる可能性があります。破産手続が遅れると、債務が増加し、利息や遅延損害金が重なって負担がさらに大きくなるからです。
また、財産が減少してしまうと、破産費用の捻出がますます困難になる場合もあります。そのため、破産の必要性を感じたら、できるだけ早く行動するのが賢明です。
早期に破産手続を開始すれば、予納金や専門家報酬を計画的に準備する時間が確保できます。また、債権者との交渉や財産の適正処分を行うための時間も得られるでしょう。
さらに、早期の破産手続により法的な保護を受けられ、債権者からの取り立てのプレッシャーを軽減できます。このように、破産のタイミングを先延ばしにしないことは、手続を円滑に進めるための重要なポイントです。
なお、黒字経営なのに会社を廃業する場合については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、参考にご覧ください。
2-2 法人代表者の個人資産を活用する
法人破産の費用を捻出するために、法人代表者の個人資産の活用が考えられます。個人資産が多い場合は、それを現金化すれば、破産手続に必要な費用の確保が可能です。
たとえば、個人所有の不動産や車、貴金属などの売却で資金を調達できます。また、個人の預貯金や保険の解約返戻金を利用するのもひとつの手段です。
ただし、代表者自身も自己破産をする予定であれば、個人資産の直前処分とみなされ、免責が認められないおそれがあります。事前に専門家に相談したうえでの、慎重な検討が必要です。
なお、会社が倒産した場合、経営者は負債の返済義務を負うのかどうかや、責任が問われることについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。
2-3 債権を回収する
法人が持つ未回収の債権を積極的に回収して、破産費用を捻出する方法があります。債権回収は本来、会社の資金を増やすための重要な手段です。
特に、破産手続を控えた状況では、迅速な回収が求められます。弁護士に依頼して内容証明郵便を送付し、支払いを促すのが有効です。
債権回収の際には消滅時効に注意し、速やかに実行するのが重要です。債権の存在を証明し、裁判所を通じて債務者に支払い督促を行えば、時効はリセットされます。
また、場合によっては裁判も検討する価値があるでしょう。支払いを命じる判決が下されれば、強制執行によって、債務者の財産を差し押さえ、換価して債権を回収できます。
なお、会社の清算を検討する原因となりえる「債務超過」と、その解消年数や再生計画について、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
2-4 法人財産を適正価格で処分する
法人が所有する財産を適正価格で処分するのは、破産費用を捻出するための有効な手段です。破産手続前に、不要な資産を売却して現金を確保し、手続を進める資金とします。
不動産や車両、機械設備などの資産を市場価格で売却すれば、多額の資金が得られるでしょう。財産の処分にあたっては、適正な価格での売却が重要です。
急いで処分すると、低価格で売却されるリスクがあるため、事前に専門家に相談するのが賢明です。また、売却に伴う税金や手数料についても、考慮しておく必要があります。
なお、会社に解散や廃業を検討させる赤字経営の状態から、立て直しを目指すための対処法について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
2-5 専門家への依頼後に破産費用を積み立てる
破産手続に必要な費用を捻出するために、専門家に依頼してから破産費用を積み立てる方法があります。専門家の支援を受けながら、計画的に費用を準備すれば、無理なく手続を進められるでしょう。
たとえば、毎月一定額を積み立てて予納金や申立手数料を準備する方法です。この方法では、専門家が破産手続の進行に合わせて費用の管理を行います。
それにより、手続が遅延せずに進められます。また、専門家のサポートにより、債権者との交渉や財産の適正処分もスムーズに進行するでしょう。
専門家のサポートを受けながら破産費用を積み立てる方法は、安全かつ確実に手続を進めるための有効な手段です。
なお、会社が「廃業」という選択肢を選ぶ際に必要な費用と廃業までの手続きの流れについては、以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
2-6 予納金の分割払いを交渉する
破産手続において、予納金の分割払いについての裁判所との交渉も可能です。予納金は通常一括で支払う必要がありますが、分割払いが認められる場合もあります。
交渉により裁判所が承認すれば、分割払いが可能となります。一度に多額の資金を用意する負担を軽減し、破産手続を進められるでしょう。
予納金の分割払いを希望する場合は専門家と相談し、裁判所に対して現実的な支払計画を提出するのがポイントです。
なお、会社の解散や廃業を予期させる、いわゆる経営破綻の原因やその後の手続に関して、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
3章 【注意】会社破産は法テラスを利用できない
会社破産を検討している場合、法テラスは利用できないので、注意が必要です。法テラスは個人向けの法的支援を提供する機関であり、法人や会社の破産手続には適用されません。
法人破産の場合、1章で挙げたようなさまざまな費用がかかるので、相応の金額が必要となります。法テラスを利用できないため、2章で挙げたような方法で資金を調達しなければなりません。
法テラスの利用が制限されるなかで、法人破産を成功させるためには、計画的な資金準備と専門家の適切なサポートが重要です。破産手続を迅速かつ効率的に進めるために、事前に詳細な費用見積もりを行い、必要な資金の確保が欠かせません。
特に、中小企業や個人事業主の場合、費用負担が大きな課題となります。そのため、専門家への早期の相談と適切な対策が必要です。
なお、法テラスの審査期間や利用条件については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
4章 法人破産にかかる専門家への費用を抑える方法
法人破産を進める際には、弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。しかし、その費用が高額になる場合も少なくありません。
そのため、法人破産にかかる専門家への費用を抑えるための努力が必要です。主な方法としては、次の2つが挙げられます。
- 着手金無料の事務所に相談する
- 費用の分割払いを交渉する
これらの方法を活用すれば、法人破産にかかる費用を抑え、スムーズに手続を進められます。それぞれの内容を見ていきましょう。
4-1 着手金無料の事務所に相談する
法人破産を進める際、法律事務所の選び方が非常に重要です。特に費用を抑えたい場合は、着手金が無料の事務所に相談することを検討しましょう。
着手金無料の法律事務所では、手続が完了した後に報酬が発生するため、初期費用の負担を大幅に軽減できます。それにより、資金繰りが厳しい状況でも専門家のサポートを受けることが可能です。
また、法律事務所によっては初回相談が無料で提供されている場合もあります。初回無料相談を活用し、複数の事務所で見積もりを取れば、費用対効果の高い法律事務所を選べます。
また、相談を通じて、弁護士の対応や信頼性を確認することも重要です。着手金無料の事務所を選べば、コストを抑えつつ、適切な法的サポートが受けられるでしょう。
なお、会社破産(法人破産)で経営者個人が連帯保証している場合の返済義務については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
4-2 費用の分割払いを交渉する
法人破産に必要な費用を一度に支払うことが難しい場合は、法律士事務所に分割払いを交渉する方法がおすすめです。多くの法律事務所では、依頼主の経済状況に応じて柔軟な支払い方法を提供しています。
分割払いを利用すれば、一度に大きな金額を準備する負担を軽減し、破産手続をスムーズに進められるでしょう。
分割払いを希望する場合は、専門家と相談しながら、詳細な支払い計画を立てることが重要です。具体的な支払いスケジュールを作成し、双方が合意することで、手続が円滑に進みます。
まとめ
会社破産をする際の費用は、予納金、申立手数料、郵便切手代、官報の掲載費用、そして専門家に支払う報酬など多岐にわたります。これらの費用は、会社の規模や負債総額によって異なるため、事前に正確な見積もりを立てるのが重要です。
また、破産のタイミングを先延ばしにせず、法人代表者の個人資産を活用する、債権を回収する、法人財産を適正価格で処分するなどの方法で、破産手続に必要な資金を確保する姿勢が求められます。
専門家に依頼してから費用を積み立てる方法や、予納金の分割払いを交渉することも有効です。さらに、法人破産にかかる専門家への費用を抑えるためには、着手金無料の法律事務所に相談したり、費用の分割払いを交渉したりするのもよいでしょう。
本稿でご紹介した方法を活用すれば、初期費用を抑えつつ、専門的なサポートを受けられます。専門家の支援を受けながら、計画的に手続を進めることで、会社破産をスムーズに行い、経済的な再スタートを切るための準備が整えられるでしょう。
なお、会社の破産に際して、ご自身の連帯保証についてお悩みの経営者のみなさんは、グリーン司法書士法人にお気軽にお問合せください。経営者個人の債務整理に関して、専門家としてお力になります。