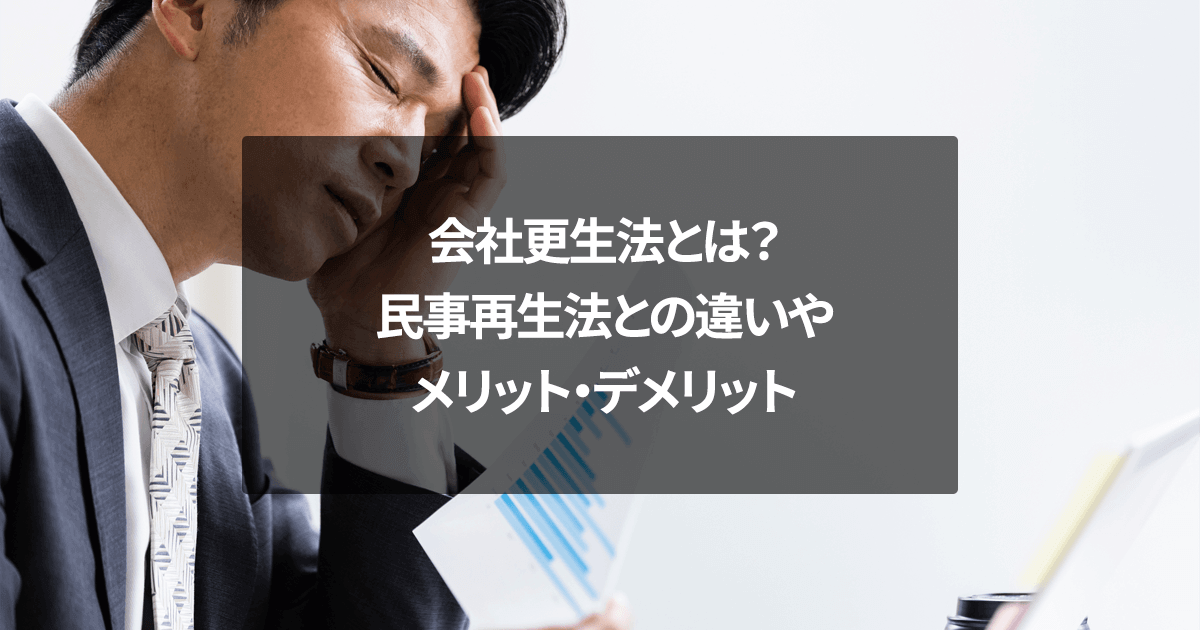この記事は約 12 分で読めます。
- 会社更生法とはどういうものか
- 会社更生をするメリットとデメリット
- 会社更生の一般的な手順
企業が経営危機に直面した際、再建の道を模索するために重要となるのが法的手続です。特に大企業においては、会社更生法が適用されることが多く、再建のための有力な選択肢となります。
今回の記事では、会社更生法の基本的な概要から、民事再生法との違いや、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。企業再建を目指す際の具体的な手続の流れも紹介し、理解しやすいように整理しましょう。
事業の継続や経営再建を考えている企業の経営者や担当者のみなさんにとって、役立つ情報となるでしょう。会社更生法を理解し、適切な判断を下すための参考としてください。
目次 ▼
1章 会社更生法とは
会社更生法は、経営に困難を抱える株式会社を再建するための法的手続です。この法律の目的は、債務超過や支払不能に陥った企業が、事業を継続しながら財務状況を改善することです。
会社更生手続を通じて、債務の整理や経営再建が行われます。具体的には、裁判所が選任した管財人が会社の経営を管理し、債権者との調整を行いながら更生計画を作成します。
この計画が裁判所に認可されれば、債務の一部免除や返済期間の延長などが行われ、会社の再建が進められます。
なお、会社更生の道を歩めずに倒産した場合、経営者は負債の返済義務を負うのかどうかや、責任が問われることについて、以下の記事で詳しく取り上げています。
ぜひそちらも、参考にご覧ください。
1-1 会社更生法と民事再生法の違い
会社更生法と民事再生法は、どちらも企業再建を目指す法的手続ですが、適用対象や手続の内容に違いがあります。
会社更生法は主に大企業向けで、管財人が企業の経営権を握り、徹底的な再建を図るのに対し、民事再生法は中小企業や個人事業主も対象となり、現経営陣が経営を続けながら再建を進めます。
さらに、民事再生法は手続が比較的簡単で迅速に進められるのが特徴です。一方、会社更生法は手続に時間がかかり、費用も高額になる傾向があります。
また、会社更生法では、債権者の同意が必要であり、株主の権利が失われることが多いのに対し、民事再生法では、株主の権利が保持されることが一般的です。
なお、会社更生や民事再生を検討する原因となりえる「債務超過」と、その解消年数や再生計画について、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、参考にご覧ください。
2章 会社更生をするメリット
会社更生をする主なメリットとしては、次の2点が挙げられます。
- 事業を継続できる
- 会社を再建しやすくなる
それぞれの内容を見ていきましょう。
2-1 事業を継続できる
会社更生法を適用すれば、事業の継続が可能となるのが大きなメリットです。企業が抱える債務を整理しながらも、事業活動を続けられます。
この手続を通じて、裁判所が選任した管財人が企業の経営を管理し、再建計画を策定します。それによって、経営陣の刷新と事業の再建が進められるのです。
さらに、債務の返済の猶により、資金繰りが改善され、事業運営の安定が図れます。また、担保に設定された資産も保全されるため、企業の基幹資産を維持しながら再建を目指すことが可能です。
それによって、企業は新たな投資や事業展開を模索する余裕を持てます。このプロセスは、企業の存続と成長を両立させるために非常に有効です。
なお、黒字経営なのに会社を整理する場合については、以下の記事で詳しく取り上げています。
ぜひ、参考にご覧ください。
2-2 会社を再建しやすくなる
会社更生法を利用すると、企業再建が容易になる点も大きなメリットです。管財人が企業の財務状況を管理し、効率的な再建計画を立案すれば、債権者との調整がスムーズに進みます。
さらに、民事再生法と比較して、会社更生法は大規模な企業向けに設計されているため、担保権の行使が制限され、主要な資産を保護しながら再建を進められます。
また、債務の一部免除や返済期間の延長が可能であり、企業の財務負担が軽減されます。
このようにして、企業は再建のための資金を確保しやすくなり、新たな事業戦略を実行に移せます。結果として、企業は持続的な成長を目指すための基盤を築くことができるのです。
なお、会社の再建ができない場合に陥る、倒産および法人破産とはどういうものか、廃業や破産との違いなどを以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
3章 会社更生をするデメリット
会社更生をするとメリットはあるものの、次のようなデメリットがあることも否めません。
- 手続費用が高額である
- 経営陣は退陣を求められる
- 株式会社でないと適用できない
個別に内容を見ていきましょう。
3-1 手続費用が高額である
会社更生法の手続を進めるには、高額な費用がかかることが大きなデメリットです。まず、裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金の額は、会社の負債総額によって異なり、数百万円から数千万円に及ぶこともあります。さらに、弁護士費用や申立手数料、郵便切手代などの諸費用も加わります。
それによって、会社更生手続に必要な総費用は非常に高額になります。特に、中小企業にとっては、この費用負担が大きな障壁となります。
このように、手続費用が高額であるため、会社更生法の利用を検討する企業は、事前に十分な資金計画を立てる必要があります。
なお、会社が「廃業」という選択肢を選ぶ際に必要な費用と廃業までの手続きの流れについては、以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
3-2 経営陣は退陣を求められる
会社更生法の適用により、現在の経営陣が退陣を求められることが一般的です。更生手続が開始されると、裁判所によって選任された管財人が会社の経営権を掌握します。
それによって、既存の経営陣は経営権を失い、会社の再建プロセスから外れることになります。この措置は、経営陣の刷新と新しい経営体制の確立を目的としていますが、現経営陣にとっては大きなデメリットとなります。
また、退陣に伴い、経営陣の知識や経験が失われることもあり、新たな経営体制が軌道に乗るまでには時間がかかる場合があります。
なお、会社更生や民事再生ができず会社が倒産した場合の、経営者や経営陣がどうなるのかや自己破産時に受ける影響について、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、参考にご覧ください。
3-3 株式会社でないと適用できない
会社更生法は株式会社にのみ適用されるため、そのほかの企業形態の会社には利用できません。この制約により、合同会社や有限会社、個人事業主などの企業は、会社更生法の恩恵を受けられないのです。
そのため、これらの企業が経営困難に陥った場合は、ほかの法的手続、たとえば民事再生法や特別清算などを検討する必要があります。
また、株式会社であっても、会社更生法の適用には厳格な条件があるため、すべての株式会社がこの手続を利用できるわけではありません。このように、適用範囲がかぎられていることは、会社更生法の大きな制約といえるでしょう。
なお、会社の倒産が危ぶまれる、いわゆる経営破綻の原因やその後の手続に関して、以下の記事で詳しく取り上げています。
ぜひ、そちらも参考にしてください。
4章 会社更生の流れ
会社更生の流れとしては、おおむね次の5つのステップを踏んで進行します。
STEP① 更生手続開始を申立てる
STEP② 更生手続開始の決定・管財人が選任される
STEP③ 債権届出期間に入る
STEP④ 更生計画案を提出・決議・認可を受ける
STEP⑤ 更生計画を遂行する
それぞれのステップを補足しておきましょう。
STEP① 更生手続開始を申立てる
会社更生の第一歩は、裁判所に更生手続開始の申立てを行うことです。申立てができるのは、会社自身、一定割合の株主、もしくは一定額の債権を有する債権者です。
申立書には、会社の財務状況、事業計画、更生計画の概要などが記載されます。この段階で、裁判所は申立ての正当性を審査し、必要であれば保全管理人を選任するでしょう
保全管理人は、会社の財産を保全し、不正な処分を防ぐ役割を果たします。申立ての後、裁判所は更生手続開始の決定を行い、会社の財産と経営は管財人の管理下に置かれます。
STEP② 更生手続開始の決定・管財人が選任される
裁判所が更生手続開始を決定すると、管財人が選任されます。管財人は、会社の財産を管理し、債権者の利益を保護するために任命される専門家です。
彼らは、会社の経営権を掌握し、財務状況を把握して再建計画を立案します。管財人は、会社の全財産を詳細に調査し、不正な取引や資産の隠匿がないかを確認します。
また、債権者や株主との交渉を行い、再建計画の承認を得るために尽力するでしょう。この段階では、会社の経営陣は管財人に対して全面的に協力しなければなりません。
STEP③ 債権届出期間に入る
更生手続が開始されると、債権者は一定期間内に債権を裁判所に届け出なければなりません。この期間を、債権届出期間と呼びます。
債権者は自らの債権が認められるよう、証拠書類を添付して届け出ます。裁判所と管財人は、届出された債権を精査し、認否を判断します。
この過程で、債権者間の調整が行われ、公正な債権整理が図られるでしょう。また、届出期間中に届出をしなかった債権者は、以後の債権者集会や再建計画の決議に参加する権利を失うことがあります。
STEP④ 更生計画案を提出・決議・認可を受ける
管財人は、更生計画案を作成し、裁判所に提出します。この計画案には、債務の整理方法、返済スケジュール、再建の具体策が詳細に記載されます。
更生計画案は、債権者集会で決議され、債権者の過半数以上の同意が必要です。同意が得られた場合、裁判所は計画案を認可します。
認可後、計画案にもとづき、債務の整理と事業の再建が進められます。この段階で、債権者や株主との協議が綿密に行われ、公正で実現可能な再建計画の策定が重要です。
STEP⑤ 更生計画を遂行する
更生計画が認可されると、計画にもとづき再建が進行します。管財人は、計画の遂行を監督し、債務の返済や事業の再編成を行うでしょう。
会社は計画に従って事業を継続し、収益を上げることで債務の返済を進めます。管財人は、定期的に裁判所に報告を行い、計画の進捗状況を確認します。
計画が順調に進むことで、会社は再建に成功し、健全な経営状態を取り戻せるでしょう。最終的に、裁判所が再建の完了を認め、更生手続は終了します。
なお、会社が赤字経営の場合に、立て直しを目指すための対処法について、以下の記事で詳しく取り上げています。
ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
まとめ
会社更生法は、経営困難に陥った大企業が再建を図るための法的手続であり、その適用には高額な費用や厳しい条件が伴います。手続費用が高額である点、経営陣が退陣を求められる点、そして株式会社でなければ適用できない点がデメリットです。
一方で、事業を継続しながら再建を図ることができ、債権者の同意を得て実効性のある再建計画を立案・遂行できる点が大きなメリットです。また、管財人の選任により、経営の透明性が確保されることも企業にとって重要なメリットです。
企業が経営危機に直面した際には、これらの情報をもとに、適切な法的手続を選択し、再建の道を進めるでしょう。
なお、会社の再建や整理の法的な手続に関してお困りの経営者のみなさんは、グリーン司法書士法人にお気軽にお問合せください。司法書士としてサポートできる範囲で、お力になります。
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!
よくあるご質問
- 会社更生法と民事再生の違いは何ですか?
- 会社更生法と民事再生法は、どちらも企業再建を目指す法的手続ですが、適用対象や手続の内容に違いがあります。
会社更生法は大企業向けであるのに対し、民事再生は中小企業や個人事業主も対象となります。
- 民事再生のメリットは何ですか?
- 民事再生のメリットは、主に下記の通りです。
・会社の存続を目指せる
・経営権を維持できる
・手元に資金を確保できる
・借金の減額や分割弁済を行える
・最大10年間にわたり弁済期間を延長できる
▶民事再生のメリットについて詳しくはコチラ