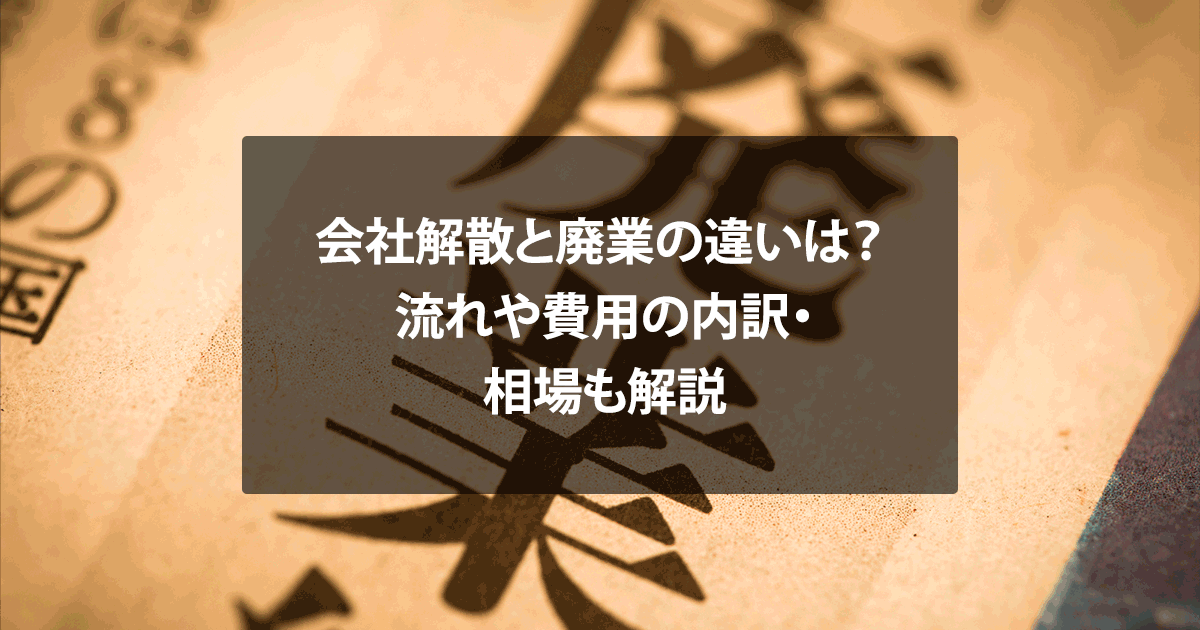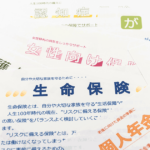この記事は約 13 分で読めます。
- 会社解散・廃業と清算の違い
- 会社解散・廃業の流れ
- 会社解散・廃業の費用内訳・相場
会社の運営を終わらせる際には、会社解散と廃業、清算といった異なるプロセスがあります。これらは似ているようでいて、それぞれ異なる手続や法的な意味を持つ言葉です。
今回の記事では、会社解散と廃業、清算の違いを詳しく解説します。さらに、それぞれの手続の流れや関連する費用についても見ていきましょう。
目次 ▼
1章 会社解散と廃業・清算の違い
会社を閉じる際には、解散、廃業、そして清算という3つの主要な概念があります。これらはそれぞれ異なる意味と手続を持ちますが、多くの人にとっては混同しやすいものです。
会社解散は会社の営業活動を停止し、その後の清算手続を開始するための第一歩です。一方、廃業は会社が事業を終了することを意味し、解散を含む場合もあれば含まない場合もあります。
清算とは、解散後に会社の資産や負債を整理し、最終的に法人格を消滅させるプロセスです。これらの違いを理解することで、適切な手続を進めるための重要な基礎知識を得ることができます。
この章では解散、廃業、清算の各概念を詳しく解説し、それぞれの手続の流れや必要な対応についても見ていきましょう。
なお、会社の再建ができない場合に選ぶ、清算の別表現ともいえる法人破産や倒産とはどういうものか、廃業や破産との違いなどを以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
1-1 会社の解散とは
会社の解散とは、法人の存在を終了させるために法的手続を開始することを指します。一般的に、解散の決定は株主総会での特別決議により行われるものです。
会社解散の理由には、定款で定めた存続期間の満了や株主総会での、解散決議などが含まれます。解散後は、清算手続が行われ、会社の資産や負債が整理されます。
解散の具体的な手続として挙げられるのは、まず株主総会での解散決議、解散登記の申請、そして清算人の選任です。解散の登記が完了すると、会社は法的に解散状態となり、その後は清算手続が進められます。
解散の手続は複雑であり、専門家の支援が必要になることが多いです。解散後の清算手続では、会社の資産を売却し、債務を返済し、残余財産を株主に分配します。最終的に、清算が完了したことを登記することで、会社の法人格は消滅します。
なお、会社解散に持ち込めずに倒産した場合、経営者は負債の返済義務を負うのかどうかや、責任が問われることについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。
1-2 廃業とは
廃業とは、会社が事業活動を停止し、運営を終了することです。廃業の理由はさまざまで、経営者の引退、後継者の不在、経営不振などが挙げられます。
法人の場合、廃業には解散と清算の手続が伴いますが、個人事業主の場合は単に事業を終了することを意味します。廃業の手続としては、まず廃業の決定、関係者への通知、各種届出の提出が必要です。
具体的には、税務署や法務局、市町村役場などへの届出を行います。また、従業員がいる場合は労働局への届出も必要です。
廃業に伴う手続は煩雑であり、事前にしっかりとした計画が求められます。廃業を選択する場合、事前に専門家に相談し、適切な手続を進めることが賢明です。
なお、黒字経営なのに会社を廃業する場合については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、参考にご覧ください。
1-3 清算とは
清算とは、会社が解散した後にその資産と負債を整理し、最終的に法人格を消滅させる手続です。清算には通常清算と特別清算の2種類があります。
通常清算は、会社がすべての債務を返済できる場合に行われ、清算人が中心となって手続を進めます。特別清算は、債務超過ですべての債務を返済できない場合に行われ、裁判所の監督のもとで進められる手続です。
清算手続では、まず会社の資産を売却し、債権を回収します。次に、売却収益をもとに債務を返済し、残余財産を株主に分配します。
清算手続の最終段階は、決算報告を作成し、株主総会で承認を受けた後の清算結了の登記です。それによって、会社の法人格は正式に消滅します。
なお、会社の清算を検討する原因となりえる「債務超過」と、その解消年数や再生計画について、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
2章 会社解散・廃業の流れ
会社解散・廃業の流れは、おおむね次のようなステップを踏んで進みます。
- STEP① 株主総会の開催・解散決議を行う
- STEP② 解散登記と清算人選任登記を行う
- STEP③ 財産目録および貸借対照表の作成・解散確定申告を行う
- STEP④ 公告・催告を行う
- STEP⑤ 清算事務と残余財産の分配を行う
- STEP⑥ 清算結了登記を行う
それぞれのステップの内容を、見ていきましょう。
なお、会社に解散や廃業を検討させる赤字経営の状態から、立て直しを目指すための対処法について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
STEP① 株主総会の開催・解散決議を行う
会社の解散を決議するためには、まず株主総会を開催し、特別決議を行う必要があります。この特別決議は、株主の過半数が出席し、そのうち3分の2以上の賛成が必要です。
株主総会の招集通知は、開催の2週間前までに発行しなければなりません。解散の決議が成立すると、その内容を株主総会議事録に記録し、署名・押印を行います。
解散の決議理由は、たとえば定款に定めた存続期間の満了や定款に定めた解散事由の発生、合併、破産手続の開始などが一般的です。株主総会では解散のほかにも清算人の選任も行います。
選任された清算人の役割は、会社の解散後の清算手続を進めることです。解散決議の詳細は、法務局に提出する書類に添付されるため、正確な議事録の作成が求められます。
STEP② 解散登記と清算人選任登記を行う
株主総会での解散決議後、次に行うのが解散登記と清算人選任登記です。解散登記は会社の解散を公式に認めるもので、解散の日から2週間以内に法務局に申請しなければなりません。
この登記が完了すると、会社は解散状態となり、事業活動を停止します。同時に、清算人選任登記も行われるのが一般的です。
清算人は解散後の清算手続を進める責任者で、通常は取締役や株主から選任されます。登記の申請には、株主総会議事録や選任された清算人の承諾書などが必要です。
これらの登記が完了することで、清算手続が正式に始まります。解散登記と清算人選任登記は、会社の清算プロセスの重要な第一歩です。
STEP③ 財産目録および貸借対照表の作成・解散確定申告を行う
解散登記が完了したら、次に清算人は財産目録および貸借対照表を作成します。財産目録は、会社のすべての資産と負債が詳細に記載されるでしょう。
貸借対照表は、解散時点の財務状況を示すもので、株主総会での承認を受ける必要があります。それによって、会社の財産状況が明確になります。
また、解散確定申告も重要です。これは、解散時点での所得税や法人税の確定申告を行うもので、税務署に対して提出します。
解散確定は、解散の日から1か月以内に行う必要があります。それによって、解散に伴う税務上の義務を果たせるわけです。
STEP④ 公告・催告を行う
清算手続の開始にあたり、会社は債権者に対して公告と催告を行います。公告とは、官報に掲載することです。会社が解散したことと債権の申し出を求めることを周知します。
この公告は、最低2か月間継続して行わなければなりません。同時に、会社の既知の債権者には個別に催告書を送付し、債権の内容を申し出るよう求めます。
公告および催告によって、会社の負債状況が明確になり、清算手続がスムーズに進むようになります。これらの手続は、法的に義務付けられており、適切に行わなければなりません。
STEP⑤ 清算事務と残余財産の分配を行う
公告・催告期間が終了すると、清算人は具体的な清算事務を開始します。会社の資産を売却し、現金化する作業がスタートです。
売却される資産には、不動産、機械設備、在庫などが挙げられます。次に、債権の回収を行い、精算人は債務の弁済を進めるでしょう。
債務がすべて弁済された後、残余財産がある場合は株主に分配します。分配の方法は、株主総会で決議された内容に従わなければなりません。
清算人はこの過程を、透明かつ公正に行う義務があります。清算事務の詳細は、最終的に決算報告書としてまとめられ、株主総会においての承認を受けなければなりません。
STEP⑥ 清算結了登記を行う
清算事務がすべて完了したら、最後に清算結了登記を行います。この登記は、会社の清算が終了し、法人格が正式に消滅することを法的に認めるものです。
清算人は、清算結了登記の申請書を法務局に提出し、株主総会で承認された決算報告書を添付します。清算結了登記が完了すると、会社の法人格は法的に消滅し、登記簿から抹消されます。
それによって、すべての清算手続が終了します。この最終ステップは、会社の清算プロセスを締めくくる重要な手続です。
なお、会社の解散や廃業を予期させる、いわゆる経営破綻の原因やその後の手続に関して、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
3章 会社解散・廃業にかかる費用の内訳・相場
会社解散・廃業にかかるおもな費用としては、次の6項目が挙げられます。
- 登録免許税:41,000円程度
- 官報公告費用:32,301円〜39,479円程度
- 書類収集費用:商業・法人登記情報334円/通 登記事項証明書480円〜600円/通
- 専門家に支払う報酬:20万円から40万円程度
- 在庫・設備などの処分費用:数万円から数十万円程度
- 不動産などの原状回復費用:数万円から数十万円程度
それぞれを補足しておきましょう。
3-1 登録免許税
会社を解散する際には、解散登記を法務局に申請するための登録免許税が必要です。具体的には、解散登記には30,000円の登録免許税がかかります。
さらに、解散後に清算人を選任するための清算人登記にも9,000円の登録免許税が必要です。清算が完了した際には、清算結了登記を行い、この際にも2,000円の登録免許税が発生します。
これらの登記費用を合計すると、会社の解散および清算に必要な登録免許税は41,000円となります。これらの費用は、法務局に支払うもので、登記が完了するために必須の支出です。
3-2 官報公告費用
会社の解散および清算手続においては、官報に公告を行う必要があります。官報公告は、会社が解散したことを広く知らせ、債権者に対して債権の申し出を促すためのものです。
公告費用は、官報の1行あたり約3,589円で、通常9〜11行程度の公告を行うため、費用は32,301円から39,479円程度となります。この費用は、債権者保護手続の一環として法的に義務付けられているため、必ず負担しなければなりません。
3-3 書類収集費用
会社解散および清算手続には、各種証明書や書類の収集が必要です。具体的には、商業・法人登記情報や登記事項証明書の取得費用が発生します。
商業・法人登記情報の取得には1通あたり334円、登記事項証明書の取得には1通あたり480円から600円が必要です。また、これらの書類の郵送費用もかかります。
さらに、これらの書類を取得するためにかかる手数料や交通費などの実費も考慮する必要があります。これらの費用は、解散・清算手続の各段階で必要となるもので、確実に準備しておかなければなりません。
3-4 専門家に支払う報酬
会社解散および清算手続は、専門的な知識が求められるため、税理士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。専門家に依頼する場合の報酬費用は、依頼内容によって異なりますが、通常数十万円程度かかります。
たとえば、解散登記や清算人選任登記、清算結了登記の申請を依頼する場合、それぞれの登記に対して報酬が発生します。さらに、清算に関する確定申告や債権・債務の整理に関する業務も含まれるため、総額で20万円から40万円程度の報酬が必要です。
3-5 在庫・設備などの処分費用
会社解散に伴い、事業で使用していた在庫や設備の処分費用が発生します。在庫の処分は、一括で売却することが難しい場合が多く、処分業者に依頼することが一般的です。この場合、処分業者への手数料が発生します。
また、設備や機械などの処分には、その状態や種類によって処分費用が異なります。特に、老朽化が進んでいる設備や機密情報を含む機器などは、専門の処分業者に依頼する必要があり、その費用は数万円から数十万円に上ることがあります。
3-6 不動産などの原状回復費用
事業で使用していた賃貸物件を解約する際には、原状回復費用が発生します。原状回復とは、賃貸契約終了時に物件を借りたときの状態に戻すことです。
この費用には、壁紙の張替え、床の修理、クリーニングなどが含まれます。原状回復費用は物件の広さや状態によって異なりますが、数万円から数十万円程度が一般的です。
特に、長期間使用していた場合や大規模な改装を行った場合には、費用が高額になります。
なお、会社が「廃業」という選択肢を選ぶ際に必要な費用と廃業までの手続きの流れについては、以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
まとめ
会社の解散と廃業は、事業を終えるための重要な手続ですが、それぞれに異なる法的な意味と手続があります。解散は会社の法人格を消滅させるための第一歩であり、清算手続を開始するための準備段階です。
これに対し、廃業は事業活動の終了を意味し、必ずしも法人格の消滅を伴うものではありません。解散後の清算手続では、会社の資産や負債を整理し、最終的に法人格を消滅させるプロセスが含まれます。
また、これらの手続を進めるには、多くの費用が発生し、登録免許税や官報公告費用、書類収集費用、専門家への報酬などが必要となります。会社解散や廃業の手続を正しく進めるためには、各段階で必要な手続を確実に行うことが求められます。
株主総会での解散決議、解散登記と清算人選任登記、財産目録と貸借対照表の作成、公告と催告、清算事務と残余財産の分配、そして最終的な清算結了登記まで、各ステップを適切に実施することが重要です。
なお、会社の解散や廃業、清算にかかわる法的な手続に関してお困りの経営者のみなさんは、グリーン司法書士法人にお気軽にお問合せください。司法書士としてサポートできる範囲で、お力になります。
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!