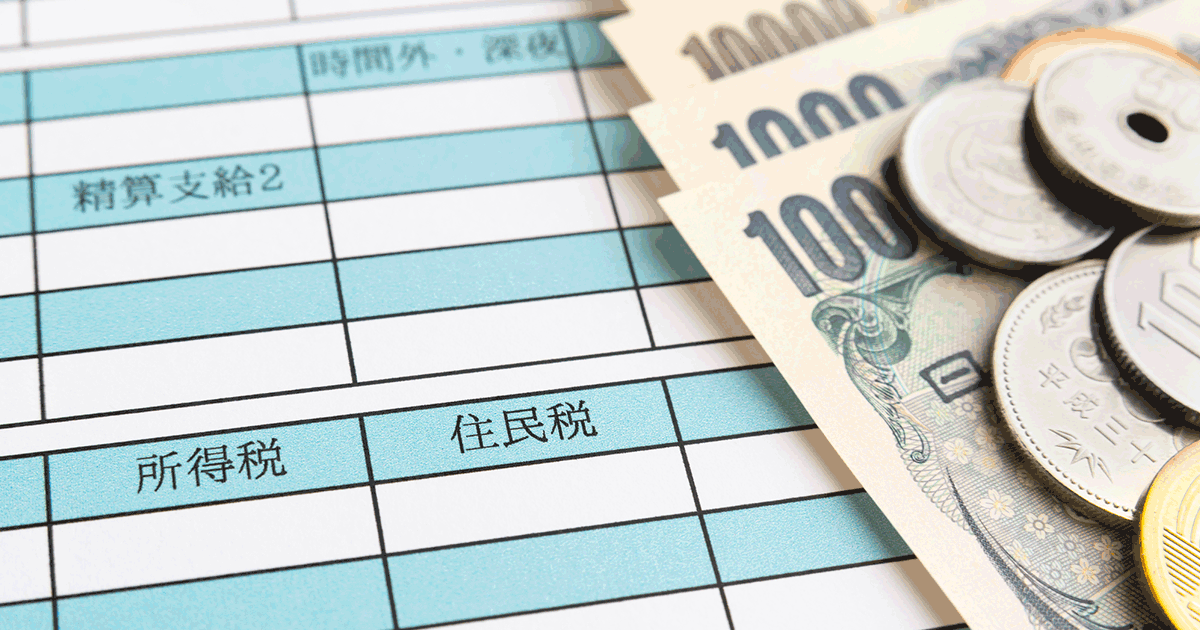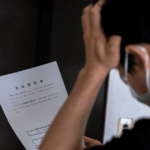この記事は約 9 分で読めます。
- 退職後も住民税の納税をしなければいけない
- 払えない場合は住んでいる自治体に相談が必要
- 滞納を続けると延滞税の加算や差押えになる
- 住民税は債務整理で免除にならないので注意
住民税は、その年の1月1日時点で自分が住んでいる市区町村に納める義務があります。会社勤めのときは特別徴収として会社が住民税を納めていましたが、退職後は自身で住民税を納めなければいけません。
しかし、退職後で収入がなく、住民税が払えない方も多いでしょう。この記事では、退職後に住民税が払えない場合の対処法を解説します。納税の免除や猶予を受けるための条件も紹介するので、納税にお困りの方は参考にしてください。
目次 ▼
1章 退職しても住民税の納税義務は発生する!
税金は収入の有無にかかわらず、国民の義務として定められています。そのため、退職しても住民税の納税義務が発生するので注意が必要です。
住民税は、前年の所得に応じて金額が決定し、翌年6月から支払いが開始されます。もし、退職後に収入がない場合でも前年の所得に合わせた金額を納税しなくてはいけません。
納付額を見て、住民税が払えないと判断した場合は早めに自治体に相談しましょう。
2章 退職後の住民税の納付方法は?
退職後の住民税の納付方法は、退職時期や再就職の時期によって異なります。
では、ケースごとに納付方法を見ていきましょう。
2-1 1月1日~5月31日に退職する場合
住民税の納付方法は、第1期(6月)に一括納付、もしくは6月、8月、10月、1月の4期に分けて納付する方法の2パターンです。
1月1日から5月31日までに退職した場合は、5月までの住民税が退職月の給料や退職金から一括徴収になります。一括徴収できなかった分は普通徴収として自身で納税しなければいけません。
2-2 6月1日~12月31日に退職する場合
6月1日から12月31日までに退職する場合は、退職月の住民税は通常通り給料から天引きになります。その翌月以降の住民税は、普通徴収となるため自身で納税しましょう。
会社によっては退職時に翌年5月までの住民税を一括徴収してもらえる場合もあるため、希望する場合は相談するのをおすすめします。
2-3 退職後すぐに再就職する場合
退職後すぐに別の職場に就職する場合は、転職先で引き続き特別徴収してもらえます。特別徴収を希望する場合は、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を転職先に提出しましょう。
再就職までの期間が空く場合は、転職先で特別徴収を続けられないため、住民税の納付書が届いた分は自身で納付する必要があります。
3章 退職後の住民税が払えない場合は自治体に相談しよう
退職後で収入がない場合でも、前年分の所得に応じた住民税を納付しなくてはいけません。また、退職後は住民税の納付以外にも国民健康保険料や国民年金の支払いも必要です。
つまり、収入がない状態で住民税や国民健康保険料、国民年金の支払いを続けなければいけないので注意しましょう。もし、前年度の所得や経済的事情によって住民税が払えない場合は、各自治体に相談して分割払いや減免などの対応ができないか相談するのをおすすめします。
3-1 分割払いが可能なケースがある
経済的事情や入院や介護など、やむを得ない事情によっては分割払いが可能なケースがあります。自治体によって対応は異なりますが、滞納する前に相談すると柔軟に対応してくれる場合が多いです。
退職して収入がない場合は、離職票や退職証明書を持って行き、状況を説明するとスムーズでしょう。どのような理由にせよ、納付できない理由を説明して納税の意思を見せることが大切です。
3-2 住民税が減免・免除になる具体例
住民税は、状況によって減免や免除になる可能性があります。住民税が減免や免除になるケースは、以下に該当する場合です。
- 生活保護を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に該当する人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が一定以下の人
あくまで一例ですが、経済的に払うのが難しいと判断されたら減免や免除を受けられる可能性があるため、まずは各自治体に一度相談するのがよいでしょう。
4章 住民税が払えないと最終的に差押えになる!
退職後、収入がないからといって住民税を滞納し続けると最終的に差押えになってしまいます。預金口座や現金の一部や車などの財産が差し押さえられるため、より経済的に厳しい状況になるでしょう。
では、住民税を滞納してから差押えになるまでの期間と流れを解説します。住民税は退職後も納税義務が続くため、無視せずに早めの対応を心がけましょう。
4-1 【納付期限を過ぎてから】延滞税がかかる
納付期限を過ぎると滞納となり、延滞税がかかります。住民税はこれまで給料から天引きされていたため、自身で納付することになれずにうっかり忘れてしまうケースも多いです。延滞税を余分に払わないためにも納付書が届いたら早めに払いましょう。
延滞税は、納付期限を過ぎてから未納期間に応じて追加されます。つまり、延滞期間が長引くほど延滞税がかかるので早めに対応するのがおすすめです。
4-2 【納付期限から20日程度】督促状が送られてくる
納付期限を過ぎてから20日程度経つと、督促状が送られてきます。
督促状は、支払いが遅れていることを知らせるための通知です。督促状には再設定された期限内に住民税を払うように求める内容が記載されています。
再設定された期限内でも払える見込みがない場合は、早めに各自治体に相談して分割払いや納税猶予などの救済措置を検討しましょう。
4-3 【督促状から11日】財産が差し押さえられる
督促状が届いてから11日程度経つと、財産が差し押さえられます。11日経ったら必ずしも差押えになるわけではありませんが、法律では督促状を発行した日から10日を経過した日までに完納しない場合は差押えが可能であると定められています。
滞納者がこの督促を受けた場合で、その督促のため督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないときは、差押えをすることができる。
引用:国税庁
※ただし、この法律は国税を滞納した場合に適用されるため、地方税の滞納に関する手続きは国税徴収法の例によるとされています。
そのため、督促状が届いても10日以上無視している場合は、いつ差押えになってもおかしくない状況です。督促状を無視して納付をしないと、延滞金が加算されるだけではなく差押えになるため、払えない場合でも絶対に無視してはいけません。
5章 借金が原因で住民税が払えない場合は債務整理を検討しよう
借金が原因で住民税が払えない場合は、早めに債務整理を検討しましょう。債務整理とは、借金の減額や免除できる法的手続きです。
債務整理は、大きく分けて3種類の方法があります。それぞれ特徴が異なるため、借金の総額や今後の就職状況に合わせて確認しましょう。
| 債務整理の種類 | 手続きの方法 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 任意整理 | 利息や手数料など元金以外の支払いをカットする手続き | 借金の返済が長期化して利息が膨らんでしまった人 借金を選んで返済したい人 |
| 個人再生 | 借金そのものを大幅にカットして完済を目指す手続き | 借金の総額が大きい人 減額すれば返済できる可能性がある人 |
| 自己破産 | 借金自体を免除して支払い義務をなくす手続き | 完済の目処が立たず返済不能に陥った人 今後も就職が困難で経済的立て直しが難しい人 |
債務整理は法律に則って手続きを進めるため、手続きを最短で成功させるためにも司法書士や弁護士などの専門家と一緒に進めるのを強くおすすめします。手続きには費用がかかるため、貯金に余裕があるうちに債務整理に踏み切るのがよいでしょう。
5-1 住民税は債務整理で免除にならないので注意
住民税や国民健康保険料、国民年金などの滞納は、債務整理の対象にならないので注意が必要です。
債務整理の手続きで減額もしくは免除になるものは、クレジットカードやローンの借入や消費者金融などの借金、奨学金などが挙げられます。一方で、住民税のような税金は非免責債権に該当するため、自己破産をした場合でも支払い義務が残るのを覚えておきましょう。
つまり、住民税が払えない場合は各自治体に相談する以外の方法がありません。債務整理を利用する場合は、税金の支払い義務が残ることを理解して計画的に対応しましょう。
6章 退職後に住民税が払えない場合は早めの相談を!
退職後に住民税が払えない場合は、早めに市区町村へ相談することが大切です。無視して滞納を続けると、延滞税の発生や財産の差押えといった厳しい措置が取られてしまいます。
分割払いや納税猶予などの救済措置を利用できる場合もあるため、安心して生活を続けるためにも迷わず早めに行動しましょう。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!