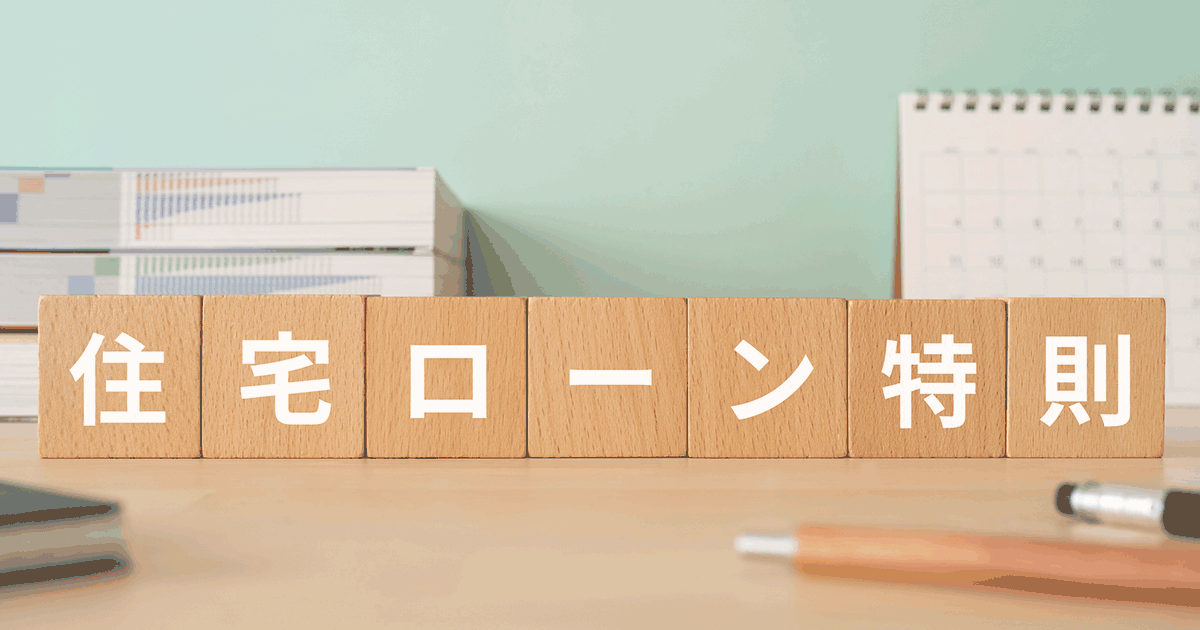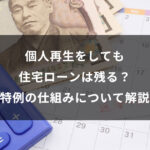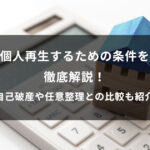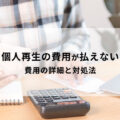この記事は約 11 分で読めます。
- 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の概要
- 住宅資金特別条項を活用するための条件
- 住宅資金特別条項を活用する際のおすすめの相談先
住宅資金特別条項とは、個人再生を行う際に住宅ローンを組んでいる人がマイホームを手放さずに借金を整理できる制度です。マイホームを残せるという大きなメリットがありますが、「そもそも住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の仕組みがわからない」「住宅資金特別条項を活用する条件を満たしているのか知りたい」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、住宅資金特別条項の概要や活用するための条件を解説します。住宅資金特別条項に関するよくある質問も掲載しているので、確認して仕組みを理解する際に役立ててください。
目次 ▼
1章 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は個人再生時に活用可能
住宅ローン特則とも呼ばれる住宅資金特別条項は、個人再生をする際に活用できます。個人再生とは、借金を大幅に減額して原則3年で返済を目指す債務整理です。個人再生によって借金を減額する際、住宅や車といった抵当権が設定されている財産は、競売にかけられてしまいます。
しかし住宅資金特別条項を活用すれば、住宅ローンを個人再生の対象から外せるのです。住宅ローン残高は減額されませんが、他の借金を減らすことでマイホームを残したまま借金問題の解決を目指せます。
なお、個人再生では減額後の借金を計画通りに返済することが条件となるため、安定した収入がなければ基本的に申し立てが認められません。収入源がない場合に債務整理を行いたいのであれば、マイホームを含む財産の大半を処分して債務を帳消しにする自己破産も候補に加える必要があります。
2章 住宅資金特別条項を活用するための6つの条件
借金問題の解決を目指す際、同じ家に住み続けられる住宅資金特別条項の活用を検討している方も多いのではないでしょうか。ただし、以下の条件を満たしていなければ、住宅資金特別条項を活用する個人再生の申し立ては認められません。
- 住宅購入やリフォームのためのローンであること
- 個人再生をする人が所有する住宅であること
- 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
- マンションの場合は管理費や修繕積立金を滞納していないこと
- 保証会社による代位弁済から6か月以内に個人再生の申し立てをすること
- 個人再生を行った後に継続して返済できる収入があること
それぞれの条件について詳しく解説します。自分が住宅資金特別条項を活用できるかどうか確認しながら、読み進めてください。
2-1 住宅購入やリフォームのためのローンであること
住宅資金特別条項を適用するためには、対象となる住宅ローンが住宅購入やリフォームを目的としたものでなければなりません。例えば一軒家やマンションの購入、老朽化した家のリフォームのために組んだ住宅ローンであれば、住宅資金特別条項を活用できます。
一方で、事業資金や車の購入、教育費の支払いなどの目的で組んだローンは住宅資金特別条項の適用外になります。
2-2 個人再生をする人が所有する住宅であること
住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生を申請する本人が住宅の所有者でなければなりません。個人再生を行う人が住んでいる家の名義が親や配偶者になっていれば、住宅資金特別条項の適用は認められないのです。
また、投資用の不動産やマイホームとは別に所有している別荘なども申請者が住んでいないため、住宅資金特別条項を適用できません。なお、自宅兼事務所や自宅兼店舗の場合、床面積の2分の1以上が自宅である必要があります。
2-3 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
住宅ローンを組む際は金融機関によって抵当権が設定されますが、住宅ローン以外の抵当権が設定されていれば住宅資金特別条項を適用できません。抵当権とは、大きい金額の融資取引をする際に金融機関をはじめとする債権者が借主の不動産を担保にする権利です。抵当権が設定されている住宅の所有者が滞納を続けると、金融機関は住宅を競売にかけてお金を回収できます。
例えば事業資金の担保を住宅にしていたり、不動産を担保にするローンを借りていたりする場合は、住宅ローン以外にも抵当権が設定されていることになります。このような複数の抵当権が設定されているケースでは住宅資金特別条項を適用できず、個人再生によってマイホームを失ってしまうのです。
2-4 マンションの場合は管理費や修繕積立金を滞納していないこと
マンションに住んでいる場合、管理費や修繕積立金を滞納していないことも住宅資金特別条項を適用するための条件になります。建物の維持管理や将来の修繕工事のために必要な資金であるマンションの管理費や修繕積立金は、特別の先取特権に該当します。
そして、特別の先取特権は個人再生の手続きとは関係なく行使可能です。権利が行使されると不動産を失うことになるため、特別の先取特権に該当するマンションの管理費や修繕積立金を滞納していると住宅資金特別条項を適用できないのです。
したがって、住宅資金特別条項を適用したい場合は、個人再生の申し立てを行う前にマンションの管理費や修繕積立金や滞納を解消しておきましょう。
2-5 保証会社による代位弁済から6か月以内に個人再生の申し立てをすること
住宅ローンの返済が滞った場合、保証会社が代位弁済を行います。代位弁済とは、保証会社が借主に代わって金融機関にローンの支払いを行う手続きのことです。代位弁済が行われた場合は基本的に住宅資金特別条項を適用できませんが、6か月以内であれば例外的に認められています。
一方で、申し立てが遅くなると住宅資金特別条項の適用が不可能に近くなります。そのため、滞納を続けて代位弁済が行われてしまった場合は、なるべく早く個人再生の申し立てに向けて動き出しましょう。
2-6 個人再生を行った後に継続して返済できる収入があること
住宅資金特別条項を適用して個人再生を行った場合でも、住宅ローンと大幅に減額された借金を継続的に返済する必要があります。そのため、債務整理後も安定して返済できるだけの収入がなければ、申し立ては認められません。
3章 住宅資金特別条項に関するよくある質問
住宅資金特別条項が絡むことによって、個人再生の手続きはより複雑になります。そのため、住宅資金特別条項の条件以外にも、疑問点や不明点がある方も多いのではないでしょうか。ここでは住宅資金特別条項に関するよくある質問を掲載しているので、住宅ローン特則への理解を深める際に役立ててください。
3-1 相続した住宅でも使えますか
住宅資金特別条項は住宅を取得するための借入(住宅ローン)に適用されるため、相続した住宅には使えません。そして個人再生には、圧縮後の借金が持っている財産の価値を下回ってはいけないという決まりがあります。
したがって、500万円の借金をしている方が相続で1,500万円の価値がある住宅に住んでいる場合、個人再生をしても借金は減額されないので申し立て手続きをする意味がないのです。
3-2 ほかに住宅資金特別条項を使えないケースがありますか
管理費を滞納していると、住宅資金特別条項を使えません。住宅資金特別条項は、住宅が住宅ローン以外の担保になっていないことが要件になっていますが、管理費を滞納すると住宅に対して先取特権という担保権が生じるためです。
また、住宅ローンの契約に車購入のための借入といった住宅購入に必要のない借金が含まれている場合も、住宅資金特別条項は使えません。
なお、住宅ローンの完済が近いときは住宅資金特別条項を使えないこともないですが、債務が圧縮されないケースが多いです。なぜなら、個人再生で支払う金額の下限は、清算価値(所有する財産額)によって決まるためです。たとえば、住宅ローンの残高が300万円で不動産の価値が1000万円の場合は差額の700万円が清算価値となるため、住宅ローン以外の借金が700万円以下なら個人再生をしても債務は圧縮されません。
3-3 ほかに借金がなくても住宅資金特別条項を使えますか
住宅ローンの期限の利益を喪失して一括請求になった場合などであれば、再度分割に戻すためだけに住宅資金特別条項を使えます。ただし、個人再生の手続きを終えた後でも借金は圧縮されない点に注意が必要です。
3-4 ペアローンでも住宅資金特別条項は使えますか
共有している財産に対して、住宅資金特別条項の適用を認めるべきではないという意見があります。しかし、ペアローンを組んだ債務者が個人再生手続きの申し立てをして、住宅資金特別条項の適用が認められたケースが存在しています。その際に示されたペアローンで住宅資金特別条項を使う条件は以下の通りです。
- 同一家計を営んでいる者が、いずれも個人再生手続きの申し立てをする
- いずれも住宅資金特別条項を定める旨の申述をする
これらの条件を満たしたケースではペアローンでも住宅資金特別条項を適用できると、大阪地方裁判所第6民事部は示しています。
3-5 代位弁済の開始通知が届いた後でも住宅資金特別条項を定められますか
保証会社が保証人である場合は、住宅資金特別条項を定められます。ただし、保証会社が代位弁済をして債務の全部を履行した日から6か月を経過すると、申し立てが認められません。そのため、住宅資金特別条項を定めたい場合は、代位弁済から6か月以内の再生手続き開始の申し立てが必要です。
なお、住宅ローンを滞納していると保証会社が競売にかけられることがあります。再生手続きが完了するまでに競落してしまうと、住宅資金特別条項を利用する余地がなくなってしまいます。そのため、再生計画の認可の見込みがあれば、債務者は抵当権の実行の中止を命じる「中止命令」の制度を活用しなければなりません。
3-6 住宅ローンを負担していながら住宅資金特別条項を定めない場合の留意点はありますか
住宅資金特別条項を定めずに個人再生手続きを進める場合でも、要件となる「負債総額が5,000万円を超えないこと」に住宅ローン残高は含まれません。ただし、住宅ローンに別除権が行使されて住宅の所有権を失うと、住宅ローン残高を含めた金額が5,000万円以内に収まっていないと個人再生手続きを利用できなくなります。
また、住宅資金特別条項を利用しないことで、最低弁済額を決定する際の基準債権額が大きくなります。作成された再生計画の最低弁済額が多額になるため、個人再生後に本当に債務を弁済できるかどうか慎重に考慮して、住宅資金特別条項を使用するか判断しましょう。
4章 住宅資金特別条項を活用する際は弁護士・司法書士に相談しよう
個人再生の手続きは複雑なうえに、住宅資金特別条項には条件が設けられていて、個人で申し立てを行うのは難しいです。そのため、住宅資金特別条項を活用する際は弁護士・司法書士に相談しましょう。
なお、代位弁済が行われた後に個人再生をする場合、期限ギリギリに動き始めると申し立てまでに必要な費用を支払えない可能性があります。費用を支払う前の申し立ても可能ですが、その費用も個人再生によって圧縮されてしまうため、弁護士・司法書士は依頼を受けない傾向にあります。したがって、確実に個人再生の手続きを終えてマイホームを残しつつ借金問題の解決を目指したいのであれば、なるべく早めに弁護士・司法書士に相談することが重要です。
グリーン司法書士法人では、住宅資金特別条項を活用した個人再生をサポートしています。無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
まとめ
住宅資金特別条項は、個人再生手続きにおいてマイホームを守りながら借金を整理できる制度です。しかし、以下の条件を満たしていない場合、住宅資金特別条項を適用できません。
- 住宅購入やリフォームのためのローンであること
- 個人再生をする人が所有する住宅であること
- 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
- マンションの場合は管理費や修繕積立金を滞納していないこと
- 保証会社による代位弁済から6か月以内に個人再生の申し立てをすること
- 個人再生を行った後に継続して返済できる収入があること
また、対応が遅くなると個人再生の申し立てが認められない恐れもあります。そのため、住宅資金特別条項の活用を考えているのであれば、なるべく早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。
グリーン司法書士法人では、マイホームを残しつつ借金問題の解決をサポートした実績が多数あります。オンライン相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。
住宅ローンに関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:任意整理 住宅ローン
住宅ローンの無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!