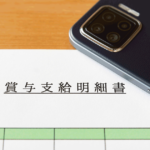この記事は約 8 分で読めます。
- 同一世帯の人は賃貸契約の連帯保証人になれない理由
- 賃貸契約の連帯保証人になれる人の条件
- 賃貸契約の連帯保証人を見つけられないときの対処法
賃貸契約を結ぶ際、連帯保証人の選定は同一世帯に住む家族では認められない場合が多く見られます。連帯保証人になれる人はかぎられており、その条件は厳格です。
今回の記事では、なぜ同居する家族が連帯保証人になれないのか、そして連帯保証人を見つける際の注意点について詳しく解説します。また、保証人が見つからない場合にどのような対処法があるのかについても、見ていきましょう。
目次 ▼
1章 同一世帯の人は賃貸契約の連帯保証人になれない
賃貸契約において「同一世帯」とは、同じ住所で生活を共にする家族や同居人を指します。この場合、親子や兄弟姉妹、配偶者などが該当し、法律上の関係がなくとも、生活費を共にする場合も同一世帯と見なされるケースが多いです。
これらの同一世帯の人々が賃貸契約の連帯保証人になるのは、賃貸借契約上では避けるべきとされています。同一世帯の人が連帯保証人になれない主な理由は、賃貸契約のリスク分散の観点からです。
同一世帯内の人が連帯保証人になると、経済的な問題が発生した際に、同じ家庭内での収入源が一斉に滞る可能性があります。
貸主側の未回収リスクを軽減するため、異なる収入源を持つ第三者を連帯保証人とするのが一般的です。
なお、賃貸契約の連帯保証人は家族でもなれるかどうかや、用意できないときの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
2章 連帯保証人になれる人物
賃貸契約において連帯保証人を立てる場合、一定の条件を満たす必要があります。一般的には、現役で働いており安定した収入があるという事実が必要です。
また、連帯保証人は借主と同様に国内に居住していることが基本条件です。親や兄弟姉妹、子どもといった3親等内の親族が多く選ばれますが、これに限定されず友人でも可能な場合があります。
ただし、連帯保証人としての責任は重いため、親族でももちろん、親族以外なら相当慎重に依頼するのが賢明です。
前章で述べたとおり、連帯保証人として同居人が選ばれる事態は通常避けられます。同居人と借主が同一世帯で生活しているため、家賃の支払いが滞った際に両者が同時に経済的困難に陥る可能性が高いからです。
そのような状態はリスクの分散を妨げ、貸主にとって不利な状況を招く恐れがあります。したがって、賃貸契約では、同居人以外でなおかつ安定収入がある人物を、連帯保証人に立てるのが推奨されています。
なお参考までに、賃貸借契約における連帯保証人の解除方法や、特例および更新拒否については、以下の記事で詳しく取り上げています。そちらも、ぜひ参考にお読みください。
3章 賃貸契約の連帯保証人を見つけられないときの対処法
賃貸契約時に連帯保証人が見つからない場合、いくつかの対処法があります。連帯保証人を不要とするケースは珍しくなく、多くの物件で対応策が用意されています。
連帯保証人が見つからない場合でも、契約を諦める必要はありません。特に近年は、家族構成や社会の変化に伴い、連帯保証人を立てるのが難しいケースが増えています。
こうした背景から、賃貸契約の連帯保証人を見つけられないときの主な対処法としては、次の2つが挙げられます。
- 保証会社を利用する
- 連帯保証人不要の賃貸住宅を選ぶ
それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。
3-1 保証会社を利用する
保証会社の利用は、連帯保証人が見つからない場合の有効な手段です。保証会社は、借主が家賃を支払えない場合に、代わって支払いをする役割を担います。
貸主は家賃のリスクを軽減できるため、安心して物件を貸せるわけです。保証会社を利用する際は、家賃の一部を保証料として支払う必要があります。
初回の金額は一般的に家賃月額の50〜100%程度で、その後は年間1万円程度を支払うのが相場です。また、契約期間は賃貸契約と同じく設定されるのが一般的です。
近年の民法改正により、賃貸借契約における連帯保証の性質が「個人根保証」であることが明確になりました。連帯保証人が負う責任範囲が明確化され、極度額(保証人が負う最大の負担額)の設定が必須となっています。
この改正に伴い、個人保証の手続が煩雑化し、個人根保証よりも手続が簡便である保証会社の利用が増加しています。特に、外国人や高齢者など連帯保証人を立てることが難しい借主が増えている現代において、保証会社の利用は一層普及しているのです。
このように、保証会社の利用は、借主と貸主双方にとって安心感を提供する手段として、賃貸市場で重要な役割を果たしています。保証会社を利用することで、賃貸契約をスムーズに進められます。
なお、賃貸借契約における保証に関して、保証会社と連帯保証人のどちらを選ぶべきか、またどういうケースでは両方必要なのかについては、以下の記事で詳しく取り上げています。そちらも、ぜひ参考にご覧ください。
3-2 連帯保証人不要の賃貸住宅を選ぶ
賃貸契約において連帯保証人を立てることが難しい場合、保証人が不要な物件を選ぶことが有効です。こうした物件は、主に「UR賃貸住宅」や「保証人不要物件」として提供されており、特に高齢者や外国人の方に人気があります。
UR賃貸住宅は、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理しており、礼金や仲介手数料が不要で、保証人も不要という特徴があります。このため、初期費用を抑えたい方や保証人を用意できない方にとって、非常に魅力的な選択肢となっています。
保証人不要の賃貸住宅は、他にも家賃債務保証会社の利用を前提とした物件があります。家賃債務保証会社は、入居者が家賃を支払えなくなった場合に代わりに支払うことで、貸主さんのリスクを軽減するのです。
この仕組みを利用することで、連帯保証人がいなくても賃貸契約を結べます。特に近年では、社会の高齢化や単身世帯の増加に伴い、こうした物件も増加中です。また、外国人の入居者にも対応している物件が多く、住まいの選択肢が広がっています。
連帯保証人不要の物件を選ぶ際には、特定の条件があることも多いです。たとえば、収入証明書や住民票の提出が求められる場合があり、家賃の支払い能力が確認されます。
また、UR賃貸住宅の場合、敷金は通常の2か月分必要ですが、礼金や更新料が不要であるため、長期的に見ると経済的に有利です。さらに、UR賃貸住宅はDIYが可能な物件もあり、入居者が自分の好みに合わせてリフォームできます。
このように、連帯保証人不要の賃貸住宅は、さまざまな理由で保証人を用意できない方にとって非常に有用な選択肢です。物件を探す際には、こうした特典を提供している物件やサービスを活用することで、自分に合った住まいを見つけられます。
なお参考までに、連帯保証人が簡単にやめられない件や、やめられるケース、請求されたときの対処法などについては、以下の記事で詳しく取り上げています。そちらも、ぜひ参考にご覧ください。
まとめ
賃貸契約を結ぶ際、同一世帯の家族が連帯保証人になることは認められにくくなっています。これは、家賃滞納時に同一世帯内の収入源が、一斉に途絶えるリスクがあるためです。
そのため、賃貸借契約では異なる収入源を持つ第三者を保証人にすることが推奨されています。連帯保証人を見つけることが難しい場合には、保証会社を利用することがひとつの解決策です。
保証会社は、家賃滞納時に代わりに支払う役割を果たします。貸主にとっても借主にとっても安心な選択肢です。保証会社を利用する際には、保証料の支払いが必要ですが、それにより賃貸契約をスムーズに進められます。
保証人が見つからない場合には、連帯保証人不要の賃貸物件を選ぶことも有効です。特にUR賃貸住宅は、保証人不要である上に、礼金や仲介手数料が不要であるため、初期費用を抑えられます。また、DIY可能な物件もあり、自分の好みに合わせて住まいをカスタマイズできる点も魅力です。このように、保証人がいない場合でも安心して賃貸契約を結ぶ方法は複数あります。自身の状況に合った最適な方法を選び、安心して新生活をスタートさせてください。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!