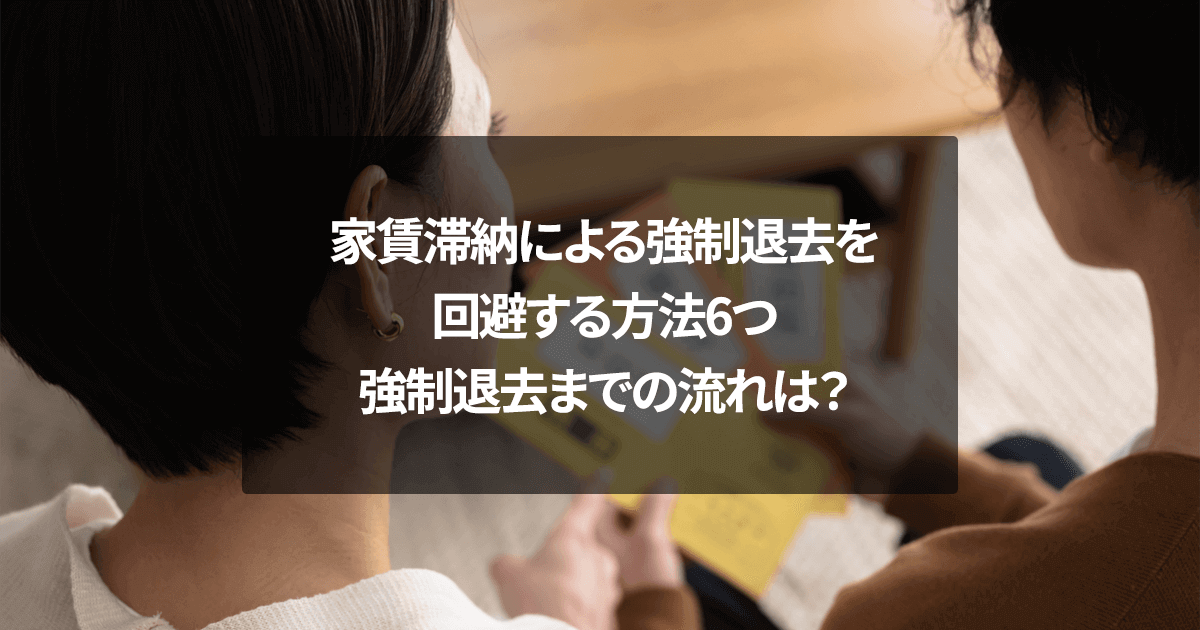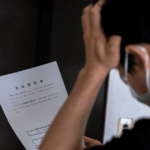この記事は約 14 分で読めます。
- 家賃滞納で強制退去となるケース
- 家賃滞納による強制退去を回避する方法
- 家賃滞納から強制退去までの流れ
- 家賃滞納をするリスクやデメリット
家賃を3ヶ月以上滞納すると、強制退去を求められる可能性が高まります。
ただし、強制退去をするには法的な手続きが必要であり、すぐに実行されるわけではありません。
そのため、早期に大家や管理会社に相談し、分割払いや支援制度を活用することで退去を防げるケースもあります。
本記事では、家賃滞納による強制退去を回避する方法や強制退去までの流れを解説します。
目次 ▼
1章 家賃滞納で強制退去となるケース
家賃滞納によって実際に強制退去となるのは、主に次の2つのケースです。
- 3か月以上の家賃滞納が続いている
- 大家と賃借人との間に信頼関係がなくなってしまった
それぞれを詳しく見ていきましょう。
1-1 3か月以上の家賃滞納が続いている
賃貸契約には家賃滞納に関する厳しい条項が含まれていることが多く、大家が強制退去を要求する正当な理由となります。滞納が続くと、遅延損害金や法的費用も追加される可能性が高まるでしょう。
家賃を3か月以上滞納すると、大家は法律的な手続を開始する権利を持つようになります。まず、賃貸契約にもとづき、滞納分の支払いを求める通知が送られてくるでしょう。
この通知を無視し、支払いが行われない場合、次のステップとして裁判所に訴えられること(いわゆる明け渡し裁判)があります。判決にて、物件からの退去及び滞納家賃の支払いを命じられます。
本来の強制退去は、建物明渡訴訟の判決に基づく強制執行によるものを指しますが、その前段階の「3か月以上の家賃滞納」の状態において、支払わないのであれば出て行かざるを得ないので、広義での強制退去といえるでしょう。
なお、家賃滞納時に明渡しの裁判を起こされる際は、滞納家賃の支払いについても付帯して請求されることがほとんどです。賃貸借契約書には勤務先などを緊急連絡先として書くことが多いので、強制執行では給与の差押えなども起こりえるでしょう。
このような状況を避けるためには、早めの対応が不可欠です。経済的な問題が発生した場合は、速やかに大家や管理会社に相談し、支払い計画を立てることが重要です。家賃滞納は信頼関係にも大きな影響を与えるため、誠実な対応が求められます
1-2 大家と賃借人との間に信頼関係がなくなってしまった
賃貸契約は、大家と賃借人の間の信頼関係にもとづいて成立するものです。この信頼関係が崩れると、家賃滞納が発生する前でも契約解除の理由となることがあります。
たとえば、賃借人が物件を損傷させたり、近隣住民とのトラブルを引き起こしたりした場合、大家は信頼関係の破綻を理由に契約を解除できます。また、賃借人が頻繁に家賃を遅延する場合や、無断で他人に転貸する場合も同様です。
信頼関係の破綻は法的な手続においても重要な要素となり、裁判所が契約解除を認める際の判断基準となります。大家が賃貸物件の管理に不安を感じる場合、契約解除を選択することが正当化される場合があります。
このため、賃借人は日常的なコミュニケーションを大切にし、問題が発生した際には早急に対処することが必要です。信頼関係を維持するためには、誠実な対応と相互理解が欠かせません。
なお、家賃滞納と強制退去の関係や、強制退去になったらその後はどうなるかについて、以下の記事でも詳しく解説しています。
ぜひ、参考にご覧ください。
2章 家賃滞納による強制退去を回避する6つの方法
家賃滞納による強制退去を回避する主な方法として、次の6つが挙げられます。
- 大家や管理会社に家賃の支払いに関する交渉・相談をする
- 家族・親族や消費者金融から借金をして家賃を払う
- 住居確保給付金制度を活用する
- 失業手当・傷病手当を受け取る
- 生活保護の申請をする
- 債務整理について司法書士・弁護士に相談する
個別に詳しく見ていきましょう。
2-1 大家や管理会社に家賃の支払いに関する交渉・相談をする
家賃滞納が発生した場合、まずは大家や管理会社に直接交渉・相談することが重要です。家賃支払いの遅延や滞納の理由を正直に説明し、誠意を持って話し合いを行いましょう。
多くの場合、大家や管理会社は事情を理解し、柔軟な対応を検討してくれる可能性があります。たとえば、滞納分の家賃を分割払いにしてもらったり、支払い期限を延長してもらったりできる場合があります。
また、今後の家賃支払いの見通しについても、具体的な計画を示すとよいでしょう。特に、支払いが難しい期間が一時的なものであることを説明し、支払い再開の時期や方法を具体的に提案すると効果的です。
さらに、現在の収入状況や家計の状況を共有することで、相手の理解を得やすくなります。交渉の際には、文書でのやり取りも行い、合意内容を記録に残しておくことが重要です。
このように、大家や管理会社との信頼関係を維持しつつ、柔軟な対応を引き出すことで、強制退去を回避できる可能性が高まります。
なお、家賃を滞納した場合に早急に相談すべき先と、その後の流れについては、以下の記事で詳しく取り上げています。
ぜひ、そちらも参考にしてください。
2-2 家族・親族や消費者金融から借金をして家賃を払う
家賃滞納が続き、強制退去の危機に直面した場合、家族や親族からの支援を求めることもひとつの方法です。身近な人に事情を説明し、一時的な貸付をお願いすることで、滞納分の家賃を支払うことができます。
家族や親族からの支援は、利子や返済条件が柔軟であることが多く、精神的な負担も軽減されます。消費者金融からの借入は手続が迅速で、急な資金調達が可能なため、緊急時には有効な手段といえるでしょう。
ただし、高金利での借入は将来的な返済負担を増加させるため、計画的な返済計画を立てることが重要です。どちらの方法を選ぶにしても、強制退去になるよりは傷が浅いので、いずれかの迅速な対応を取るのが賢明でしょう。
借入によって家賃滞納を解消し、住居を維持できますが、長期的な解決策としては収入の安定化や生活費の見直しを検討する必要があります。
2-3 住居確保給付金制度を活用する
住居確保給付金制度は、収入が減少し家賃の支払いが困難になった人々を支援する制度です。この制度は、主に失業や休業などで収入が減少した人を対象としており、一定期間家賃の一部を給付金として支給します。
支給期間は原則として3か月ですが、条件を満たせば最大で9か月まで延長可能です。申請方法は、居住地の自治体にある生活支援窓口で行います。必要な書類には、収入状況を証明するものや賃貸借契約書の写しなどです。
申請が受理されると、自治体から直接大家や管理会社に家賃が支払われます。この制度を利用することで、滞納家賃を解消し、強制退去を回避できるでしょう。
2-4 失業手当・傷病手当を受け取る
失業や病気・ケガによる休職が原因で、家賃の支払いが困難になった場合、失業手当や傷病手当を受け取ることが有効です。
失業手当は、雇用保険に加入している労働者が失業した場合に一定期間給付されます。受給するためには、ハローワークで求職の申請を行い、積極的に就職活動をする必要があります。
失業手当の給付期間は、年齢や被保険者期間に応じて異なりますが、通常は90日から330日間です。
一方、傷病手当は、病気やケガで働けない場合に健康保険から支給される手当です。これを受け取るためには、医師の診断書が必要となり、最長で1年6か月間給付されます。
これらの手当を活用することで、収入の減少を補い、家賃の支払いを継続できます。急な収入の減少に対して、一時的な支援を受けられるため、家賃滞納のリスクを軽減できるでしょう。
2-5 生活保護の申請をする
生活保護は、収入が最低生活費を下回る場合に支給される公的支援です。家賃の支払いが困難な場合も対象となり、生活扶助の一環として家賃も支給されます。
生活保護を申請するには、市区町村の福祉事務所に相談し、必要な書類を提出する必要があります。申請には収入や、資産の状況を証明する書類が必要です。
審査が通ると、生活扶助費や住宅扶助費が支給されます。生活保護を受けることで、経済的な安心感が得られ、再び生活を立て直すための基盤が整うでしょう。
また、生活保護受給者は医療費も無料になるため、健康管理もしやすくなります。生活保護は最後の手段とされますが、適切に利用することで、住居を失うリスクを大幅に軽減できます。
なお、生活保護を受けていても自己破産できるかどうかや、自己破産の生活保護への影響について、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
2-6 債務整理について司法書士・弁護士に相談する
家賃滞納が続き、ほかの借金も抱えている場合、債務整理を検討することが有効です。債務整理は合法的に、債務の一部または全部を免除してもらうための、法的な手続です。
債務整理の手続を開始すると、債権者からの取り立てや督促が即座に停止されるため、精神的な負担が軽減されます。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、利息の減額や返済期間の延長を図る方法です。個人再生は、裁判所の手続を通じて借金の一部を減額し、残りを分割して返済する方法で、住宅ローンを抱えている場合でも自宅を維持できます。
自己破産は、すべての借金を免除してもらう方法ですが、一部の債務は免除されず、信用情報に長期間の影響があります。司法書士や弁護士に相談することで、自分の状況に最適な債務整理の方法を選ぶことができるでしょう。
借金の返済を優先しているために家賃が払えない場合は、おおむね任意整理で解決できるのではないでしょうか。
強制退去を回避することに特化するのであれば、任意整理で家賃以外の借金負担をまず軽減し、それによって余裕ができた分を、家賃滞納の返済に回し、強制退去を解消するという手順です。
いずれにしても、司法書士などの債務整理のプロフェッショナルに相談することで、効率的かつ適切な解決策を見つけることができます。
借金問題から家賃を滞納してしまい、強制退去になりそうでお困りのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
3章 家賃滞納から強制退去までの流れ
家賃滞納から強制退去までの流れは、おおむね以下のようになります。
- 滞納開始
- 催告書の送付
- 契約解除通知
- 訴訟の提起
- 判決の取得
- 強制執行の申立て
- 強制退去の実施
- 滞納の開始
家賃の支払いが遅れると、まずは大家や管理会社から督促が始まります。
そして、支払いがない場合、内容証明郵便で催告書が送られ、正式に支払いを求められます。
催告に応じないと、賃貸契約の解除通知が届き、訴訟の提起も行われるでしょう。
明け渡し判決後に賃借人が従わない場合は、強制執行となり、退去日時が決定されてしまいます。
このように、家賃滞納から強制退去に至るまでには、複数のステップと法的手続が存在します。各段階で適切な対応を行うことで、強制退去のリスクを軽減可能です。
4章 家賃滞納をするリスク・デメリット
家賃を滞納することで生まれる、主なリスクやデメリットは次の4つです。
- 遅延損害金がかかる
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 連帯保証人に滞納分を請求される
- 強制退去になる
ひとつずつ見ていきましょう。
4-1 遅延損害金がかかる
家賃を滞納すると、遅延損害金が発生します。遅延損害金は、契約書にもとづき設定されることが一般的であり、法律で定められた上限を超えない範囲で適用されます。
日本の民法では、2020年の改正により、法定利率の年3%までとされていますが、契約書でそれ以上の利率が設定されている場合もあります。遅延損害金は滞納額に対して日割りで計算されるため、滞納期間が長引くほど支払額が増加します。
また、滞納家賃に対する遅延損害のほか、契約解除後に明け渡すまでの損害賠償もあります。多いのは、賃料の2倍を損害賠償として求められるケースです。
よくあるのは賃料の2倍を損害賠償としてとられるという内容です。
これは、家賃滞納が長期化することで、負担がさらに増大するリスクを意味します。そのため、早期に対策を講じることが重要です。
4-2 信用情報機関に事故情報が登録される
家賃を滞納し、信販系の保証会社やクレジットカードを利用している場合、滞納情報が信用情報機関に登録されるでしょう。
信用情報機関に登録された事故情報は、いわゆる「ブラックリスト」に載ることを意味し、今後のクレジットカードやローンの審査に大きな影響を及ぼします。
具体的には、新規のクレジットカード発行や住宅ローン、自動車ローンなどの審査が基本的に通りにくくなります。
また、既存のクレジットカードの利用限度額が減少したり、更新が拒否されたりすることもあります。信用情報機関においては、事故情報が5年間保存されるため、この間は信用取引に厳しい制約がかかります。
信用情報機関に事故情報が登録されることを避けるためにも、家賃滞納を未然に防ぐことが重要です。万が一滞納してしまった場合でも、早急に支払いを行い、事態の悪化を防ぐことが求められます。
4-3 連帯保証人に滞納分を請求される
賃貸契約で連帯保証人を立てている場合、家賃滞納が発生すると、連帯保証人に滞納分が請求されます。連帯保証人は、賃借人と同等の責任を負うので、賃借人が家賃を支払えないのであれば、無条件で保証人が全額支払う義務を負います。
これは、家族や友人を連帯保証人にしている場合、彼らにも経済的な負担が及ぶことを意味します。保証人に対する請求は法的に有効であり、支払い義務を拒否することはできません。
そのため、家賃の滞納は連帯保証人との信頼関係に影響を及ぼします。また、連帯保証人が支払いを行った場合、その金額を賃借人に対して求償する権利を持つため、賃借人は最終的にその金額を返済しなければなりません。
このように、家賃滞納は自分だけでなく、連帯保証人にも大きな負担とリスクをもたらすことを認識しなければなりません。
4-4 強制退去になる
家賃滞納が続くと、最終的には強制退去に至る可能性があります。滞納が3か月以上続くと、大家は賃貸借契約を解除し、退去を求めることが法的に可能です。
まず、内容証明郵便で支払いを催告し、それでも支払いがない場合には契約解除の通知が送られます。その後、明け渡し請求訴訟を起こし、裁判所から明け渡しの判決を得ます。
判決後も退去しない場合、強制執行の手続が行われ、裁判所の執行官が立ち会いのもと、強制的に退去させられます。これを回避するために裁判所からの催告書を受け取った段階で対策を講じることが重要です。
また、強制退去は物理的な立ち退きだけでなく、信用情報にも悪影響を与え、再び賃貸住宅を借りることが難しくなるリスクも高まるので注意を要します。
まとめ
家賃滞納による強制退去を回避するためには、迅速かつ適切な対応が求められます。家賃滞納が続くと、遅延損害金の発生や信用情報機関への登録、連帯保証人への負担、最終的には強制退去といった深刻なリスクが伴います。
まずは大家や管理会社に相談し、支払い方法や期限について交渉することが重要です。また、住居確保給付金制度や失業手当・傷病手当、生活保護などの公的支援を活用することで、家賃支払いの負担を軽減できます。
そもそも、ほかの借金問題によって起きた滞納であれば、債務整理を通じて、ほかの借金を減額しつつ家賃滞納を解消し、強制退去を回避する解決方法があります。専門家の助けを借りることで、苦しい状況を改善し、再び安定した生活を取り戻すことが可能です。
借金問題から家賃を滞納してしまい、強制退去になりそうでお困りのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!
よくあるご質問
- 家賃滞納で強制執行されたらどうなりますか?
- 強制執行が実施されると、裁判所の執行官が物件に訪れ、室内の家具や荷物が強制的に運び出されます。
その際、玄関の鍵も交換され、借主は住居への立ち入りができなくなります。
- 家賃滞納により強制執行されるのは何ヶ月後ですか?
- 一般的に、家賃滞納が始まってから3ヶ月ほどで強制執行の手続きに移ります。
そして、強制執行に至るまでの期間はそこからさらに数ヶ月程度かかります。