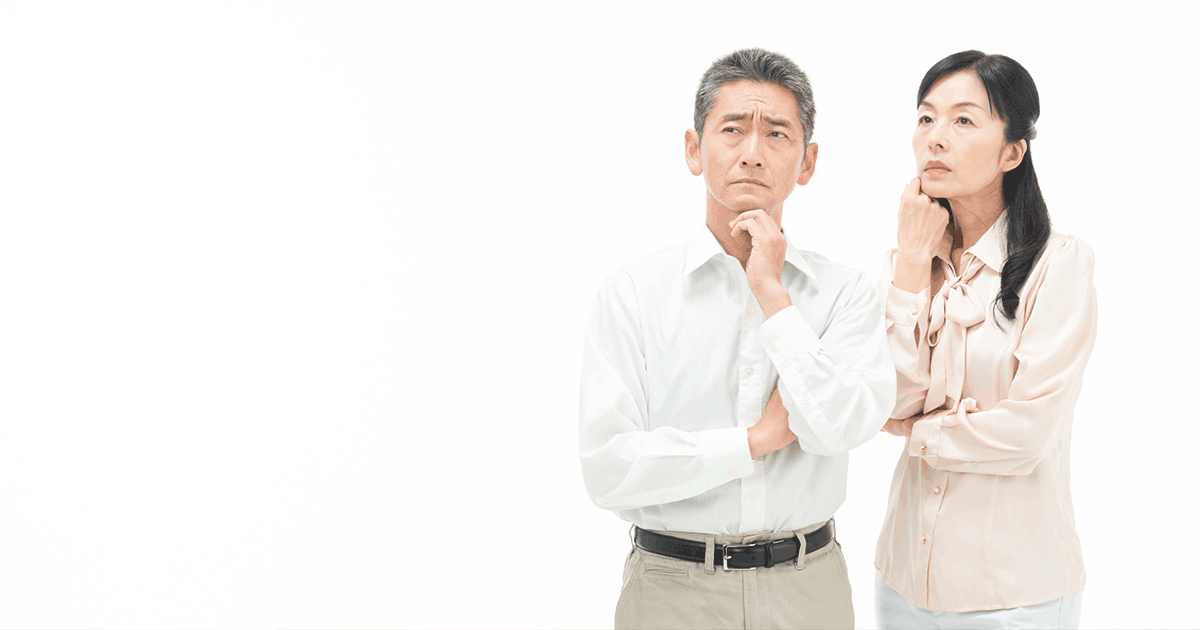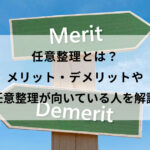この記事は約 8 分で読めます。
- 自己破産で同居家族の収入・財産は調査されるケース
- 自己破産で提出する同居家族の収入・財産に関する書類
- 自己破産で同居家族の収入に影響を与えることはない理由
- 自己破産で同居家族に与える影響
- 自己破産でデメリットが大きい場合の対処法(債務整理)
自己破産をしても、原則、同居家族の収入や財産に影響することはありません。
ただし、支払いができるかどうかを判断するために、同居家族の収入や財産を調査されることがあります。
また、財産隠しを疑われるケースにおいては、家族名義の財産が破産する本人のものではないことを証明する書類を細かく求められることもあります。
自己破産は手続をする本人のみが対象ですが、同居家族へ負担をかけることもあるため、何に影響を与えるのか事前に把握しておくことが必要です。
そこで、自己破産における同居家族の収入・財産の調査や、与える影響などについて解説します。
目次 ▼
1章 自己破産時に同居家族の収入・財産は調査される
自己破産をしても、原則、家族の財産は調査の対象に含まれません。
ただし、財産隠しなどが疑われる場合は、家族の財産も調査されることはあります。
また、自己破産は支払い不能であることが必要なため、本当に支払いできない状態なのか確認が必要になります。
その上で問題になるのは、以下のように、夫婦の生活費が収入多寡による負担割合ではないケースです。
たとえば、毎月の夫婦それぞれの収入が同額の場合において、生活費はすべて夫の収入を充て、妻は貯金していたとします。
しかし、夫の収入だけで生活費を賄えないため、不足分を補うために借金をしたとしましょう。
本来は、夫婦の生活費は夫と妻が半分ずつ負担するべきであるため、「夫の借金=妻の貯金」と判断されます。
この場合、妻の資産に対して破産管財人から追求される可能性が高く、争いの泥沼化後におおよその金額で和解することになるでしょう。
なお、自己破産で免責が認められるかは破産管財人が大きく関係するため、免責不許可にならない範囲での和解が必要です。
上記に加え、自己破産後に債務者の家計収支がプラスになるのか確認するためにも、家族の収入・財産を調査することはあります。
2章 自己破産時に提出する同居家族の収入・財産に関する書類
自己破産では、本人が支払不能の状態であるかと、支払義務を免除してもよいかを判断するための確認が行われます。
そのため、本人の収入以外に、生計を共にする配偶者や同居家族の収入や財産が確認できる次の書類の提出が必要です。
- 同居家族の収入を証明する書類
- 同居家族の通帳
- 家計全体の収支表(家計簿)
それぞれ説明します。
2-1 同居家族の収入を証明する書類
世帯収入の確認のため、生計を共にする同居家族の収入を証明する書類が必要です。
自己破産は、基本的に債務者本人の経済状況のみを評価しますが、本人の経済状況を詳しく知るために同居人を含めた世帯収入も確認されます。
そのため、同居家族の収入を証明する書類として、給与明細や課税証明書の提出を求められます。
2-2 同居家族の通帳
生計を共にする同居家族が開設している銀行口座の通帳も、提出を求められます。
ただし、提出が必要になるのは、水道光熱費や電話代の引き落としがあるものや破産者の口座から生活費などが振り込まれている場合などです。
お金の流れに不審な点がないか、債務者から同居家族へ財産が移されていないかなどを確認するためともいえます。
2-3 家計全体の収支表(家計簿)
世帯全体で毎月どのようにお金を使っているのか調べるため、自己破産の申立ての直近2~3か月分の家計全体の収支表(家計簿)も提出が必要です。
収支表には、同居家族の収入や毎月の生活費を記載し、金額等を証明する資料も添えて裁判所へ提出します。
自己破産は、債務者の生活を再建する手続であるため、たとえば高額な家賃が再建の足手まといであると判断される場合などは、指摘を受ける場合もあります。
3章 自己破産をすることが同居家族の収入に影響を与えることはない
自己破産は、債務者本人の手続であり、その事実が同居家族の収入に影響を与えることはありません。
手続したことが周囲に知られたとしても、同居家族の収入も差押えの対象にされることはないといえます。
そのため、同居家族に収入があっても、債務者本人が支払い不能になれば、自己破産は可能です。
なお、自己破産で借金返済の義務を免除してもよいか、お金の使い道に問題はなかったのかなどを確認するために、世帯収入は調査されます。
同居家族を含む世帯収入やお金の流れを調査し、財産隠しなどが発覚すれば自己破産は認めてもらえません。
4章 自己破産をしたときに同居家族に与える影響
自己破産をしても、基本的に、同居家族の収入・財産に影響を与えることはありません。
ただし、自己破産では債務者本人の財産は処分しなければならないため、同居家族に以下の影響が及ぶ恐れはあります。
- 持ち家の処分で引っ越しが必要になる
- 自動車の処分で移動手段が限定される
- 家族が保証人または連帯保証人の場合は返済義務が移る
- クレジットカードの家族カードが利用できなくなる
- 貯蓄タイプの保険解約で保険を失う
- 奨学金の保証人になれないため機関保証制度の利用が必要になる
ただし、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはないため、同居家族の結婚に影響することはありません。
同居家族の仕事に影響することもなく、自己破産手続をした債務者本人以外の信用情報も悪化しないため、クレジットカードやローンの申し込みもできます。
5章 自己破産によるデメリットが大きいのであれば他の債務整理を検討しよう
自己破産で借金の支払いが免除されれば、返済に追われる生活から抜け出せます。
しかし、持ち家や自動車などの資産を失うなどのデメリットが大きく、手続できないケースもあります。
この場合、以下の債務整理を検討しましょう。
- 任意整理
- 個人再生
それぞれ説明します。
5-1 任意整理
「任意整理」は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、利息や遅延損害金の減免などにより借金の返済条件を見直す手続です。
減額後は、3~5年間の分割払いで完済を目指します。
自己破産がすべての借金を対象にしなければならない一方で、任意整理では対象とする借金を選べるため、自動車ローンや同居家族が保証人になっている借入れ以外の返済負担を軽減することも可能です。
また、任意整理では同居家族の収入や財産にも影響を与えません。
スムーズに手続を進めるためには、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
5-2 個人再生
「個人再生」は、裁判所を介して借金を大幅に圧縮する手続です。
自己破産と異なり、原則財産を保持したまま行うことができます。
借金を圧縮した後は、原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で完済を目指します。
個人再生では、住宅ローン返済中の持ち家を残したまま、他の借金総額を5分の1程度まで大幅減額できます。
そのため、債務者が自宅の名義人であり、住宅ローンの返済は継続したまま借金問題を解決したいときにおすすめです。
まとめ
自己破産をしても、同居家族の収入や財産を調査されることはないものの、財産隠しを疑われるケース等ではその限りではありません。
本人が支払い不能でなければ手続できないため、支払い義務を免除してもよいか判断するために、確認される場合もあります。
なお、自己破産で同居家族の収入に影響はありませんが、持ち家や自動車の名義が債務者本人であれば生活に影響するといえます。
この場合、自己破産以外の債務整理も検討できるため、一度グリーン司法書士法人までご相談ください。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:自己破産 条件
自己破産の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!