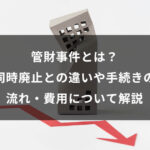この記事は約 11 分で読めます。
- 連帯保証人も時効援用できること
- 連帯保証人の時効は5年もしくは10年であること
- 連帯保証人の時効の更新についての取扱い
- 管財事件と同時廃止の取扱いの違い
- 連帯保証人が時効援用を行う方法・必要な書類
- 時効援用を自分で行うのは現実的ではないこと
- 連帯保証人が時効援用する際の注意点
連帯保証人としての役割を担うことは、親しい人を支援するための重要な決断です。しかし、債務が履行されない場合、連帯保証人は多大な責任を負うことになります。
その際に重要なのが「時効援用」という概念です。これは、一定期間が経過することで債務が法的に消滅するというもので、連帯保証人も適用を受けられます。
しかし、時効の成立には条件が伴い、適切な手続も必要です。今回の記事では、連帯保証人として時効援用を行う際の基本的な知識や、具体的な手続について詳しく解説します。
目次 ▼
1章 連帯保証人も時効援用できる
連帯保証人は、主債務者および自分自身が支払いを行わずに一定期間が経過した場合、消滅時効によりその債務を免責される権利を持っています。時効の成立による免責の権利を主張する行為が「時効の援用」です。
連帯保証人が時効援用を行うには、主債務者が債務を承認していないことが前提となります。主債務者が最後に支払いを行ってから、5年または10年が経過した場合、連帯保証人は時効援用を主張できるのです。
しかし、債権者が連帯保証人に対して支払いの催促を行った場合や、連帯保証人が債務を承認する行為を行った場合には、時効が更新(リセット)されます。連帯保証人が時効援用を検討する際には、債務の状況の慎重な確認が欠かせません。
連帯保証人として時効援用を行えば、法的な支払義務から解放される可能性がありますが、状況によっては複雑な法的問題が絡みます。そのため、専門家の助言を受けながら、適切な手続を踏むのが重要です。
連帯保証人としての債務の時効援用を考えておられるみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。債務問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
2章 連帯保証人の時効は5年もしくは10年
連帯保証人の債務も通常の債務と同様に、消滅時効が適用されます。時効期間は5年もしくは10年です。
具体的には、商行為にもとづく債務や債権者が企業である場合は5年、個人間の貸借や企業でない債権者(日本政策金融公庫など)からの借入れの場合は10年とされています。この期間が経過すると、連帯保証人は債務から解放される権利を主張できるのです。
ただし、時効が成立するためには、債権者が連帯保証人に対して何らかの法的措置を取らなかったことが条件です。また、連帯保証人が債務を承認したり、一部でも返済を行ったりした場合、時効は更新されます。
したがって、連帯保証人が時効を援用しようとする場合は、債権者とのやり取りや支払い履歴を慎重に管理しなければなりません。
また、時効が成立するまでの間に債権者が裁判所に訴訟を起こし、判決が確定した場合も時効が更新されます。判決によって確定した債務は10年間有効とされ、その期間内に債権者が権利を行使できるのです。
時効の成立には多くの条件が絡むため、連帯保証人として時効援用を検討するなら、専門家と相談するのが不可欠です。連帯保証人としての債務の時効援用を考えておられるみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
3章 連帯保証人の時効の更新についての取扱い
連帯保証人の時効の更新については、次の具体的な4つのケースに分けて解説します。
- 主債務者・連帯保証人に対して請求が行われたとき
- 主債務者・連帯保証人が債務の承認をしたとき
- 主債務者が一部弁済を行ったとき
- 主債務者が自己破産をしたとき
3-1 主債務者・連帯保証人に対して請求が行われたとき
主債務者や連帯保証人に対して債権者から法的な請求が行われると、時効が更新されます。法的な請求とは、具体的には裁判所を通した支払督促や訴訟の提起です。
連帯保証人は、このような法的措置が取られた場合、時効の主張は困難です。債権者が連帯保証人に請求を行う際、一般的にはまず主債務者に請求が行われ、その後連帯保証人に対して同様の請求がなされます。
しかし、連帯保証人には主債務者と同等の責任があるため、主債務者の信用状況が不安定な場合には、直ちに連帯保証人に請求が行われるでしょう。
特に、債権者が連帯保証契約書を公正証書で作成している場合、強制執行が迅速に行われる可能性が高くなります。
このような請求が行われた場合、連帯保証人は速やかに対応し、必要に応じて専門家の助言を得るのが賢明です。特に、裁判所からの通知や公正証書による請求は無視せず、適切な対応を取るべきでしょう。
3-2 主債務者・連帯保証人が債務の承認をしたとき
主債務者や連帯保証人が債務の存在を認める行為を行うと、その時点で時効が更新されます。たとえば、債権者に対して支払いを猶予するよう求める行為は、「債務の承認」として法的に認められ、時効期間が更新されるのです。
なお、債務の承認は書面だけでなく口頭で行われた場合でも、時効の更新は有効とされます。たとえば、連帯保証人が債権者と対面して、もしくは電話にて、「支払いを少し待ってほしい」と口頭で伝えた場合、債務の承認と見なされます。
3-3 主債務者が一部弁済を行ったとき
連帯保証人の時効更新の一因として、主債務者が一部弁済を行う場合が挙げられます。この際、主債務者の行動は連帯保証人の時効にも影響を与えるのです。
特に、時効期間が経過する前と後では、影響の度合いが異なります。
3-3-1 主債務者が一部弁済を行った場合の連帯保証人への影響
主債務者が一部弁済を行った場合の連帯保証人への影響は、以下の表のとおりです。
| 主債務者が一部弁済を行った時期 | 連帯保証人への影響 |
| 時効期間の経過前 | 主債務の時効および連帯保証人の時効が更新され、連帯保証人の時効援用が困難になる |
| 時効期間の経過後 | 主債務者の時効援用権は消滅するが、連帯保証人の時効援用権には影響がなく、連帯保証人は時効援用を主張できる |
3-4 主債務者が自己破産をしたとき
主債務者が自己破産を申請すると、その破産手続が「管財事件」と「同時廃止事件」の、どちらで進行するかによって、連帯保証人の時効への影響も異なります。
管財事件とは、破産者が処分可能な一定以上の財産を持っている場合に適用される、破産管財人が選任されて財産の管理や清算が行われる破産手続です。一方、同時廃止は、処分する財産がほとんどない場合の、略式の破産手続となります。
自己破産における管財事件と同時廃止の違いについては、費用や手順の詳細も含めて、以下の記事で解説しています。そちらも、ぜひ参考にご覧ください。
3-4-1 管財事件と同時廃止の取扱いの違い
管財事件と同時廃止の取扱いの違いは、以下の表のとおりです。
| 破産手続の種類 | 連帯保証人への影響 |
| 管財事件 | 破産手続において債権者が債権を届け出た場合、連帯保証人の時効が更新され、新たに10年の時効期間が開始される |
| 同時廃止事件 | 財産がないため債権者の届け出がなく、連帯保証人の時効が更新されず、既存の時効期間がそのまま進行する |
時効の更新は、連帯保証人にとって予期せぬ負担をもたらしかねません。専門家であれば時効援用のタイミングや手続についての適切な判断でき、リスクを最小限に抑えられます。連帯保証債務の時効援用は、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。個々のケースに応じた提案にて、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
4章 連帯保証人が時効援用する方法・必要書類
連帯保証人が時効を援用するには、「時効援用通知書」を作成し、債権者に内容証明郵便にて送付します。時効援用通知書は、債権者に対し債務の消滅時効を主張する手段です。
具体的な時効援用の流れとしては、次の3つのフェーズを経て行われます。
- Fase1:消滅時効の成立を確認
- Fase2:時効援用通知書の作成
- Fase3:債権者に内容証明郵便で時効援用通知書を送付
時効援用通知書は、内容証明郵便(いつ誰が誰にどういう内容を差し出したかを郵便局が証明する制度)を利用して送付するのが一般的です。
内容証明郵便はインターネットを利用して送る「e内容証明(電子内容証明)」もあり、これを利用すれば簡便に手続を進められます。
ただし、書式に不備があったり、送るタイミングを間違えたりすると、時効の完成が困難になるので、専門家の助言を受けながら進めるのがよいでしょう。
時効援用の方法の詳細や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。そちらも、ぜひ参考にご覧ください。
5章 【注意】時効援用を自分で行うのは現実的ではない
連帯保証人が時効援用を自分で行うのは現実的ではないといえるでしょう。これは、時効援用の成立には複雑な法律的条件が関わり、個々のケースで異なる判断が必要だからです。
特に、主債務者が時効の途中で弁済を行ったり、債務を認めるたりするような行為をしていないか確認する必要があります。また、債権者が裁判を起こした場合には時効が更新されるため、その記録も精査しなければなりません。
これらの要素を正確に把握するためには、専門的な知識が不可欠です 。また、時効援用を行う際に内容証明郵便を使って送る、前述の「時効援用通知書」の作成には、法律の専門知識が要求され、内容や形式に不備があると時効援用が無効になるおそれがあります。
加えて、通知後に債権者とやり取りをする際には、言動が債務の承認とみなされないよう慎重に対応しなければなりません 。時効援用を自分で行うのは、リスクが伴う可能性が高いため、実際には司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが現実的な選択です。
専門家は時効の成立要件を満たしているかどうかを適切に判断し、必要な手続を代行できます。長期にわたり請求されていない借金があるなら、まずは司法書士や弁護士に相談しましょう。連帯保証債務の時効援用なら、グリーン司法書士法人にご相談ください。個々のケースに応じた提案で、実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
6章 連帯保証人が時効援用するときの注意点
連帯保証人が時効援用する際には、次に挙げる2項目に注意する必要があります。
- 連帯保証人が複数いる場合は個別に時効がカウントされる
- 連帯保証人も主債務の時効を主張できる
それぞれを補足しておきましょう。
6-1 連帯保証人が複数いる場合は個別に時効がカウントされる
連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人の時効は相対的にカウントされます。これは、各連帯保証人が独立して債務を保証しているためです。ひとりの連帯保証人が債務を承認したり支払いを行ったりした場合でも、ほかの連帯保証人の時効には影響を与えません。
逆にいえば、ある連帯保証人が時効を援用しても、ほかの連帯保証人が時効援用を行わなければ、債務が残ることになります。
この相対性は、連帯保証人が時効援用を検討する際に重要なポイントとなります。また、連帯保証人同士で情報を共有し、最適な時効援用のタイミングを見計らうのも賢明です。
連帯保証人が複数いる場合は、各人の状況に応じた手続を個別で踏む必要があります。専門家のサポートを受ければ、各連帯保証人の状況に最も適した時効援用を進められるでしょう。連帯保証債務の時効援用は、グリーン司法書士法人にご相談ください。個々のケースに応じた解決方法で、実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
6-2 連帯保証人も主債務の時効を主張できる
連帯保証人は、連帯保証債務だけでなく主債務の時効援用を主張できます。これは、連帯保証債務が主債務に従属する「附従性」を持つためです。
主債務が時効によって消滅すると、その結果として連帯保証債務も消滅することになります。連帯保証人は主債務者の時効が成立しているかどうかを確認したうえで、必要に応じて附従性を利用して、主債務の時効援用を進めましょう。
なお参考までに、奇妙な状態ですが「連帯保証人だけに時効の更新が起こっている」というケースが、ごくまれにあります。前述の附従性はややこしい論点なので、金融機関が間違えて、ということが起こりえるようです。
まとめ
連帯保証人が時効援用を行う際には、まず債務の時効期間を正確に把握することが重要です。一般的には5年または10年が時効期間とされており、この期間が経過すれば債務は法的に消滅する可能性があります。
しかし、時効の成立には、債権者からの請求や債務者の返済などによる更新や中断が関与するため、詳細な確認が不可欠です。また、連帯保証人自身が債務を承認する行為を行うと、時効援用の権利を失うため、注意が必要となります。
また、連帯保証人が複数いる場合、それぞれの時効は個別にカウントされるため、他の連帯保証人の行動が自分の時効援用に影響を与えることはありません。しかし、主債務者が時効援用を行った場合、連帯保証人もその影響を受けます。
この附従性を利用して、連帯保証人が主債務の時効を援用するのも可能です。このように、連帯保証人としての立場は複雑であり、正確な情報と専門的な知識が求められます。
連帯保証人としての債務の時効援用を考えておられるみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。債務問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
時効の援用に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:消滅時効
時効援用の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!