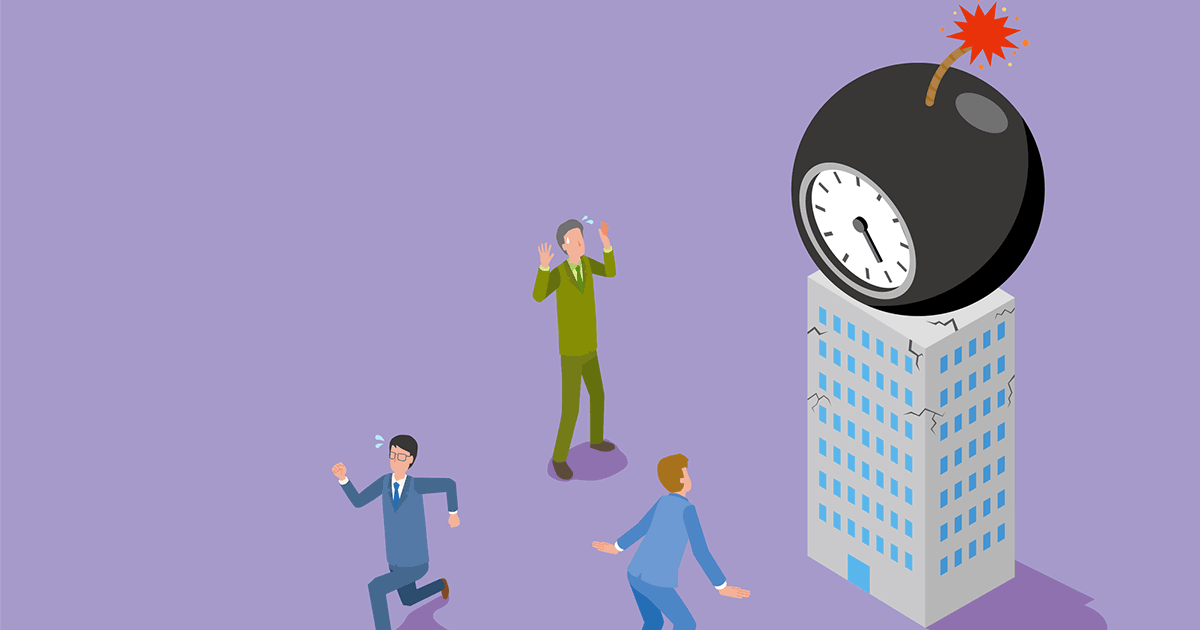この記事は約 19 分で読めます。
- 倒産しそうな会社の特徴
- 会社が倒産すると起きること
- 会社の倒産を防ぐためにすべきこと
会社の経営は、常に順風満帆とは限りません。市場の変動や内部の問題が原因で、経営が傾き始めることもあります。経営者としては、早期にその兆候を察知し、適切な対策を講じることが求められます。
今回の記事では、倒産しそうな会社に見られる21の特徴を紹介し、それぞれの特徴について具体的に解説します。また、倒産を防ぐための具体的な対策についても見ていきましょう。
目次 ▼
1章 倒産しそうな会社の特徴21個
倒産しそうな会社には、次の21の特徴のいずれかが見られます。
- 経営陣が辞めていく
- 経理部門が辞めていく
- 細かい経費を削減しようとする
- 上層部・経営陣の打ち合わせ回数が増えてきている
- 業務量が少なくなった
- 設備投資が難しくなった
- 同業他社の評判が悪くなってきた
- 大口の取引先が倒産した
- ボーナスの支給が難しくなってきた
- 手当の支給が難しくなってきた
- 給料を減額せざるを得なくなった
- 従業員のノルマが厳しくなってきた
- 給料の振り込みが間に合わなくなってきた
- 希望退職者を募ろうか検討している
- 取引先への支払いが遅れてしまう
- 銀行の内部視察が増えた
- 督促状が届く
- 資産売却を検討している
- 売掛金を早期回収しようとしている
- 取引先から付き合いを断られる
- 銀行の借入審査が通らない
それぞれの特徴を、補足しておきましょう。
1-1 経営陣が辞めていく
経営陣が辞めていく現象は、会社が倒産の危機に直面している兆候のひとつです。経営陣は会社の内部情報に精通しているため、財務状況や経営戦略の失敗をいち早く察知します。
そのため、経営陣が次々と退職する場合、会社の将来に対する不安が高まっている可能性があります。特にCEOやCFOなどの主要なポジションが空席になると、会社の運営に重大な影響を与えかねません。
また、経営陣の退職は、社員や投資家にも不安を与え、士気の低下や株価の下落を招くことがあります。経営陣が去る理由としては、会社の将来性に対する疑念や、内部での対立、あるいはよりよい機会を求めるためなどが考えられます。
なお、会社更生や民事再生ができず会社が倒産した場合の、経営者や経営陣がどうなるのかや自己破産時に受ける影響について、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
1-2 経理部門が辞めていく
経理部門の従業員が次々と辞めていくことも、会社が倒産の危機に瀕しているサインです。経理部門は会社の財務状況を直接管理しているため、財務問題や経営の不透明さを最も早く察知する部門です。
そのため、経理部門の離職率が高まると、会社の内部で何か問題が起きている可能性が高いと考えられます。たとえば、未払いの請求書や増大する負債、キャッシュフローの問題などが原因で、経理部門がプレッシャーを感じて辞めることがあります。
さらに、経理部門の人員が減少すると、財務管理がさらに困難になり、悪循環に陥るリスクも否めません。したがって、経理部門の離職が増えた場合は、早急に原因を調査し、適切な対策を講じる必要があります。
1-3 細かい経費を削減しようとする
会社が倒産の危機に直面している場合、細かい経費を削減しようとする傾向が見られます。経営陣は、財務状況が悪化する中で、コストカットを図るためにさまざまな手段を講じます。
たとえば、日常的な経費削減への注力です。オフィスの備品や消耗品、出張費用のカット、福利厚生の見直しなどが挙げられます。これらの削減策は一時的な効果しか持たず、根本的な財務問題の解決には至りません。
むしろ、従業員の士気低下や作業効率の悪化を招く可能性があります。細かい経費の削減が頻繁に行われるようになった場合、会社の財務状況が深刻であることを示唆していると考えられます。
1-4 上層部・経営陣の打ち合わせ回数が増えてきている
上層部や経営陣の打ち合わせ回数の増加は、会社が倒産の危機に直面している兆候のひとつです。通常、経営陣が頻繁に会議を行うのは、重大な問題に直面している場合や、緊急の対策を必要とする状況下です。
特に、財務状況の悪化や重要な取引先とのトラブルなど、会社の存続に関わる問題が発生している可能性があります。また、経営戦略の見直しやリストラ計画など、社内で大きな変革を検討している場合も会議が増える傾向があります。
こうした状況は社員にも伝わり、士気の低下や不安感を招くことが多いです。上層部の会議が頻繁になることは、会社の安定性に疑問が生じていることの、ひとつのサインといえるでしょう。
1-5 業務量が少なくなった
業務量の減少も、会社が倒産の危機に直面している兆候のひとつです。通常、業務量の減少は、受注の減少や取引先の倒産などが原因です。
また、新規プロジェクトの縮小やキャンセルも業務量の減少につながります。このような状況では、社員の業務負担が軽くなり、社内の活気が失われることが多いです。
さらに、業務量の減少は、収益の低下に直結するため、会社の財務状況にも悪影響を与えます。それによって、従業員のリストラや給与の遅配などの問題が発生する可能性が高まります。
1-6 設備投資が難しくなった
設備投資が難しくなることも、会社が倒産の危機に直面している兆候のひとつです。通常、設備投資は会社の成長や競争力の維持に必要不可欠ですが、財務状況が悪化すると資金不足により設備投資が困難になります。
特に、老朽化した設備の更新ができない場合、業務効率の低下や品質の低下が懸念されます。また、設備投資の停滞は、競争力の低下につながり、市場でのシェアを失うリスクも否めません。
さらに、設備投資ができない状況は、取引先や投資家に対する信頼感の低下を招き、会社全体の評価にも悪影響を与えることがあります。このような状況は、会社の経営が危機的な状況にあることを暗示しています。
1-7 同業他社の評判が悪くなってきた
同業他社の評判が悪くなることは、業界全体の健康状態を反映している可能性があります。もし同業他社が次々と倒産したり、評判が悪化したりしている場合、その業界に共通する問題が潜んでいるかもしれません。
たとえば、需要の減少や競争の激化、技術革新の遅れなどが考えられます。同業他社の悪評は、自社にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
特に、同業他社の倒産が相次ぐ場合、自社も倒産の危険にさらされるかもしれません。このような状況では、業界全体のトレンドを注意深く監視し、自社の戦略を見直す必要があります。
1-8 大口の取引先が倒産した
大口の取引先が倒産すると、会社にとって大きな打撃です。取引先の倒産により、売上の大幅な減少や売掛金の未回収が発生し、キャッシュフローが悪化する恐れがあります。
特に、大口の取引先からの売上が会社の収益の大部分を占めている場合、その影響は甚大です。それによって、従業員の給与支払いや固定費の捻出が難しくなることがあります。
加えて、銀行からの信用が低下し、追加融資が受けられなくなるリスクもあります。このような状況に備えて、取引信用保険を利用するなどの対策を講じることが重要です。
1-9 ボーナスの支給が難しくなってきた
ボーナスの支給が難しくなることは、会社の財務状況が悪化している兆候です。通常、ボーナスは会社の業績が良好である場合に支給されるため、これが支給されない、もしくは大幅に減額される場合、会社の収益が減少していることを意味します。
ボーナスが支給されないことで、社員の士気低下を招き、さらなる生産性の低下を引き起こすかもしれません。会社は賞与積立金を計画的に蓄えることで、安定した支給の維持が求められます。
1-10 手当の支給が難しくなってきた
手当の支給が難しくなることも、会社の財務状況が悪化しているサインです。特に、通勤手当や家族手当、資格手当などの支給が減少する場合、会社はコストカットを強いられていることが考えられます。
これらの手当は社員の生活に直接影響を与えるため、削減されると社員のモチベーションや会社へのエンゲージメントが低下するかもしれません
手当が減額される背景には、売上の減少や利益率の低下があることが多いため、経営陣は根本的な財務改善を図る必要があります。従業員に対する透明な説明と、将来的な改善計画の共有が重要です。
1-11 給料を減額せざるを得なくなった
給料の減額は、会社の経営が危機的状況にあることを示す明確な兆候です。法律では不当な理由での給料減額を禁じていますが、会社の財務状況が極めて悪化した場合、給料を減額せざるを得ないことがあります。
これは、社員の生活に重大な影響を与えるため、深刻な問題です。給料の減額は、社員の士気や生産性に悪影響を及ぼし、結果的に会社のパフォーマンス全体を低下させるリスクがあります。
経営陣は、このような状況に陥らないように、早期に財務改善策を講じるとともに、社員に対しても誠実な状況説明が求められます。
1-12 従業員のノルマが厳しくなってきた
従業員に課されるノルマが急に厳しくなることは、会社の業績が思わしくない兆候のひとつです。経営が苦しい場合、会社は売上や利益を上げるために、従業員に過剰なプレッシャーをかけることがあります。
特に、営業目標や生産目標が急激に引き上げられた場合、経営陣が売上を無理にでも伸ばそうとしている可能性が高いです。ノルマが過度に厳しくなると、従業員の士気が低下し、結果としてパフォーマンスの低下や離職率の上昇を招くことがあります。
また、ノルマを達成するための無理な営業活動が顧客との信頼関係を損なうリスクも否めません。このような状況に対処するためには、現実的な目標設定と社員の働きやすい環境づくりが重要です。
1-13 給料の振り込みが間に合わなくなってきた
給料の振り込みが遅れることは、会社の資金繰りが非常に厳しい状態を示しています。通常、給与の支払いは最優先されるべき事項であり、これが滞る場合、会社のキャッシュフローが極めて不安定であることを意味します。
特に、給与が毎月遅れるようになると、会社の倒産リスクが高まりかねません。従業員にとっては生活に直結する問題であり、給与の未払いが続くとモチベーションの低下や退職を招くことになります。
経営陣は、早急に財務状況を見直し、資金繰り改善策を講じる必要があります。たとえば、不要な経費の削減や新たな資金調達手段の検討が求められます。
1-14 希望退職者を募ろうか検討している
希望退職者を募ることは、会社が人件費を削減しようとしているサインです。特に、大規模な希望退職募集は、会社が深刻な経営危機に陥っていることを示唆します。
人件費は企業の固定費の中でも大きな割合を占めるため、経営が悪化するとまず人件費削減が検討されがちです。希望退職を募ることで一時的にコストを削減できます が、同時に重要な人材が流出するリスクもあります。
また、残った従業員の負担が増加し、士気の低下も避けられません。経営陣は、希望退職に頼らず、根本的な経営改善策の模索が求められます。
1-15 取引先への支払いが遅れてしまう
取引先への支払いが遅れることは、会社の財務状況が悪化している明らかなサインです。支払いの遅延は、取引先との信頼関係を損ない、取引条件の悪化や取引停止のリスクを伴います。
特に、重要な取引先への支払いが滞ると、サプライチェーン全体に悪影響を与える可能性が高まりかねません。また、支払いの遅延は会社の信用力を低下させ、新たな取引先の確保や金融機関からの融資を受ける際にも不利になります。
このような状況を避けるためには、財務管理を徹底し、キャッシュフローの改善策を講じることが重要です。
1-16 銀行の内部視察が増えた
銀行の内部視察が増えることは、会社の財務状況が懸念されている兆候です。通常、銀行は取引先企業の経営状況を定期的にチェックしますが、頻繁に視察が行われる場合、銀行がリスクを感じている可能性があります。
特に、融資先の財務状態が悪化している場合、銀行は返済能力を確認するために視察を増やします。それによって、会社はさらなるプレッシャーを受けることになります。
銀行の視察が増えた場合、経営陣は速やかに財務状況の改善策を講じ、銀行との信頼関係の維持が求められます。たとえば、資金繰りの見直しやコスト削減策の実施が考えられます。
1-17 督促状が届く
督促状とは、借金や未払い金を返済しない場合に債権者から送られる書面です。督促状の目的は、借金の返済を促すことにあり、法的効力は持ちませんが、企業にとっては不名誉かつ不安定な状態を示します。
会社に督促状が届いたら、まずは冷静に内容を確認し、返済のための資金繰りを検討する必要があります。返済が難しい場合は、すぐに債権者に連絡を取り、返済計画の見直しや分割払いの相談を行うことが推奨されます。
なお、督促状やそれが届いた際の対処方法については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
1-18 資産売却を検討している
会社が経済的困難に直面し、資金繰りが厳しくなると、資産売却を検討する場合があります。資産売却は、現金を確保するための最終手段として考えられることが多いです。
売却対象となる資産には、不動産、設備、在庫などが含まれます。資産の売却で一時的に現金を確保できるものの、長期的には経営資源の喪失となりえます。
資産売却の決断は、迅速かつ慎重に行う必要があります。まずは、不動産や高価な設備などの流動性が高い資産から売却を検討するのが一般的です。
次に、不要な在庫や余剰資産を売却して資金を調達します。ただし、これらの売却は一時的な資金繰りの改善にしかならず、根本的な経営改善策を講じる必要があります。
資産売却後の資金の使い道を明確にし、無駄な支出を抑えることが重要です。経営再建に向けた戦略的な計画を立てることも必要です。
1-19 売掛金を早期回収しようとしている
企業が資金繰りに困窮すると、売掛金の早期回収を積極的に行うことがあります。売掛金とは、商品の販売やサービスの提供後に受け取るべき代金のことです。
早期回収のためには、顧客との関係を損なわないよう、慎重な対応が求められます。具体的には、未収金のリストを作成し、優先順位をつけて回収を進めます。
また、顧客に対し、柔軟な支払い条件の提示も有効です。たとえば、分割払いの提案や、早期支払いに対する割引の提案で、回収を促進できます。
さらに、定期的なフォローアップを行い、支払いの確認を怠らないことが重要です。売掛金回収の専門家やコンサルタントの活用も考慮すべきです。
回収が進まない場合は、法的手段を検討する場合もあります。売掛金の回収が進むことで、企業の資金繰りが改善される可能性も残されています。
1-20 取引先から付き合いを断られる
取引先からの付き合いを断られることは、倒産の兆候として非常に深刻です。企業間の信用関係が崩れると、取引先はリスクを避けるために関係を見直すことがあります。
特に、大口の取引先からの取引停止は、企業の収益に直接影響します。このような事態は、取引先からの支払い遅延や、品質や納期に関する問題が原因となることが多いです。
また、企業の財務状況が悪化している場合も、取引先はそのリスクを避けるために関係を断つことがあります。取引先からの信頼を失うことは、新規の取引先獲得にも悪影響を及ぼします。
その結果、売上の減少やキャッシュフローの悪化がさらに進みます。このような状況を避けるためには、日頃から取引先とのコミュニケーションを密にし、問題が発生した際には迅速な対応が重要です。
1-21 銀行の借入審査が通らない
銀行の借入審査が通らないことも、企業の倒産リスクを示す重大なサインです。銀行は企業の財務状況や信用情報を厳しくチェックします。
借入審査が通らない理由には、既存の借入金の返済遅延や、財務諸表の健全性が損なわれていることが挙げられます。また、売上の減少や利益率の低下も審査通過の障害です。
特に、複数の金融機関からの借入がある場合、その管理が不十分だと審査に影響を及ぼすことがあります。審査が通らないことで、必要な資金調達ができず、経営資金の枯渇につながりかねません。
その結果、日常業務に支障が出るだけでなく、従業員への給与支払いが滞ることも考えられます。銀行からの信頼を得るためには、透明性の高い財務管理と、健全な経営体制の維持が必要です。
2章 会社が倒産すると起きること
会社が倒産すると、次の2つのことが起こります。
- 会社の資産を失ってしまう
- 社員は全員解雇になってしまう
個別に見ていきましょう。
2-1 会社の資産を失ってしまう
会社が倒産すると、まずその資産はすべて失われます。清算の過程で、会社の財産は債権者に分配され、事実上ゼロになるためです。
これには不動産、設備、在庫などすべてが含まれます。さらに、倒産した企業が大きければ大きいほど、影響を受ける関係者も多くなります。
特に大企業の場合、その影響は業界全体に波及し、連鎖的な倒産を引き起こす可能性もあります。加えて、消費者にも影響を与えることがあり、特定の製品やサービスが市場から消えることになります。
そのため、倒産は企業内部だけでなく、広範な経済的影響を及ぼす重大な事象です。企業経営者は、倒産リスクを最小限に抑えるために、常に健全な財務管理を行うことが求められます。
従業員の失業問題も深刻で、再就職の支援が必要です。倒産後の対応策として、社員や取引先への迅速な通知と対応が求められます。
なお、会社倒産時に経営者は負債の返済義務を負うのかどうかや、責任が問われることについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。
2-2 社員は全員解雇になってしまう
会社が倒産すると、社員は全員解雇されることになります。仕事を失った社員は、新しい職を探さなければなりません。
特に倒産が大規模なものである場合、多くの社員が同時に失職し、その影響は大きくなります。さらに、未払い賃金や退職金の問題も発生するでしょう。
倒産により、従業員の生活は大きく影響を受けます。社員だけでなく、その家族にも経済的な打撃が及ぶ可能性があります。倒産後、従業員は失業保険の申請や、再就職支援サービスの利用を検討する必要があります。
また、倒産が公になると、その企業に関連する取引先や顧客にも影響が波及します。従業員の立場から見ると、倒産は予期しない突然の出来事であり、精神的なショックも大きいです。
したがって、企業側は倒産前に従業員への情報提供やサポートを行うことが重要です。
なお、会社倒産時に従業員は全員解雇になるのかどうかや、そのタイミングや流れについて、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
3章 会社の倒産を防ぐためにすべきこと
会社の倒産を防ぐためにすべきことには、主に次の4項目があります。
- 資金管理を徹底する
- 取引先の状況を把握する
- 無理のない借入を行う
- 経営判断を小まめに行う
ひとつずつ見ていきましょう。
3-1 資金管理を徹底する
資金管理の徹底は、倒産を防ぐために最も重要な対策のひとつです。まず、キャッシュフローの見える化を図り、毎月の収入と支出の詳細な把握が求められます。
資金繰り表を作成すれば、予算と実績の比較で、異常が発生した際に早期に対処できます。また、無駄な支出を削減したうえでの、利益の最大化も重要です。
さらに、短期的な資金調達の手段として、売掛金の早期回収や在庫の適正管理も有効です。資金繰りが厳しい場合は、金融機関と交渉し、リスケジュールや追加融資の依頼も検討しましょう。
それによって、手元のキャッシュを確保し、経営の安定化を図れます。加えて、定期的な資金状況のチェックと、経営陣の迅速な意思決定が重要です。特に、予期せぬトラブルが発生した際には、速やかに対応策を講じることが求められます。
3-2 取引先の状況を把握する
取引先の状況の把握は、倒産リスクを回避するために欠かせません。取引先の財務状況や経営状態を定期的に確認したうえでの、信用度の評価が大切です。
特に、大口の取引先が倒産した場合、自社にも大きな影響が及ぶため、リスク分散を図ることが推奨されます。具体的には、取引先の決算書を定期的に確認し、異常が見られた場合は早期に対応策を講じなければなりません。
また、取引先との関係を良好に保つために、コミュニケーションを密にし、問題が発生した際には迅速に情報共有を行いましょう。さらに、新規取引先の開拓を積極的に行い、取引先の多様化を図ることもリスク管理の一環です。
取引先の信用力の把握で、取引のリスクを最小限に抑え、安定したビジネス関係を維持できます。
3-3 無理のない借入を行う
無理のない借入を行うことは、企業の健全な経営にとって重要です。借入額が過大になると、返済負担が増加し、資金繰りが悪化するリスクが高まります。
まずは、事業計画を慎重に策定し、返済計画の明確化が求められます。金融機関との交渉では、借入の目的や返済能力を十分に説明し、適切な融資を受けることが重要です。
また、借入に頼りすぎず、内部留保や自己資本の増強を図ることも大切です。借入金の管理には、定期的な見直しと、必要に応じたリスケジュールが有効です。
さらに、借入の際には、金利や返済条件をよく確認し、最適な条件を選ぶよう心がけましょう。無理のない借入を行うことで、経営の安定化と長期的な成長を目指せます。
3-4 経営判断を小まめに行う
経営判断を小まめに行うことは、企業の持続的な成長と倒産回避に不可欠です。市場の変化や経営環境の変動に対応するためには、迅速かつ的確な意思決定が求められます。
まずは、経営陣が定期的にミーティングを行い、最新の経営状況の共有が大切です。また、経営戦略を柔軟に見直し、必要に応じて修正を加えることも欠かせません。
たとえば、新規事業の展開やコスト削減策の導入など、状況に応じた対応策を講じる必要があります。さらに、従業員や取引先からのフィードバックを積極的に取り入れ、経営判断の材料としましょう。
小まめな経営判断を行うことで、リスクを早期に察知し、適切な対応策を講じることができます。それによって、経営の安定化と持続的な成長を実現できます。
まとめ
倒産の兆候を見逃さないことは、企業の存続にとって極めて重要です。たとえば、経営陣や経理部門の退職、資金繰りの悪化、取引先からの信用低下などの兆候に気づいたら、直ちに詳細な調査と改善策の実施が必要です。
また、資金管理の徹底、取引先の状況把握、無理のない借入、そして小まめな経営判断が倒産を回避するための基本的な対策となります。倒産を防ぐためには、日常的な資金管理や取引先の信用調査を怠らないことが大切です。
キャッシュフローを常に把握し、適切な借入を行い、経営戦略を適時に見直すことで、倒産リスクを低減できます。さらに、従業員や取引先との良好な関係を維持し、問題が発生した際には迅速な対応が求められます。
なお、会社の再建や整理の手続に関してお困りの経営者のみなさんは、グリーン司法書士法人にお気軽にお問合せください。司法書士としてサポートできる範囲で、お力になります。