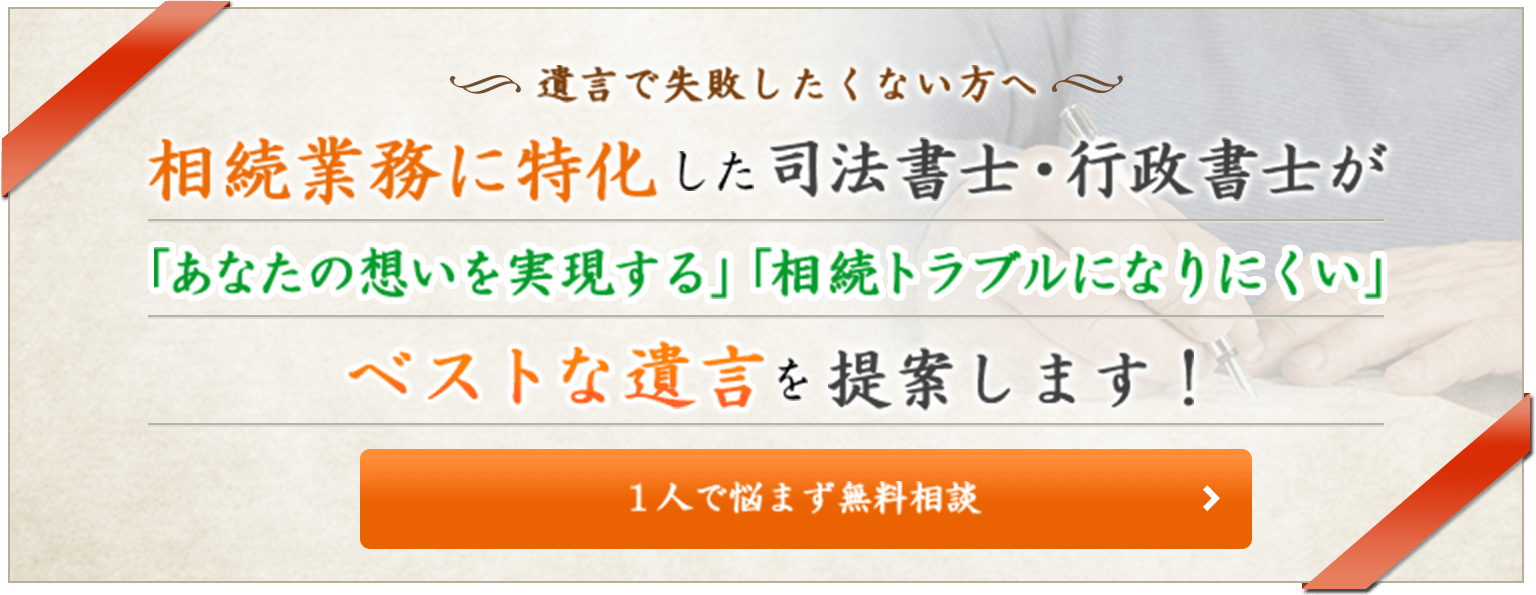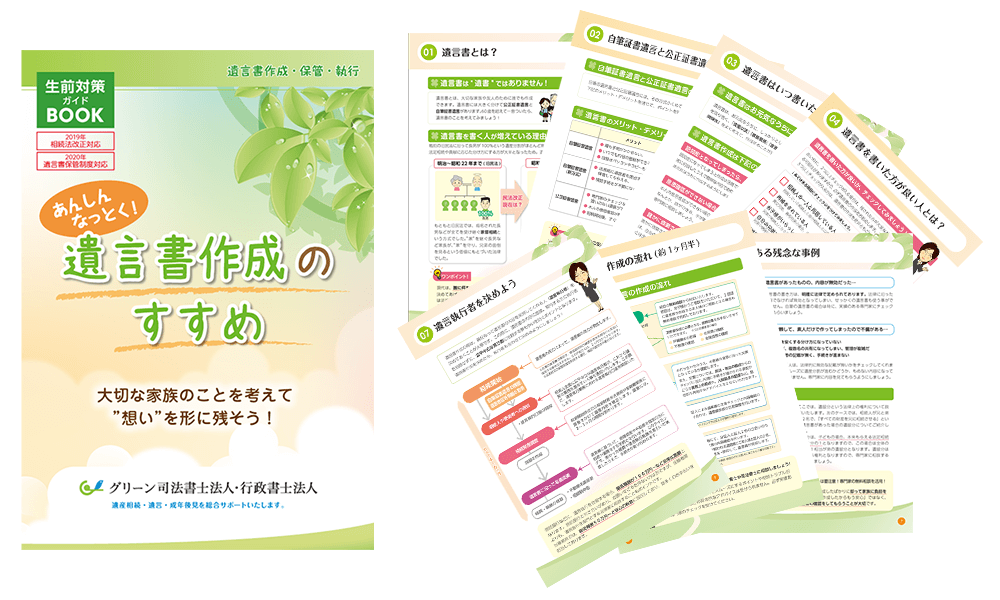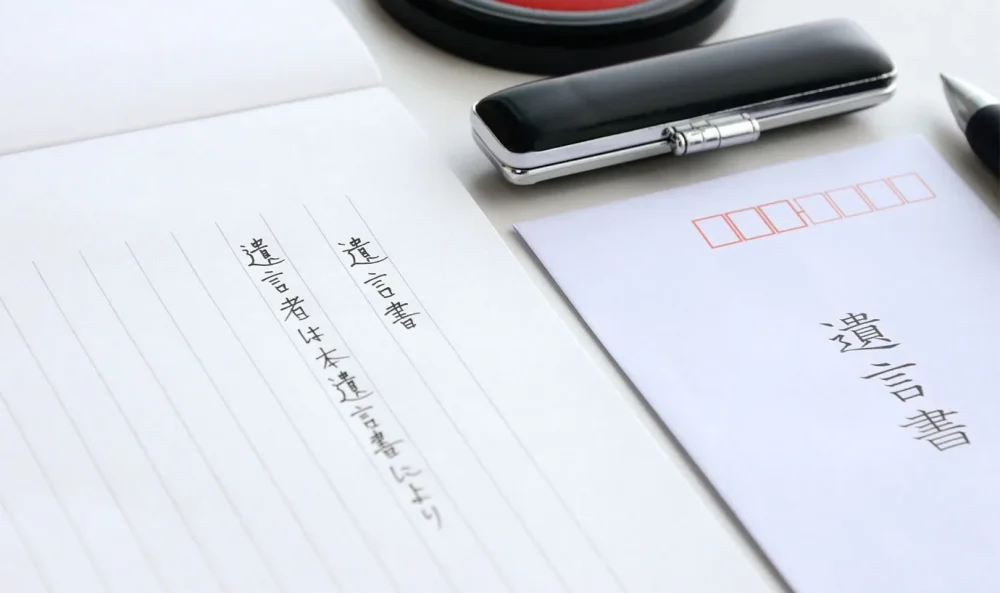
【この記事でわかること】
- 遺言書が無効になるケースとは何か
- 遺言書を勝手に開封しても無効にならない
- 遺言書を無効にしたいときの対処法
遺言書を用意しておけば、希望の人物に財産を受け継いでもらえます。
その一方で、所定の要件を満たしていない場合には、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう恐れもあるので注意しなければなりません。
遺言書には複数の種類があり、それぞれの特徴は、下記の通りです。
| 遺言書の種類 | 作成がおすすめな人 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言書の作成に費用をかけたくない人 |
| 公正証書遺言 | 信頼性が高い遺言書を作成したい人 |
| 秘密証書遺言 | 遺言の内容を誰にも知られたくない人 |
また、遺言書はそれぞれ要件が定められており、要件を満たしていない場合は、無効となってしまいます。
遺言書が無効になることを防ぎたいのであれば、相続に精通した司法書士や弁護士などに遺言書の作成を依頼することをおすすめします。
本記事では、遺言書が無効になってしまうケースや、遺言書を無効にしたいときの対処法を解説します。
目次
- 1 1章 遺言書が無効になる13のケース
- 1.1 1-1 【すべての遺言】遺言書に他の人の意思が介在している可能性がある
- 1.2 1-2 【すべての遺言】遺言書が偽造されている
- 1.3 1-3 【すべての遺言】遺言書の内容が公序良俗に違反している
- 1.4 1-4 【すべての遺言】新しい遺言と内容が矛盾している
- 1.5 1-5 【すべての遺言】15歳未満の人が作成した
- 1.6 1-6 【すべての遺言】作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下している
- 1.7 1-7 【自筆証書遺言】遺言書を自筆で書いていない
- 1.8 1-8 【自筆証書遺言】遺言書に日付の記載がない
- 1.9 1-9 【自筆証書遺言】遺言書に署名・押印がない
- 1.10 1-10 【自筆証書遺言】遺言書の内容が不明確である
- 1.11 1-11 【自筆証書遺言】遺言書の加筆・修正の方法が適切でない
- 1.12 1-12 【自筆証書遺言】遺言書が共同で書かれている
- 1.13 1-13 【公正証書遺言】不適切な証人を立てた
- 2 2章 遺言書を勝手に開封しても無効にならない
- 3 3章 遺言書を無効にしたいときの対処法
- 4 まとめ
1章 遺言書が無効になる13のケース
遺言書は種類ごとに要件が定められており、満たしていないと無効になってしまいます。
遺言書が無効になるケースは、主に下記の通りです。
- 【すべての遺言】遺言書に他の人の意思が介在している可能性がある
- 【すべての遺言】遺言書が偽造されている
- 【すべての遺言】遺言書の内容が公序良俗に違反している
- 【すべての遺言】新しい遺言と内容が矛盾している
- 【すべての遺言】15歳未満の人が作成した
- 【すべての遺言】作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下している
- 【自筆証書遺言】遺言書を自筆で書いていない
- 【自筆証書遺言】遺言書に日付の記載がない
- 【自筆証書遺言】遺言書に署名・押印がない
- 【自筆証書遺言】遺言書の内容が不明確である
- 【自筆証書遺言】遺言書の加筆・修正の方法が適切でない
- 【自筆証書遺言】遺言書が共同で書かれている
- 【公正証書遺言】不適切な証人を立てた
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 【すべての遺言】遺言書に他の人の意思が介在している可能性がある
遺言者が詐欺や強迫を受けていた疑いがあるような場合や、遺言の内容に他人の意思が介入しているとみなされた場合には、遺言は無効になります。
ただし、自動的に遺言が無効になるわけではなく、相続人などが「遺言無効確認訴訟」を申立て、認めてもらう必要があります。
とはいえ、遺言者が詐欺や強迫を受けていたといった証拠を用意することは困難なことが多く、争いが長引くことも珍しくありません。
1-2 【すべての遺言】遺言書が偽造されている
見つかった遺言書が正式なものではなく、偽造されたものだった場合には、その遺言は無効と判断されます。
さらに、遺言書を偽造することは「相続欠格事由」に該当するため、その人物は相続人としての資格を永久に失います。
1-3 【すべての遺言】遺言書の内容が公序良俗に違反している
遺言の内容が公序良俗に反する場合、その遺言は無効とみなされます。
例えば「不倫相手に全財産を相続させる」といった遺言内容は、公序良俗違反と判断される可能性があり、効力を持たないことがあります。
ただし、不倫相手に財産を遺す遺言がすべて無効になるわけではなく、遺言の有効性はケースごとに判断されます。
具体的な事情や背景が考慮されるため、一律に無効と決まるものではありません。
なお、公正証書遺言を作成する際には、公序良俗に反する内容については公証人が指摘し、作成が中止されることがほとんどです。
そのため、実際にこのような遺言が正式に残されるケースは極めて稀です。
1-4 【すべての遺言】新しい遺言と内容が矛盾している
複数の遺言書が法的な要件を満たしている場合、原則として最新の日付のものが優先されます。
そのため、内容に食い違いがある複数の遺言書が存在する場合は、もっとも新しく作成された遺言書が有効とされ、以前に作られたものは無効となるのが一般的です。
1-5 【すべての遺言】15歳未満の人が作成した
遺言書を作成できるのは、法律上15歳以上と定められています。
そのため、15歳に達していない人が作成した遺言は、どのような内容や形式であっても無効となります。
1-6 【すべての遺言】作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下している
遺言書を作成する際、遺言者が認知症などにより判断能力を失っていると、その遺言書は無効と判断される可能性があります。
認知症などにより判断能力を喪失した状態では、遺言書の作成をはじめとする法律行為が認められなくなるからです。
公正証書遺言を作る場合には、公証人のほかに2名の証人が立ち会うため「判断能力に問題があれば誰かが気づくのでは?」と思うかもしれません。
しかし、実際には判断能力が著しく低下しているにもかかわらず、公正証書遺言が作成されてしまうケースも存在します。
公正証書遺言の作成にあたっては、事前に公証人と内容を綿密に打ち合わせる必要があります。
司法書士や弁護士などの専門家に作成を依頼した場合には、打ち合わせも専門家が代行し、当日は遺言者が公証人に口頭で伝えるだけで手続きが進むのが一般的です。
そのため、遺言作成当日の遺言者の判断能力について、見落とされてしまう可能性があるのです。
もし、遺言執行の段階でこの口述が適切に行われたか疑問が生じた場合、相続人から「遺言無効確認の訴訟」が起こされ、それが認められれば遺言は無効となってしまいます。
1-7 【自筆証書遺言】遺言書を自筆で書いていない
自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を手書きで作成しなければならず、パソコンやワープロで作成した遺言は無効です。
ただし、2019年1月の法改正により、財産の内容を記載する「目録」に限っては、手書きでなくても差し支えないことになりました。
例えば、パソコンで作成した財産目録や、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付資料として利用することが可能です。
とはいえ、法改正後も目録以外の遺言部分については、すべて手書きで作成する必要がありますので、その点にはご注意ください。
また、自筆証書遺言はあくまで「自筆」が求められる形式のため、音声や映像による遺言は有効とは認められません。
1-8 【自筆証書遺言】遺言書に日付の記載がない
遺言書においては、「いつ作成されたか」が非常に重要な要素となるため、日付の記載がない遺言書は無効と判断されます。
また、作成日が特定できる必要があるため、「●年■月吉日」といったように日付が曖昧な表現は認められていません。
一方で、「●年の誕生日」や「還暦の日」など、具体的な日付が明記されていなくても、その日が明確に特定できるものであれば有効とされます。
とはいえ、確実性を高めるためにも、年月日をしっかりと書いておくことをおすすめします。
1-9 【自筆証書遺言】遺言書に署名・押印がない
遺言書では、誰が作成したのかを明確にするために、「署名」と「押印」が欠かせません。
署名や押印がない場合には、自筆証書遺言としての効力が認められなくなります。
なお、押印に関しては実印である必要はなく、認印やシャチハタタイプのインク印、さらには拇印でも差し支えないとされています。
とはいえ、遺言書の信頼性をより高めたい場合には、実印で押印し、印鑑証明書を添えておくと良いでしょう。
1-10 【自筆証書遺言】遺言書の内容が不明確である
遺言の内容があいまいである場合には、無効と判断される可能性があります。
遺言書は第三者、たとえば裁判官が見ても、どの財産を指しているのかがはっきりと分かるように記載しなければなりません。
例えば、不動産について言えば、「住所」と「地番」は異なるため、住所だけを記載しても物件を特定できず、無効とされるリスクがあります。
そのため、不動産を遺言に盛り込む際は、登記簿に記載されている以下の情報を正確に記載しましょう。
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 家屋番号
- 構造
- 床面積
これらの記載が難しい場合には、財産目録に登記事項証明書を添付し、日付・署名・押印をしておく方法でも対応可能です。
1-11 【自筆証書遺言】遺言書の加筆・修正の方法が適切でない
自筆証書遺言において、加筆や修正が適切に行われていない場合には、その遺言自体が無効となる可能性があります。
これは、遺言書が後から他人によって改ざんされるリスクがあるため、通常の文書よりも修正に関するルールが法律で厳しく定められているためです。
自筆証書遺言を修正する際の基本的な手順は以下の通りです。
- 修正箇所に二重線を引く
- 修正した内容をその横に書き、印を押す
- 遺言書の余白(末尾など)に「●行目の●文字を削除し、●文字を加筆した」といった形で補足を記載する
このように、修正には細かな決まりがあるため、訂正箇所が多い場合は、一から書き直す方が確実でスムーズです。
1-12 【自筆証書遺言】遺言書が共同で書かれている
遺言書は単独で作成する必要があり、共同で作成したものは無効となってしまいます。
たとえ夫婦であっても、共同で作成するのは絶対にやめましょう。
これは、共同の遺言が認められてしまうと、それぞれの意思や内容が不明確になる恐れがあるからです。
加えて、一方の遺言が法律上の要件を満たしていないと、もう一方の有効性まで判断が難しくなってしまいます。
1-13 【公正証書遺言】不適切な証人を立てた
公正証書遺言を作成するには、証人を2名立てる必要があります。
証人には特別な資格は求められませんが、以下に該当する人は証人として認められません。
- 未成年者
- 相続人になる可能性のある人
- 遺言によって財産を受け取る予定の人、その配偶者や直系の親族
- 遺言作成を担当する公証人の配偶者や四親等以内の親族
- 公証役場に勤務している職員
これらの条件に該当する人を証人にしてしまうと、後に相続人から指摘された際に、公正証書遺言自体が無効になってしまいます。
証人を自分で手配する場合は、必ず上記に該当しない適切な人物を選ぶように注意しましょう。
証人を用意することが難しい場合には、司法書士や弁護士に証人になってもらうよう依頼も可能です。
2章 遺言書を勝手に開封しても無効にならない
遺言書の要件を満たしていない場合には、遺言が無効になる一方で、下記のケースでは遺言の効力が失われることはありません。
- 自筆証書遺言を開封してしまった
- 自筆証書遺言に封がされていない
- 遺言書に書かれている遺産が既になくなっている
封をしていない自筆証書遺言も要件を満たしている場合には、効力を持ちます。
しかし、改ざんリスクもありますので、封をしておくことを強くおすすめします。
また、遺言書に書かれている遺産が、他者への譲渡や災害での滅失等により、既になくなっていたとしても、遺言書そのものが無効になることはありません。
既に存在していない遺産についての部分は、遺言書が無効になりますが、残りの部分については効力を持ち続けます。
とはいえ、遺言書に記載されている財産のうち、ほとんどがなくなっている場合には、遺族も困惑する可能性が高いでしょう。
そのため、遺言書作成当時と資産状況が大幅に変わった場合には、遺言書の作り直しもご検討ください。
2-1 遺言書を勝手に開封すると過料が科せられる恐れがある
遺言書を勝手に開封しても無効にならない一方で、開封してしまうと過料が科せられる恐れがあるのでご注意ください。
法務局による保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所による検認手続きが必要です。
検認手続きを行う前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科せられる恐れがあります。
また、開封した遺言書や、もともと封をされていない自筆証書遺言であっても、検認手続きは必要となるのでご注意ください。
検認手続きの申立て方法や必要書類は、下記の通りです。
| 手続きする人 | 遺言書の保管者 遺言書を発見した相続人 |
|---|---|
| 手続き先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 手続き費用 | 【手続き時】 収入印紙800円分(遺言書1通につき) 連絡用の郵便切手代(数百円から数千円程度) 【完了後】 検認済み証明書の交付費用:収入印紙150円分 |
| 必要書類 |
|
3章 遺言書を無効にしたいときの対処法
故人が遺言書を作成していたものの、無効にしたい場合には、下記のいずれかの方法で対処しましょう。
- 遺産分割協議
- 遺言無効確認調停
- 遺言無効確認訴訟
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 遺産分割協議
故人が遺言書を用意していたとしても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって財産を分けることが可能です。
ただし、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意を得たうえで協議を進める必要があります。
また、遺言では最長5年までの期間を定めて、遺産分割の禁止を指定することができます。
遺産分割の禁止が指定されている場合には、相続開始後、その定められた期間内は遺産分割を行うことができません。
3-2 遺言無効確認調停
特定の相続人に偏った内容の遺言書がある場合などでは、相続人全員の合意が得られず協議が成立しないケースも多くあります。
このような場合には、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立て、話し合いによる解決を目指す場合もあります。
遺言無効確認調停とは、相続人同士の話し合いをサポートする場であり、合意に至らないこともあるでしょう。
その場合には、次の段階として遺言無効確認訴訟に進むことになります。
遺言無効確認訴訟に進む可能性も考慮して、調停の段階から相続問題に詳しい弁護士に相談しておくと、スムーズに対応できるはずです。
3-3 遺言無効確認訴訟
調停によっても問題が解決しない場合には、遺言無効確認訴訟へと進みます。
遺言無効確認訴訟では、裁判所が遺言の有効性について最終的な判断を下します。
遺言の無効を主張する相続人側には、無効であることを裏付ける証拠を提出しなければなりません。
証拠の収集や法的手続きの対応など、専門的な知識が必要となるため、相続トラブルに精通した弁護士に依頼するのが良いでしょう。
まとめ
遺言書を作成すれば、自分が希望する人物に財産を遺せます。
一方で、せっかく作成した遺言書が要件を満たしていないと、無効になる恐れもあるので注意しなければなりません。
遺言書の要件は複数あるので、ミスなく確実に遺言書を作成したいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
司法書士や弁護士であれば、遺言書の作成だけでなく、遺言内容の提案から行えるのもメリットといえるでしょう。
グリーン司法書士法人では、遺言書の作成について相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。