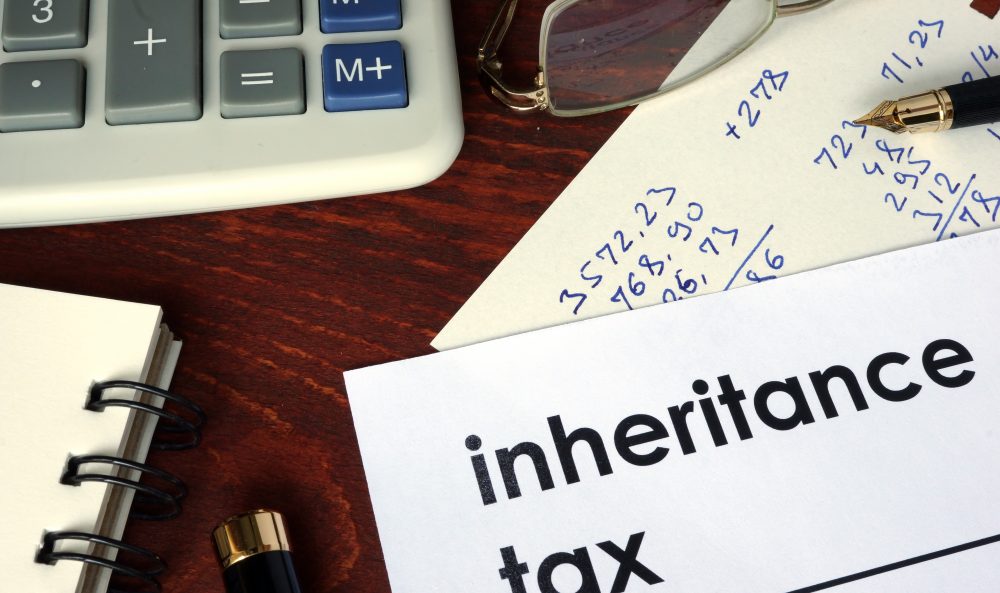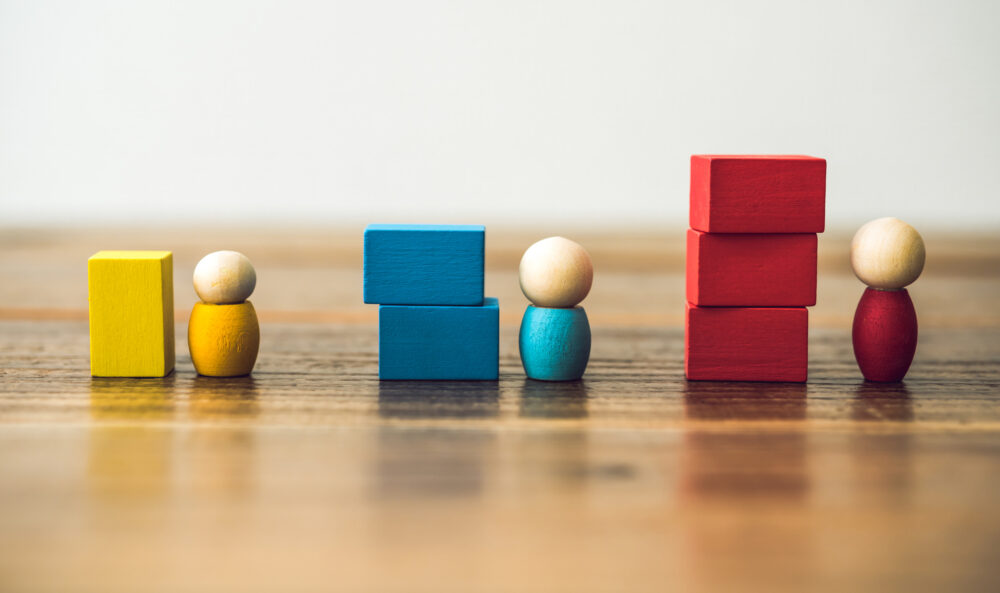- みなし相続財産とは何か、具体例
- 生命保険金・死亡保険金の非課税枠とは何か
- みなし相続財産を受け継いだときの注意点
みなし相続財産とは、本来は相続財産に該当しないものの相続税の課税対象となる財産です。
生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産として扱われ、遺産分割の対象にならないものの相続税の課税対象になります。
家族や親族が亡くなり相続税の計算や申告をする際には、みなし相続財産も漏れがないように計算しなければなりません。
また、生命保険金や死亡退職金には相続税の非課税枠が用意されているので、相続税申告時には忘れずに適用しましょう。
本記事では、みなし相続財産とは何か、相続時の取り扱いや非課税枠の計算方法を紹介します。
相続財産については下記の記事で解説しているので、ご参考にしてください。
目次
1章 みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、本来は相続財産に該当しないものの相続税の課税対象となる財産です。
生命保険金と死亡退職金は受取人固有の財産として扱われるため相続財産ではありませんが、故人の死亡により支給されることから相続税はかかります。
みなし相続財産の特徴は、主に下記の3点です。
- 遺産分割の対象とならない
- 相続放棄をしても受け取れる
- 相続税の課税対象となる
それぞれの特徴を詳しく解説していきます。
1-1 みなし相続財産は遺産分割の対象とならない
死亡退職金や生命保険金などのみなし相続財産は受取人固有の財産という扱いになるので、遺産分割の対象になりません。
- 遺産分割協議に含める必要がない
- 相続人で分配する必要がない
上記の必要がなく、死亡退職金や生命保険金は受取人が自由に使用して問題ありません。
1-2 みなし相続財産は原則として遺留分の対象にもならない
みなし相続財産は相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われるため、遺留分の計算対象にもなりません。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。
ただし、みなし相続財産の金額が遺産に対して多すぎる場合には、例外的にみなし相続財産を遺留分の計算対象に含める場合があります。
1-3 みなし相続財産は相続放棄をしても受け取れる
みなし相続財産は受取人固有の財産として扱われるので、相続放棄をしても受け取り可能です。
一方で、預貯金や不動産など通常の相続財産を少しでも相続してしまうと、相続する意思があるとされ相続放棄が認められなくなってしまいます。
1-4 みなし相続財産は相続税の課税対象となる
死亡退職金や生命保険金などのみなし相続財産は、故人の死亡によって支給されるお金なので相続税の課税対象財産に含まれます。
ただし、受け取った死亡退職金と生命保険金のすべてに相続税がかかるわけではなく、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。
死亡退職金や生命保険金の金額が非課税枠の範囲内であれば、相続税がかかることはありません。
そのため、非課税枠を上手に活用すれば、生命保険などで相続税対策を行えます。
2章 みなし相続財産の例
みなし相続財産には複数の種類がありますが、代表的なものは「生命保険金」および「死亡退職金」です。他にも、下記の財産がみなし相続財産に分類されます。
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 相続発生から3~7年以内に行われた贈与
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 生命保険金
生命保険金は、被保険者が死亡したときに保険会社から受取人に支払われるお金です。
故人が遺したお金ではないので、相続財産には該当せず遺産分割協議の対象にはなりません。
しかし、下記の理由により生命保険金は相続財産の課税対象となっています。
- 生命保険金は故人が死亡したことにより支給されるお金である
- 故人が契約者として保険料を負担し続けていた
生命保険金に加入しておけば相続税がかからなくなるわけではないので、ご注意ください。
ただし、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されているため、相続税対策として生命保険を活用するのも一定の効果があります。
なお、生命保険金は①保険料を負担していた契約者と②被保険者と③受取人が誰かによって、税金の取り扱いが変わります。
契約者と被保険者が別の人物だった場合、生命保険金を受け取っても相続税の課税対象にならないので加入している保険契約を確認しておきましょう。
2-2 死亡退職金
死亡退職金は、故人が在職中に亡くなった際に会社から支給されるお金です。(会社によっては死亡退職金がないこともあります)
多くの会社では退職金規定で死亡退職金を受け取る人物の優先順位を定めているため、相続人同士の話し合いで死亡退職金の受取人を決められません。
そのため、死亡退職金も会社が定めた受取人固有の財産として扱われます。
一方で、下記の理由により死亡退職金も生命保険金と同様に「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
- 死亡退職金は故人が死亡したことにより支給されるお金である
- 故人が個人事業主だった場合に科度な節税を行うことを防止する
死亡退職金も生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。
2-3 相続発生から3~7年以内に行われた贈与
故人が亡くなる3~7年以内に贈与した財産は、みなし相続財産として課税対象となります。
死期が迫った人が相続税から逃れるために、亡くなる直前に生前贈与をすることを防ぐために規定されています。
相続税の課税対象となる贈与の期間は、下記の通りです。
| 贈与が行われた時期 | 相続税の課税対象となる期間 |
| 2023年12月31日まで | 相続発生から3年以内に行われた贈与 |
| 2024年1月1日以降 | 相続発生から7年以内に行われた贈与 |
なお、過去に行われた生前贈与が相続税の課税対象になるのは、相続人や受遺者に対して行われた贈与のみです。
そのため、遺産を受け取っていない孫に行われた贈与に関しては、贈与の時期に関わらず相続税の課税対象にはなりません。
2-4 その他のみなし相続財産
これまで紹介した財産以外にも、下記の財産はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
| 名称 | 概要・具体例 |
| 定期金 | 故人が掛け金を払い、受取人が配偶者など故人以外になっていた個人年金など |
| 生命保険契約 | 故人が保険料を支払い、被保険者が配偶者など故人以外になっていた生命保険など 生命保険の解約返戻金に対して相続税がかかる |
| 債務の免除 | 故人が遺言書などで借金を免除していた場合、免除された借金に対して相続税がかかる |
| 信託受益権 | 故人が信託していた財産に発生する利益 |
| 公共法人などから受ける利益 | 法人に対して財産の遺贈が行われ、関係者が特別な利益を受けた場合など |
| 特別縁故者への分与財産 | 家庭裁判所に特別縁故者として認められた人が受け取った分与財産 |
| 低額の譲受 | 遺言などで故人が時価よりも大幅に低い金額で財産を譲り渡した場合、時価と売買価額の差額に対して相続税が課税される |
このように、みなし相続財産として相続税が課税される財産の種類は多いです。
知らずに相続税の申告漏れをしてしまうことがないように、故人に関連する財産や利益に関する取扱いは相続を専門とする税理士に相談するのが良いでしょう。
3章 生命保険金・死亡退職金の非課税限度枠
生命保険金や死亡退職金には相続税がかかりますが、一定額まで非課税になります。
生命保険金と死亡退職金の非課税になる限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
- 夫が死亡
- 法定相続人は妻および子供3人の合計4人
- 下記の死亡退職金および生命保険金を妻が受け取った
- 死亡退職金:1,000万円
- 生命保険金:3,000万円
上記のケースで死亡退職金および生命保険金の非課税枠を計算してみましょう。
それぞれの非課税枠は「500万円×4人=2,000万円」です。
- 「死亡退職金1,000万円-非課税枠2,000万円=-1,000万円」なので死亡退職金に相続税はかからない
- 生命保険金3,000万円-非課税枠2,000万円=1,000万円」なので生命保険金1,000万円が課税対象となる
上記のように、生命保険金のみ相続税の課税対象となります。
なお、死亡退職金と生命保険金の非課税枠は受取人が相続人の場合のみ適用可能です。
内縁の妻や代襲相続人でない孫など法定相続人以外が受け取った場合は、非課税枠を利用できないのでご注意ください。
生命保険金の非課税枠を利用すれば、現金や預貯金で遺産を遺すよりも相続税を節税できる可能性があります。
次の章では、非課税枠を利用して相続税を節税する方法を紹介します。
4章 非課税枠を利用して相続税を軽減する方法
生命保険金には非課税枠が用意されており、利用すれば相続税を節税可能です。
すべての財産を現金で相続した場合と一部を生命保険金として受け取った場合で、相続税額がどの程度変わってくるのか具体的なケースで見てみましょう。
【条件】
- 法定相続人は子供2人
- 計算例で紹介している以外の相続財産はなかったものとする
- 相続税の課税対象から差し引く債務や葬儀費用もないものとする
現金で1億円を均等に相続した場合
各相続人は現金を5,000万円ずつ受け取った場合を考えてみましょう。
基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税遺産総額:現金1億円-基礎控除額4,200万円=5,800万円
各人の課税遺産総額:5,800万円÷2人=2,900万円
1人あたりの税額:2,900万円×15%-50万円=385万円
相続税の総額:385万円×2人=770万円
現金5,000万円を均等に相続し、保険金5,000万円を均等に受け取った場合
各相続人が現金を2,500万円、保険金を2,500万円ずつ受け取ったケースを考えてみましょう。
保険金非課税枠:500万円×2人=1,000万円
保険金の課税価格:保険金5,000万円-非課税枠1,000万円=4,000万円
基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税遺産総額:現金5,000万円+保険金4,000万円-基礎控除額4,200万円=4,800万円
各人の課税遺産総額:4,800万円÷2人=2,400万円
1人あたりの税額:2,400万円×15%-50万円=310万円
相続税の総額:310万円×2人=620万円
財産の一部を生命保険に組み替えることで、相続税を合計150万円(770万円-620万円)節税することができます。
なお、相続税の基礎控除や計算方法については下記の記事もご参考にしてください。
5章 みなし相続財産における注意点
みなし相続財産は相続税が課税されるだけでなく、相続放棄しても相続税がかかる場合があるなどいくつか注意しなければなりません。
みなし相続財産で注意すべき点は、主に下記の5つです。
- 相続放棄をしてもみなし相続財産は課税される
- 相続放棄をすると生命保険金・死亡退職金の非課税枠を利用できない
- 生命保険金は保険料負担者によって税金の種類が異なる
- 遺産分割に支障が出ることがある
- みなし相続財産は遺留分の計算対象に含まれない
それぞれ詳しく解説していきます。
5-1 相続放棄をしてもみなし相続財産は課税される
みなし相続財産は受取人固有の財産として扱われるので、みなし相続財産を受け取っても相続放棄することは認められています。
しかし、みなし相続財産も相続税の課税対象にはなるので、相続財産を相続放棄したからといって課税されないわけではありません。
相続放棄をした人もみなし相続財産を受け取った場合は、相続税の計算をして申告が必要か確認しましょう。
5-2 相続放棄をすると生命保険金・死亡退職金の非課税枠を利用できない
相続放棄をした相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取っていた場合、相続税の非課税枠は適用できません。
生命保険金および死亡退職金の非課税枠を利用できるのは、法定相続人のみだからです。
相続放棄すると最初から相続人ではなかった扱いになるので、非課税枠を利用できなくなってしまいます。
5-3 生命保険金は保険料負担者によって税金の種類が異なる
生命保険は相続税の対象となると解説しましたが、厳密にいうと保険料の負担者(契約者)と非保険人、受取人の関係で相続税ではなく違う税金として課税されてしまいます。
生命保険契約の種類によっては、非課税枠が使用できないがあるので注意しましょう。
税金の種類は以下の通りです。
【父親が亡くなり、妻と子が相続人のケース】
| 保険料負担者 | 被保険者 | 保険金の受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 父(被相続人) | 父(被相続人) | 妻または子(相続人) | 相続税 ※非課税枠が適用される |
| 妻(相続人) | 父(被相続人) | 子(相続人) | 贈与税 |
| 妻(相続人) | 父(被相続人) | 妻(相続人) | 所得税 |
5-4 遺産分割に支障が出ることがある
みなし相続財産は遺産分割の対象にはならないと解説しましたが、それが原因でトラブルになってしまうこともあります。
- 長男には家などの固定資産を遺す
- 次男には生命保険金として相応の現金を遺す
上記のように平等に財産を分配しようと考えたとした場合、生命保険金はみなし相続財産なので本来の相続財産は1円も取得できていないことになります。
結果として、家を含む他の財産について次男が「自分も相続したい」と主張してトラブルになる可能性もゼロではありません。
このように故人の生前の思いが空回りしてしまう可能性もあるので、遺言書の作成など複数の相続対策を組み合わせて行う必要があるでしょう。
5-5 みなし相続財産は遺留分の計算対象に含まれない
みなし相続財産は遺産分割の対象にならないだけでなく、原則として遺留分の計算対象にも含まれません。
ただし、遺産がほとんど遺されておらずほとんどが生命保険金として用意されていたケースなど、相続財産に偏りがある場合はみなし相続財産を遺留分の計算対象に含める場合があります。
まとめ
みなし相続財産は相続税の課税対象となるので、相続税の計算や申告時には漏れのないように注意が必要です。
また、生命保険金や死亡退職金には非課税枠も容易されているので利用を忘れないようにしましょう。
みなし相続財産は相続放棄をしても受け取れる、遺産分割の対象にならないので希望の人物に財産を遺せるなどのメリットがあります。
一方で、かえって相続トラブルを引き起こす恐れもありますし、相続放棄をした人も相続税の計算が必要になるなどのデメリットもあります。
そのため、生命保険を活用して相続対策を行う際には相続に詳しい司法書士や弁護士に相談しながら進めるのが良いでしょう。
相続に関する専門家であれば、資産状況や希望の相続にマッチする提案を行えます。
グリーン司法書士法人では、相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、オンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
みなし相続財産は課税対象?
みなし相続財産は本来は相続財産に該当しないが、相続税の課税対象になります。
みなし相続財産にあたるものは?
みなし相続財産に該当するものは、主に下記の通りです。
・生命保険金
・死亡退職金
・相続発生から3~7年以内に行われた贈与




 遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ
遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ

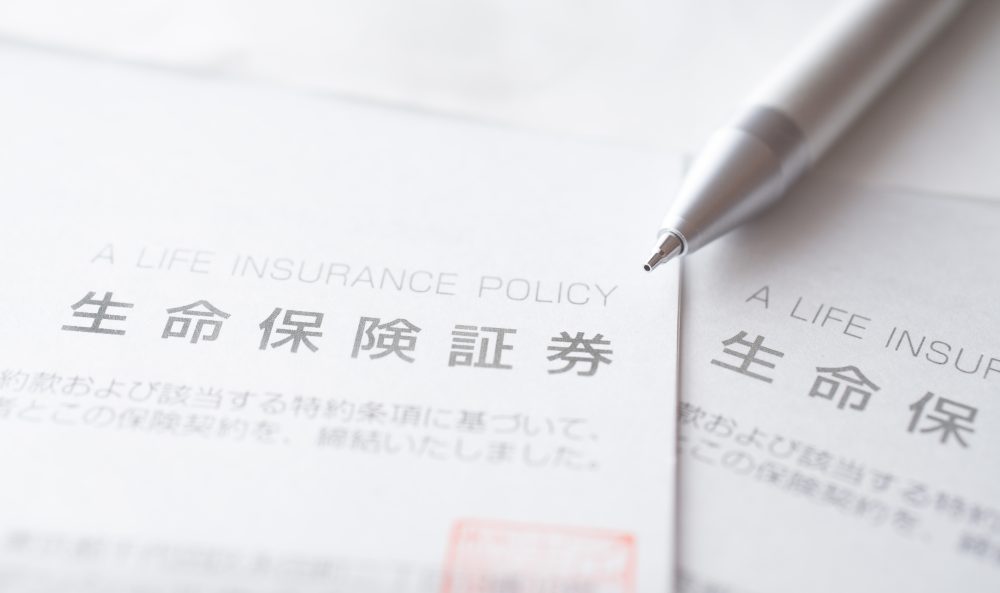

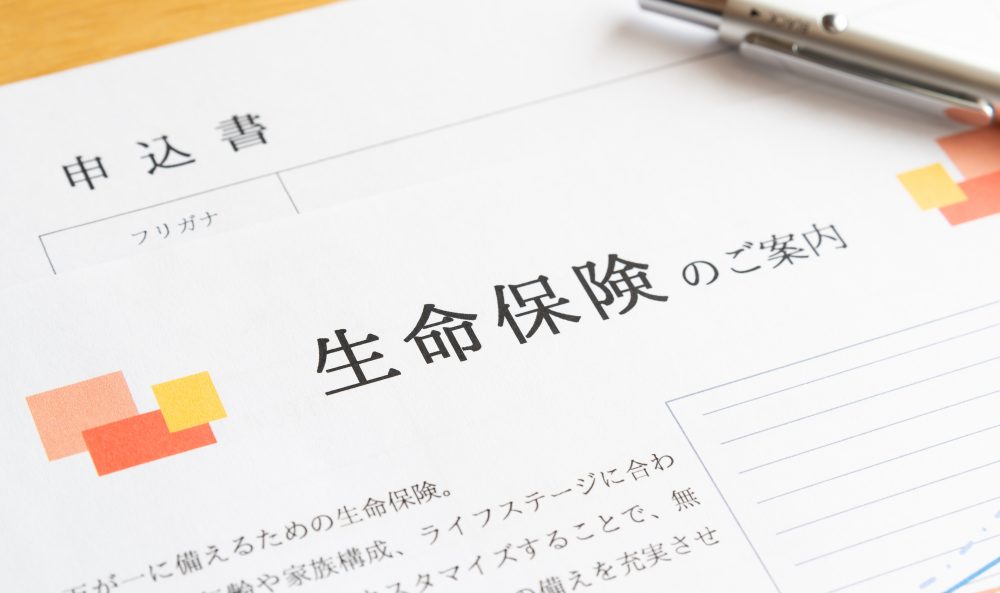
 生前贈与をした年に贈与者が死亡したときの贈与税・相続税の取り扱い
生前贈与をした年に贈与者が死亡したときの贈与税・相続税の取り扱い