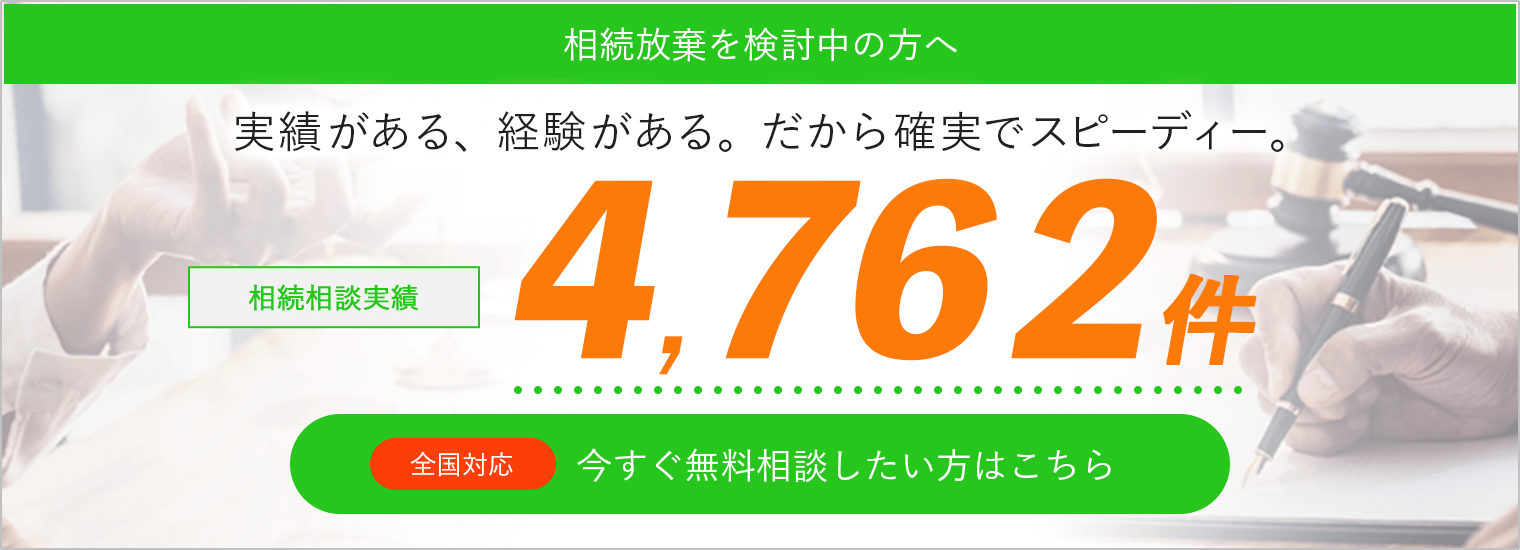- 相続放棄後に見つかった財産を相続することはできるのか
- 相続放棄を例外的に取り消せるケース
- 相続放棄が後から取り消されるケース
- 相続放棄後に後から財産が見つかることを防ぐ方法
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。
故人が多額の借金を遺していた場合には、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄は一度認められると、原則として取り消すことはできません。
相続放棄が受理された後に多額の遺産が見つかったとしても、受け取ることはできないのでご注意ください。
本記事では、相続放棄後に財産が発見された場合の取り扱いや、例外的に放棄を取り消せるケースについて解説します。
目次
1章 相続放棄後に後から見つかった財産を相続することはできない
相続人が相続放棄の手続きをしたにもかかわらず、後から思いがけず財産が見つかるケースはゼロではありません。
例えば、価値のある不動産や株式、預貯金の存在が後日判明した場合、「やっぱり放棄せずに相続すればよかった」と思う方もいるでしょう。
しかし、結論から言えば、相続放棄後に見つかった財産も相続することはできません。
本章では、相続放棄の取り扱いについて、詳しく解説していきます。
1-1 相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなる
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかった扱いとなり、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。
相続放棄では、故人の借金など特定の財産だけを放棄することはできず、遺産のすべてを放棄することとなります。
そのため、「故人の借金が多いから相続放棄したけれど、預貯金が後から見つかったからそれだけ欲しい」といった希望は、認められません。
1-2 相続放棄が一度受理されると原則として取り消せない
相続放棄は、一度受理されると、原則として取り消すことができません。
つまり、「もっと遺産について調べてから判断すればよかった」と後悔しても、後から見つかった財産に対して相続権を回復させることはできません。
ただし、家庭裁判所が「重大な事実に基づく錯誤があった」と判断した場合などでは、例外的に相続放棄の無効や取り消しが認められる可能性があります。
次の章では、相続放棄を例外的に取り消せるケースを詳しく解説していきます。
2章 相続放棄を例外的に取り消せるケース
相続放棄は一度家庭裁判所で受理されると、原則として撤回・取り消しはできません。
しかし、すべてのケースで取り消しできないわけではなく、一定の条件を満たす場合には取り消しが認められる場合があります。
詳しく解説していきます。
2-1 意思能力のない人物が単独で相続放棄したケース
相続放棄をした人物に意思能力がなかった場合には、相続放棄を取り消せます。
例えば、未成年者や認知症により判断能力が著しく低下している高齢者が、単独で相続放棄を行ったようなケースが該当します。
未成年者が相続放棄をする際には、原則として親権者が代理人として申述します。
しかし、親権者も相続人であり、利害関係が対立する場合には、特別代理人の選任をしなければなりません。
このようなケースでは、特別代理人を選ばずに相続放棄をすると、無効になる可能性があります。
また、高齢者が認知症などで正常な判断ができない状態にあったにもかかわらず、本人が単独で放棄した場合には、意思表示に法的効力がないとして、無効とされる可能性があります。
このようなケースでは、成年後見人を申し立てて、相続放棄をしなければなりません。
2-2 詐欺や強迫によって相続放棄をしたケース
相続放棄が、第三者による詐欺や強迫を受けた結果である場合には、その意思表示を取り消せます。
例えば、他の相続人から「借金しかないから相続放棄しろ」などと虚偽の説明を受けて放棄をした場合や、脅すような言動によって放棄させられた場合が該当します。
一方で、単に情報不足だったというだけでは取り消しは認められません。
取り消しを認めてもらうには、詐欺・強迫の事実や状況について明確な証拠を示す必要があるため、実際に取り消しが認められるには高いハードルがあるといえるでしょう。
2-3 錯誤により相続放棄をしたケース
相続放棄の取り消しが認められるケースに、「重要な事実についての錯誤(勘違い)」があった場合があります。
これは、本人が自分の意思で放棄をしたものの、故人の財産内容に重大な認識違いがあった場合などが当てはまります。
例えば、「相続財産は負債しかない」と信じきって相続放棄した相続人が、後日、多額の預貯金や不動産があることを知った際に、重大な錯誤であったとして、相続放棄の取り消しを認められた場合が過去にはあります。
ここで重要な点は、錯誤が本人の注意不足によるものではない場合や、他の相続人などによって重要な事実が隠されていたなどの事情がある場合にのみ取り消しが認められるということです。
単純に、相続財産調査を怠ったことが原因であった場合などは「自らの過失による錯誤」とみなされ、取り消しが認められない可能性が高くなります。
このように、錯誤による相続放棄の取り消しは、一定の条件を満たした場合のみ認められます。
取り消しが認められるかは、ケースバイケースのため、相続放棄に関する錯誤が疑われる場合には、速やかに相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することが望ましいでしょう。
3章 相続放棄が後から取り消されるケース
相続放棄は原則として撤回できない手続きですが、一定の例外的な事情がある場合、家庭裁判所により後から取り消されるケースがあります。
本章では、実務上特に問題になりやすい2つのパターンを紹介します。
3-1 相続放棄の申立書類が偽造されていたケース
相続放棄の申述は、相続人本人が家庭裁判所に対して自ら行うことが原則とされています。
しかし、過去には相続人の同意なく、他の相続人や親族が本人になりすまして、書類を作成・提出したケースもゼロではありません。
このように、本人の署名や押印が偽造されていたことが後に発覚した場合には、相続放棄の手続きが無効とされます。
とはいえ、家庭裁判所は、相続放棄の申立て時に本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提出を求めるため、不正が発覚しやすくなっており、このようなケースは決して多くはありません。
3-2 相続放棄した後に遺産を使用・処分したケース
相続放棄が一度受理された後であっても、放棄者がその後に遺産の一部を使ってしまったり、処分したりした場合には、相続放棄を取り消される恐れがあります。
遺産を使用、処分してしまうと、相続する意思があるとみなされ、放棄の効力が失われると決められているからです。
例えば、相続放棄後に故人名義の預金を引き出して生活費にあてたり、不動産を売却して金銭を得たりした場合には、相続放棄の効力が失われる可能性があります。
4章 相続放棄後に後から財産が見つかることを防ぐ方法
相続放棄をしてから「実はプラスの財産があった」と判明するのは、非常に悔やまれる事態のはずです。
相続放棄が一度受理されると、原則として撤回できないため、相続財産調査を事前に行うことが何より重要です。
相続財産調査は自分で行うこともできますが、司法書士や行政書士に依頼することも可能です。
自分で行うことが難しい場合や、相続放棄すべきかを正確に判断したい場合には、専門家に依頼すると良いでしょう。
5章 【補足】相続放棄の期限を過ぎていても申立てできる?
相続放棄には、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内という期限が設定されています。
しかし、実際には「相続が発生していたこと自体に気づかなかった」「遺産に多額の借金があると知らなかった」などの事情があり、相続放棄の期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
このような状況でも、相続放棄の申立てが認められる可能性はゼロではなく、実際に以下のようなケースでは受理される可能性があります。
- 故人の死亡を知らなかった(疎遠な親族が亡くなったなど)
- 自分が相続人であることを知らなかった(代襲相続や数次相続などが発生していた)
- 故人に資産がないと思っていたが、後から多額の借金が発覚した
- 他の相続人により財産状況を隠されていた、または誤解させられていた
- 精神的ショックや病気などにより、判断力を欠く状態が続いていた
ただし、このような事情があったら、絶対に相続放棄が認められるということではありません。
上記のような事情があり、相続放棄の申立て期限を過ぎてしまった場合には、3ヶ月以内に申立てをできなかったやむを得ない事情や理由を家庭裁判所に説明する必要があります。
家庭裁判所への説明の際には、事情を証明する証拠も必要となり、自分で申立てをすることは現実的ではありません。
万が一、相続放棄の申立て期限を過ぎてしまった場合には、相続放棄に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
相続放棄は、一切の権利義務を放棄する手続きであり、原則として後から撤回できません。ただし、錯誤や詐欺、意思能力の欠如といった特別な事情があれば、例外的に取り消しや無効が認められることもあります。
相続放棄後に遺産を使ってしまえば、単純承認とみなされる恐れもあるのでご注意ください。
相続放棄をすべきか判断するためには、事前に相続財産調査を行うことが重要です。
グリーン司法書士法人では、相続財産調査や相続放棄についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。