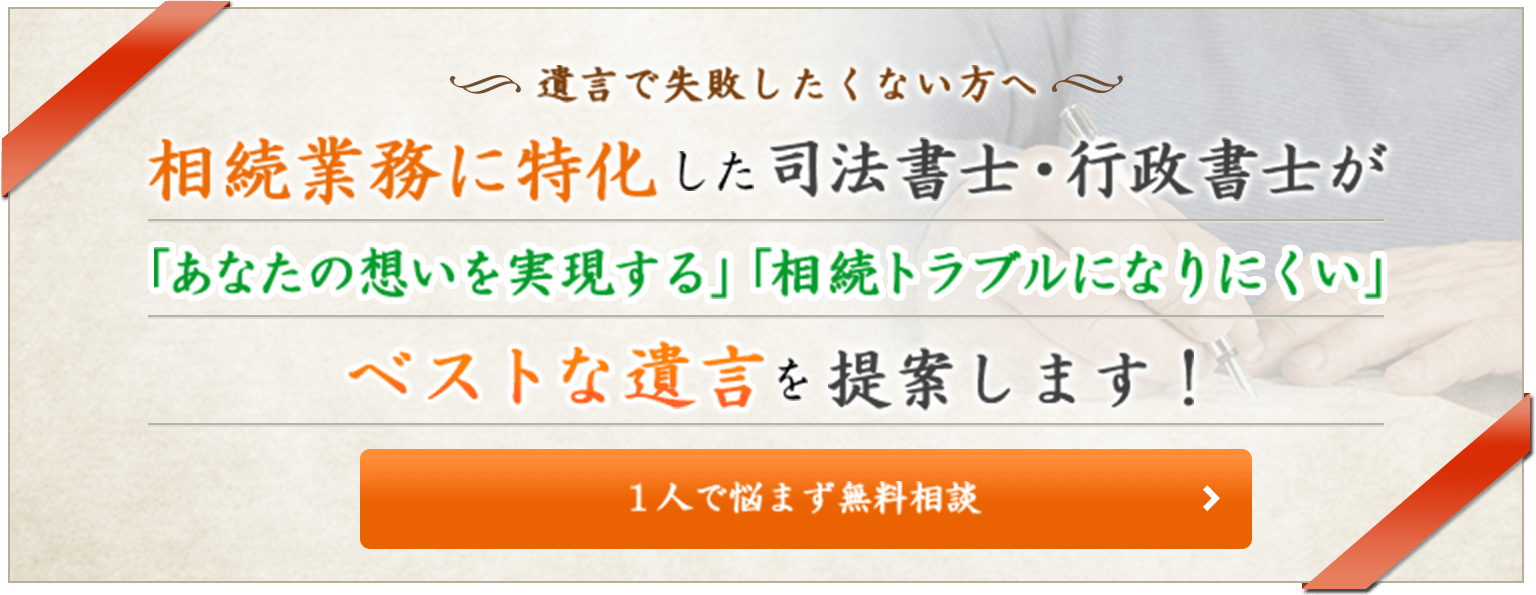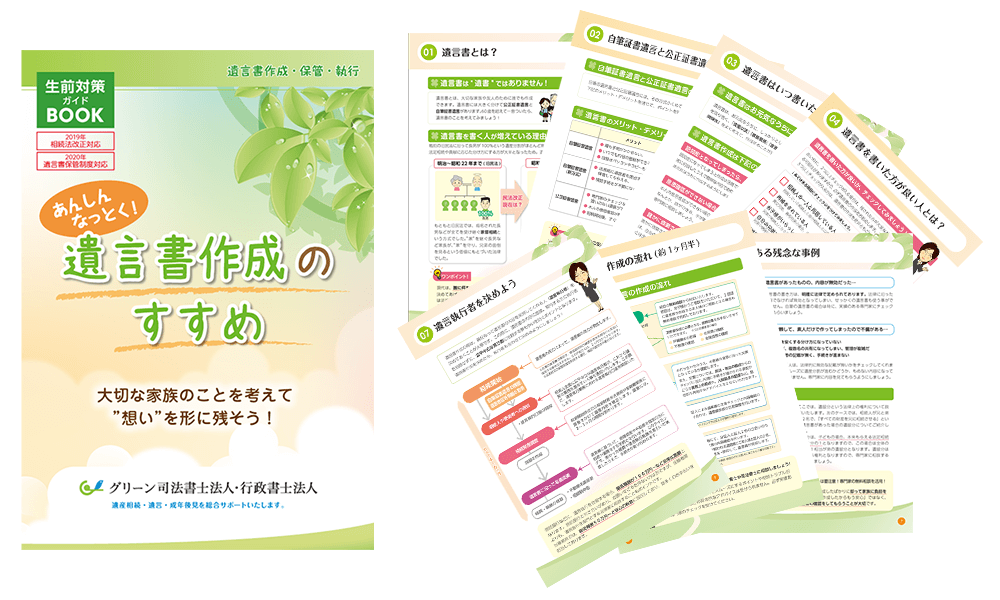「デジタル遺言が始まるらしい」「スマホで遺言書が作れるようになるって本当?」——そんなご相談を、2025年に入ってから多くいただくようになりました。
確かに、法務省の法制審議会で「デジタル技術を使った新しい遺言制度」が議論されているのは事実です。試案レベルとはいえ、遺言書のデジタル化に向けた動きが進んでいるのは間違いありません。
しかし、いまの民法(現行制度)では、全文自筆で書き、署名押印する(自筆証書遺言の場合)といった厳格な要件が設けられており、電子データや録音・録画だけで遺言の効力を持たせることはできません。
つまり、「デジタル遺言がすぐに使える」という状況ではないのです。
むしろ現時点で確実なのは、先行して「デジタル化」が進む公正証書遺言の仕組みを活用すること。
本記事では、デジタル遺言の最新動向と注意点、そして2025年時点で専門家としておすすめできる方法を、できる限りわかりやすく解説していきます。
目次
第1章 そもそも「デジタル遺言」はもう使えるの?
「デジタル遺言」という言葉だけが先行して、「もう電子署名で作れるの?」「スマホアプリで遺言書を保存できるの?」と期待されている方も少なくありません。
しかし、現行の民法では、電子データによる遺言書は成立しません。
1-1 現在の法律では「書面・自筆」が原則
遺言は、遺産分割、遺贈、寄付など、相続財産をめぐる重要な効力を生じさせる文書です。
そのため、民法は非常に厳格な要件を定めています。
特に自筆証書遺言については、
- 全文を自書(自筆)すること
- 署名と押印があること
- 書面として存在すること
が求められています。
自筆ではなく電子データに打ち込んだテキストや、録音・録画による口述だけの遺言は、本人の真意・意思をどこまで確認できるかが問題となり、無効となります。
1-2 電子データが認められない理由
「マイナンバーカードの本人確認や電子署名がこれだけ普及しているのに、なぜダメなの?」と疑問に思う方もおられるでしょう。
理由として大きいのは以下の点です。
- 改ざん・変造の痕跡が残りにくい
- 録音や録画は「その場の一時的な意思表示」に過ぎず、遺言書のような厳格性に欠ける
- 家庭裁判所での検認手続でトラブルが増えるおそれがある
特に、相続トラブルが起きる場面では、「本当に本人が書いたのか」「認知症などで判断能力に問題はなかったのか」「第三者が介入していないか」といった点がシビアに争われます。
デジタル・データは便利ですが、「最終意思を確定する文書」としての信頼性が十分ではないと判断されているのが現状です。
1-3 「デジタル遺言が解禁される」は半分本当・半分まだ先
2025年現在、法制審議会がデジタル遺言の制度化を検討中であり、試案も公表されています。
しかし、これは「すぐに制度として始まる」という段階ではなく、まだ議論の途中です。
- 本人確認をどう行うのか
- デジタル遺言を公的機関が保管するかどうか
- 税務(相続税申告)や登記の実務にどう反映させるか
- 相続人同士の争いをどう防ぐか
こうした論点が多く、専門家の間でも意見が分かれています。
第2章:デジタル遺言は本当に導入されるの?——2025年の法制審議会の動き
「今は使えないのは分かった。でも、デジタル遺言って本当に実現するの?」
ここが、多くの方が一番気になるポイントだと思います。
結論から言えば、デジタル遺言を可能にするための本格的な議論が、2025年現在、法務省の法制審議会で進んでいます。
ただし、まだ「試案」レベルで、制度として確定したものではありません。
2-1 法制審議会が検討している「デジタル遺言」案とは
検討されている主な方向性は次のとおりです。
◆電子署名の活用
- 本人の電子署名+マイナンバーカード
- デジタル・データで「本人の意思による作成」を担保する案
◆公的機関による電子データ保管
- 法務局などが電子遺言書を保管する仕組み
- 改ざん・変造・紛失を防ぐのが目的
◆録音・録画の扱い
- 意思確認の補助資料として検討
- ただし単独で遺言の効力を持たせる案は慎重意見が強い
2-2 デジタル化が求められる背景
- 高齢化で遺言ニーズが増えている
- 相続手続・登記・税務のデジタル化が進行
- 紙の遺言書の不備・無効・偽造リスク
- 事業承継でデジタル資料が増えている
特に遺留分・特別受益・遺贈など、相続トラブルが増える中、「本人の真意を確実に残す方法を整備する必要がある」とされているのが背景です。
2-3 専門家の間では慎重論も多い
弁護士、司法書士、税理士などの実務家からは、
- 電子データの改ざんリスク
- 家庭裁判所での審理の複雑化
- 税務(相続税申告)との整合性
- “厳格さ”を保てるのか
といった課題が指摘されており、実現には慎重な検討が続いています。
2-4 結論:2025年ではまだ「議論段階」
- 実現の方向ではある
- ただし民法改正が必要
- すぐ使えるわけではない
- 導入されても「厳格な要件」は必ず残る見込み
つまり、デジタル遺言の導入に期待しつつも、当面は現行制度で確実な遺言書を作っておくことが重要だといえます。
第3章:まず進むのは「公正証書遺言の手続デジタル化」
「デジタル遺言がすぐには使えないのなら、結局どうすればいいの?」
そう感じた方も多いかもしれません。
実は2025年現在、デジタル遺言よりも先に“確実に進む”のは、公正証書遺言に関わる手続のデジタル化です。
これは、実務でも大きなメリットが期待されており、今すぐの相続対策にも直結します。
3-1 なぜ公正証書遺言のデジタル化が先に進むのか
公正証書遺言は、以下の理由からもともと信頼性が高く、デジタル技術との相性も比較的よい方式です。
- 公証人が立ち会い、本人確認を実施
- 証人によるチェック
- 公証役場に原本が保管され、偽造・変造のリスクが極めて低い
- 登記(不動産)や相続税申告など、後の手続でそのまま使いやすい
こうした公的機関による関与の強さがあるため、「手続の一部を電子化できるのでは」という議論が現実的に進んでいます。
3-2 検討されている「デジタル化の内容」とは
公正証書遺言そのものは従来どおり公証人が作成しますが、手続の一部がデジタル化される方向です。
◆(1)事前資料の電子提出
- 財産目録
- 相続人情報
- 本人確認書類
などをオンラインで送る仕組みが想定されています。これにより、公証役場に足を運ぶ回数が減り、負担軽減が期待されます。
◆(2)オンラインでの本人確認
マイナンバーカードを利用したオンライン本人確認が検討対象。
デジタル遺言の議論でも出てくるテーマですが、公証人が関与する公正証書遺言の方が安全性の担保がしやすいため、導入に現実味があります。
◆(3)電子データと書面の併存
公証人が作成する「公正証書」は法律上書面ですが、
- 電子データのバックアップ
- 閲覧・確認のオンライン化
など、デジタル化との併用が検討されています。
3-3 「デジタル化されても公正証書遺言が最も安全」と言われる理由
公正証書遺言が専門家から強く推奨されるのは、デジタルであれ紙であれ、根本的な信頼性の高さが変わらないためです。
- 公証人が内容をチェックするため、不備で無効になるリスクがほぼゼロ
- 本人確認が徹底されるため、意思能力のトラブルになりにくい
- 偽造・変造・紛失のリスクが低い
- 家庭裁判所での検認が不要
- 不動産の登記や相続税の申告でスムーズに使える
デジタル時代においても、「遺言の厳格性」「本人の真意の確実性」を担保できる方式は公正証書遺言が圧倒的に優位という評価は変わらないのです。
3-4 今後の見通し:デジタル化は“手続の効率化”が中心
公正証書遺言のデジタル化は、
- 本人確認
- 情報提出
- データ保管
といった「手続の効率化」が中心で、公正証書そのものを完全な電子データにするわけではない点が重要です。
つまり、「公正証書遺言の信頼性を担保しつつ、手続きを便利にする」という方向で整備が進むと考えられます。
第4章:2025年時点で専門家がおすすめする遺言作成方法——結論は「公正証書遺言」
ここまで見てきたように、デジタル遺言は2025年現在、法制審議会で試案レベルの議論が進んでいる段階で、民法の改正もまだこれから。
一方で、相続や遺産分割の現場では、遺言書の不備・無効・争いが絶えず発生しているのが現実です。
そこで、2025年時点で専門家として最も強くおすすめできるのが、「公正証書遺言」です。
ここでは、その理由と、どのような人に特に向いているかを解説します。
なお、遺言書の種類については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
4-1 公正証書遺言がもっとも確実で安心な理由
公正証書遺言は、以下の点で他の方式を圧倒します。
◆(1)無効リスクがほぼゼロ
- 公証人が内容をチェック
- 証人が立ち会い
- 本人確認も厳格
これにより、形式的な不備や無効となる危険が極めて低くなります。
◆(2)偽造・変造・紛失の心配がほとんどない
- 原本は公証役場で厳重に保管
- 改ざんの可能性が極めて低い
公的機関による保管で、信頼性が担保されます。
◆(3)相続手続がスムーズ
- 家庭裁判所の検認が不要
- 不動産登記にも利用しやすい
- 相続税申告の際にも扱いやすい
と、後の手続で非常に有利です。
総じて、相続人が「揉めない」ための前提がしっかり整っている方式といえます。
4-2 こんな人は公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言は、特に以下のようなケースで最適です。
◆(1)相続人同士が揉めそうな予感がある場合
- 再婚家庭
- 兄弟姉妹間で関係性が複雑
- 事業承継や会社株式が絡む
- 特別受益・遺留分などの主張が予想される
こうした家庭では、デジタルどころか自筆証書でもリスクが高くなります。安全性の高い公正証書遺言が特におすすめです。
◆(2)不動産が多い・財産の種類が複雑
- 不動産登記の手続
- 事業用資産
- 株式・保険・預貯金などの多岐にわたる相続財産
これらの整理・記載は専門的で、正確な遺言書を作るのにもプロの関与が必要です。
◆(3)認知症などの心配がある場合
本人の判断能力に疑問が生じると、遺言の効力そのものが争点になってしまいます。
その点、公正証書遺言の場合、公証人が「真意」や「意思」を確認して作成するため、後の争いを防ぐ効果が高いのです。
4-3 デジタル化時代でも公正証書遺言が優位であり続ける理由
将来、電子署名やデジタル・データを使った遺言が可能になったとしても、公正証書遺言の「専門家によるチェック機能」は置き換えられないと考えられています。
理由は以下のとおりです。
- 本人確認の確実性
- 内容のリーガルチェック
- 録音・録画に頼らない“真意”の確定
- 公的機関による保管と信頼性
- デジタル化によって逆に複雑化する税務・登記への対応
つまり、デジタルの世界になればなるほど、専門家と公証人が介入する安全な方式の価値が高まる のです。
4-4 「デジタル遺言が始まってから作ればいい」は危険
制度が整うまで待つことには、大きなリスクがあります。
- いつ法律が改正されるかは未確定
- 体調の変化で遺言能力(意思能力)が問題になることがある
- 相続トラブルは予期せず発生する
特に、判断能力に不安が出てきたタイミングで作成した遺言は、相続人から「無効」だと争われる危険があります。
「準備できるうちに確実な遺言を残しておく」
これは、デジタル時代であっても変わらない大原則です。
4-5 司法書士・弁護士・税理士と連携するメリット
遺言書の作成は、公正証書遺言であっても専門家との連携が非常に重要です。
専門家がサポートすることで、
- 財産の整理
- 相続税対策
- 登記・税務・相続全体の見通し
が一気に明確になり、「遺言の目的」がブレずに実現しやすくなります。
特に、事業承継が絡むケースや、不動産が多いケースでは、複数の専門家(弁護士・税理士・司法書士)による総合的なサポートが欠かせません。
まとめ
デジタル化が加速する2025年、「デジタル遺言がそろそろ使えるようになるらしい」という噂は決して間違いではありません。
実際に、法務省の法制審議会では、電子署名などデジタル技術を活用した新しい遺言方式が検討されており、試案としての議論も進んでいます。
しかし、現行の民法では、電子データ・録音・録画等を使った遺言は無効です。
デジタル遺言はあくまで「将来的な可能性」であって、いますぐ自由に使える制度ではありません。
一方で、公正証書遺言の手続デジタル化は、より現実的な改革として先に進む見込みです。
これは、遺言の厳格さや信頼性を損なわず、利便性だけを高められるため、実務上も歓迎されています。
2025年現在、最も安全で確実な遺言方法は、「公正証書遺言」であることに変わりありません。
「デジタル時代の遺言作成」=「便利になる未来を見据えつつ、現行制度で確実に備えること」
これが2025年時点の最適な結論です。
グリーン司法書士法人では、遺言書の作成を始めとする相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。