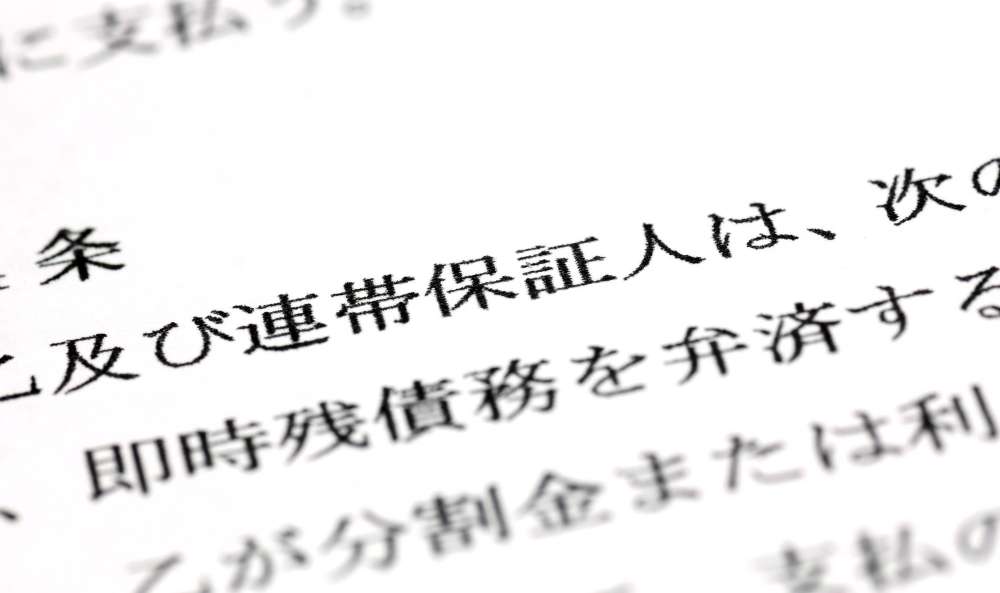
亡くなった人が連帯保証人になっていた場合、相続人は連帯保証人の地位や借金を受け継ぎます。
相続は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産に関しても発生するからです。
そのため、主債務者(借金をした本人)が返済できなければ、相続人が連帯保証人として代わりに借金を返済しなければなりません。
連帯保証人としての地位を受け継ぎたくないのであれば、相続放棄や限定承認などの申立てを行いましょう。
ただし、相続放棄や限定承認は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」と申立て期限が決められています。
したがって相続発生時には限られた期間の中で、故人が連帯保証人になっているかなどの情報を集め相続放棄すべきかの判断をしなければなりません。
本記事では、連帯保証人の地位も相続するのか、相続しない方法について解説します。
故人の借金を相続しない方法については、下記の記事でも解説しているのでご参考にしてください。
目次
1章 連帯保証人の地位・責任は相続される
連帯保証人とは、主債務者と「連帯して」借金支払いの責任をかぶる人であり、主債務者と同じだけの責任を負っています。
例えば1,000万円の借金の連帯保証人になった場合、主債務者の返済が滞ったら債権者に1,000万円全額を請求される恐れがあるため、連帯保証人の責任は非常に重いので、亡くなった人が連帯保証人だった場合は相続するか慎重に判断しなければなりません。
1-1 連帯保証人を相続する人物
連帯保証人としての地位は借金と同様に、相続人が受け継ぎます。
すでに主債務者が支払いを滞納して連帯保証人に督促が来ている場合はもちろんのこと、今のところ主債務者が順調に返済している状態でも「連帯保証人の地位」が相続対象になります。
そのため現時点では主債務者が滞りなく返済しており、連帯保証人に請求が来ていない場合でも安心はできません。
将来的には、債権者が相続人に対して借金返済の請求をしてくる可能性がゼロではないからです。
なお、相続人の範囲や優先順位は、法律で下記のように決まっています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |
| 第一順位 | 子供や孫 |
| 第二順位 | 親や祖父母 |
| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
1-2 連帯保証債務は「相続割合」に分割されて相続される
連帯保証人の地位が相続されるとき、相続人が複数いれば借金や連帯保証の義務が「法定相続割合」に従って相続されるのが原則です。
例えば、下記の具体例を見てみましょう。
- 亡くなった人:父親
- 相続人:母親および子供2人
- 父親は生前、1,000万円の借金の連帯保証人になっていた
上記のケースで、相続人全員が連帯保証人の地位を受け継いだ場合の相続割合は下記の通りです。
- 母親:500万円の連帯保証債務を負う
- 子供たち:それぞれ250万円の連帯保証債務を負う
1-3 遺産分割協議で決定した相続割合は債権者に主張できない
連帯保証人としての地位を法定相続割合で受け継ぐのではなく、遺産分割協議によって1人に集中させることも可能です。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれくらいの割合で受け継ぐかを決定する話し合いです。
例えば、先ほどのケースでは相続人全員が合意すれば母親が1,000万円の連帯保証債務を受け継げます。
ただし、遺産分割協議などで決定した相続割合は、法的な拘束力はなく債権者に対して主張できない点に注意が必要です。
そのため、主債務者が返済を滞納した場合、連帯保証人としての地位を受け継いだ母親だけでなく、子供たちにも債権者が取り立てを行う可能性があります。
亡くなった人の連帯保証人の地位を受け継がないようにするには、相続放棄や限定承認の手続きをするしか方法はありません。
相続放棄や限定承認については、本記事の3章で詳しく解説します。
1-4 連帯保証債務は債務控除の対象にならない
債務控除とは、亡くなった人が借金を遺していた場合、相続税を計算する際にプラスの相続財産から借金や葬儀費用などの控除できる制度です。
しかし、連帯保証人としての地位を受け継いだだけでは、債務控除の対象にはならないのでご注意ください。
債務控除が認められるのは、故人が連帯保証人として主債務者の代わりに返済をし、主債務者から返済してもらえる見込みがない場合のみです。
2章 故人が連帯保証人だったか確認する方法
家族や親族が亡くなり相続が発生したときには、故人が連帯保証人だったかを確認しなければなりません。
知らずに遺産を受け継いでしまうと、連帯保証人の地位まで受け継いでしまう可能性があるからです。
ただし、亡くなった人が連帯保証人だったかどうか100%完全に調べる方法はありません。
下記の5つの方法で個別に確認する必要があります。
- 自宅内で債権者から届いた書類や契約書を探す
- 留守電やメールなども確認する
- 通帳などで過去の返済履歴を調べる
- 信用情報機関で情報開示請求をする
- 知人や親族に尋ねてみる
むしろ、主債務者がしっかり返済続けていると余計に連帯保証人に何ら請求きていないので見つけるのが難しい場合もあります。
特に、個人間の借金の場合、調べるのに限界もあるので注意しましょう。
亡くなった人が連帯保証人だったらどうしよう、連帯保証人としての地位を受け継ぎたくないと考える場合は、本記事の3章で紹介する相続放棄も検討すべきです。
2-1 自宅内で債権者から届いた書類や契約書を探す
まずは、故人の自宅を整理し債権者から届いた書類がないか探してみましょう。
具体的には、下記の書類が見つかった場合は故人が借金をしていた、もしくは連帯保証人になっていた可能性があります。
- 契約書類(借用書や金銭消費貸借契約書など)
- 振込証
- 自宅に届いている督促状や催告書、内容証明郵便
- 裁判所から届いた書類
- 借金の督促に関する留守電
上記の郵便物や書類が見つかった場合は、差出人を確認し内容を問い合わせてみましょう。
2-2 留守電やメールなども確認する
借金を滞納していると、債権者から電話やメールで督促が入るケースもあります。
死亡後連絡が取れなくなると、留守電やメールが溜まっている可能性があるので家の電話・携帯電話・パソコンを確認しましょう。
2-3 通帳などで過去の返済履歴を調べる
故人名義の通帳を記帳して過去の返済履歴を確認してみるのも、故人の借金に関する情報を探るのに有効です。
定期的に振り込みをしている場合や特定の企業や人物に振り込みをしていた場合は、故人が借金の返済をしていた可能性があります。
2-4 信用情報機関で情報開示請求をする
金融機関の借金に対し連帯保証人となっていた場合は、信用情報機関に情報開示請求を行えば確認可能です。
信用情報機関とは、個人が借りているローンやクレジットカードの利用履歴を登録、管理している機関です。
相続人であれば、信用情報機関への情報開示請求を行い、個人が借金をしていたかどうか残債がいくらかどうか確認できます。
日本に信用情報機関は3つあり、それぞれ請求方法は下記の通りです。
| 信用情報機関 | 請求方法 |
| JICC |
|
| CIC |
|
| KSC |
|
信用情報機関にて情報開示請求を行う際には、本人確認書類や故人と相続人の関係を証明する書類などが必要です。
また、請求時には手数料が数百円~1,000円程度かかるので、事前に確認しておきましょう。
加えて、信用情報機関の情報開示請求でわかるのは、金融機関からの借金で連帯保証人になっているかどうかのみです。
下記の借入先に関する情報は入手できないのでご注意ください。
- 信用情報機関に加盟していない会社
- 個人
2-5 知人や親族に尋ねてみる
故人が連帯保証人になっていたか知っていそうな知人や親族がいれば、尋ねてみるのも良いでしょう。
ただし、尋ねるときには「自分は〇万円貸していた」などと主張され、騙されないように注意が必要です。
故人が連帯保証人になっていたかどうか調べる方法は複数ありますが、100%確実に調査する方法はありません。
本章で紹介した方法を試し、できるだけ丁寧に自宅や事業所などで書類を探すしかないのが現状です。
故人が会社経営者や事業者だった場合は特に注意が必要
故人が会社経営者や事業者であった場合、一般人よりも連帯保証人になっている可能性が高いです。
特に会社経営者は、経営している「法人(会社)」の債務について連帯保証しているケースが多数あります。
その場合、契約書などの書類は会社に保管されている可能性が高いので、会社に問い合わせて状況を調べましょう。
個人事業者の場合にも、知人との付き合いなどで保証人になっているケースがよくあります。
事業所や金庫などに契約書類が保管されていないか、しっかり調べましょう。
3章 連帯保証人の借金を相続しないための2つの対処法
相続人が連帯保証人の地位を受け継ぎたくない場合は、相続放棄もしくは限定承認を申立てる必要があります。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。
限定承認とは、故人が遺したプラスの財産の範囲内で故人が遺した借金を返済する方法です。
相続放棄と限定承認について、詳しく見ていきましょう。
3-1 相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きであり、手続きをすると最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
したがって、連帯保証人の地位も受け継ぎません。
相続放棄をすれば故人の借金や連帯保証債務を受け継がなくてすみますが、一方で下記のデメリットがあるのでご注意ください。
- 預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなる
- 相続放棄の手続きは原則として取り消せない
- 同順位の相続人が相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移る
相続放棄するとすべての財産を受け継げないため、故人が連帯保証人になっているけれど多額の資産を持っている場合は相続放棄しない方が得なケースもあります。
また、連帯保証人はあくまでも主債務者が返済できなくなったときに代わりに借金を負う人物であり、主債務者が計画通り返済できれば借金を負わずにすみます。
相続放棄をする際には、家庭裁判所で申立て手続きが必要であり、必要書類や申立て方法は下記の通りです。
| 申立てする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
| 申立先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 |
|
| 必要書類 |
|
3-2 限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。
限定承認では、相続人の財産から故人の連帯保証債務や借金を返済しなくて良いメリットがあります。
ただし、限定承認は「相続人全員」でしなければならず、1人でもプラスの財産もマイナスの財産も相続したいと考える人がいると手続きできません。
また限定承認の手続きには長い時間がかかります。
ようやく終了して少額の遺産を受け取ったら、それを再度、相続人全員で「遺産分割協議」をして分配しなければなりません。
手続きに手間と時間がかかるため、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。
限定承認の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
| 申立てする人 | 相続人全員が共同して行う |
| 申立先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円 郵便費用1,000円程度 |
| 必要書類 |
|
相続放棄にも限定承認にも、「期限」があるので注意が必要です。
「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」に相続放棄もしくは限定承認の申立てを行わないと、強制的に「単純承認」が成立して資産も負債も全部相続してしまいます。
相続放棄や限定承認は原則として取り消しできないので、申立てを検討するためには相続財産調査、故人が連帯保証人になっていたかの調査が必要です。
相続人が自ら行うのは現実的ではないので、相続放棄や限定承認に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。
また、3ヶ月で相続放棄や限定承認すべきか判断がつかない場合は「熟慮期間伸長の申立」を行いましょう。
熟慮期間伸長の申立を行えば、相続放棄や限定承認の期限を延ばせます。
4章 相続開始後3ヶ月が経過している場合の対処法
状況によっては、故人が亡くなってから3ヶ月以上経ってから、故人が連帯保証人だったことを知るケースもあるでしょう。
その場合には、相続放棄の期限の起算点を確認するなど下記の対処法をお試しください。
- 相続放棄できる可能性はないか確認する
- 借金が「時効」になっている可能性はないか確認する
- 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討する
- 債権者と話し合いの余地はないか探る
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1 相続放棄できる可能性はないか確認する
相続放棄の期限は「自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内」なので、相続開始から時間が経っていても相続放棄できる可能性はあります。
例えば、故人と疎遠であり死亡の事実を知らなかった場合は、3ヶ月の熟慮期間は進行しません。
他にも、自分が相続人と知っていたものも「遺産がない」と信じており、そのことに過失がなければ3か月が経過しても相続放棄が認められる可能性があります。
このように、相続開始から時間が経っているケースで相続放棄が認められるかは状況によって変わります。
自己判断して諦めるのではなく、まずは相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
4-2 借金が「時効」になっている可能性はないか確認する
借金には時効があり、貸金業者や金融機関の場合は5年、個人からの借入の場合には10年です(民法改正後はいずれも5年)。
主債務が時効で消滅した場合、連帯保証債務も消滅するため、借金が時効を迎えていれば連帯保証人としての地位も時効となります。
なお、故人が生きている間に経過した期間および相続人が連帯保証債務を受け継いでからの期間は継続して時効を判定可能です。
借入時期が古く、長年取り立てが行われていなければ時効を主張できる可能性があるので一度契約書などで確認してみましょう。
4-3 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討する
すでに主債務者が滞納して債権者から請求が来ており、どうしても支払いができないなら「債務整理」によって連帯保証債務の減額や免除をしてもらうことも検討しましょう。
債務整理には、下記の3種類の手続きがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれメリットとデメリットがあるため、状況によってどの債務整理を行うか判断しなければなりません。
また、それぞれの手続きは複雑で手間がかかるため、自分で行うのは現実的ではありません。
そのため債務整理をしたい場合や連帯保証人の地位を受け継いでしまいお悩みの人は、債務整理や借金問題に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、相続だけでなく債務整理に関する相談もお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
4-4 債権者と話し合いの余地はないか探る
借金トラブルは、債権者との話し合いによって解決できる可能性もあります。
例えば債権者の同意を得ることにより、相続人のうち特定の誰かが連帯保証人の地位を引き継ぐことや信用のある第三者に連帯保証人を交代してもらえたりするケースは珍しくありません。
すでに主債務者が支払いを滞納して連帯保証人の支払いが現実化している場合でも、「免責的債務引受」という方法で相続人のうち特定の誰かが支払いを全面的に引き継ぐことも可能です。
こうした債権者との交渉もご本人たちには難しいので、早めに専門家に相談して進めましょう。
4-5 連帯保証債務を受け継ぐ
亡くなった人が連帯保証人になっていたものの遺産が多い場合や連帯保証人として請求を受ける可能性が低いと予想される場合は、相続放棄をせずに連帯保証人としての地域を受け継いでしまうことも考えましょう。
連帯保証人はあくまでも主債務者が借金を返済できない場合に借金を請求される立場ですし、故人の遺産が多い場合は請求された借金を遺産から払えば良いからです。
とはいえ、相続放棄の期限は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」です。
相続放棄の期限までに相続財産調査を行い遺産や連帯保証債務の金額を自分で調べることは、あまり現実的とはいえないでしょう。
そのため、相続に詳しい司法書士や弁護士に相続財産調査を依頼し、遺産や連帯保証債務の有無や金額を調べてもらい相続放棄すべきかアドバイスをもらうことをおすすめします。
まとめ
連帯保証人の地位を相続すると、将来思わぬ借金トラブルに巻き込まれる危険性が高くなります。
そのため、家族や親族が亡くなり相続人になった際には、故人の遺産や借金の総額、連帯保証人だったかどうかの調査を行いましょう。
故人に遺産がない場合や連帯保証人の地位を受け継ぎたくない場合は、相続放棄や限定承認をご検討ください。
相続放棄や限定承認は申立期限があるため、確実に実行するためにも、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談もお受けしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
連帯保証人が死亡するとどうなる?
亡くなった人が連帯保証人になっていた場合、相続人は連帯保証人の地位や借金を受け継ぎます。
相続は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産に関しても発生するからです。










