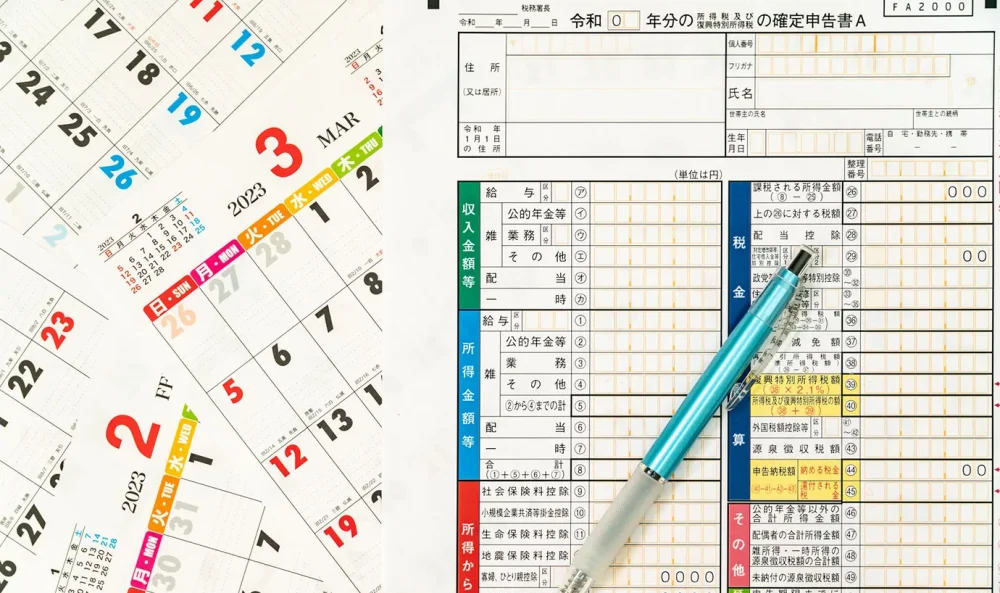
- 準確定申告の期限を過ぎたらどうなるのか
- 準確定申告を期限内に完了させる方法
- 準確定申告の期限に間に合わないときの対処法
準確定申告は、故人の死亡日までの所得を相続人が代わりに申告・納付する手続きです。
準確定申告は、相続開始の翌日から4ヶ月以内と期限が定められており、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税といったペナルティが課せられます。
準確定申告はすべての相続で必要とされるわけではないので、まずは故人の収入状況を調べ、準確定申告が必要か判断していきましょう。
本記事では、準確定申告の期限を過ぎたときのペナルティや期限内に準確定申告を完了させる方法を解説します。
目次
1章 準確定申告の期限は相続開始の翌日から4ヶ月以内
準確定申告とは、相続人が故人の代わりにその年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、申告・納付を行う手続きです。
準確定申告の期限は、相続開始の翌日から4ヶ月以内と定められており、例えば5月10日に相続が開始した場合は9月10日が期限となります。
期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが課せられるため、故人が賃貸収入を得ていた場合などは速やかに準確定申告の準備を始めましょう。
2章 準確定申告の期限を過ぎたら延滞税・加算税が課せられる
期限内に準確定申告を行わなかった場合、延滞税と無申告加算税が課されてしまいます。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
2-1 延滞税
延滞税は、本来の納期限の翌日から実際に納税するまでの日数に応じて課せられる税金であり、税率は以下の通りです。
| 延滞期間 | 税率 |
|---|---|
| 納付期限の翌日から2ヶ月後まで | 年利7.3% |
| 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降 | 年利14.6% |
なお、上記の延滞税の税率は原則であり、令和7年分として発表されている税率は年利2.4%と8.7%となっています。
延滞税は日割り計算されるため、延滞日数が長いほど負担が大きくなります。
2-2 無申告加算税
無申告加算税とは、準確定申告が必要にもかかわらず行わなかった場合や、期限後に自主的に申告した場合に課せられる税金です。
無申告加算税の税率は、以下の通りです。
| 申告時期 | 税率 |
|---|---|
| 自主的に申告した | 追加で納めた税金の5% |
| 税務調査後に申告した |
|
上記のように、無申告加算税は自主的に申告した場合、税率が低くなります。
そのため、準確定申告をしていないことに気付いたら、税務署から指摘を受ける前に申告することが大切です。
3章 準確定申告を期限内に完了させる方法
準確定申告を期限内に済ませるには、以下の対策や準備をしておきましょう。
- 準確定申告が必要かどうかを確認する
- 昨年の確定申告書・必要書類を収集する
- 税理士に準確定申告を依頼する
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 準確定申告が必要かどうかを確認する
まずは、故人の収入状況などを確認し、準確定申告が必要かを判断しましょう。
例えば、以下のようなケースでは、準確定申告をしなければなりません。
- 自営業者や個人事業主だった
- 2ヶ所以上から給与を受けていた
- 給与所得と退職所得以外の所得が合計20万円以上あった
- 給与の年間収入が2,000万円以上だった
- 給料の年末調整を行っていなかった
- 公的年金などによる収入が400万円を超えていた
- 公的年金などによる雑所得が20万円を超えていた
- 土地建物や株式の譲渡所得があった
- 不動産所得があった
- 貸付金の利子収入や家賃などの不動産収入を受け取っていた
- 生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた
また、上記に当てはまらなくても医療費控除や寄附金控除などが申告できる控除がある場合には、準確定申告をすることにより還付金を受け取れる可能性があります。
3-2 昨年の確定申告書・必要書類を収集する
準確定申告が必要だとわかったら、必要書類の収集をしていきましょう。
準確定申告時には、故人の所得を証明する以下のような書類を用意する必要があります。
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 特定口座年間取引報告書
上記の書類だけでなく、前年度の確定申告書の控えも見つけておくと、故人の収入状況をより把握しやすくなるはずです。
他にも、医療費の領収書や保険料支払証明書などを漏れなく収集しておきましょう。
3-3 税理士に準確定申告を依頼する
自分たちで準確定申告をすることが難しい場合には、税理士に依頼することをおすすめします。
準確定申告の期限は相続開始の翌日から4ヶ月以内と短いので、早めに税理士を見つけておくことも大切です。
故人が生前、確定申告を依頼していた税理士がいる場合には、その方に準確定申告を依頼しても良いでしょう。
他には、相続税申告も税理士に依頼する場合、準確定申告もまとめて依頼することも選択肢のひとつです。
4章 準確定申告の期限に間に合わないときの対処法
万が一、準確定申告の期限に間に合わない場合には、一旦仮の内容で申告書を提出しましょう。
仮の内容でも、期限内に申告書を提出すれば、延滞税や無申告加算税が課せられることはなくなるからです。
その後、正確な所得額や控除額の計算が完了したら、速やかに修正申告か更正の請求を行いましょう。
5章 準確定申告の期限を過ぎても還付申告を行える
準確定申告の期限を過ぎてしまっても、故人の所得税を納めすぎていることがわかった場合には、還付申告により払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。
還付申告の期限は、相続開始の翌日から5年以内とされています。
還付申告の対象となるケースは、主に以下の通りです。
- 医療費控除や寄附金控除など、本来適用できる各種控除を申告していなかった場合
- 源泉徴収や中間納付で過大に納税していた場合
ただし、故人の所得税の還付金は相続財産に含まれます。
そのため、相続人が故人の代わりに還付申告をする場合には、相続税の申告期限である「相続開始の翌日から10ヶ月以内」に行うことが望ましいでしょう。
まとめ
準確定申告には、相続開始の翌日から4ヶ月以内という期限が設定されています。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が課せられてしまうのでご注意ください。
万が一、準確定申告の期限に間に合わない場合には、一旦仮の内容で申告をしておき、後から修正申告や更正の請求を行いましょう。
また、相続発生後は速やかに準確定申告が必要かどうかの調査や、故人の収入に関する書類を集めておくことも大切です。
相続手続きの中には、準確定申告のように期限が定められているものもいくつかあります。
自分で手続きすることが難しい場合や、何からすれば良いかわからない場合には、司法書士や行政書士に相談することもご検討ください。
グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。










