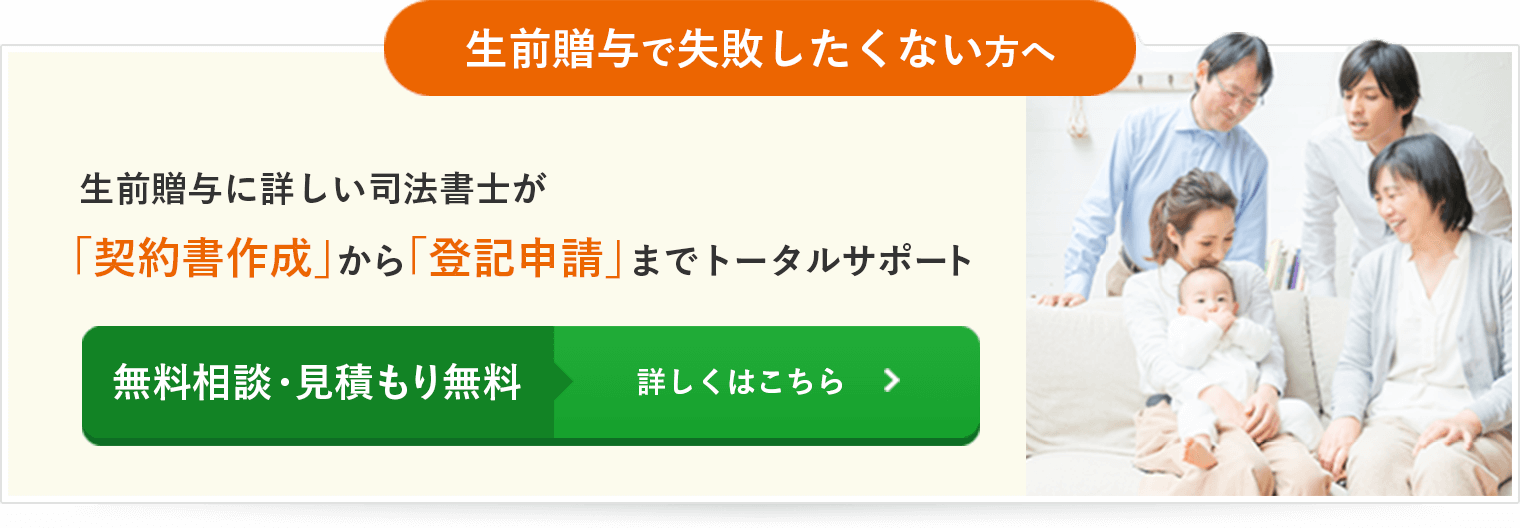- 生前贈与時に贈与契約書が必要な理由
- 贈与契約書を作成するメリット・デメリット
- 贈与契約書を作成する流れ
生前贈与で契約書は必須というわけではありませんが、作成していないと思わぬトラブルが発生する可能性があります。
トラブルを未然に防いで確実に贈与を進めるためには、贈与契約書を作っておくと安心です。
贈与契約書は法的に決まったフォーマットはありませんが、贈与者と受贈者の氏名や贈与財産についてわかりやすく記載しておく必要があります。
本記事では、生前贈与の際に作成する贈与契約書とは何か、作成方法や注意点を解説します。
生前贈与については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
目次
1章 生前贈与の際に作る贈与契約書とは
生前贈与は相続と異なり、生きている間に財産を他者へ贈与することです。
生前贈与の方法について法的なルールはなく、口頭でも内容を確認し合意すれば贈与が成立します。
しかし、口頭による贈与では、実際に生前贈与があったかどうかを第三者が知る術がありません。
そこで生前贈与の証拠のひとつとして作成されるものが「贈与契約書」です。
贈与契約書は、生前贈与がおこなわれたことを証明するための書類であり、贈与する人と贈与を受ける人の間で締結します。
贈与契約書は、贈与があったことのほかに贈与財産の内容や日付などが細かく記されているのため、税務署の職員などの第三者に対しても生前贈与が行われたことを証明できます。
1-1 贈与契約書を作成しないリスク
先ほど解説したように、贈与契約書があれば後からでも生前贈与の事実を証明できます。
逆に言えば、贈与契約書がないと後から贈与の事実を証明することができず、トラブルや税負担が発生する恐れがあります。
生前贈与の事実が問題になるのは、主に相続発生時や税務署による調査が行われたときです。
例えば、相続人が「生前贈与なんてなかったはずだ」と主張して、贈与財産を遺産に含めるよう主張する可能性もあります。
他には、税務署が過去の贈与を認めず、贈与財産も相続税の計算対象に含めるように主張するケースもあるでしょう。
このようなトラブルを避けるためにも、生前贈与を行う際には必ず贈与契約書を作成しておく必要があります。
2章 贈与契約書を作成するメリット
先ほどの章で解説したように、贈与契約書を作成しておけば生前贈与の事実を証明できるなど、下記のメリットがあります。
- 生前贈与があったことを証明できる
- 贈与を撤回できなくなる
- 贈与の内容を細かく記録できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 生前贈与があったことを証明できる
贈与契約書を作成する一番大きなメリットは、生前贈与があったことを証明できることです。
確実に証明できれば、基礎控除額に対して課税されるリスクを抑えられます。
また、贈与する人と贈与を受ける人の間における、認識の違いをなくしておくことも可能です。
贈与に関わる当事者だけでなく税務署の職員に対しても生前贈与があったことを証明できるため、税務調査に備えることもできるでしょう。
2-2 贈与を撤回できなくなる
贈与契約書があると、贈与者が贈与を撤回できなくなる点もメリットです。
口頭での贈与の場合は、突然「贈与はやめた」といわれてしまうリスクが残ります。
一方で、贈与契約書があれば、一度贈与されたものを撤回することはできません。
2-3 贈与の内容を細かく記録できる
贈与契約書には、贈与の内容が細かく記されていることもメリットです。
どんな財産をどれくらい、いつ、誰に贈与したのかがわかる書類であるため、今後起こり得るさまざまなトラブルを防ぐことができます。
贈与契約書は、生前贈与を滞りなくトラブルなく履行するための書類であるといえるでしょう。
3章 贈与契約書を作成するデメリット
贈与契約書を作成するデメリットは、作成に手間と時間がかかることです。
たった1枚の書類だとはいえ、作成するためには入力して印刷して署名するなどの手間と時間がかかります。
加えて、公証役場で確定日付をもらう場合は、その分手間と時間もかかるでしょう。
ただし、本記事ですでに解説しているように、贈与契約書を作成しないと大きなトラブルが発生するリスクがあります。
贈与を撤回されてしまうケースや、税務調査によって基礎控除額分にも贈与税が課せられる恐れもあります。
これらを避けるためには、手間と時間がかかっても贈与契約書は作成したほうが安心だといえるでしょう。
4章 生前贈与における贈与契約書を作成する流れ
生前贈与の贈与契約書には、法的に決まった形式はありません。
ただし、贈与者と受贈者の氏名や贈与財産など、必要事項が記載されていないと贈与契約書として認められない可能性があるので注意しましょう。
贈与契約書を作成する流れは、下記の通りです。
- 贈与の内容を詳しく決める
- 贈与に合意する
- 贈与契約書を作成する
- 贈与する人と贈与を受ける人がそれぞれ1枚ずつ保管する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP① 贈与の内容を詳しく決める
生前贈与をすると決まったら、まずは贈与する人と贈与を受ける人が贈与の内容について細かく決めていきましょう。
贈与する財産は現金なのか不動産なのかといった、贈与する財産についてを決め、実際にどれくらい贈与するのかも決めておきます。
STEP② 贈与に合意する
次に贈与する日付を決め、贈与する人、贈与を受ける人、双方が贈与に合意します。
認識に齟齬がないように、あらためて贈与内容を確認しておきましょう。
STEP③ 贈与契約書を作成する
生前贈与することが決まったら、すぐに贈与契約書の作成に入りましょう。
当事者同士で決めた贈与内容を記載して署名押印し、贈与契約書を完成させます。
贈与契約書の詳しい書き方や記載内容については、本記事の後半で解説します。
STEP④ 贈与する人と贈与を受ける人がそれぞれ1枚ずつ保管する
贈与契約書は2枚作成し、贈与する人と贈与を受ける人がそれぞれ1枚ずつ保管すると安心です。
もしくは1枚作成して、一方はコピーの保管でも良いでしょう。
5章 贈与契約書の書き方・記載内容
贈与契約書の書き方に決まりはありませんが、文書作成ソフトなどを利用して作成するのが一般的です。
パソコンが苦手な場合には、手書きで作成しても問題ありません。
ただし、下記6つの項目は記載しておく必要があります。
- 贈与する人の氏名と住所
- 贈与を受ける人の氏名と住所
- 贈与契約を締結した日付
- 実際に贈与する日付
- 贈与したものの情報
- 贈与の方法
またパソコンで作成する場合であっても、署名だけは自筆でおこないましょう。
すべて印字されているよりも、自筆の署名があれば信頼性が高まるからです。
双方の押印も入れることも、忘れてはいけないポイントです。
6章 【ダウンロード可能】贈与契約書の書式
書き方に決まりがない贈与契約書では、一体どうやって作成したらいいのかで迷うケースは少なくありません。
ここからはケース別に書式をご紹介するので、状況に合うものを参照してください。
6-1 現金を贈与する場合
現金を贈与する場合は、現金を手渡しするよりも口座へ振り込むほうが安心です。
口座への振り込みならば、お金の移動が口座に記録されるからです。
贈与契約書の「実際に贈与した日付」とお金の移動日が一致すれば、生前贈与をより確実に証明できるでしょう。
下記が、現金を贈与する場合の贈与契約書の雛形です。
贈与契約書
○○○○(以下「甲」という)と、○○○○(以下「乙」という)は、以下の通り贈与契約を締結する。
第1条 甲は、乙に対し、現金○○万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第2条 甲は、前条の贈与金を、平成〇年〇月〇日までに、乙が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。その振り込みに要する費用は甲の負担とする。
以上を証するため、甲及び乙は本書を2部作成し、記名、押印のうえ各1部を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 ○○県○○市○○一丁目一番一号
○○ ○○ ㊞
乙 ○○県○○市○○二丁目二番地二
○○ ○○ ㊞
契約書をダウンロードしたい人はこちら
6-2 土地や家屋を贈与する場合
土地や家屋を贈与するする場合には、贈与契約書だけでなく収入印紙を用意しなければなりません。
必要な収入印紙は、それぞれ下記の通りです。
- 不動産価額の記載をしていない贈与契約書:200円の収入印紙
- 不動産価額を記載している贈与契約書:価額に合った収入印紙
また、不動産の贈与契約書には、地番や家屋番号を正確に記載する必要があります。
事前に正確な地番や家屋番号を調べておき、相違がないように準備しておきましょう。
下記が、土地や家屋を贈与する場合の贈与契約書の雛形です。
贈与契約書
○○○○(以下「甲」という)と、○○○○(以下「乙」という)は、以下の通り贈与契約を締結する。
第1条 甲は、乙に対し、甲の所有する下記の不動産(以下「本件不動産」という。)を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
(土地)
所在 ○○県○○市○○一丁目
地番 〇番〇号
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
(家屋)
所在 ○○県○○市○○一丁目
家屋番号 〇番〇号
種類 居宅
構造 木造ストレート葺2階建
床面積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
第2条 甲は、令和〇年〇月〇日までに、本件不動産を乙に引き渡し、また、その所有権移転登記を行う。所有権移転登記手続に要する一切の費用は乙の負担とする。
第3条 本件不動産に係る公租公課は、所有権移転登記の日までに相当する部分は甲の負担とし、その翌日以降に相当する部分は乙の負担とする。
以上を証するため、甲及び乙は本書を2部作成し、記名、押印のうえ各1部を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 ○○県○○市○○一丁目一番一号
○○ ○○ ㊞
乙 ○○県○○市○○二丁目二番地二
○○ ○○ ㊞
契約書をダウンロードしたい人はこちら
6-3 株式を贈与する場合
株式を贈与する際に作成する贈与契約書には、贈与する株式の情報を正確に記載しなければなりません。
贈与契約書の作成前に、会社名や会社の住所、株券の記番号などの情報を得ておくことを覚えておきましょう。
下記が、株式を贈与する場合の贈与契約書の雛形です。
贈与契約書
贈与者 ○○○○(以下「甲」という)と、受贈者 ○○○○(以下「乙」という)は、以下の通り贈与契約を締結する。
第1条 甲は、株式会社○○(本店 ○○県○○市○○一丁目〇番〇号)の普通株式○○株(株券の希望番号○○○○)(以下、「本件株式」という。)を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 前条の贈与は、令和〇年〇月〇日に行われるものとし、同日をもって、本件株式に関する権利は乙に移転するものとする。
以上を証するため、甲及び乙は本書を2部作成し、記名、押印のうえ各1部を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 ○○県○○市○○一丁目一番一号
○○ ○○ ㊞
乙 ○○県○○市○○二丁目二番地二
○○ ○○ ㊞
契約書をダウンロードしたい人はこちら
7章 生前贈与で贈与契約書を作成する際の注意点
生前贈与で贈与契約書を作成する際には、贈与契約書以外に贈与の証拠も残しておくことに注意しておきましょう。
また、受贈者が未成年者の場合は、受贈者のみでなく親権者などの法定代理人も贈与契約書に署名しておくとより安心です。
生前贈与の際に贈与契約書を作成するときの注意点は、主に下記の通りです。
- 実際に贈与したことを証明できる書類も用意しておく
- 公証人役場で確定日付をもらう
- 贈与契約書への押印は実印が望ましい
- 贈与契約書の代筆は避けた方が良い
- 孫などの未成年者へ贈与する場合は親権者も署名押印する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
7-1 実際に贈与したことを証明できる書類も用意しておく
贈与契約書だけでも贈与した事実を証明することは可能ですが、実際に贈与をしたことを証明できる書類があるとさらに安心です。
例えば、口座へ振り込みをした際の書類の控えや登記事項証明書などといった事実証拠があるといいでしょう。
こうした書類があれば、より明確に生前贈与があったことを証明できます。
一方で、贈与契約書は作成していたものの贈与の事実を証明できる証拠がない場合、贈与者が亡くなったときに税務署などから過去の贈与を否認される恐れがあるのでご注意ください。
7-2 公証人役場で確定日付をもらう
贈与契約書を作成したら、公証役場で確定日付をもらうと、より信頼性が上がります。
確定日付をもらうと、その時点で贈与契約書が存在していたということを証明できるからです。
というのも、節税対策として日付を遡って贈与契約書を作成し、贈与があったことにするケースも中にはあるからです。
税務調査が入った際も、公証人役場で確定日付をもらっておけば生前贈与があったことを認められやすくなります。
7-3 贈与契約書への押印は実印が望ましい
贈与契約書には、贈与する人と贈与を受ける人双方が押印する必要があります。
使用する印鑑に指定はありませんが、印鑑登録されている実印で押印して印鑑証明書と一緒に保管しておくと信頼性が高まります。
7-4 贈与契約書の代筆は避けた方が良い
贈与契約書の代筆は後日のトラブルの元になるため、しない方がよいです。
なぜなら本人が死亡した場合などに、本人の意思が伴っていたのかどうか、疑義を生む可能性が高くなるからです。
代筆は贈与する人が高齢により自筆できない場合など、やむを得ない事情がある場合だけにしましょう。
また、間違いなく本人の意思によって代筆されたと証明するためには、実印で押印しておくと効果的です。
他にも贈与契約書を締結する際に、第三者に立ち会ってもらい立会人の印鑑をもらうという方法もあります。
7-5 孫などの未成年者へ贈与する場合は親権者も署名押印する
子供や孫などの未成年者への贈与をする際には、受贈者だけでなく親権者などの法定代理人の同意も必要です。
そのため、贈与契約書を作成するときには、未成年者の受贈者の署名押印だけでなく、親権者にも署名押印してもらいましょう。
まとめ
贈与契約書があれば、生前贈与に関わるさまざまなトラブルを防ぎやすくなります。
作成するための手間や時間こそかかるものの、贈与を気持ちよくスムーズに進めるためには、作成しておくと安心でしょう。
また、贈与契約書は自分たちで作成するだけでなく、司法書士や弁護士に作成を依頼できます。
相続対策や生前贈与に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、贈与契約書の作成だけでなく、資産や相続人の状況に適した相続対策の方法も提案してもらえるはずです。
グリーン司法書士法人では、生前贈与を始めとする相続対策について相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
贈与契約書の作り方は?
贈与契約書は以下の流れで作成します。
①贈与の内容を詳しく決める
②贈与に合意する
③贈与契約書を作成する
④贈与する人と贈与を受ける人がそれぞれ1枚ずつ保管する
▶贈与契約書の作成について詳しくはコチラ生前贈与は誰に相談すべき?
生前贈与は自分でも手続きできますが、後々のトラブルや税務署からの指摘を避けるために税理士や司法書士に依頼するのが良いでしょう。
贈与税の計算・申告:税理士
贈与契約書の作成や不動産の名義変更手続き:司法書士
▶生前贈与の手続き依頼先について詳しくはコチラ贈与契約書は実印を捺すべきですか?
贈与契約書には、贈与する人と贈与を受ける人双方の押印が必要です。
使用する印鑑に指定はありませんが、印鑑登録されている実印で押印して印鑑証明書と一緒に保管しておくと信頼性が高まります。
▶贈与契約書の押印について詳しくはコチラ贈与契約書はなぜ必要なのですか?
贈与契約書があれば生前贈与があったことを確実に証明可能です。
贈与契約書があれば、生前贈与が成り立つ条件である「贈与する人と贈与を受ける人双方が合意していること」を立証でき、万が一のトラブルを防止できます。
▶贈与契約書の必要性について詳しくはコチラ贈与契約書は手書きで作成しても良い?
贈与契約書の書き方に決まりはありませんが、文書作成ソフトなどを利用して作成するのが一般的です。
パソコンが苦手な場合には、手書きで作成しても問題ありません。生前贈与の契約書に押す印鑑は?
生前贈与の契約書に押す印鑑に指定はありません。
ただし、印鑑登録されている実印で押印しておくと信頼性が高まります。贈与契約書はパソコンで作成できる?
贈与契約書はパソコンで作成しても問題ありません。
ただし、信頼性を高めるため署名および日付は手書きが良いでしょう。親から100万円もらうと贈与税はかかりますか?
親から100万円もらっただけでは、贈与税はかかりません。
贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されているからです。
▶親から100万円もらったときの贈与税について詳しくはコチラ