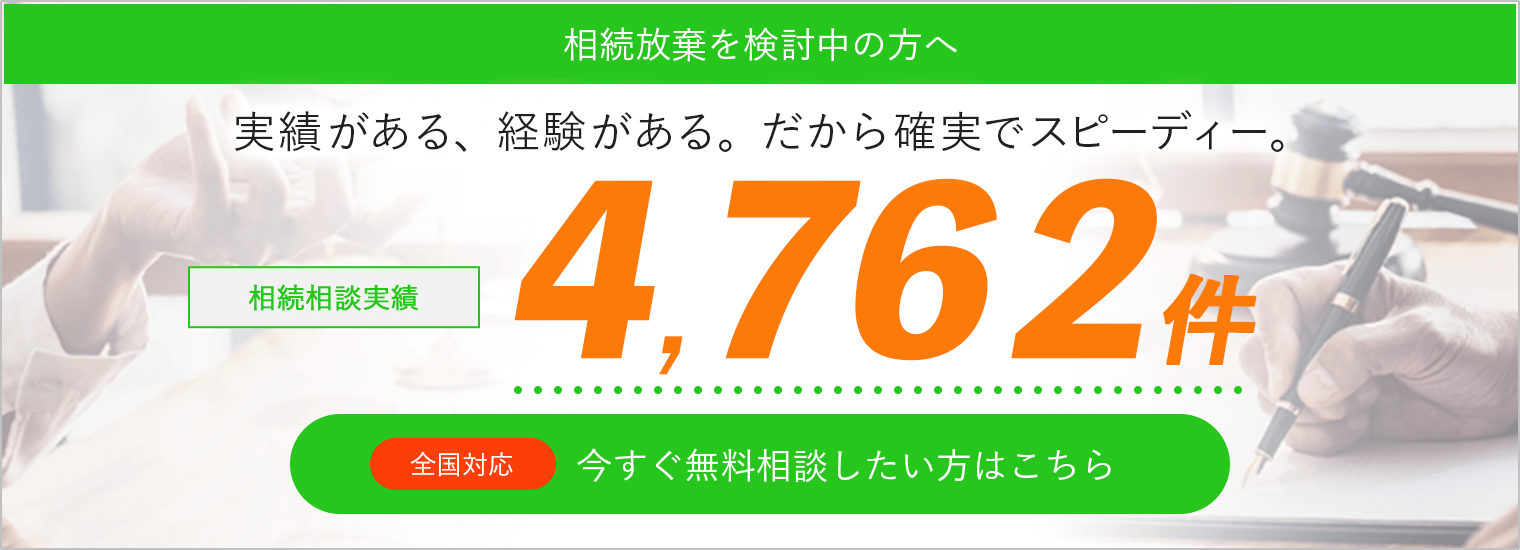遺産に借金があるケースや所有しているだけで負担となる不動産があるケースでは、相続放棄を検討する人もいるでしょう。
また、このように相続放棄すべき理由がある場合には、相続人全員で相続放棄することも珍しくありません。
相続人全員で相続放棄した場合には、故人が遺した財産がどうなるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、故人が借金を遺して亡くなった場合には相続放棄したプラスの財産を各債権者に分配します。
行き場のない財産に関しては国庫に帰属(国が取得)されます。
本記事では、法定相続人全員が相続放棄するとどうなるのか、手続きの流れをわかりやすく解説していきます。
相続放棄に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
目次
1章 相続人全員が相続放棄することは認められている
故人が借金を遺している場合や故人の財産に活用できそうにない不動産がある場合などに、相続人全員が相続放棄することは可能です。
法定相続人とは、下記のように優先順位が決められています。

- 配偶者:常に相続人になる
- 子供(または孫、ひ孫など)の直系卑属:第一順位
- 両親(または祖父母、曽祖父母など)の直系尊属:第二順位
- 兄弟姉妹(または甥姪):第三順位
優先順位の高い相続人がいる場合、低い人物は法定相続人にはなれません。
したがって、配偶者と子供が相続人になっているときには、故人の兄弟姉妹は相続人になれません。
そして、相続放棄をすると優先順位が低い人物に相続権が移ります。
例えば、配偶者と子供が相続放棄をした場合には、下記のように相続権が移っていきます。
- 配偶者と子供が相続放棄をする
- 故人の両親もしくは祖父母が相続人となる
- 故人の両親、祖父母がすでに他界している、もしくは相続放棄したら兄弟姉妹が相続人となる
相続人全員が相続放棄する状態とは、故人の兄弟姉妹(または甥姪)全員が相続放棄した状態です。
先ほど解説したように、優先順位の高い人物が相続放棄をすると、次の相続順位の人物に相続権が移ります。
また、相続放棄により別の人物が法定相続人になったとしても、家庭裁判所から連絡が届くことはありません。
自分が相続放棄をする際には、次に相続人となる人物と連絡が取れるなら、迷惑がかからないように、相続放棄をしたことや理由を連絡するようにしましょう。
2章 相続人全員が相続放棄をすると起きること
相続人全員が不動産などを相続放棄すると、相続財産は特別縁故者が受け継ぐか国庫に財産が帰属されます。
相続人全員が相続放棄した際に起きることは、下記の4つです。
- 相続財産管理人の選任が必要になる
- 故人のプラスの財産は債権者に分配される
- 特別縁故者に財産が渡るもしくは国庫に財産が帰属される
- 相続人は固定資産税を支払う義務がなくなる
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 相続財産管理人の選任が必要になる
遺産に借金などがある場合、相続人全員が相続放棄したとしても借金を清算しなければなりません。
相続放棄した相続人のかわりにその役割を担うのが、相続財産管理人です。
法律上の相続人がいない(または相続放棄によりいなくなったとき)は、債権者などの利害関係者や検察官が裁判所に申立て相続財産管理人を選任してもらいます。
相続人たちが相続財産管理人の選任の申立てを強制されることはなく、必要であると判断した人が申立てをするのが一般的です。
ただし、債権者が名乗り出ない場合や換価して国庫に帰属するほどの財産がない場合には、そのまま放置されるケースも多いのが実情です。
相続財産管理人の選任申立ての手続き概要と必要書類は、下記の通りです。
| 申立てできる人 | 利害関係者 債権者 |
| 申立て先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 必要書類 |
|
2-2 プラスの財産が債権者に分配される
遺産に借金があり、借金の債権者が相続財産管理人を申立てた場合、相続財産管理人はの財産を換価して債権者に返済します。
お金にかえられる遺産(不動産や株式など)で可能な限り借金を返済して清算していきます。
2-3 特別縁故者に渡るもしくは国庫に財産が帰属される
下記のケースでは故人のプラスの財産が特別縁故者にわたります。
- 故人に特別縁故者がいる場合
- 借金清算後にプラスの財産が残っている場合
特別縁故者とは、亡くなった人と特別な関係にあった人を指します。
例えば、内縁の妻や家族同然に生活をともにしていた他人などが該当します。
相続人全員が相続放棄し特別縁故者もいない場合には、残りの財産はすべて国庫に帰属されます。
2-4 相続人は固定資産税を支払う義務がなくなる
不動産の固定資産税は、遺産分割が完了していない状況では相続人全員に支払う義務があります。
固定資産税の納税通知書も相続人宛に届きます。
しかし、相続放棄をした人はたとえ相続人であったとしても固定資産税を支払う義務がなくなります。
相続人全員が相続放棄した場合には、誰も固定資産税を払う必要がなくなるのでご安心ください。
もし、相続順位の上位の人が相続放棄をした場合、順位の低い相続人の元に突然、固定資産税の納税通知書が届く可能性もあります。
迷惑をかけないようにするためにも、相続放棄後の連絡は必ず行いましょう。
本記事で解説しているように、相続放棄をすると次の相続順位となる人物に相続権が移ります。
相続人全員で相続放棄するには、相続順位を把握して効率よく手続きを進めることが大切です。
次の章では、相続人全員で相続放棄する流れを紹介していきます。
3章 相続人全員で相続放棄をする際の流れ
全員で相続放棄をする場合、それぞれの相続人がバラバラに手続きをするのではなく皆さんで一緒に手続きするのが効率的です。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合も、複数人で依頼をすれば資料を共有できるため費用が割安となる場合もあります。
何より専門家がスケジュール管理のうえ、相続放棄すべき順番ごとにスムーズに裁判所での手続きを行ってくれるので安心です。
相続人全員で相続放棄する流れは、下記の通りです。
- 全員で相続放棄するべきか話し合う
- 家庭裁判所で相続放棄の申立てをする
- 照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP① 全員で相続放棄するべきか話し合う
まずは、相続人全員で相続放棄をするべきか話し合いましょう。
故人の借金を背負わずにすむ方法には、相続放棄だけでなく限定承認もあります。
相続時の状況や故人の資産状況によっては限定承認のほうが良い場合もあるので、判断に迷った場合には司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
なお、相続放棄は他の相続人の合意がなくても手続きは可能ですが、勝手に手続きを進めるとトラブルに発展する恐れもあります。
可能であれば、相続人間で話し合いましょう。
STEP② 家庭裁判所で相続放棄の申立てをする
相続人全員で相続放棄することを決定したら、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行いましょう。
相続放棄を行う際には、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。
提出方法は郵送もしくは直接窓口に出向くのでも問題ありません。
郵送で提出する場合には、荷物の追跡ができるレターパック等の封筒を用いると、万が一配送業者や郵便局の手違いで書類が届かなかった場合にも安全です。
相続放棄の申立ては、相続人1人につき1件として取り扱われますが、代表者が全員分の書類をまとめて提出する方法も認められています。
相続放棄の申立て手続きの概要および必要書類は、下記の通りです。
| 申立てする人 | 相続放棄する人 法定代理人 |
| 申立て先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立て費用 |
|
| 必要書類 |
など |
STEP③ 照会書に回答する
相続放棄の申立て後しばらくすると、裁判所から照会書・回答書が届くことがあります。
なお、すべての相続放棄で照会書・回答書が届くわけではありません。
照会書と回答書は、本当に相続放棄する意思があるか確認する目的で送られているので速やかに回答しましょう。
記載されている内容は、主に下記の通りです。
- 相続放棄の申述は自分の意思によるものかどうか
- 相続人になったことをいつ知ったか
- 相続放棄をする理由
STEP④ 相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が受理されたら「相続放棄申述受理書」が届きます。
相続放棄申述受理書が届いたら、相続放棄の手続きは終了です。
相続放棄が完了すれば、故人の財産を受け継がなくて良くなりますが、不動産の管理義務は引き続き残ります。
次の章で、詳しく解説していきます。
4章 相続放棄後も不動産の管理義務は残る
相続放棄をすれば、故人が遺した借金や管理に困るだけの活用予定もない土地から解放されると考えている人もいるかもしれません。
しかし、不動産など管理が必要な財産に関しては、次に管理する人物が見つかるまでは管理義務が残ってしまいます。
不動産などの財産の管理義務を負うのは、原則として最後に相続放棄した相続人です。
つまり、相続時の状況によっては故人の甥や姪など疎遠な親族が不動産の管理をしなければならない可能性もあるでしょう。
相続放棄した不動産の管理義務について詳しく解説していきます。
4-1 相続人が行うべき不動産の管理
不動産の管理義務を負った相続人は、以下の管理を行う必要があります。
- 立て付けが悪化していないかの確認・対処
- 老朽化によって倒壊の恐れがないかの確認・対処
- 雑草の処理
- 害虫・害獣の処理
4-2 管理を怠った場合のリスク
相続人が不動産の管理を怠った場合には、以下のようなリスクがあります。
- 損害賠償請求される
- 犯罪の温床となり事件に巻き込まれる
例えば、相続放棄した建物の管理を怠り市場価値が下がってしまうと、債権者が債権を回収できない、特別縁故者が遺産を取得できないなどの恐れがあります。
その場合、管理責任者が損害賠償請求を受けることもあるので注意が必要です。
また、管理を怠った建物が倒壊し、歩行者をケガさせた場合にも損害賠償請求される恐れがあります。
空き家は犯罪者の隠れ家になる、放火されやすいなど犯罪に繋がるリスクもあるので、適切な管理をしなければなりません。
4-3 勝手に処分をすると相続放棄の効果が無くなる可能性がある
不動産の管理義務を負いたくないからと不動産の売却もしくは寄付をしてしまうと、単純承認とみなされ相続放棄できなくなってしまう恐れがあります。
相続放棄をする場合には、相続財産を勝手に処分、売却することは避けましょう。
とはいえ、老朽化による倒壊など解体しなければ危険と判断されるケースも中にはあります。
判断に迷うケースでは、司法書士や弁護士など専門家と相談するのがおすすめです。
4-4 不動産の管理責任を免れるためには相続財産管理人の選任が必要
本記事で解説してきたように、相続人全員が相続放棄した後は不動産が国庫に帰属するなど次の所有者が決まるまで最後に相続放棄した相続人が管理責任を負います。
しかし実際のところ、勝手に国が不動産を処分してくれるケースはほとんどなく、いつまでも放置されることが多いです。
相続放棄した不動産を処分してもらい管理義務から解放されるためには、相続財産管理人を選任しなければなりません。
相続財産管理人を選任して、遺産の管理を任せれば相続放棄者の管理義務はなくなります。
相続放棄した不動産の管理義務以外にも、相続人全員で相続放棄する際にはいくつか注意しなければならないことがあります。
次の章で詳しく見ていきましょう。
5章 相続人全員で相続放棄をする際の注意点
相続人全員で相続放棄する際には、以下に注意して慎重に手続きを進めていきましょう。
- プラスの財産も全員で手放さなければならない
- 他に相続人がいないか確認する
- 相続財産管理人の申立ての手間と裁判所に支払う予納金がかかる
それぞれ詳しく解説していきます。
5-1 プラスの財産も全員で手放すこととなる
相続放棄は一切の相続権を手放す手続きであり、プラスの財産もマイナスの財産も相続できなくなってしまいます。
故人の借金だけでなく、思い入れのある実家なども相続放棄すると失うことになるので慎重に決断しましょう。
実家などどうしても遺したい財産がある場合には、相続放棄ではなく限定承認を行うのも選択肢のひとつです。
5-2 他に相続人がいないか確認する
本記事の序盤で解説したように、相続放棄を行うと相続順位の低い人物に相続権が移ります。
そのため、自分が相続放棄したことにより、別の親族が知らないうちに相続人になってしまう可能性もあります。
相続人全員で相続放棄する場合には、必ず他に相続人になる人物がいないかを確認し、万が一相続人になる人物が見つかった場合には報告してあげましょう。
相続人になる人物を探す際には、下記の記事もご参考にしてください。
5-3 相続財産管理人の申立ての手間と裁判所に支払う予納金がかかる
故人が遺した財産の中に実家など不動産がある場合、相続人全員で相続放棄したとしても不動産を管理する義務は残り続けます。
不動産の管理義務からも解放されるためには相続財産管理人の選任が必要ですが、申立て時には手間と費用がかかります。
相続財産管理人の選任にかかる費用の内訳と相場は、下記の通りです。
| 費用 | 相場 |
| 申立て手数料(収入印紙代) | 800円 |
| 連絡用の郵便切手代 | 1,000円程度 |
| 官報公告費用 | 3,775円 |
| 予納金 | 数十万から百万円程度 |
5-4 勝手に他の相続人の相続放棄をすることは認められない
相続放棄することは相続人の自由であり、どのような事情があったとしても他の相続人や関係者が強制することは認められません。
原則として相続放棄は一度してしまうと撤回できませんが、詐欺や強迫、勝手に相続放棄されたケースでは家庭裁判所にて相続放棄の取消しが認められる場合もあります。
いずれにせよ、自分の意思に反して相続放棄させられた場合には、自分で解決することは難しいので相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。
6章 相続放棄をしても受け取れる財産
相続放棄をすると、相続権の一切を失うことになりますが、相続財産に含まれないものであれば相続放棄をしたとしても受け取り可能です。
具体的には、以下の2つの財産は相続放棄をしていても受け取れます。
- 葬儀費用
- 受取人名義の財産(生命保険金や共済年金・死亡退職金など)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
6-1 葬儀費用
葬儀費用は、相続放棄前に遺産から捻出しても問題ないとする判例があります。
ただし、常識的な範囲を超える高額な葬儀代や会葬者の飲食代は認められない可能性があるので注意が必要です。
もし、葬儀費用が高額になる可能性がある場合には、事前に司法書士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
6-2 受取人名義の財産(生命保険金や共済年金・死亡退職金など)
生命保険金や共済年金、死亡退職金など受取人が指定されている保険金は相続放棄をしても受け取れます。これらの財産は、相続財産ではなく指定された受取人の財産だからです。
ただし、相続税計算時にはこれらの保険金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象財産に含まれます。
また、生命保険金や死亡退職金の種類によっては、受取人指定がされていないケースもあります。
受取人が指定されていない保険金は、相続財産に分類される可能性があるので受取前に保険会社や司法書士、弁護士などの専門家に確認しておきましょう。
まとめ
相続人全員が相続放棄することは可能であり、故人が借金を遺した場合や活用しにくい財産がある場合には相続放棄を検討しても良いでしょう。
ただし、相続放棄には3ヶ月と期限が決まっていて、相続放棄をすると次の相続順位の人物に相続権が移ります。
相続人全員で相続放棄を成功させるためには誰が相続人なのかを把握し、効率よく手続きを進めることが大切です。
相続放棄の手続きをスムーズに進める、ミスなく確実に手続きをするためにも相続放棄に詳しい司法書士や弁護士への相談をおすすめします。
また、司法書士や弁護士であればそもそも相続放棄が必要なのか、他に良い選択肢はないのかのアドバイスも可能です。
グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
全員が相続放棄するとどうなる?
全員が相続放棄すると起きることは、下記の4つです。
①相続財産管理人の選任が必要になる
②故人のプラスの財産は債権者に分配される
③特別縁故者に財産が渡るもしくは国庫に財産が帰属される
④相続人は固定資産税を支払う義務がなくなる
▶相続放棄について詳しくはコチラ全員で相続放棄できる?
故人が借金を遺している場合や故人の財産に活用できそうにない不動産がある場合などに、相続人全員が相続放棄することは可能です。
▶相続放棄について詳しくはコチラ子供たち全員が相続放棄するとどうなりますか?
子供たち全員が相続放棄した場合、故人の両親が相続権を持ちます。
そして、故人の両親がすでに死亡している場合は、故人の兄弟姉妹や甥・姪が相続権を持ちます。