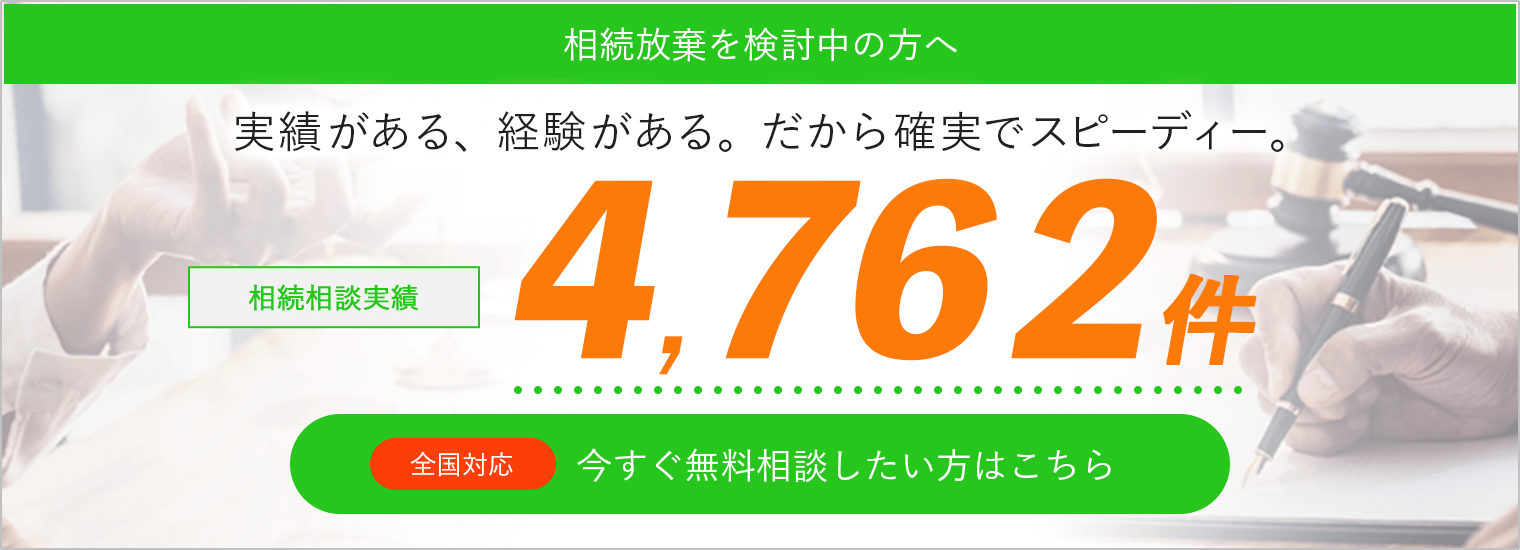- 相続放棄をしたらお墓はどうなるのか
- 祭祀承継者を決める方法
- 祭祀承継者がお墓を継げないときの対処法
墓地(永代使用権)は不動産の所有権とは異なり、たとえ相続放棄しても墓の管理義務や使用契約は残る可能性があります。
相続放棄=墓じまいとはならず、墓地管理者との契約内容を確認した上で、改葬・承継・墓じまいなど別の対応を検討する必要があります。
本記事では、相続放棄とお墓の承継の関係や、祭祀承継者を決定する方法を解説します。
目次
1章 相続放棄をしたらお墓はどうなる?
相続放棄とは、故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。
しかし、お墓は相続財産ではなく祭祀財産に分類されるため、相続放棄による影響を受けません。
本章では、相続放棄をしたときのお墓の取り扱いについて詳しく解説していきます。
1-1 相続放棄とお墓に直接的な関係はない
相続放棄とお墓に直接的な関係はありません。
したがって、相続放棄をしてもお墓を手放すことはできませんし、相続放棄をしたからといってお墓を受け継げなくなるといったこともありません。
1-2 お墓を受け継ぐのは祭祀承継者である
お墓は相続財産ではなく、祭祀財産として扱われ、受け継ぐ人物も相続人ではなく祭祀承継者とされています。
祭祀承継者とは、仏壇やお墓などといった故人の祭祀を承継する責任を負う者です。
通常、祭祀承継者は法定相続人のうち最も近い親族(配偶者や子供など)が就くことが一般的です。
祭祀承継者は相続人とは異なるため、相続放棄をした人でも祭祀承継者になることができます。
むしろ、祭祀承継者は故人の供養やお墓の維持管理を適切に行う必要があるため、相続放棄をしたとしても、祭祀承継者としての義務を果たさなければなりません。
例えば、故人に多額の借金があり、法定相続人である長男が相続放棄をしたとしましょう。
その場合でも、長男が祭祀承継者に選ばれていれば、お墓の永代使用料の支払い手続きや改葬の許可申請などを行わなければなりません。
祭祀承継者としての義務を怠ると、墓地管理者とのトラブルや、将来的に他の親族との間でお墓の扱いをめぐって揉める恐れもあるでしょう。
2章 祭祀承継者を決める方法
祭祀承継者を誰にするかについては、法定相続人と異なり、法律で決められているわけではありません。
一般的には、以下の方法で祭祀承継者を決定します。
- 故人が遺言書などで指定する
- 親族間での話し合いや慣習によって決める
- 家庭裁判所の調停や審判で決める
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 故人が遺言書などで指定する
祭祀承継者を最も確実に決める方法は、故人が遺言書などで指定することです。
遺言書に「祭祀承継者として〇〇を指定する」と記載しておけば、相続人同士で争いが起こりにくくなります。
2-2 親族間での話し合いや慣習によって決める
故人が遺言書を用意していないケースでは、親族同士の話し合いによって祭祀承継者を決定します。
一般的には、長男や配偶者など、故人と最も近い血縁関係にある者を祭祀承継者とすることが多いでしょう。
ただし、地域や家の慣習、家督の考え方などによって順序は異なるため、一律のルールはありません。
話し合いを進める際には、誰が実際に仏壇やお墓の管理をしやすいかどうかや、それぞれの健康状態なども考慮することが大切です。
話し合いの内容については、議事録や承継契約書などにまとめ、後日のトラブルを防ぐと良いでしょう。
2-3 家庭裁判所の調停や審判で決める
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「祭祀承継者指定調停」の申し立てをすることも可能です。
祭祀承継者指定調停では、調停委員を交えた話し合いを行います。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所の審判に移行します。
審判では、裁判官が祭祀承継者としてふさわしい者を選定し、確定的な判断を下します。
調停や審判を行えば、祭祀承継者を決められますが、手続きに時間と費用がかかるため、当事者同士での話し合いで決定できると良いでしょう。
3章 祭祀承継者がお墓を継げないときの対処法
祭祀承継者として選ばれても、お墓の遠方に住んでいる場合や高齢で介護を受けている場合などでは、お墓の維持管理が難しくなることもあるでしょう。
本章では、祭祀承継者がお墓を継ぐことが難しい場合の対処法を解説していきます。
3-1 墓じまいをする
祭祀承継者がお墓を継げない事情がある場合には、墓じまいを検討しましょう。
墓じまいとは、現在の墓地・納骨堂を閉鎖し、埋蔵されている遺骨を取り出して別の方法で供養する手続きです。
墓じまいは、以下の流れで進めることが一般的です。
- 寺院や霊園管理者に墓じまいについて相談する
- 改葬許可申請をする
- 遺骨の取り出しと供養方法を選択する
- 墓石撤去後に管理者へ使用契約の解除を届け出る
3-2 お墓を移転する
祭祀承継者が遠方に住んでいてお墓の管理が難しい場合には、よりアクセスの良い霊園や納骨施設へ「改葬」することも選択肢のひとつです。
お墓の移転は、以下の流れで進めていきます。
- 移転先を選定する
- 改葬許可申請を行う
- 改葬先の墓地と契約する
- 遺骨の搬出・搬入を行う
まとめ
お墓は相続財産ではなく祭祀財産に分類されるため、相続放棄と直接的な関係はありません。
そのため、相続放棄をしてもお墓を継ぐことは認められますし、反対に相続放棄してもお墓の管理義務は残り続けます。
お墓が遠方にある場合や、年齢や健康状態などが理由でお墓を継ぐことが難しい場合には、墓じまいやお墓の移転も検討しましょう。
お墓の承継に限らず、相続放棄をする際には、故人の遺品や形見の取り扱いなど悩まれることも多いはずです。
不安なことがある場合には、相続放棄に精通した司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続放棄についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
仏壇や仏具は相続放棄できますか?
仏壇や仏具は、お墓と同様に祭祀財産として扱われ、相続放棄することはできません。
そのため、相続放棄をしても祭祀承継者である場合には、仏壇や仏具の管理をしなければなりません。相続放棄をする前に墓じまいやお墓の移転をしても良いですか?
相続放棄とお墓の管理には直接的なつながりはないため、相続放棄の申立てをする前に墓じまいやお墓の移転をしても問題はありません。
しかし、相続放棄の申立ては、自分が相続人であると知ってから3か月以内と期限が設定されています。
そのため、墓じまいやお墓の移転に関する手続きに追われ、相続放棄の申立て期限を過ぎてしまわないように注意する必要があります。遺産でお墓を購入しても良いですか?
相続放棄をしたとしても、遺産でお墓を購入することが認められる場合があります。
しかし、高額なお墓を購入する場合、遺産の使用や処分とみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れもあるのでご注意ください。
相続放棄をする際、遺産でお墓の購入を検討しているのであれば、事前に司法書士や弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。相続放棄をするとお墓の管理費を払わなくてよくなりますか?
相続放棄をしても、お墓の管理費や供養に関する費用の負担義務は残ることがあります。
お墓や仏壇は「祭祀財産」と呼ばれ、相続財産とは別に祭祀承継者が引き継ぐためです。