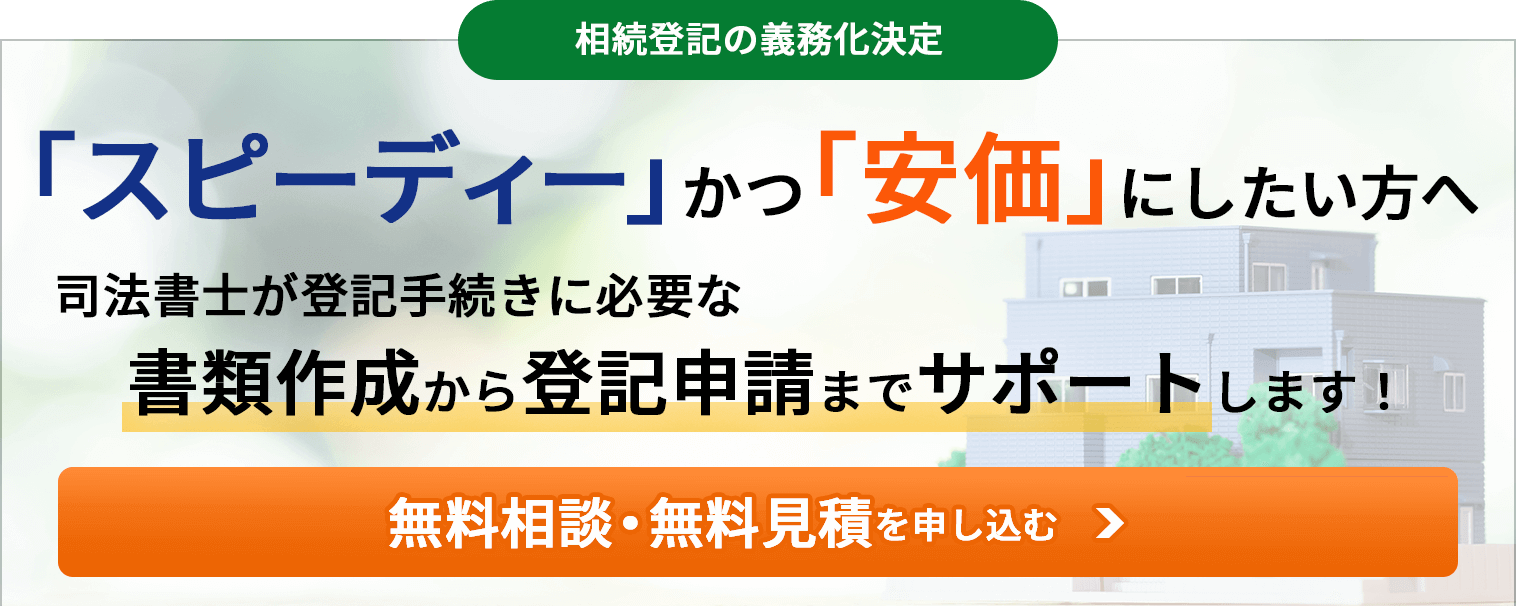- 相続人申告登記とは何か
- 相続人申告登記を行うメリット・デメリット
- 相続人申告登記の手続き方法・必要書類
2024年4月に不動産登記法が改正され、相続登記の義務化が施行されました。これにより、相続によって不動産を取得した相続人は、期限内に登記を申請しなければ過料を科せられる可能性があります。
しかし、実際には遺産分割協議がまとまるまで時間がかかることも多く、期限までに正式な登記をするのが難しいケースも少なくありません。そこで創設されたのが「相続人申告登記」です。
本記事では、相続人申告登記の概要・できる人・メリットとデメリット・必要書類・注意点について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
相続登記の義務化については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
目次
1章 相続人申告登記とは
「相続人申告登記」とは、被相続人が死亡した場合に、その不動産を相続する権利がある人が、法務局に対して「自分が相続人である」ことを申出する制度です。
従来は、相続が発生した際には相続登記(所有権移転登記)を行わないまま放置されるケースが多く、土地や建物の登記簿に登記名義人として既に死亡した人物が残ってしまう問題がありました。これにより、所有者不明土地が増加し、公共事業の妨げや空き家問題につながっていたのです。
こうした背景を踏まえて、2024年4月に不動産登記法が改正され、相続登記の義務化が施行されました。相続によって不動産を取得した相続人は、原則として相続の開始(死亡を知った日)から3年以内に登記を申請する義務があります。これを怠ると、正当な理由がない限り、法務省が定める過料(罰則)を科せられる可能性があります。
しかし、相続財産が複数あり、遺産分割協議がすぐにまとまらない場合も少なくありません。そのようなケースで義務を履行するために設けられたのが「相続人申告登記」です。
この申告登記を行うと、法務局が職権で登記記録に「被相続人が死亡したこと」「相続人の氏名や住所」といった情報を付記します。これにより、登記名義人の死亡と相続人の存在が公示され、相続登記の義務を一旦果たしたものとみなされます。
つまり、相続人申告登記は、
- 「相続登記の義務化に対応するための暫定的な手段」
- 「遺産分割や名義変更が未了の段階でも義務を免れることができる制度」
という役割を持っているのです。
1-1 相続人申告登記は相続登記義務化を受けて創設された
相続人申告登記が新設された最大の理由は、所有者不明土地問題の解消です。
これまで、不動産の登記簿に死亡した登記名義人が残ったまま放置されると、相続人を調べるために膨大な戸籍や除籍を取り寄せる必要があり、土地の利活用が事実上困難となっていました。こうした不動産は「国庫帰属」や「未了の遺産相続」として処理が複雑化し、行政や地域社会に大きな影響を与えていました。
そこで2024年4月の不動産登記法改正により、
- 相続登記を義務化(死亡を知った日から3年以内に登記申請を行うこと)
- 義務を怠った場合は過料を科すことが可能に
- ただし遺産分割がまとまらない状況に配慮し、相続人申告登記を設ける
という制度が施行されました。
つまり、相続人申告登記は、「すぐに所有権の名義変更ができなくても、とりあえず期限内に申告しておけば義務を果たしたとみなされる仕組み」なのです。
2章 相続人申告登記をできる人
相続人申告登記を行えるのは、相続を原因として不動産を承継する立場にある人です。具体的には、民法で定められた法定相続人が対象となります。
相続人は、被相続人との関係によって優先順位(相続順位)が決まります。例えば、配偶者は常に相続人となり、子ども(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹などが法定相続分に応じて相続権を持ちます。
法定相続人の例
- 第一順位:子どもや孫(直系卑属)
- 第二順位:父母・祖父母などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人ですが、直系尊属や兄弟姉妹は、第一順位の相続人がいない場合に限って相続権を取得します。
2-1 相続放棄をした人は申告できない
相続人申告登記は、法定相続分に基づいて相続権を持つ人が行うものです。したがって、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理された人は、相続人としての資格を失うため、申告を申し出ることはできません。
2-2 代理人による申告も可能
相続人本人が直接法務局に行かなくても、代理人を通じて申告登記を行うことが可能です。例えば、司法書士に依頼すれば、次のような支援を受けられます。
- 必要書類(戸籍謄本・除籍・戸籍の附票・住民票など)の収集代行
- 申告書や委任状の作成
- 法務局への申出・オンライン申請
- 登記簿の確認や権利関係の整理
この場合、相続人は司法書士に委任状を交付し、代理人として申請をしてもらうことになります。
3章 相続人申告登記を行うメリット
相続人申告登記は、2024年の相続登記義務化に伴って新設された制度であり、相続人にとって大きな利点があります。特に、相続登記の期限内に義務を履行するための有効な手段として注目されています。ここでは、その主なメリットを3つに分けて解説します。
3-1 相続登記の義務を履行できる
2024年4月の不動産登記法改正により、相続登記は義務化されました。被相続人が死亡し、相続が開始したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならないと定められています。
しかし、遺産分割協議が未了であったり、相続人の間で話し合いがまとまらなかったりすると、期限内に相続登記を完了させることが難しいケースが多くあります。
その場合でも、相続人申告登記を行えば、期限内の義務を履行したものとみなされるのです。
これにより、相続登記を放置して過料を科されるリスクを免れることができます。法務局は職権で登記記録に付記を行い、登記簿上に「相続人の氏名・住所」が記録されるため、相続人が存在することが公示される仕組みです。
3-2 相続人が単独で行える
通常の相続登記は、相続人全員による遺産分割協議の成立や、遺言書の有無の確認などが必要です。そのため、全員の合意がなければ手続きを進められず、相続人が多い場合や数次相続が発生している場合は時間がかかります。
一方、相続人申告登記は、相続人の一人が単独で申し出ることが可能です。つまり、協議が未了の状態でも、相続人の一人が申告するだけで義務を履行したと認められます。
この仕組みによって、法定相続人の間で協議が長引いても、最低限の手続を進められる点が大きなメリットです。
3-3 手続きが簡易で費用もかからない
相続人申告登記は、通常の相続登記と異なり登録免許税が不要です。つまり、申告登記そのものに費用はかかりません。
また、必要となる書類も限定的で、主に以下のものです。
- 被相続人の出生から死亡までを証する戸籍謄本・除籍
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票や戸籍の附票(住所証明情報)
これらの書類を揃えて申告書を作成すれば、法務局に申出るだけで手続きが完了します。
さらに、法務省が整備したシステムを利用すれば、オンライン申請や電子署名による提出も可能です。
つまり、相続人申告登記は「費用がかからず、簡単に行える義務履行の手段」という利点を持っています。
4章 相続人申告登記を行うデメリット
相続人申告登記は、相続登記義務化に伴う救済措置として有効な制度ですが、メリットばかりではありません。制度の特性上、将来的に二度手間になったり、相続人に不利益となる可能性もあります。ここでは、代表的なデメリットを3点に分けて解説します。
4-1 相続不動産の活用や売却はできない
相続人申告登記は、あくまで「義務を履行するための申告」に過ぎません。所有権を正式に移転する「名義変更(相続登記)」ではないため、以下のような不動産活用はできません。
- 相続した土地や建物の売却
- 贈与や生前贈与による名義変更
- 担保提供や抵当権の設定
つまり、申告登記をしただけでは、登記簿上の所有者は依然として被相続人のままです。法務局は職権で「相続人が申告した」という付記を登記記録に残しますが、それは「所有権が移転した」ことを意味しません。
そのため、実際に相続財産を処分したい場合には、最終的に必ず相続登記を行う必要があります。
4-2 遺産分割完了後は相続登記が必要になる
相続人申告登記をしても、それで相続手続が完了するわけではありません。遺産分割協議が成立した場合には、改めて相続登記を申請し、不動産の登記簿に正しい相続人の名義を記載しなければなりません。
そのため、次のようなデメリットが生じます。
- 結局、正式な相続登記が必要になり二度手間となる
- 相続人全員の協議や合意形成を省略することはできない
- 相続財産の権利関係が複雑な場合、追加の書類が必要になる
相続人申告登記は「とりあえず義務を履行するための暫定的な制度」であり、将来的に遺産分割が成立すれば、再度の登記が必須です。
4-3 登記事項証明書に住所氏名が掲載されてしまう
相続人申告登記をすると、登記事項証明書に相続人の氏名・住所・生年月日などが記録されます。これは「登記簿の公示機能」に基づくものであり、誰でも法務局で登記事項証明書を取得すれば閲覧可能です。
このため、以下のような懸念があります。
- 相続人の個人情報が第三者に知られるリスク
- 相続人が複数いる場合、それぞれの氏名・住所が公開される
- プライバシーを重視する人にとっては大きなデメリット
特に近年は個人情報保護の観点からも注意が必要であり、「申告によって義務を履行できる代わりに、一定の情報が公示される」という点を理解しておく必要があります。
登記事項証明書は誰でも閲覧できるので、不動産の営業チラシが届く場合もありますし、代表者として相続した不動産の固定資産税納税通知書が送られてくる可能性もあります。
相続した不動産の固定資産税を納税する義務は、相続登記が完了していない場合は相続人全員が負います。
しかし、固定資産税の納税通知書は相続人全員に送付されるのではなく、代表者宛に送られてくるのでご注意ください。
他の相続人が不動産の相続手続きや固定資産税の支払いに非協力的な場合、相続人申告登記をした人が固定資産税を納めざるを得ない場合もあるでしょう。
5章 相続人申告登記の手続き方法・必要書類
相続人申告登記は、相続登記義務化に対応するために創設された制度であり、申請先や必要書類が明確に定められています。ここでは、手続の流れと必要書類について整理します。
| 手続きできる人 |
|
| 手続き先 | 相続不動産の住所地を管轄する法務局 |
| 手続き方法 |
|
| 費用 | 無料 (戸籍謄本類の収集費用は別途かかる) |
| 必要書類 |
|
5-1 相続人申告登記の手続きの流れ
- 必要書類を収集する
- 被相続人の出生から死亡までを証する戸籍謄本や除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本・住民票・戸籍の附票などの住所証明情報
- 遺言書(ある場合)
- 委任状(代理人に依頼する場合)
- 申告書を作成する
- 相続人の氏名・住所・生年月日・本籍などを記載
- 被相続人の情報(死亡日・本籍地・最後の住所)を記載
- 相続人が「相続人であることを証する」ことを明示
- 管轄法務局へ申出る
- 不動産の所在地を管轄する法務局に提出
- 窓口での提出だけでなく、オンライン申請(電子署名・押印省略可能)も利用できる
- 法務局が職権で登記記録を付記する
- 被相続人が登記名義人である不動産の登記簿に「相続人申告登記済」の付記がなされる
- 登記事項証明書には相続人の氏名・住所などが記載され、公示される
このように、申告登記は「申出る」ことで完了し、法務局が職権で処理してくれる点が特徴です。
5-2 相続人申告登記に必要な書類
相続人申告登記で求められる主な書類は以下のとおりです。
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までを証するもの)
- 除籍謄本(被相続人の婚姻や死亡に伴う戸籍)
- 相続人の戸籍謄本(相続関係を明らかにするため)
- 住民票または戸籍の附票(相続人の住所証明情報)
- 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言などがある場合)
- 委任状(司法書士など代理人に依頼する場合)
場合によっては、法務局から追加資料の提出を求められることもあります。
5-3 登録免許税や費用について
相続人申告登記は、通常の相続登記と異なり登録免許税がかかりません。そのため、費用面での負担はほとんどなく、必要なのは戸籍や住民票の取得費用程度です。
ただし、代理人(司法書士)に依頼する場合は、書類収集や申告書作成、登記簿調査にかかる報酬費用が必要になります。
5-4 相続人申告登記は司法書士に依頼できる
相続人申告登記は本人でも手続可能ですが、相続財産の数が多い場合や、複雑な権利関係が絡む場合は、司法書士に依頼するのが安心です。
司法書士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 戸籍や除籍など複雑な書類の収集を代行してもらえる
- 相続関係説明図や遺産分割協議の状況に応じた適切なアドバイスを受けられる
- オンライン申請や法務局への提出を代理してもらえる
- 将来的な相続登記(所有権移転登記)へのスムーズな移行が可能
特に数次相続や、兄弟姉妹が多く関わる相続では、書類の不備が生じやすいため、司法書士への依頼が有効です。
グリーン司法書士法人でも、相続登記についての相談をお受けしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
6章 相続人申告登記を行う際の注意点
相続人申告登記は、相続登記義務化に対応する便利な制度ですが、利用にあたってはいくつか注意すべき点があります。ここを誤解すると、せっかくの申告が義務の履行と認められなかったり、後々の相続登記で余計な手間が生じる可能性があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
6-1 過去に相続した不動産についても相続人申告登記を行える
相続人申告登記は、2024年の施行以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続にも遡って適用できます。
例えば、2020年に被相続人が死亡して登記が未了のまま放置されている土地についても、2025年以降に相続人申告登記を申し出ることが可能です。
これにより、すでに死亡した登記名義人の不動産でも、相続人が申告を行えば義務を履行したとみなされる仕組みになっています。
ただし、遡って申告を行った場合でも、将来的に遺産分割協議が成立すれば相続登記を改めて行う必要がある点は変わりません。
そのため、過去に相続したものの登記申請がすんでいない不動産をお持ちの人は、とりあえず相続人申告登記だけを行っておいても良いでしょう。
ただし、相続登記をせずに不動産を放置し続けると、次の相続が発生していまい、権利関係者が増え登記申請が複雑になるリスクもあります。
そのため、可能であれば相続人申告登記を行うのではなく、登記申請を行ってしまう方が安心です。
相続登記の手続きを行うのが難しい場合や遺産分割協議が難航している場合は、相続に詳しい司法書士に相談することも検討しましょう。
6-2 相続登記の義務を果たすには相続人全員が相続人申告登記をする必要がある
相続人申告登記は、相続人の一人が単独で申し出ることが可能です。しかし、それで相続登記義務を完全に履行できるわけではありません。
なぜなら、不動産登記簿に記録されるのは「申告を行った相続人」だけだからです。
仮に相続人が3人いる場合、そのうち1人だけが申告しても、残りの2人が義務を果たさなければ、相続登記の義務を履行したことにはなりません。
相続登記の義務を免れるためには、法定相続人全員が相続人申告登記を行う必要があります。
6-3 その他の注意点
相続人申告登記には、以下のような細かい注意点も存在します。
- プライバシーの問題:申告により、登記事項証明書に氏名・住所・本籍などが記載され、公示される。
- 期限内の対応が必要:申告を怠ると、期限を過ぎてしまい過料を科される可能性がある。
- 遺言や協議の有無に関わらず利用可能だが、遺産分割が成立すれば再度登記が必要になる。
- 代理人申請の場合は委任状が必須であり、司法書士に依頼すれば正確に処理できる。
まとめ
2024年の不動産登記法改正により、相続登記の義務化が始まりました。被相続人の死亡を知った日から3年以内に相続登記を行わなければならず、義務を怠れば過料を科される可能性があります。
しかし、遺産分割協議がまとまらず、すぐに相続登記を行うことが難しいケースも少なくありません。そのような場合に有効なのが相続人申告登記です。
相続人申告登記を行えば、
- 期限内に義務を履行したとみなされる
- 相続人が単独で申告できる
- 登録免許税が不要で、手続も比較的容易である
といったメリットがあります。
一方で、
- 売却や贈与などの不動産活用はできない
- 遺産分割が成立したら再度相続登記が必要
- 登記事項証明書に氏名や住所が公示される
といったデメリットや注意点もあるため、制度の性質を理解したうえで活用することが大切です。
相続人申告登記は、あくまで「義務を履行するための暫定的な制度」であり、最終的には正式な相続登記(所有権移転登記)を行わなければ、遺産相続の手続は完了しません。
不動産の相続は、法定相続人の人数や権利関係によって複雑化しやすく、相続人全員の協議や書類準備が欠かせません。
そのため、少しでも不安がある場合は、司法書士など専門家に相談し、スムーズかつ確実に手続きを進めることをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。