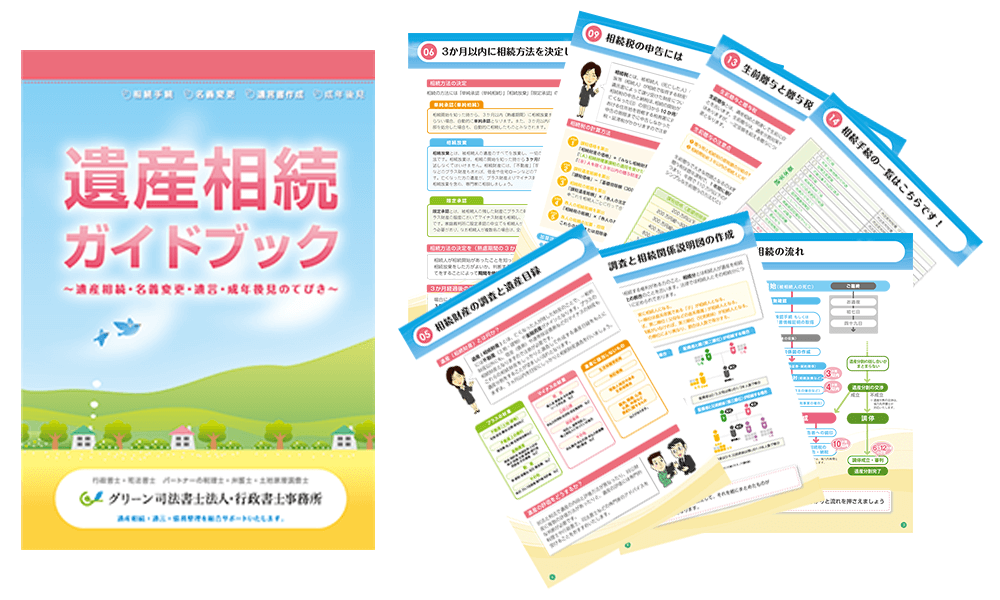- 被保佐人とは何か
- 被保佐人と成年被後見人・被補助人の違い
- 被保佐人が単独でできる行為・できない行為
「成年被後見人」と似たものに「被保佐人」というものがあります。
成年被後見人は耳にしたことはあっても後者の「被保佐人」は聞いたことがないという人が多いのではないでしょうか。
「被保佐人」とは、認知症や病気などにより、判断能力が不十分であると家庭裁判所で審判を受けた人のことをいます。
被保佐人や成年被後見人は成年後見制度を活用し、資産管理や契約手続きをサポートしてもらう必要があります。
本記事では、被保佐人とは何か、成年被後見人や被補助人との違いは何かを詳しく解説していきます。
成年後見制度については、下記の記事で詳しく解説しているので、合わせてお読みください。
目次
1章 被保佐人とは
被保佐人とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分とされ、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことです。
判断能力の程度は、成年被後見人より軽く、被補助人より重いとされます。
本人だけでは重要な契約などが困難な場合、保佐人が選任され、財産管理や法律行為の支援を行います。適切な支援により、被保佐人の生活や権利を守ることが目的です。
2章 「被保佐人」「成年被後見人」「被補助人」の違い
前項で解説したとおり、精神障害によって支援を必要とする人は「後見人」「保佐人」「補助人」に分けられています。
それぞれの違いは以下の通りです。
| 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
| 判断能力の程度 | 常に判断能力が欠けている人。日常の買い物を含め常に援助が必要な状況。病気により寝たきりな人や、脳死判定された人、重度の認知症の人、重度の知的障がいの人など。 | 判断能力が著しく不十分な人。日常的な買い物はできるが、不動産や車などの大きな財産の購入や、契約締結などが困難な状況。中度の認知症の人や中度の知的障がいの人など。 | 判断能力が不十分な人。日常的な買い物だけでなく、家や車などの大きな財産の購入、契約締結も一人で可能だが、援助があったほうが良いと思われる状況。軽度の認知症の人や、軽度の知的障がいの人など。 |
| 支援をする人(法定代理人)の呼び方 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 法定代理人に与えられる権利 | 代理権 | 同意権・代理権 | 同意権・代理権 ※代理権のみが付与される場合もある |
| 代理権付与に対する本人の同意 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 法定代理人の同意が必要な行為 | なし | 重要な財産行為 | 重要な財産行為の一部 |
| 遺言に関する規定 | 意思能力が一時的に回復したことを前提に、医師2人以上の立ち会いのもと可能 | なし(いつでも遺言が可能) | なし(いつでも遺言が可能) |
上記のように、被保佐人は日常的な買い物などは自分で行えるものの、不動産や自動車など大きな財産の購入は難しい状態です。
成年後見制度によって、保佐人が選ばれた場合は同意権が与えられます。
また、被保佐人は遺言書をいつでも作成できるなど、自分で財産の処分方法をある程度は決定可能です。
ただし、認知症の症状は一気に進むこともあるので、相続対策をしたい場合はできるだけ早く準備することをおすすめします。
次の章では、被保佐人が単独で行える行為、行えない行為について詳しく見ていきましょう。
3章 被保佐人が単独で行える行為・行えない行為
被保佐人は中度の認知症や知的障がいであり、判断能力が著しく不十分な人です。
そのため、日常生活を送る上で買い物をすることは可能ですが、不動産や自動車などの大きな財産の購入は難しい場合があります。
被保佐人と判断された場合に単独で行える行為、行えない行為について詳しく見ていきましょう。
3-1 被保佐人が単独で行える行為
被保佐人は、日常生活を送る上での買い物は自分1人で行えます。
また、保佐人の同意権や代理権の対象にならない遺言書の作成や結婚などといった法律行為については自分で行うことが可能です。
3-2 被保佐人が単独で行えない行為
被保佐人と判断されると、下記の行為を単独で行えない可能性があります。
- 不動産の購入・売却・賃貸借
- 金融機関などからの借金
- 他人へ金銭を貸す行為
- 他人の借金の保証人になる行為
- 預貯金の払い戻し
- クレジットカードの契約
- 遺産分割、相続の承認または放棄
- 建物の新築、リフォーム
- 裁判の提起
- 贈与
万が一、被保佐人と判断された後に上記の行為を行いたい場合は、家庭裁判所に申立てをして保佐人を選んでもらう必要があります。
4章 被保佐人に保佐人が必要となるケース
先ほどの章で解説したように、被保佐人と判断されると大きな金額が関係する契約行為や法的手続きは自分だけでは行えない恐れがあります。
このような契約行為を行いたい場合や自分1人でお金の管理をするのが難しいケースなどでは、保佐人に代わりに行ってもらわなければなりません。
被保佐人に保佐人が必要となるケースは、主に下記の通りです。
- 不動産の管理・運用・処分が難しい
- お金の管理が難しい
- 家族による使い込みがある
- 不当な契約や売買をする恐れがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1 不動産の管理・運用・処分が難しい
父が不動産を所有しており、日常生活は送ることはできているものの認知症などによって不動産の管理・運用・処分が難しい場合に保佐人が必要となってくる場合があります。
具体的には、下記の事情が発生したときに保佐人の選任を検討するケースが多いです。
- 賃貸するなど活用できない
- 売った方がよくても売れない
- 修繕が必要なのに業者との打ち合わせなどができない
4-2 お金の管理が難しい
一人暮らしをしている母が、認知症によって過剰な買い物や通信販売などでお金を過剰に使ってしまう、ギャンブルに過剰につぎ込み借金をしてしまうなど金銭管理が難しいケースでも、保佐人の選任が必要な場合があります。
他には、知的障がいのある人が他人にお金を貸してしまう、借金の保証人になるケースでも保佐人が選任される場合があります。
4-3 家族による使い込みがある
本人が認知症であることをいいことに、子供や配偶者が年金や財産などを使い込んでいるケースです。
保佐人をすれば家族や本人の代わりに保佐人が被保佐人の財産を管理するので、家族や親族による使い込みを防止できます。
4-4 不当な契約や売買をするおそれがある
認知症により判断能力が低下した人もとに、不動産会社やリフォーム会社と名乗る人が度々訪れては家の設備の新調やリフォームを進めてくるようなケースも保佐人を選任した方が良い場合があります。
保佐人には取消権があり、被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った契約行為を後から取り消すことが可能です。
保佐人選任をすすめる前に「家族信託」や「任意後見」などの方法を選択できないか、検討しておきましょう。
なぜなら保佐人を選任すると、原則として途中で制度の利用をやめることはできないからです。
また、家族が保佐人の候補者に名乗りをあげていても、第三者の司法書士や弁護士が選ばれる可能性もあります。
ひとえに認知症といっても症状はまちまちで、時期によって調子が良いこともあるでしょう。
一定以上の判断能力があれば、家族信託や任意後見制度といった本人の希望をより反映しやすい選択を取ることもできる可能性があります。
保佐人選任を検討しているのであれば、なるべく早いタイミングで生前対策や相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
5章 被保佐人のために保佐人が行うこと
中度の認知症や知的障がいであり資産管理を行えない場合や何か大きな契約行為が必要になった場合には、保佐人を選任する必要があります。
保佐人を選任すれば、被保佐人が契約をするときに一緒に同意をしてくれる、保佐人の同意なく契約行為が行われた場合は後からでもその契約を取り消すことが可能です。
保佐人の権利および義務には、下記のものがあります。
- 被保佐人が契約を結ぶ際の同意(同意権)
- 被保佐人が行った行為の取消し(取消権)
- 被保佐人の行為への追認(追認権)
- 被保佐人に代わって契約を結ぶ(代理権)
- 家庭裁判所への定期報告
それぞれ詳しく見ていきましょう。
被保佐人のために、保佐人は様々なことを行ってくれます。どのようなことを行ってくれるのか、詳しく見ていきましょう。
5-1 被保佐人が契約を結ぶ際の同意(同意権)
被保佐人は、重要な財産行為を行う際に保佐人の同意が必要になります。
保佐人の同意が必要な行為は以下の通りです。
- 不動産の購入・売却・賃貸借
- 金融機関などからの借金
- 他人へ金銭を貸す行為
- 他人の借金の保証人になる行為
- 預貯金の払い戻し
- クレジットカードの契約
- 遺産分割、相続の承認または放棄
- 建物の新築、リフォーム
- 裁判の提起
- 贈与
5-2 被保佐人が行った行為の取消し(取消権)
上記で紹介した保佐人の同意が必要な行為については、万が一被保佐人が保佐人の同意なく勝手に行ってしまった場合は、保佐人によってあとから取り消すことが可能であり、これを「取消権」と呼びます。
保佐人によって取り消された契約等については、契約当初から無効であったことになります。
もし、被保佐人が土地を売ってしまったケースでは、取消権が行使されると売買契約が取り消され、売り主は代金を買主に返却し、買主は売主に土地を返却することとなります。
5-3 被保佐人の行為への追認(追認権)
保佐人は、被保佐人が単独で行った行為について、あとから行為を追認することができます。
4-2で、被保佐人が保佐人の同意なく行った行為は、保佐人によって取り消すことができると解説しましたが、保佐人がその行為に対して追認すれば、取り消しができなくなります。
契約をする相手は、後ほど保佐人によって契約を取り消されてしまう可能性があると、被保佐人と契約を結ぶことを躊躇してしまうこともあるでしょう。
そこで、相手方から保佐人に被保佐人の行為について追認するか取り消すかを回答するよう求められます。
そして、保佐人が一定期間回答をしない場合は、被保佐人の行為を追認したとみなされ、その後保佐人によって取り消せない仕組みとなっています。
保佐人は回答をせず放置してしまうと、どんな不利な契約であっても取り消すことができなくなるので、ご注意ください。
5-4 被保佐人に代わって契約を結ぶ(代理権)
保佐人は被保佐人の行為に同意したり、被保佐人が単独で行った行為を取り消せますが、被保佐人の代わりに契約を結ぶことは原則としてできません。
ただし、特定の法律行為については、事前に家庭裁判所から「代理権の付与」を受けている場合のみ被保佐人の代理人として契約を結ぶなどの行為を行えます。
特定の法律行為に該当するものは、主に下記の通りです。
- 財産上の行為
- 介護・保険の契約
- 介護保険の認定
- 裁判手続き
- 登記申請
一方、法律行為の中でも、婚姻や子供の認知、嫡出認否などの身分に関する行為や、一身専属的な行為に加え、遺言については代理権の付与は認められていません。
5-5 家庭裁判所への定期報告
保佐人は、定期的に家庭裁判所に対し保佐人として行った行為を定期報告しなければなりません。
定期報告の頻度は、基本的に年1回です。
報告内容は、被保佐人の健康状態や実際に行った行為のほか、財産管理の代理権を付与されている保佐人は財産管理状況を報告するため、通帳などの資料提出もしなければなりません。
6章 被保佐人から保佐人への報酬
保佐人は被保佐人から報酬を受け取ることができ、金額については家庭裁判所が決定します。
報酬額は同意権・取消権の行使状況によって変動しますが、およそ月額2万円程度で、加えて財産管理の代理権も付与されている場合は月額3〜5万円程度になることが多いようです。
7章 被保佐人となるための手続き(保佐人選任の手続き)
被保佐人として判断されるには、保佐人選任の申立てを家庭裁判所に対して行う必要があります。
保佐人の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
| 申立てできる人 |
|
| 申立て先 | 被保佐人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | |
| 必要書類 |
|
家庭裁判所に保佐開始の申立をし、保佐人が選任されると、法務局で「成年後見登記」として登記されます。
登記されれば、被保佐人・保佐人であることを登記事項証明書で証明できます。
まとめ
被保佐人とは、認知症や知的障がいなどによって判断能力が不十分であると家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことを指します。
被保佐人を援助する人を「保佐人」といい、保佐人には同意権や取消権など、被保佐人が単独で行った行為を管理可能です。
ただし、保佐開始の申立には非常に多くの書類が必要であり、保佐開始後は原則として被保佐人が亡くなるまで制度の運用が続きます。
司法書士や弁護士が保佐人になると報酬もかかりますので、保佐人選任を検討しているのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、成年後見制度や認知症対策についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
成年後見人の費用は誰が払う?
成年後見人の費用は、被後見人の財産から支払われます。
そのため、被後見人の家族や親族が報酬を支払う必要はありません。
▶成年後見人の費用について詳しくはコチラ被保佐人とは?
被保佐人とは、精神障害により判断能力が不十分な状態であるとして家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことを指します。
▶被保佐人について詳しくはコチラ遺言書の作成は自分でできますか?
被保佐人が自分で遺言書を含む、遺言を残すことは可能です。
また、遺言に対して保佐人の同意は必要ありません。
ただし、意思能力の可否について相続人間でトラブルになることもあるので、被保佐人が遺言をする場合は、公正証書で作成し、司法書士や弁護士などの法律の専門家に証人として立ち会ってもらうのが良いでしょう。
▶遺言書作成方法について詳しくはコチラ結婚にも保佐人の同意が必要ですか?
結婚だけでなく、離婚、養子縁組などの行為(身分行為)は、保佐人の同意は必要はなく、被保佐人の単独で行えます。
とはいえ、被保佐人の財産を目当てに結婚をしようとする人が現れないとは限りません。
そのような疑いがあるケースでは、財産の贈与などをしていないか確認しましょう。
なお、贈与に関しては保佐人の取消権を行使可能です。被保佐人は自分の自宅を売却できる?
被保佐人は不動産の売買など大きな財産が関わってくる契約行為を自分だけでは行えないとされています。
そのため、中度の認知症や知的障がいであり判断能力が不十分な人は、保佐人を申し立てた上で自宅売却の手続きをしなければなりません。被保佐人は日用品の購入を自分で行える?
被保佐人とされる中度の認知症や知的障がいの人も、日用品の購入は単独で行えるとされています。
被保佐人は確定申告を自分で行える?
被保佐人が確定申告を自分で行うかは、家庭裁判所が保佐人に対し与えた代理権の内容によって異なります。
家庭裁判所が保佐人に対して確定申告の代理権を与えていれば保佐人が代わりに申告業務を行えます。被保佐人は相続放棄の手続きを行える?
被保佐人とされる中度の認知症や知的障がいの人は、自分の意思だけでは相続手続きを行えないとされています。
そのため、中度の認知症や知的障がいの人が相続放棄をする場合は、保佐人を選任した上で相続放棄の申立てをしなければなりません。
▶認知症の人の相続手続きについて詳しくはコチラ