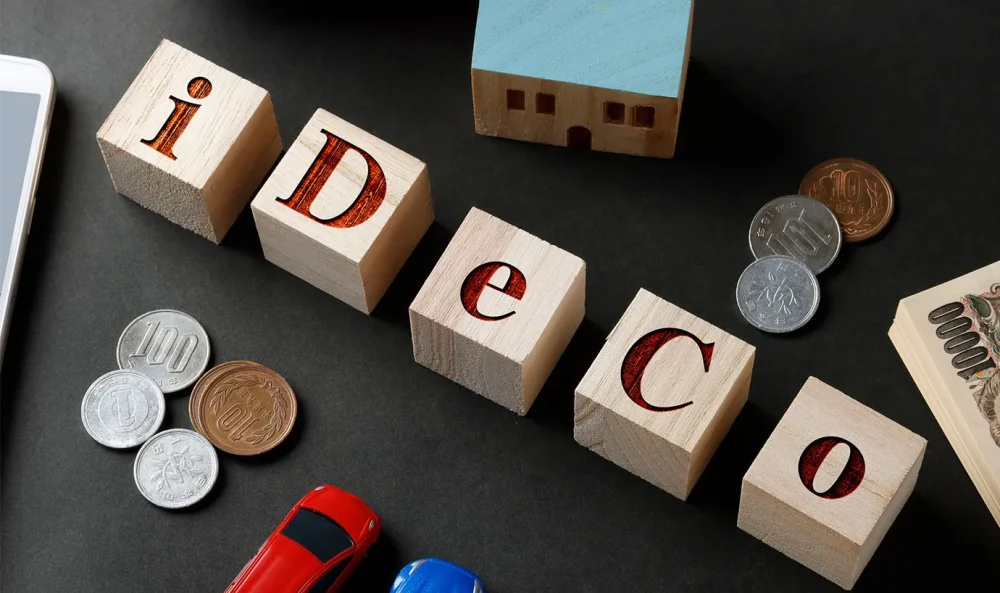
iDeCoの相続手続きの流れ・必要書類|死亡一時金は誰が受け取る?
【この記事でわかること】
- iDeCo加入者が亡くなると掛け金はどうなるのか
- iDeCoの死亡一時金を受け取れる人物・順位
- iDeCoの相続手続きの流れ・必要書類
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、老後の資産形成を目的とした制度です。
加入者は原則60歳以降になると、積み立てた資金を年金もしくは一時金形式で受け取れます。
iDeCo加入者が死亡した際には、遺族が死亡一時金を受け取り可能です。
死亡一時金を受け取れる人物は、加入者が生前のうちに指定できますが、指定していなかった場合は受取順位の高い人物が受け取る決まりです。
本記事では、iDeCo加入者が亡くなったときの相続手続きについて詳しく解説していきます。
家族や親族が亡くなったときの相続手続きについては、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。
目次
1章 iDeCo加入者が亡くなると死亡一時金として遺族に支払われる
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、老後の資産形成を目的とした制度ですが、加入者が死亡した場合、遺族に対して「死亡一時金」として支払われます。
iDeCo加入者が亡くなったときの取扱いで押さえておくべきポイントは、主に下記の通りです。
- 死亡一時金は現金で支払われる
- 死亡一時金は一括払いである
- iDeCoで運用していた投資信託は売却価格が相続税評価額となる
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 死亡一時金は現金で支払われる
iDeCoは加入者が資産を毎月積み立て、投資信託や定期預金などといった金融商品で自ら運用します。
しかし、加入者が死亡した場合、運用していた金融商品はすべて売却され、現金化されます。
受取人が特定の金融商品として、相続することはできないのでご注意ください。
そのため、加入者の死亡時期によっては、運用成績がふるわず損失が発生しているタイミングで現金化される可能性もあります。
1-2 死亡一時金は一括払いである
iDeCoの受け取り方法には、①年金形式と②一時金形式を選択できます。
しかし、加入者が死亡し、遺族が死亡一時金として受け取る場合は一括払いとなり、年金形式での受け取りを選択することはできません。
1-3 iDeCoで運用していた投資信託は売却価格が相続税評価額となる
iDeCoの死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
そして、iDeCoで運用していた投資信託は売却価格を相続税評価額とすると決められています。
iDeCo加入者が死亡し、投資信託などといった金融商品を売却するタイミングは遺族が選ぶことはできず、証券会社が定めた日に売却される決まりです。
相続税評価額を下げるために売却タイミングを調整することはできないと理解しておきましょう。
2章 iDeCoの死亡一時金を受け取れる人物・順位
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者が死亡したときに死亡一時金を受け取れる遺族については、受取順位が決められています。法定相続順位と異なるので注意しなければなりません。
加入者が生前のうちに、死亡一時金の受取人を決めていた場合は、指定されていた人物が優先的に死亡一時金を受け取り可能です。
本章では、iDeCoの死亡一時金の受取順位について、詳しく見ていきましょう。
2-1 指定されていた受取人が優先される
iDeCoでは、加入者が生前に、死亡一時金の受取人を指定できます。
加入者が受取人を指定していた場合、死亡時にはその指定された人物が優先的に死亡一時金を受け取れます。
2-2 受取人が指定されていなかった場合の優先順位
iDeCo加入者が死亡一時金の受取人を生前に指定していなかった場合には、下記の優先順位で受取人が決まります。
| 優先順位 | 人物 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の配偶者(事実婚の夫や妻を含む) |
| 第2順位 | 加入者によって生計を維持されていた子供や父母、孫や祖父母および兄弟姉妹 |
| 第3順位 | 第2順位の人以外で、加入者によって生計を維持されていた6親等内の血族と3親等内の姻族 (例:いとこなど) |
| 第4順位 | 第3順位の人以外の子供や父母、孫や祖父母および兄弟姉妹 |
上記の受取順位は、法定相続順位とは異なるので、注意しなければなりません。
また、iDeCoの死亡一時金は受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割は必要ありません。
そのため、遺産分割協議が完了していなくても、上記の順位に従った受取人が単独で手続きを行えます。
3章 iDeCoの相続手続きの流れ
個人型確定拠出年金(iDeCo)の死亡一時金は、加入者が亡くなった際に、自動で支給されるわけではなく、受取人が手続きしなければなりません。
iDeCoの相続手続き(裁定請求)の流れは、主に下記の通りです。
- 金融機関・保険会社に相続発生を連絡する
- 加入者死亡届などの必要書類を提出する
- 記録関連運営管理機関に裁定請求書などの必要書類を提出する
- 受取人の口座に死亡一時金が振り込まれる
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP① 金融機関・保険会社に相続発生を連絡する
まずは、故人がiDeCoの契約をしていた金融機関などに相続の発生を連絡します。
iDeCoは様々な金融機関で取り扱われているため、故人がどこの金融機関と契約していたか確認しておくことが重要です。
具体的には、故人の自宅などを整理し、iDeCoに関する郵便物や種類、メールなどがないか確認してみましょう。
万が一、金融機関を特定できない場合には、記録関連運営管理機関に問い合わせをする必要があります。
記録関連運営管理機関とは、iDeCoなどの確定拠出年金の記録関連業務を行っている運営管理機関であり、下記の4社があります。
- 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(JIS&T)
- 損保ジャパンDC証券
- 日本レコード・キーピング・ネットワーク(NRK)
- SBIベネフィット・システムズ
STEP② 加入者死亡届などの必要書類を提出する
金融機関などに加入者か亡くなったことを連絡したら、必要書類を準備し、提出します。
必要書類は故人と受取人の関係や金融機関によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
必要書類については、本記事の4章で詳しく解説します。
STEP③ 記録関連運営管理機関に裁定請求書などの必要書類を提出する
金融機関での手続きが完了すると、次に記録関連運営管理機関に対して裁定請求を行います。
裁定請求時には、下記のような書類が必要となります。
- 裁定請求書(運営管理機関所定のもの)
- 自分が受取人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
- 受取人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 受取人の印鑑証明書
裁定請求書の提出後、記録関連運営管理機関で審査が行われます。
STEP④ 受取人の口座に死亡一時金が振り込まれる
裁定請求が認められると、iDeCoの死亡一時金が受取人の指定した銀行口座に振り込まれます。
金融機関や保険会社などに加入者の死亡を連絡してから、死亡一時金が振り込まれるまでには、一般的に1〜2ヶ月程度かかります。
4章 iDeCoの相続手続き時に必要な書類
個人型確定拠出年金(iDeCo)の死亡一時金を受け取る場合、金融機関や記録関連運営管理機関などに必要書類を提出しなければなりません。
必要書類は、故人と受取人の関係によって変わります。
本章では、iDeCoの相続手続きにおいて必要となる書類について詳しく解説します。
4-1 すべての相続で必要となる書類
どの相続人が死亡一時金を受け取る場合でも、共通して必要となる書類は、下記の通りです。
【すべてのケースで必要となる書類】
- 金融機関や保険会社所定の加入者死亡届および裁定請求書
- 受取人のマイナンバーカードやマイナンバーがわかる書類(受取人が複数人いるときは代表者分のみ)
- 受取人の印鑑証明書(複数人いるときは全員分)
【加入者に生計を維持されていた人物が請求する場合】
- 生計維持の証明書類(源泉徴収票など)
【受取人が複数人いる場合】
- 代表受取人選任届
【生計維持関係にない同順位・先順位の遺族がいる場合】
- 対象者の生計維持証明書(複数人いるときは全員分)
- 対象者の印鑑証明書(複数人いるときは全員分)
4-2 死亡一時金を配偶者が受け取る場合の必要書類
死亡一時金を配偶者が受け取る場合、婚姻関係を証明するために、加入者の死亡がわかる戸籍謄本を提出する必要があります。
内縁の妻や夫が配偶者として死亡一時金を請求する場合は、戸籍謄本では事実婚にあったことを証明できないため、金融機関などに必要書類を確認しておきましょう。
4-3 死亡一時金を子供・親が受け取る場合の必要書類
iDeCoの死亡一時金を子供や親が受け取る場合には、下記の書類提出も必要となります。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 受取人の現在の戸籍謄本
4-4 死亡一時金を孫が受け取る場合の必要書類
孫が死亡一時金を受け取る場合、下記の書類を用意しなければなりません。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 故人の子供全員の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 父親・母親の死亡がわかる戸籍謄本類
- 受取人の現在の戸籍謄本
4-5 死亡一時金を祖父母が受け取る場合の必要書類
祖父母が死亡一時金の受取人になるケースでは、下記の書類を提出しなければなりません。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- すでに亡くなった祖父母がいるときは、祖父母の死亡を確認できる戸籍謄本類
- すでに亡くなった子供がいるときは、子供全員の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- すでに亡くなった孫がいるときは、孫の死亡を確認できる戸籍謄本類
- 父親・母親の死亡がわかる戸籍謄本類
- 受取人の現在の戸籍謄本
4-6 死亡一時金を兄弟姉妹が受け取る場合の必要書類
故人の兄弟姉妹が受取人となる場合、下記の書類を提出する必要があります。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 父親・母親の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 祖父母の死亡がわかる戸籍謄本類
- すでに亡くなった兄弟姉妹がいるときは、兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本類
- すでに亡くなった子供がいるときは、子供全員の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- すでに亡くなった孫がいるときは、孫の死亡を確認できる戸籍謄本類
- 父親・母親の死亡がわかる戸籍謄本類
- 受取人の現在の戸籍謄本
重複する戸籍謄本類がある場合は、1通のみ提出すれば問題ありません。
5章 iDeCoの相続手続きをする際の注意点
個人型確定拠出年金(iDeCo)の相続手続きや受け取った死亡一時金の取り扱いは、一般的な金融資産の取り扱いと異なる部分があるので、注意しなければなりません。
iDeCoの相続手続きをする際の注意点は、主に下記の通りです。
- iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」に含まれる
- 死亡一時金の受け取りが加入者の死亡から3年経過すると「一時所得」になる
- 死亡一時金の受け取りが加入者の死亡から5年経過すると「相続財産」になる
それぞれ詳しく解説していきます。
5-1 iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」に含まれる
iDeCoの加入者が亡くなったとき、遺族に支払われる死亡一時金は「みなし相続財産」として扱われます。
みなし相続財産とは、生命保険金などと同様に、受取人固有の財産として扱われるものの、相続税の課税対象となる財産です。
iDeCoの死亡一時金を法定相続人が受け取った場合は、生命保険金や死亡退職金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用可能です。
例えば、故人の子供がiDeCoの死亡一時金を受け取った場合、法定相続人が3人であれば「500万円×3人=1,500万円」までは相続税がかかりません。
5-2 死亡一時金の受け取りが加入者の死亡から3年経過すると「一時所得」になる
iDeCoの死亡一時金は、原則として「みなし相続財産」として扱われますが、加入者の死亡から3年以内に請求しなかった場合は、受取人の「一時所得」として課税されることになります。
一時所得として扱われる場合、相続税の基礎控除や非課税枠を適用することもできず、他の所得と合算した総合課税となるため税負担が重くなる恐れがあります。
一時所得は「(受け取った金額-特別控除額50万円)×2分の1」の金額が課税対象となるので、相続税の計算方法と異なる点にも注意しなければなりません。
iDeCoの死亡一時金を受け取る際には、早めに手続きを行うことをおすすめします。
5-3 死亡一時金の受け取りが加入者の死亡から5年経過すると「相続財産」になる
iDeCoの死亡一時金を受け取らないまま5年以上経過すると、一時所得ではなく「相続財産」として扱われます。
みなし相続財産ではなく一般的な相続財産として扱われるため、法定相続人が受け取っても相続税の非課税枠を適用することはできません。
また、みなし相続財産と異なり、受取人固有の財産ではなくなるため、遺産分割協議を行った上で受け取る人物を決定する必要があります。
このように、iDeCoの死亡一時金を5年以上請求しないでいると、受け取るまでの手続きがより複雑になる恐れもあるのでご注意ください。
相続税の非課税枠を適用したい場合や、相続税を期限内に申告したい場合には、相続に精通した税理士に相談することも検討しましょう。
まとめ
iDeCo加入者が亡くなったときには、これまで積み立てた資産を死亡一時金として遺族が受け取れます。
死亡一時金は自動的に支払われるわけではないので、故人がiDeCoに加入していた場合は、請求手続きを行いましょう。
死亡一時金は受取時期によって、みなし相続財産もしくは一時所得、相続財産として扱われます。
金額によっては、相続税の申告や確定申告が必要となるのでご注意ください。
家族や親族が亡くなると、iDeCoの相続手続き以外にも様々な手続きを行わなければなりません。
ミスなく確実に相続手続きを行いたい場合や、何から準備すれば良いかわからない場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に相談することもご検討ください。
グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの手続きも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。










