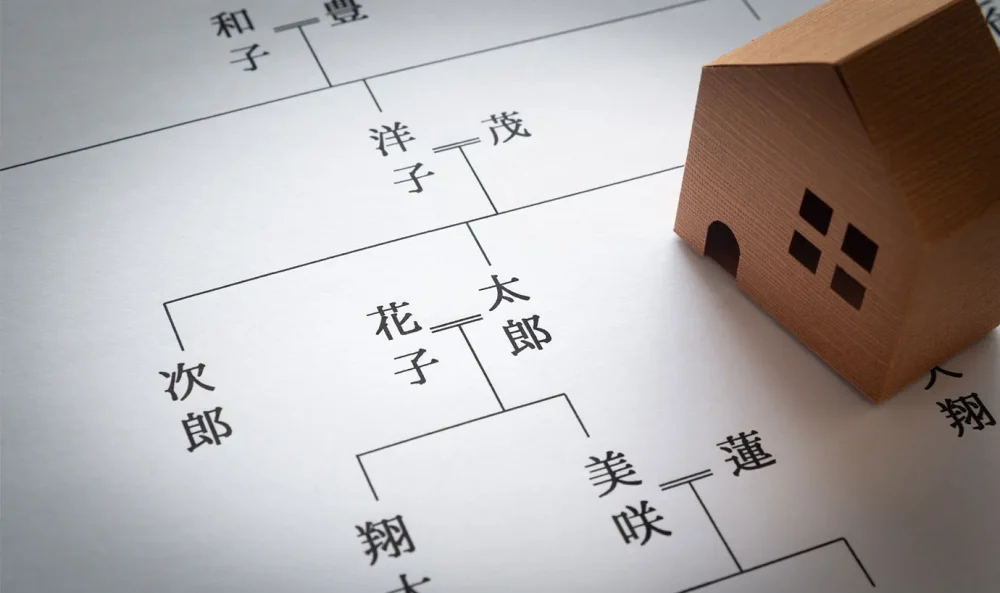
- 推定相続人とは誰か
- 推定相続人と法定相続人・相続人との違い
- 推定相続人になる人物・優先順位
- 法定相続人が相続人となれないケース
相続が発生する前に「誰が相続人になるのか」を明確に把握しておけば、相続対策をしやすくなります。
そこで重要になるのが「推定相続人」という概念です。
推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に、法律上相続人となると見込まれる人物です。
本記事では、推定相続人の意味や法定相続人・相続人との違い、誰が推定相続人にあたるのかをわかりやすく解説します。
目次
1章 推定相続人とは
推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に、法律上相続人となると見込まれる人物です。
つまり、まだ相続は発生しておらず、被相続人が健在であるものの、将来的に相続人となる可能性が高い人物です。
被相続人が元気なうちから相続関係を整理する場面では、法的に誰が相続人となる予定なのかを確認することがとても重要となります。
1-1 推定相続人と法定相続人・相続人の違い
推定相続人と混同されやすい用語として「法定相続人」や「相続人」があります。
「法定相続人」とは、法律で定められた相続人となる権利がある人であり、被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などがこれに該当します。
そして、「相続人」とは、相続が実際に発生した後に相続権を持つことが確定した人物であり、遺産分割協議に参加できるのは相続人です。
相続放棄をしたり、廃除や欠格により資格を失った人は、法定相続人であっても相続人にはなりません。
2章 推定相続人になる人・順位
推定相続人になる人物や優先順位は、法律によって以下のように決められています。

常に相続人になる | 配偶者 |
|---|---|
第1順位 | 子供や孫 |
第2順位 | 両親や祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
2-1 【常に相続人になる】配偶者
配偶者は、常に推定相続人に含まれます。
ただし、推定相続人となる配偶者は法律上の婚姻関係にある人物であり、内縁の妻・夫は含まれません。
2-2 【第1順位】子供・孫
配偶者とともに最も優先的に相続人となるのが、被相続人の子供です。
子供がすでに死亡している場合は、その子、つまり被相続人にとっての孫が「代襲相続人」となり、相続権を受け継ぎます。
子供や孫などの直系卑属の代襲相続は回数に制限なく発生するため、孫も亡くなっていればひ孫に相続権が移ります。
また、子供は実子だけでなく養子であっても相続権を持ちます。
2-3 【第2順位】親・祖父母
被相続人に子供(もしくは孫)がいない場合、次に相続人となるのは父母、あるいは祖父母などといった直系尊属です。
この場合も、故人に配偶者がいれば、配偶者と直系尊属が共同で相続する形となります。
2-4 【第3順位】兄弟姉妹や甥・姪
被相続人に子供もおらず、両親など直系尊属もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
この兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合には、その子供である甥・姪が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。甥・姪のさらに子供(つまり被相続人から見て大甥・大姪)は代襲相続権を持たない点に注意しましょう。
3章 法定相続人が相続人とならないケース
民法上の定義では、「法定相続人=相続の権利がある人」とされていますが、実際の相続手続きにおいては、法定相続人であっても相続人とならないケースがいくつか存在します。
具体的には、以下のようなケースでは法定相続人であっても相続人にはなりません。
- 相続放棄をしたケース
- 相続欠格となったケース
- 相続人廃除されたケース
- 法定相続人以外にすべての財産を遺贈されたケース
- 一部の法定相続人に全ての財産を相続させるものとされたケース
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 相続放棄をしたケース
相続放棄をした人物は、法定相続人であっても相続人にはなりません。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない手続きであり、家庭裁判所に申立てをすることで認められます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、遺産分割協議にも関与せずすべての遺産を相続しなくなります。
3-2 相続欠格となったケース
相続欠格となった法定相続人も相続権を失うため、相続人にはなれません。
相続欠格とは、一定の行為をした法定相続人が、相続権を永久に失う制度です。
具体的には、以下のような行為をすると相続欠格に該当します。
- 故人や先順位・同順位の相続人を殺害した、もしくは殺害しようとして刑に処せられた
- 故人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった
- 故人に詐欺や強迫を行い、遺言の作成や変更・取消を妨害した
- 被相続人に詐欺や強迫を行い、遺言の作成や変更、取消をさせた
- 遺言書を偽装・変造・破棄・隠蔽した
上記の行為が判明した場合、法定相続人は自動的に相続権を失い、相続発生後は相続人ではなくなります。
3-3 相続人廃除されたケース
相続人廃除となった法定相続人も、相続人にはなれません。
相続人廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立て認められると、特定の法定相続人の相続権を剥奪できる制度です。
以下のようなケースでは、相続人廃除が認められる可能性があります。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
- 被相続人の財産を不当に処分した
- ギャンブルなどの浪費による多額の借金を被相続人に返済させた
- 度重なる非行や反社会勢力へ加入している
- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている
- 被相続人の配偶者が愛人と同棲するなど不貞行為を働いている
- 財産目当ての婚姻だった
- 財産目当ての養子縁組だった
相続人廃除の手続きは生前に行うだけでなく、遺言で「○○を廃除する」と記載しておけば遺言執行者が家庭裁判所に請求することで手続きできます。
3-4 法定相続人以外にすべての財産を遺贈されたケース
遺言書によって、被相続人が「すべての財産を○○に遺贈する」と指定していた場合、法定相続人がいても遺産を受け取れないケースがあります。
例えば、内縁の配偶者や特定の友人に全財産を遺贈する内容の遺言がある場合、法定相続人は相続人にはなりません。
ただし、被相続人の配偶者や子供、両親には最低限度の金額を受け取れる遺留分が保障されています。
そのため、内縁の配偶者にすべての財産を遺贈するといった遺言書を被相続人が用意していても、遺留分侵害額請求により相当額の金銭を受け取れる可能性があります。
4章 推定相続人を調べる方法
推定相続人を把握すれば、遺言書の作成などの相続対策を考える際にも役立ちます。
特に、離婚歴がある場合や養子縁組をしている場合では、誰が相続権を持つのか判断が難しくなることもあるでしょう。
推定相続人を正確に調べるには、戸籍収集をする必要があります。
出生時から現在までの連続した戸籍謄本を収集すれば、推定相続人を特定可能です。
戸籍謄本を収集する際には、現在の戸籍謄本からさかのぼって収集していきましょう。
戸籍謄本には以前の本籍地が記載されているため、現在のものから収集すれば途切れなく集めることができるからです。
自分で戸籍収集することが難しい場合には、司法書士や行政書士などの専門家に調査を依頼することも可能です。
まとめ
推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に相続人となると見込まれる人です。
配偶者は常に相続人となり、子供や両親、兄弟姉妹の順に相続順位が定められています。
ただし、相続欠格や相続人廃除に該当する場合は相続権を失いますし、相続放棄をした法定相続人も相続人になることはできません。
推定相続人が誰かを正確に把握するには、戸籍収集をするのが良いでしょう。
戸籍収集をする際には、生まれてから現在までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
自分で戸籍謄本を収集することが難しい場合には、司法書士や行政書士に調査を依頼することもご検討ください。
グリーン司法書士法人では、相続人調査や相続対策についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。










