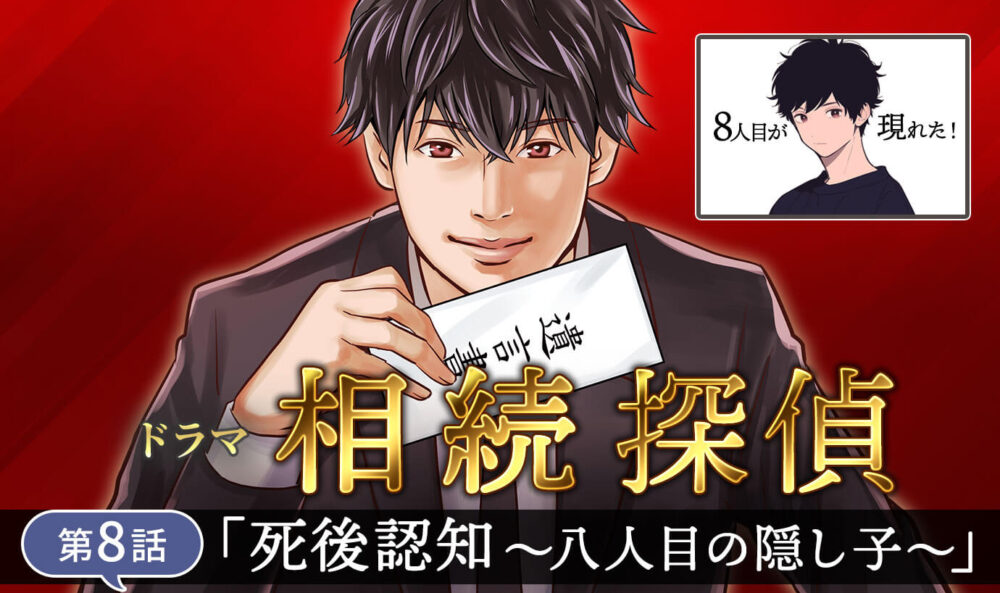
赤楚衛二さん主演のドラマ『相続探偵』(毎週土曜 夜9:00~)、いよいよ物語も佳境に入ってきましたね。
『相続探偵』は、同名の漫画を原作とするドラマで、その名の通り「相続」をめぐる人々の人間模様や、遺産を巡るミステリーが織り込まれた作品です。法律知識がベースになりながらも、エンターテインメント性が高く、専門知識がない方でも楽しめるような構成になっています。
今回の解説では、司法書士の視点から、この『相続探偵』第8話「死後認知〜八人目の隠し子〜」の内容を深掘りし、現実の相続で役立つ知識に絡めてご紹介します!
目次
ドラマ『相続探偵』とは…
ドラマ『相続探偵』は、原作:西荻弓絵、作画:幾田羊による同名の漫画を原作としたヒューマンミステリーです。
主人公の灰江七生(演・赤楚衛二)は、元弁護士でありながら、現在は相続専門の探偵として活躍する変わり者の男。
そんな彼が、「遺言書は愛する人に出す最後の手紙」という信念のもと、コミカルかつ痛快に、遺産相続に関する難解な事件を解決していくのが本作の要点となっています。
1章 『相続探偵』第8話「死後認知〜八人目の隠し子〜」の概要
1. 第8話「死後認知〜八人目の隠し子〜」あらすじ(ネタバレなし)
東大名誉教授・薮内晴天(佐野史郎)の「7人の隠し子疑惑」が解決した直後、灰江七生(赤楚衛二)のもとを、新たに「薮内の子かもしれない」と主張する青年・島田正樹(小林虎之介)が訪れます。
正樹は亡き母親から、薮内が父親だと聞かされていましたが、その証拠は写真と曖昧な記憶のみ。DNA鑑定の結果、親子関係の可能性が浮上しますが、確実な証拠を得るにはさらなる調査が必要でした。
灰江は正樹に「死後認知の訴えを起こすか、解決金だけを請求するか」という選択肢を提示します。しかし、その決断を前に、週刊誌記者・羽毛田(三浦貴大)が現れ、事態は思わぬ展開を迎えることに……。
ここに注目!
前回のエピソードの続きとなる第8話では、法律面での話題は少ないものの、「死後認知の請求をしない選択」や「相続放棄」という、相続における権利と選択肢についての言及がありました。
法的に認知を請求することは可能ですが、それを行わない選択肢もあり得ます。
また、相続放棄についても軽く言及されており、いずれも故人の権利・義務を受け継ぐかどうかの決断に関する内容となっていました。
2章 司法書士が解説!相続に関する重要ポイント
1. 死後認知の請求をしない選択肢
前回の第7話の記事で「死後認知」について詳しく説明しましたが、今回はその手続きを行わない選択肢について考えてみましょう。
死後認知とは、父親が亡くなった後に、非嫡出子(婚姻していない男女の間に生まれた子)が家庭裁判所に認知の訴えを提起し、親子関係を成立させる制度です。しかし、この手続きは義務ではなく、個人の意思によって選択することが可能です。
作中で描かれたように、認知を求めることで自分や家族のプライバシーが侵害されるリスクがある場合、あえて手続きを行わないという選択も考えられます。また、認知が認められれば相続権を得ることができますが、それによって新たな家族間のトラブルが生じる可能性もあります。
そのため、死後認知を求めるかどうかは、法的な権利だけでなく、個人の価値観や家族関係、社会的影響などを総合的に考慮して判断することが重要です。
2. 相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が遺産を一切受け取らないことを選択する制度です。
相続放棄を行うと、その人は最初から相続人でなかったものとみなされ、負債を含めた相続財産の承継義務もなくなります。
相続放棄の主なポイント:
- 申述期限:相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述。
- 撤回不可:一度放棄すると、原則として撤回はできない。
- 他の相続人への影響:自分が放棄すると、次順位の相続人(故人の親、故人の兄弟姉妹など)に相続権が移ることがある。
相続放棄は、主に故人に多額の負債がある場合や、遺産を受け取ることでトラブルが発生する可能性がある場合に有効な選択肢です。
3章 視聴者の疑問に司法書士が答えます!
Q1. 死後認知を請求しないとどうなる?
認知を請求しなければ親子関係は法的に認められず、相続権も発生しません。一方で、認知を請求しないことでトラブルを避けるメリットもあります。
Q2. 相続放棄をすると親族に迷惑がかかる?
相続放棄をすると、自分の相続権がなくなり、次順位の相続人(故人の親、故人の兄弟姉妹など)に権利が移る可能性があります。負債がある場合は、他の相続人にその負担が回るため、慎重な判断が必要です。
4章 相続の知識を深める豆知識コーナー
相続放棄と限定承認の違い
相続に際しては、遺産をそのまま引き継ぐ「単純承認」のほかに、負債を回避するための「相続放棄」や、相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ「限定承認」という選択肢があります。
手続き先は、いずれも家庭裁判所です。
項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
効果 | 相続人ではなくなる | 相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ |
申請期限 | 相続開始を知った日から3か月以内 | (最も遅く知った人が) |
申請人数 | 個人単位で申請可能 | 相続人全員が共同で申請する必要あり |
負債の責任 | 一切負わない | 相続財産の範囲内でのみ負担 |
プラスの財産 | 一切受け取れない | 財産が負債を超えた場合、余剰分を受け取れる |
相続放棄は個人で選択できるのに対して、限定承認は相続人全員の合意が必要な点に注意が必要です。
今後、ドラマで相続放棄や限定承認が取り上げられることがあれば、改めて詳しく解説します。
まとめ
『相続探偵』の第8話では、「死後認知を請求しない選択肢」や「相続放棄」に言及され、相続における個人の選択の重要性が描かれました。
相続に関する疑問や不安がある場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。 次回のエピソードも楽しみにしながら、相続の知識を深めていきましょう!




