銀行の相続手続きに期限はない!早めにすべき理由6つを解説
家族や親族が亡くなったときに行うべき手続きのひとつが、故人が遺した銀行口座の相続手続きです。 具体的には、故人から相続人に預貯金の解約手続きをする必要があります。 相続手続きの中には期限が決…
家族や親族が亡くなったときに行うべき手続きのひとつが、故人が遺した銀…
家族や親族が亡くなったときに行うべき手続きのひとつが、故人が遺した銀行口座の相続手続きです。 具体的には、故人から相続人…
平日9時〜20時 / 土日祝9時〜18時
【休業日】年末年始


相続の知識
家族や親族が亡くなったときに行うべき手続きのひとつが、故人が遺した銀行口座の相続手続きです。 具体的には、故人から相続人に預貯金の解約手続きをする必要があります。 相続手続きの中には期限が決…
家族や親族が亡くなったときに行うべき手続きのひとつが、故人が遺した銀…
家族や親族が亡くなったときに行うべき手続きのひとつが、故人が遺した銀行口座の相続手続きです。 具体的には、故人から相続人…


相続の知識
祭祀継承者とは、お墓や仏壇など死後の慰霊や鎮魂に用いられる財産である「祭祀財産」を継承する人物です。 祭祀継承者になる人物は特に決められておらず、遺言書で指定された人物や相続人同士で話し合って…
祭祀継承者とは、お墓や仏壇など死後の慰霊や鎮魂に用いられる財産である…
祭祀継承者とは、お墓や仏壇など死後の慰霊や鎮魂に用いられる財産である「祭祀財産」を継承する人物です。 祭祀継承者になる人…


相続の知識
家族が亡くなり相続が発生したときは、銀行で相続手続きを行い故人の預貯金を払い戻す必要があります。 銀行の相続手続きでは要書類の提出や銀行側の確認が必要であり、約2週間から1ヶ月程度かかります。…
家族が亡くなり相続が発生したときは、銀行で相続手続きを行い故人の預貯…
家族が亡くなり相続が発生したときは、銀行で相続手続きを行い故人の預貯金を払い戻す必要があります。 銀行の相続手続きでは要…


相続の知識
固定資産税がかからない土地も相続財産に含まれ、故人が亡くなったときには相続人に受け継がれます。 固定資産税がかからない土地であっても相続手続きや相続税申告の流れは、通常の土地を相続したときの流…
固定資産税がかからない土地も相続財産に含まれ、故人が亡くなったときに…
固定資産税がかからない土地も相続財産に含まれ、故人が亡くなったときには相続人に受け継がれます。 固定資産税がかからない土…


生前贈与
毎年110万円ずつ贈与を行う暦年贈与で相続税対策をしていた場合、相続が発生したときには注意が必要です。 相続発生から3~7年以内に行われた生前贈与の贈与財産は、相続税の課税対象財産に含めなけれ…
毎年110万円ずつ贈与を行う暦年贈与で相続税対策をしていた場合、相続…
毎年110万円ずつ贈与を行う暦年贈与で相続税対策をしていた場合、相続が発生したときには注意が必要です。 相続発生から3~…


相続の知識
両親が離婚し父親もしくは母親と別々に暮らすことになっても、子供は親が亡くなったときに相続人になれます。離婚したとしても、戸籍上の親子関係は続くからです。 また、離婚後に父親もしくは母親が再婚し…
両親が離婚し父親もしくは母親と別々に暮らすことになっても、子供は親が…
両親が離婚し父親もしくは母親と別々に暮らすことになっても、子供は親が亡くなったときに相続人になれます。離婚したとしても、戸…
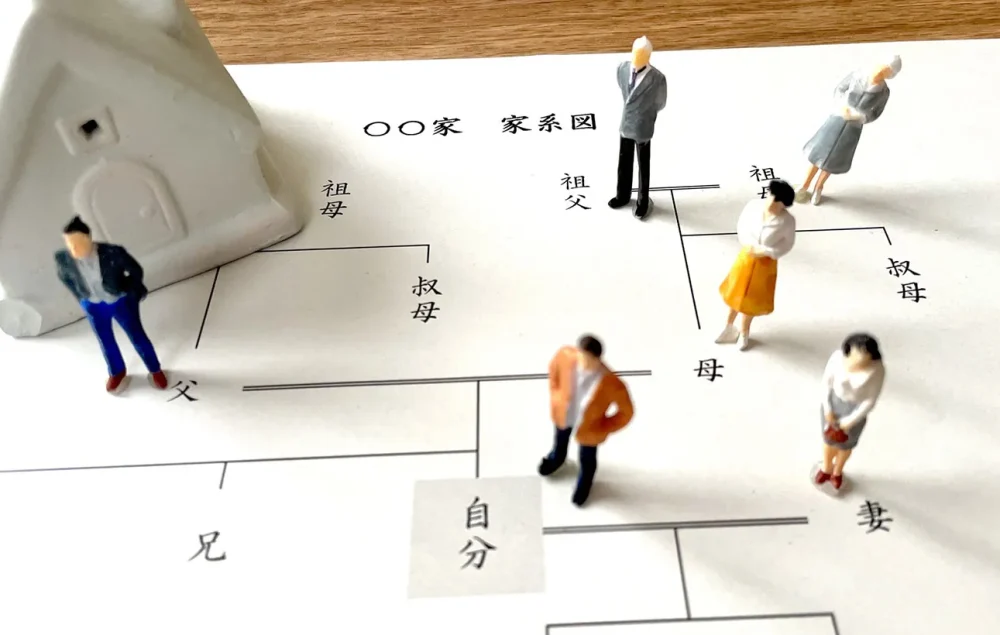
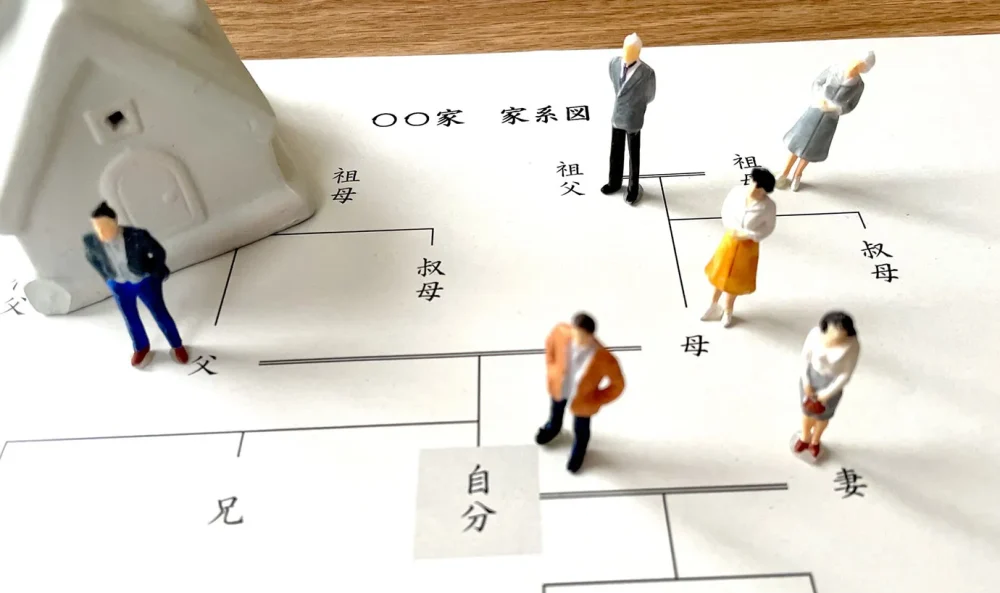
相続の知識
代襲相続とは、相続発生時点で本来であれば相続人になる人物が先に亡くなっている場合に、亡くなっている相続人の代わりにその子供が直接相続をする制度です。 例えば、故人が死亡した時点で相続人である子…
代襲相続とは、相続発生時点で本来であれば相続人になる人物が先に亡くな…
代襲相続とは、相続発生時点で本来であれば相続人になる人物が先に亡くなっている場合に、亡くなっている相続人の代わりにその子供…


相続の知識
行政書士と司法書士はどちらも相続手続きを依頼できる専門家です。 ただし、行政書士と司法書士は業務範囲が異なるので、依頼する際には任せたい内容を整理した上で専門家を選ばなければなりません。 相…
行政書士と司法書士はどちらも相続手続きを依頼できる専門家です。 た…
行政書士と司法書士はどちらも相続手続きを依頼できる専門家です。 ただし、行政書士と司法書士は業務範囲が異なるので、依頼す…


相続の知識
相続が発生したときに、亡くなった人の財産が土地しかないときには遺産分割で揉めやすくトラブルに発展しやすいので注意が必要です。 現金や預貯金と異なり、土地は分割しにくいため、遺産分割時にどうして…
相続が発生したときに、亡くなった人の財産が土地しかないときには遺産分…
相続が発生したときに、亡くなった人の財産が土地しかないときには遺産分割で揉めやすくトラブルに発展しやすいので注意が必要です…


相続税・贈与税
相続人に未成年者が含まれる場合、未成年者控除を適用できます。 未成年者控除は相続税額から直接控除できるので節税効果が大きい制度です。 相続人に未成年者が含まれる場合には、適用要件を満たしてい…
相続人に未成年者が含まれる場合、未成年者控除を適用できます。 未成…
相続人に未成年者が含まれる場合、未成年者控除を適用できます。 未成年者控除は相続税額から直接控除できるので節税効果が大き…


相続の知識
夫婦が共有名義で所有していた不動産の持分も相続財産に含まれます。 故人が遺言書を作成していなかった場合、相続人で故人が所有していた不動産の持分を相続します。 共有持分の残りの所有者である故人…
夫婦が共有名義で所有していた不動産の持分も相続財産に含まれます。 …
夫婦が共有名義で所有していた不動産の持分も相続財産に含まれます。 故人が遺言書を作成していなかった場合、相続人で故人が所…


相続の知識
